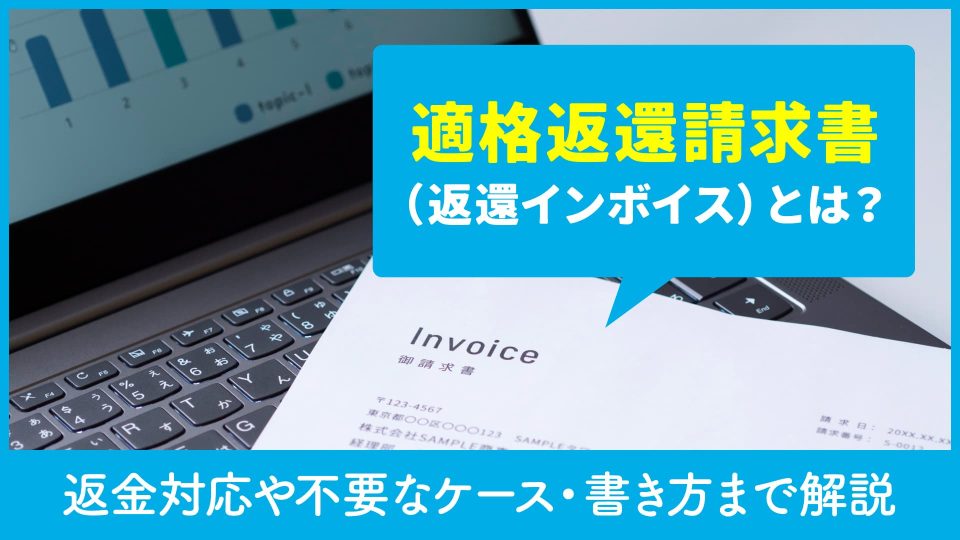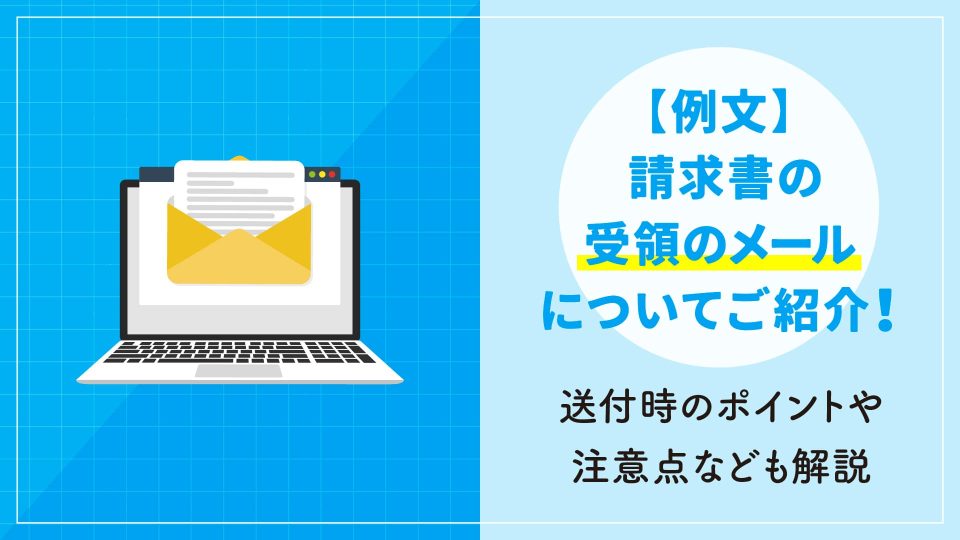一人親方の請求書は、契約や金銭などのトラブル防止のために、基本の書き方を押さえておく必要があります。取引先との契約によって、請求書の項目が異なる場合もあるため注意しましょう。この記事では、一人親方の請求書の書き方を解説します。請求書の送付や押印、書き方の注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
【必須項目】一人親方の請求書の書き方

一人親方の請求書には、必ず記載する項目があります。ここでは、必須項目について解説します。
関連記事:インボイス制度で何が変わる?建設業者が知っておきたい請求書の書き方や注意点
発行者の氏名(名称)
一人親方の請求書には、請求書に個人名や企業名、屋号を記載します。取引先から連絡できるように、住所と電話番号もあわせて記載するとよいでしょう。取引先によっては、押印が求められる場合もあります。
請求を受ける事業者の氏名(名称)
請求先である、事業者の個人名や企業名、屋号を記載します。個人名は「様」、企業名や屋号は「御中」を付けて記載しましょう。正確な名称を記載すると、請求に関するトラブルの防止につなげられます。
取引の年月日
取引の年月日は、工事の開始、完了、検収した日です。請求書を作成する日程とは異なるため、注意が必要です。取引先や業種によって、日程を記載するルールが異なる場合があるため、期間を明確に記載しましょう。
取引の内容
取引の内容は、以下のような内容を記載する必要があります。
取引が発生した日
仕事の内容
品名
数量
金額
単価(税抜)
取引先と認識違いが起きないように、正確な請求の内容を記載しましょう。
請求金額(税込)
請求金額は、消費税を含めたものです。取引で発生した金額をすべてまとめ、消費税を足した合計金額を記載します。消費税額は、請求書を発行した日の税率で計算してください。源泉徴収がある場合は、合計金額から差し引きます。
【詳細項目】一人親方の請求書の書き方
一人親方の請求書は、請求書の内容によって詳細に書く部分があります。ここでは、詳細項目の書き方を解説します。
題目
題目とは、書類の内容のことです。書類の上部中央、もしくは左上に大きく目立つように「請求書」と記載します。一目で請求書であることが分かるように、題目を記載しましょう。再発行の場合は、「請求書(再発行)」と書いてください。
請求書の発行日
請求書は、請求書の作成日ではなく、締め日を記載します。締め日は発注者が指定した日付です。指定がない場合は、請求書を作成した日付を書きましょう。請求書の発行が遅れると、支払い期限も延長になるため注意が必要です。
請求内容
請求内容は「品目」「単価」「数量」を正確に記載します。以下、それぞれの書き方の参考です。
品目
作業やサービスの内容を具体的、かつ明確に記載します。作業内容の特定の部分や、使用した特別な材料などがある場合、正確な内容を記載しましょう。
単価
作業ごとの単価を明確に記載します。作業の基準、休日・夜間などにおける単価の変動も記載しましょう。
数量
時間や個数、面積などを正確に記載します。作業時間には、作業日ごとの開始日時と終了日時を記載しましょう。
請求書番号
請求書番号とは、請求書を管理するための項目です。請求済みや入金などを確認する際に、請求書番号を照会できるため必要です。請求先からの問い合わせや、自身で請求書を管理する際にも役立ちます。
小計
小計は、商品やサービスなどの請求する項目を合計したものです。建設業の場合は、工事ごとに請求する項目の合計金額をまとめられます。小計を記載することで、取引先が請求金額を把握しやすくなります。
消費税額
小数点以下の端数を切り捨て、小計の消費税を記載します。端数に関する取り決めは、事前に取引先と話し合いをして決めるとよいでしょう。ただし、小計には消費税額が含まれないため、記載しないように注意が必要です。
源泉徴収税額
源泉徴収とは、所得税の前払いで徴収するものです。一人親方の請求した金額から、事業主が源泉徴収して税金として納めます。ただし、契約形態によって源泉の支払いの有無が異なるため、事前に確認が必要です。
振込先
請求書には、以下の振込先情報を記載します。
金融機関名
支店名
口座種別
口座番号
口座名義人
口座名義人はカタカナで記載します。振り込みの手続きの手間を省くため、銀行や支店のコードも記載するとよいでしょう。
支払の期限
支払いの期限を明確にすると、取引先と自身で入金の確認がしやすくなります。取引先への通知と、請求書への記載をすることで、トラブル防止にもつながります。支払い期限は、契約書や発注書を作成する際に決めましょう。
備考欄
備考欄には、請求に関する注意や特筆すべき項目を記載します。たとえば、振り込み手数料や支払期限などです。現場が複数ある場合、備考欄に現場ごとの金額を記載すると、詳細を把握しやすくなります。
一人親方の請求書の作成方法
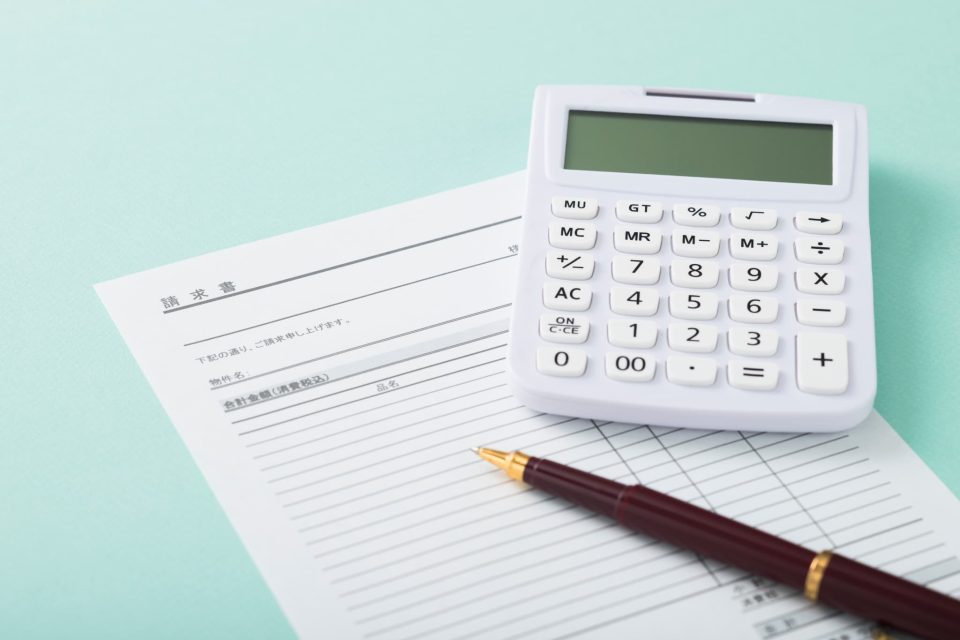
一人親方の請求書を作成する方法は、以下のとおりです。
請求先のフォーマット
テンプレート
市販の請求書
ExcelやWordなどのオフィスソフト
請求書作成アプリ
会計ソフト
請求書の作成方法は、取引先によって異なります。基本的には、取引先のルールを優先しましょう。指定外の形式で提出すると、受け取りが不可になる場合があります。請求書は作成の手間だけでなく、大量の書類を管理する負担もあります。自動計算やデータで保管できる、請求書作成アプリや会計ソフトなどがおすすめです。
関連記事:請求書の内訳の書き方は?記載例や必要項目、請求明細書との違いをまとめて解説
一人親方が請求書を作成する際の注意点
一人親方の請求書は、金額や人件費の書き方にルールがあります。ここでは、書き方の注意点を解説します。
金額の書き方
請求書の金額は「¥」もしくは「円」を記載します。「¥」マークは「¥1,000-」と、伸ばし棒を加えて記載しましょう。「円」は「1,000円」「金1,000円也」と記載してください。どちらも3桁ごとに「,」を入れて、金額を区切る必要があります。金額の記号は、「\」と「¥」のどちらかに統一しましょう。
端数の一円未満は四捨五入、切り捨て、切り上げを選べます。端数の処理に関しては、事前に取引先と話し合いが必要です。
人工代の書き方
人工代(にんくだい)とは、1日あたりの人件費のことです。人工代の書き方は「1日あたりの人工代、〇〇円」です。人工代が20,000円で5日の稼働の場合、100,000円と記載します。請求先が金額を一目で把握できるように、人数と稼働日数を記載しましょう。
一人親方の請求書に押印は必須?
一人親方の請求書に、押印は必須ではありません。ただし、取引先によっては請求書の証明として押印が求められる場合があります。押印があると請求書の信頼性を高められるため、屋号が記載されているものを用意するとよいでしょう。押印に住所や電話番号も記載しておくと、取引先との連絡がしやすくなります。
一人親方の請求書の送付方法
一人親方の請求書は、送付する際に許可や送付状が必要な場合があります。ここでは、請求書の送付方法を解説します。
郵送
一般的に、郵送では請求書の原本を送ります。原本だけではなく、送付状も添付するとよいでしょう。送付状には宛先や書類内容を書く必要があり、請求書を発行する際のトラブルを防止できるためです。送付状の送付は任意ですが、取引先から信用されやすくなるため、請求書と併せて送ることをおすすめします。
関連記事:請求書を郵送する正しい手順とマナーとは?注意点・代替手段・効率化まで徹底解説
FAX
請求書をFAXで送ることは、ビジネスのマナーとして問題ありません。郵送での請求書の送付が間に合わない場合、FAXで送付するケースがあります。ただし、取引先からFAXでの送付の許可をもらったうえで送りましょう。FAXを使用する際は、紛失や抜け漏れなどのリスクを避けるために、送付状も送るとよいでしょう。後日請求書の原本を郵送してください。
関連記事:請求書をFAXで送るのは問題ない?マナーや送付状の書き方、注意点まで解説
メール
メールで請求書を送るのも、ビジネスのマナーとして問題ありません。メールの件名には、請求書の内容を明記しましょう。送付後は、取引先に電話で確認する必要があります。メールは郵送よりもミスが起きやすいため、CCを付けて確認を徹底するとよいでしょう。請求書はPDFファイルに変換し、送付後に変更ができないようにしてください。
一人親方の請求書の保管期間
一人親方の請求書は、5年間保管する義務があります。青色申告・白色申告どちらも5年間保管してください。保管する期間は、確定申告の期限の翌日から計算します。請求書を発行した日程とは異なるため、注意が必要です。帳簿は7年間保管する必要があるため、請求書と一緒に保管するとよいでしょう。
原則として、請求書は紙で保管します。ただし、一定の要件を満たす場合はデータでの保存ができます。
一人親方の請求書はインボイス制度に対応する必要がある

一人親方の請求書は、インボイス制度への適用が必要です。ここでは、インボイス制度の概要と影響を解説します。
インボイスの全体像を把握したい場合は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:インボイス制度が建設業に与える影響とは?導入を検討する際の注意点も解説
インボイス制度とは
インボイス制度とは、仕入税額控除を受けられる、消費税法上の制度です。インボイスの正式名称は「適格請求書」で、2023年10月1日から実施されています。インボイス制度は、消費税の累積課税を避けるために必要です。事業者が売り上げと仕入れの際、消費税の2重支払いを避けられます。
適格請求書発行事業者は、税務署に登録申請書を提出する必要があります。一人親方の適格請求書が受領されると、仕入税額の控除が適用されます。
インボイス制度が一人親方に与える影響
インボイス制度を申請しないと、業務の依頼が減る可能性があります。インボイスを発行しない場合、取引先に消費税の支払いが発生するためです。一人親方がインボイスを発行できると、取引先の税制控除が適用されます。一人親方が依頼を受けやすくするために、インボイス発行事業者になることをおすすめします。
関連記事:インボイス制度が一人親方に与える影響とは?課税事業者の税負担軽減特例も解説
関連記事:インボイス制度対策とは?一人親方の廃業の可能性は?
一人親方の請求書作成には請求書作成アプリがおすすめ
請求書作成アプリは、スマートフォン1つで請求書を作成できます。取引先の情報や品目などを登録できるため、請求書を作成する負担を軽減できます。入力漏れ・請求ミスの防止にもつながり、日々の業務の効率化が可能です。
請求書をデータで保存することで、郵送費や紙代などのコストの削減にもつながります。取引先が依頼しやすいように、インボイス制度に対応しているアプリを選ぶことも大事です。
まとめ
一人親方の請求書は、必須項目と詳細項目を漏れなく記載しましょう。取引先によって書き方のルールが異なるため、金額や人工代などを正確に記載する必要があります。一人親方の請求書は、項目を自動で登録でき、請求ミスを防げる請求書作成アプリがおすすめです。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーがアプリを利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力や、年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートが特徴です。ぜひ利用をご検討ください。