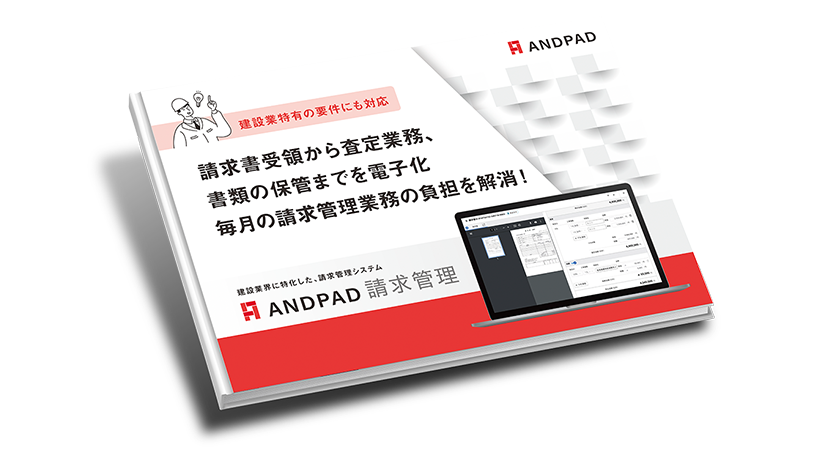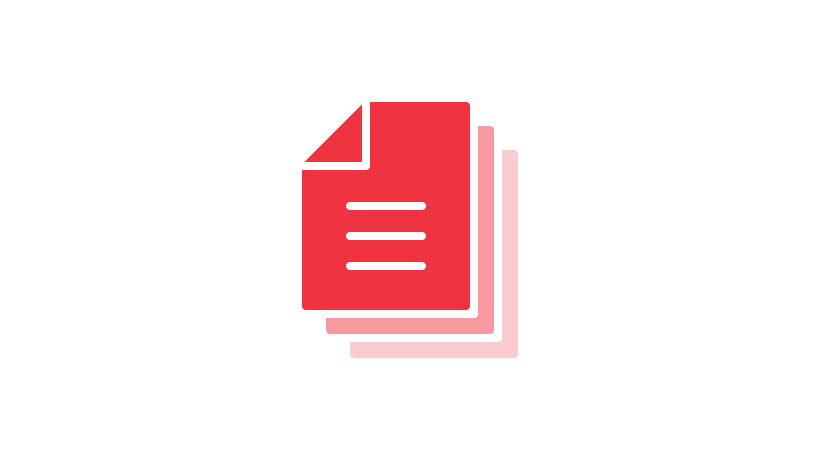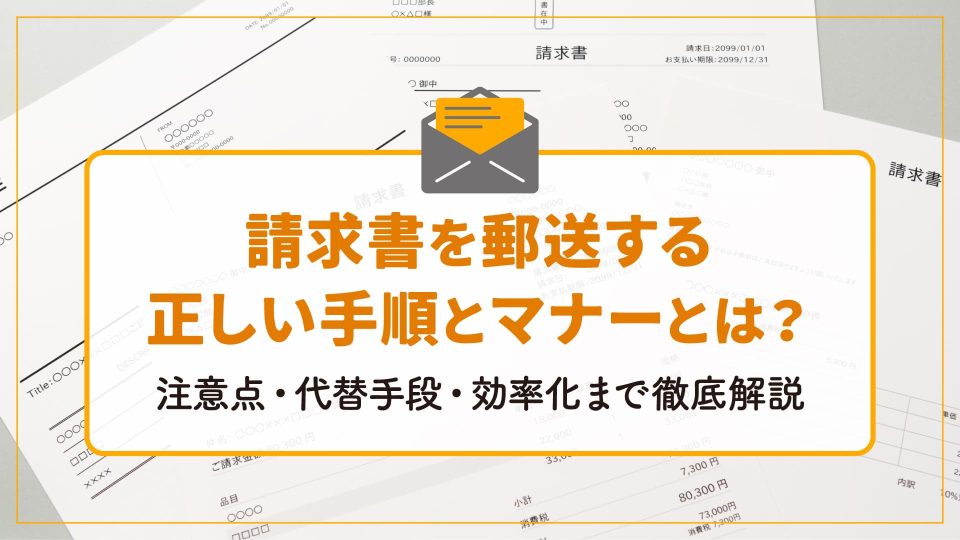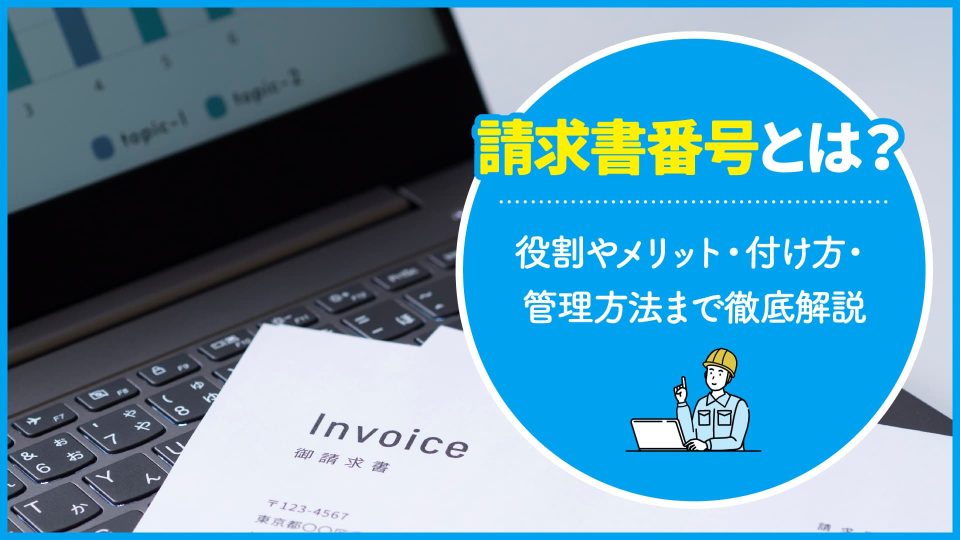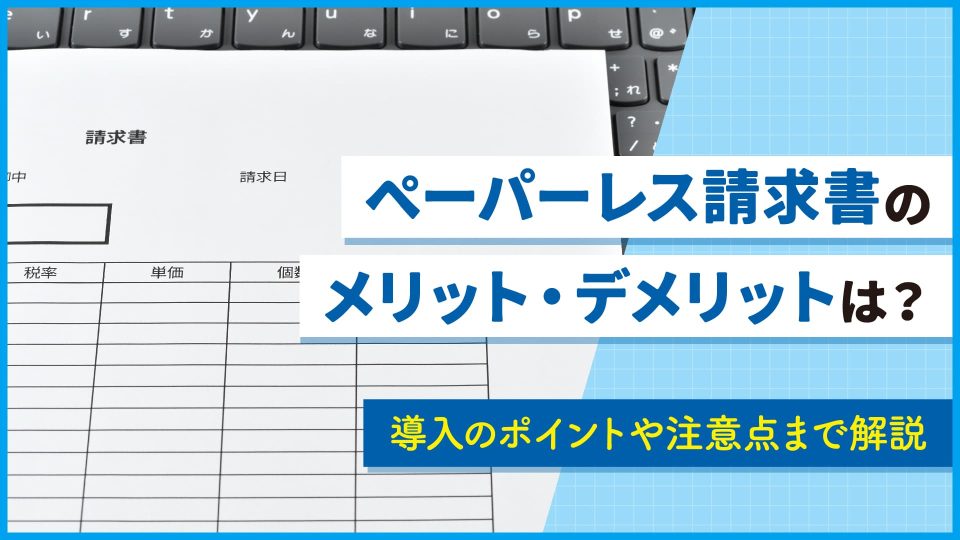多くの業種で必要となる請求書ですが、どのように郵送すればよいのか知らない人は少なくありません。この記事では、請求書の郵送方法や注意点、郵送以外で請求書を送る方法まで解説しています。業務の一環として請求書の送付に関わる可能性のある人は、参考にしてください。
請求書の郵送方法・マナー
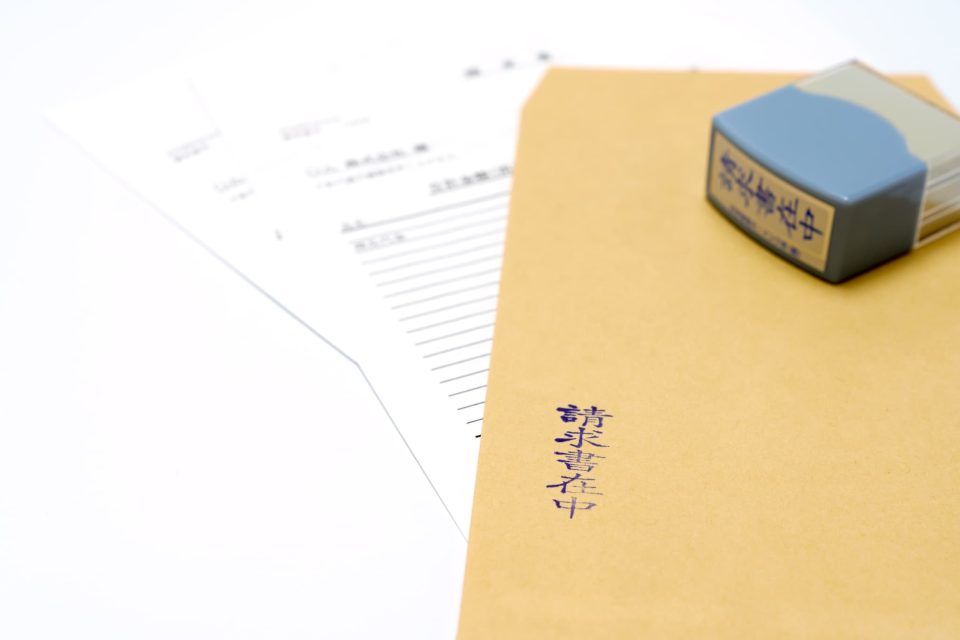
はじめに、請求書を郵送する際に用意するものや送付状の作成方法、封筒の選び方・書き方など、基本的な情報を解説します。
請求書を郵送するにあたって用意するもの
請求書を郵送する際は、はじめに次の5点を用意しておきましょう。請求書、送付状、請求書と送付状を入れる封筒、封筒の重さにあった料金の切手、封筒に請求書が入っていることを示す「請求書在中」のスタンプです。スタンプがなければ、手書きでも構いません。
送付状の作成方法
送付状は、相手企業に請求書を送付することを知らせる書類です。必要不可欠ではありませんが、ビジネスマナーの1つとして定着しているため添付したほうが安心でしょう。送付状に記載する内容は、送付日、宛先、差出人情報、本文、書類内容の5つです。本文には請求内容や挨拶文、書類を何部同封しているかを記載します。
書類の折り方・封入方法
請求書を郵送する封筒は、「長形3号」か「角形2号」を使用します。封筒のサイズにより、書類の折り方が異なります。「長形3号」の封筒を使用する場合は、三つ折りにするのがマナーです。
書類を開いた相手が最初に宛て名を確認できるよう、請求書の上に送付状を重ねます。そして、印字面を内側にして、用紙の下側から内側に折り、そのあと上側を内側に折ります。「角形2号」の封筒に入れる場合は、三つ折りにする必要はありません。
封筒の選び方
A4用紙の送付には、「長形3号」か「角形2号」の封筒を使用します。「長形3号」はA4用紙が三つ折りで入り、「角形2号」はA4用紙を折らずに入れられます。封筒のサイズは特に決まりはなく、色も決まりはありませんが、白が一般的です。
「窓付き封筒」の使用もおすすめです。「窓付き封筒」であれば宛名を書いたり、宛名シールを貼ったりする手間を省けます。「窓付き封筒」に三つ折りで入れる場合は、Z折りで入れましょう。
封筒の書き方
封筒の表面には、送付先の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名のほかに「請求書在中」の文字を記載します。縦書きなら左下、横書きなら右下に記載します。「請求書在中」の文字は黒、青、赤のどれかであれば問題ありませんが、青での記載が一般的です。
裏面には、会社名や部署名、氏名など差出人の情報と送付日を記載します。そして、宛先本人のみが開封できることを示す「〆」を記載します。封筒に切手を貼る際は、封筒を縦長に見て左上になるように貼りましょう。
封筒の送り方
請求書は「信書」扱いになるため、宅配便やゆうパックでは送付できません。信書を送付できる手段は、日本郵便の定形郵便、定形外郵便、レターパック、EMS、佐川急便の飛脚特定信書便です。急を要する場合は、速達での送付も可能です。
請求書の郵送方法における注意点

請求書を郵送する際は、内容に間違いがないかの確認が欠かせません。以下では、特に気を付けるべき、6つの注意点を解説します。
請求内容が正しいか
封筒に入れる前に、請求書の内容が正しいか確認しましょう。送付後に訂正箇所が見つかった場合は、正しい内容の請求書を再発行し、改めて郵送しなければなりません。請求書の再発行は社内だけでなく、送付先にも手間がかかります。郵送前に内容の確認を怠らないようにしましょう。
関連記事:請求書の内訳の書き方は?記載例や必要項目、請求明細書との違いをまとめて解説
送付先に誤りはないか
封筒へ記載してある送付先に誤りがないか確認しましょう。会社名や部署名、担当者の氏名に誤りがあると、相手に届くまでに時間がかかり、業務に支障をきたす可能性があります。万が一、誤った住所に送付してしまうと相手からの信用を失い、今後の取引に影響することもあります。請求内容と同じく、送付先の確認も入念に行いましょう。
適切な封筒を使用しているか
請求書は信書にあたる書類です。そのため、郵送の際や送付相手以外が封筒を手にした際に情報が漏れることがないよう、中身が透けない素材の封筒を使用しましょう。封筒は白が一般的ですが透けやすいため、厚めの封筒か透け防止加工が施された封筒がおすすめです。
郵便物の重さに合う切手を貼っているか
郵送する際は、郵便物の重さに合う切手を貼りましょう。切手が不足していると、手元に郵便物が戻り提出期限に間に合わない恐れがあります。また、差出人住所の記載があっても配達区域外であったり、消印されていたりする場合は、受取人が不足分を支払わなければならず、失礼にあたります。正確な料金は、郵便局の窓口で確認すると安心です。
普通郵便または速達で送付する
請求書は、普通郵便または速達で送付しましょう。請求書は信書に該当する書類のため、日本郵便や総務省の認可を受けた信書便事業者に依頼します。それ以外の方法で信書を送付することは法律で禁止されているため、注意が必要です。
提出期限を確認する
請求書を送付する前に、提出期限を確認しましょう。経理処理には「締め日」が設定されているため、請求書の送付が遅れると支払いが滞ります。郵送する際は、相手が受け取ってから確認するまでの日数も考慮し、早めに発送準備を進めましょう。
関連記事:請求書に収入印紙は原則不要?必要なケースや注意点・金額・貼り方を解説
請求書を郵送するメリット
多くの注意点があるにも関わらず、なぜ請求書を郵送するのでしょうか。ここでは、郵送するメリットを解説します。
原本を送付できる
請求書を郵送する最大のメリットは、請求書の原本そのものを送付できることです。印刷した請求書の原本と控えをデータでなく紙で保存することで、請求書の内容を改ざんされるリスクを減らせます。
電子データを受け取れない取引先にも対応できる
請求書を郵送で取引先に届ける方法は、これまで一般的な方法でした。請求書を受け取る際に、電子データよりも紙で受け取る方法を好む企業もあるため、そのような取引先にも対応できます。
請求書を郵送するデメリット
請求書を郵送することには、メリットだけでなくデメリットも存在します。以下で、3つのおもなデメリットを解説します。
コストや手間がかかる
請求書を郵送する場合、請求書の印刷や封入、投函など作業工程が多く、印刷代や封筒・用紙代、切手代などのコストもかかります。また、それらを1通ずつチェックする必要があり、手間も生じます。
タイムラグが生じる
請求書を郵送する場合、取引先に到着するまでに2~3日ほどタイムラグが生じます。速達を利用することで普通郵便に比べると早く届きますが、電子データほど早くは届きません。速達料金がかかるためコストもかさみます。
請求書の保管スペースが必要となる
請求書は保存が義務付けられています。保存期間は、法人の場合は原則7年間、個人事業主の場合は5年間です。郵送の場合、法人税法や所得税法などで定められたルールにより、前述した期間内は紙の請求書の保存が必須です。そのため、請求書の保管スペースの確保が必要となります。
請求書を郵送以外で送付する方法
請求書は、郵送以外の方法での送付も可能です。ここでは、どのような方法があるのか解説します。
PDFデータをメールで送付する
WordやExcelなどで作成した請求書をPDFに変換し、メールで送付する方法があります。郵送とは違い、封入や投函の手間がなく、コストもかかりません。作成した請求書を即日取引先に送ることもできます。ただし、メールで請求書を送る場合は、取引先に了承を得たうえで送るようにしましょう。
FAXで送信する
請求書を郵送よりも早く、紙形式で送りたい場合、FAXで送信することも可能です。この場合もメール同様、取引先に了承を得てからにします。また、請求書は原則として原本で保管する必要があるため、後日原本を郵送しましょう。
関連記事:請求書をFAXで送るのは問題ない?マナーや送付状の書き方、注意点まで解説
請求業務を効率化する方法
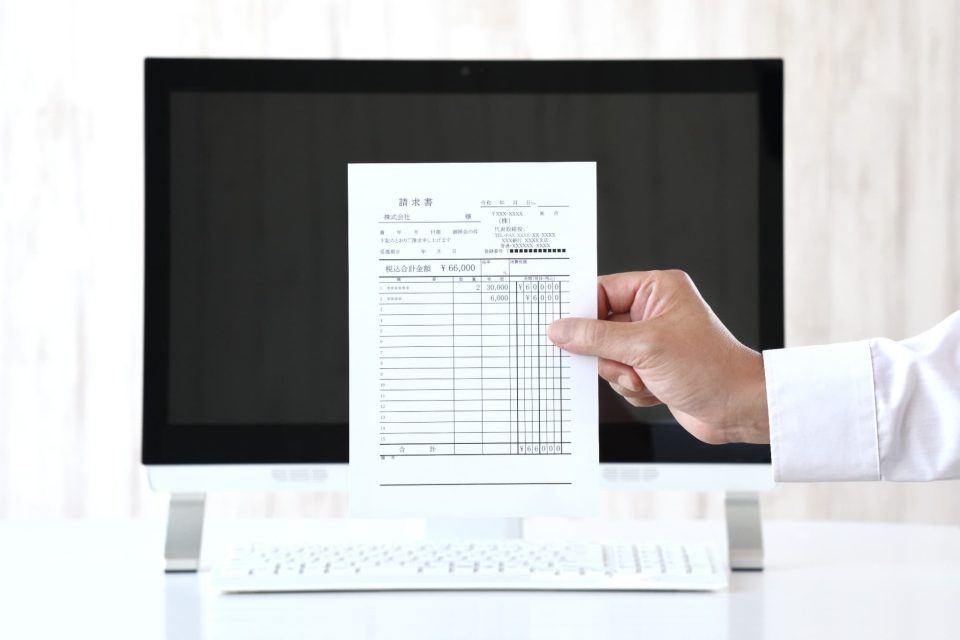
請求業務には時間と手間を要するため、改善したい人もいるでしょう。以下では、効率化する3つの方法を解説します。
電子データをメールで送付する
日常的にメールでやり取りしている取引先であれば、請求書もメールで送付する方がよい場合があります。送る側は印刷代や切手代などの請求書を送るコストを抑えられ、受け取る側はタイムラグが生じることなく請求書を受け取れます。
請求書代行サービスを利用する
請求書代行サービスとは、請求書の作成から郵送の手続きまで請求書に関わるすべての業務を任せられるサービスです。また、郵送前に不備や誤りがないかダブルチェックしたうえで発送してくれるため、ミスを減らせます。費用はかかりますが、請求書業務の手間を省け、他の業務に人員を割けるでしょう。
クラウド型のシステムを利用する
クラウド型システムとは、請求書の作成、送付、保管を一貫して実施できるサービスです。システムを利用して請求書の作成、発行を行うことで即日送付ができます。ネット環境があれば、自社内やリモートワーク先でも利用できます。ただし、あらかじめ取引先に了承を得ておきましょう。
建設業の請求書郵送を不要に!「ANDPAD請求管理」でペーパーレス化を実現
ANDPAD請求管理であれば、建設業における請求書の郵送が不要です。請求書の回収・工事ごとの振り分けから出来高査定や相殺・承認まで、建設業特有の要件を満たしているうえ、電子帳簿保存法にも対応しています。受領した請求書はシステムによって自動で振り分けられるため、手間を大幅に削減できます。
紙の請求書を大幅削減、デジタル化を推進|友渡建設株式会社様
神奈川県の友渡建設では「ANDPAD請求管理」の導入により、紙の請求書を大幅に削減しています。以前は毎月100枚を超える請求書が郵送または手渡しで届き、それを経理担当者が、現場ごとに1枚ずつ振り分けていました。その時間が省けるうえ、自社で請求書を受け取り査定後再び自社まで運ぶ移動時間や、請求書の査定業務にかかっていた手間も減少しています。
参考:請求書の振り分け・査定・保管がその場で完了、作業・移動にかかる時間を大幅削減|友渡建設株式会社 様

まとめ
請求書の郵送方法には多くのマナーと注意点があり、送付前の確認も不可欠です。取引先に到着するまでに時間を要するというデメリットもあります。手間や時間を省くには、請求書代行サービスやクラウド型のシステムの利用がおすすめです。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1のサービスであり、業種を問わず幅広い導入実績があります。使いやすいUI・UXを実現する高い開発力と、年間数千回以上の導入説明会を実施する手厚いサポート体制が特徴です。請求書の送付に加え自動での振り分けも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。