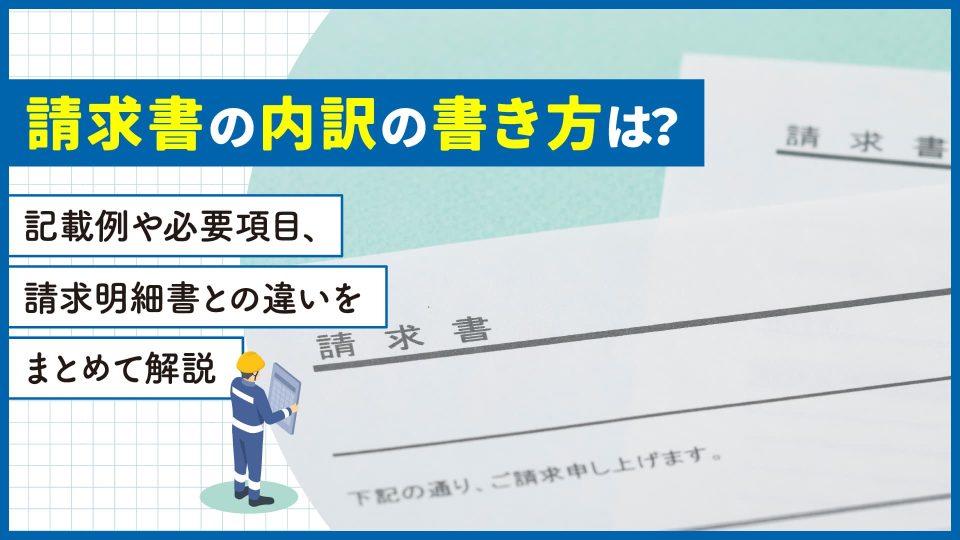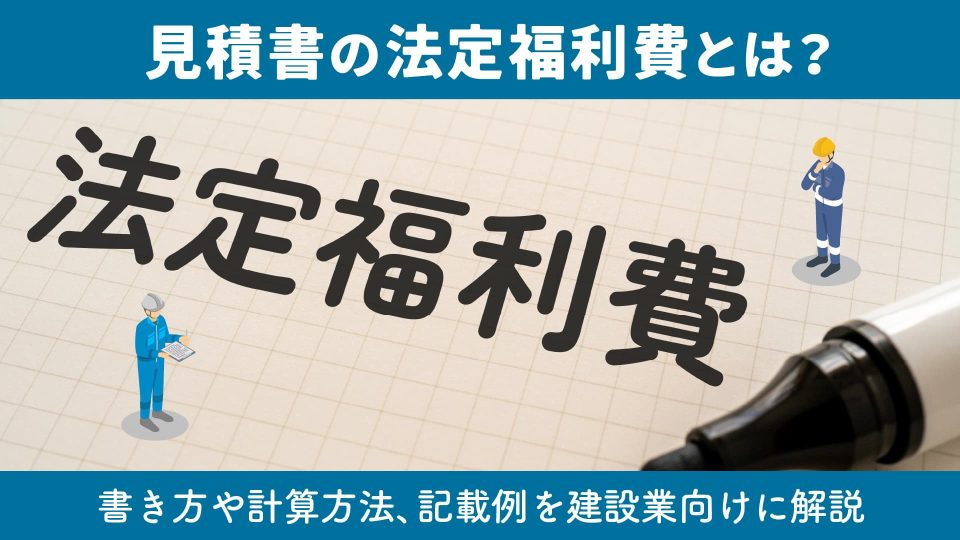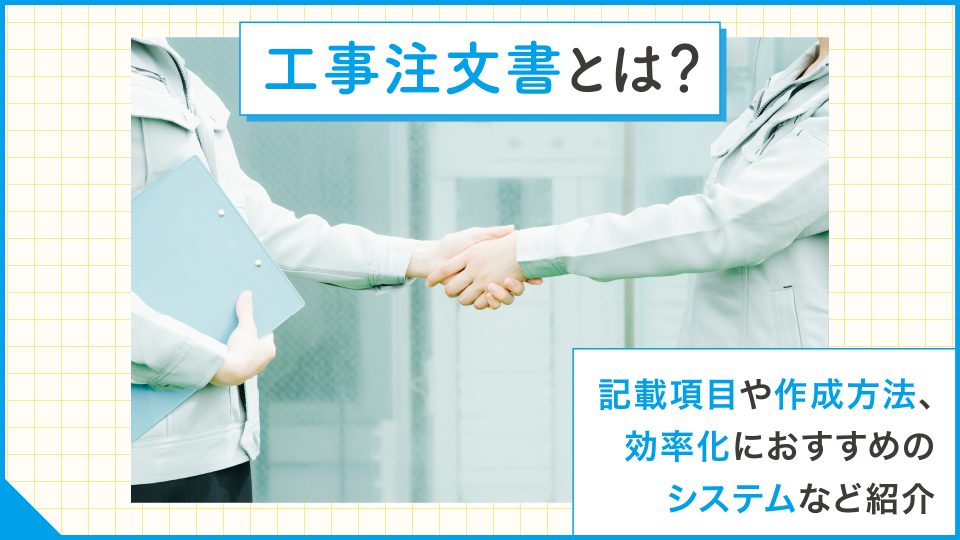請求書の内訳には、取引の内容をはじめ、多くの詳細を記載する必要があります。取引先によって名称の記載が異なるため、事前に正しい書き方を確認しましょう。この記事では、請求書の内訳の書き方や記載する事項、注意点などを解説します。請求明細書との違いも解説するため、ぜひ参考にしてください。
請求書に記載すべき事項とは

請求書には、法的には不要であっても、記載するほうがよい項目があります。ここでは、請求書に記載すべき事項を解説します。
1. 請求者の氏名または名称(発行元)
請求者の氏名や名称には、法人名、もしくは個人事業主の名前を書きましょう。一般的には、題目や日付の下に、氏名や名称を記載します。会社名は、略式の「(株)○○」ではなく、「株式会社○○」と、正しい名称を記載してください。個人事業主の場合は、屋号を併記する場合があります。商慣習として、住所か電話番号を記載してもよいでしょう。
2. 取引年月日
取引年月日には、請求書を作成した日ではなく、商品やサービスを受け取った日にちを記載します。「○○年○○月○○日」と、具体的な日時を記載しなければなりません。西暦と和暦は混在させず、どちらかに統一しましょう。掛け取引の場合、請求書を作成した年月日と、実際に商品やサービスを引き渡す日が異なるため、記載する際は注意が必要です。
3. 取引内容
取引内容には、商品やサービスの具体的な名称を記載します。取引した内容の数量も必要なため、具体的な数字を記載してください。数量が多いものは、「一式」と記載して内容をまとめる場合もあります。たとえば、建築業界の場合、工事に必要な材料をすべて記載せず、「工事名 一式」と記載します。
4. 取引金額
取引金額は、請求する金額を税込みで記載します。3桁ごとにカンマを入れた数字にすると、金額を把握しやすくなります。適格請求書や区分記載請求書では、内税(消費税込)、もしくは外税(消費税別)と、税率ごとに金額を分けなければなりません。請求金額が50,000円の場合、「8%対象10,000円」「10%対象40,000円」などと記載しましょう。
5. 請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称(取引先)
請求書の交付を受ける事業者は、氏名や名称に敬称をつけて記載します。法人に請求する場合は、「株式会社○○御中」とします。個人事業主に請求する場合は、「○○様」と記載しましょう。取引先の状況にもよりますが、住所や部署、担当者名も記載するとよいでしょう。飲食店やタクシー、小売店などは、氏名や名称の省略が可能です。
6. 上記以外に記載するとよい項目
以下の3つは、上記に含まれませんが、請求書に記載したほうがよいでしょう。
- 請求書番号
- 振込先
- 支払期限
請求書番号を記載する場所は、請求書発行者の名称の近くです。振込先は、金融口座の番号です。銀行名と支店名だけでなく、預金種別、口座番号、カタカナ記載の口座名義、銀行コード、支店コードを含めるとよいでしょう。
支払期限や振込手数料の負担者も記載すると、遅延やトラブルを避けられ、取引先とのコミュニケーションがスムーズになります。
関連記事:【例文あり】請求書の催促メールの書き方とは?対処法や5つの催促ポイントも解説
関連記事:請求書における相殺とは?相殺請求書の書き方や仕訳方法、処理の流れなども解説
請求書の内訳に記載する内容とは
請求書の内訳には、以下4つの取引の内容を記載しましょう。
商品名
単価
数量
合計額
取引先が請求内容を把握できるように、それぞれを明確に記載しなければなりません。内訳の書き方に明確な定義はありませんが、法令や税制のルールを守る必要があります。次で、内訳の具体的な書き方を解説します。
請求書の内訳の具体的な書き方
商品名には、商品・サービスの名称や内容を記載します。以下は、内装リフォームを施工した場合の記載例です。
| 商品名 | 数量 | 単価 | 合計額 |
| 内装リフォーム | 2 | 20,000円 | 40,000円 |
上記のように、簡潔に内容を記載してください。商品名は具体的に記載して、透明性を保つことが大事です。時給制の場合は、単価を時間で計算しましょう。請求書管理ソフトやエクセルを使用すると、ミスを防止できるためおすすめです。
請求書に内訳を記載する理由
請求書に内訳を記載する理由は、請求の内容を明確にするためです。請求する側と請求される側が、取引に関する具体的な内容を把握できるため、認識のずれを解消できます。商品やサービスの内容、数量、単価などの詳細を記載し、双方が納得しやすい取引にしましょう。
本来、請求書の内訳は、必ず記載しなければならないという決まりはありません。しかし、円滑な取引やトラブル防止などにつながるため、具体的な内容を記載するとよいでしょう。
請求書に内訳を記載する際の注意点
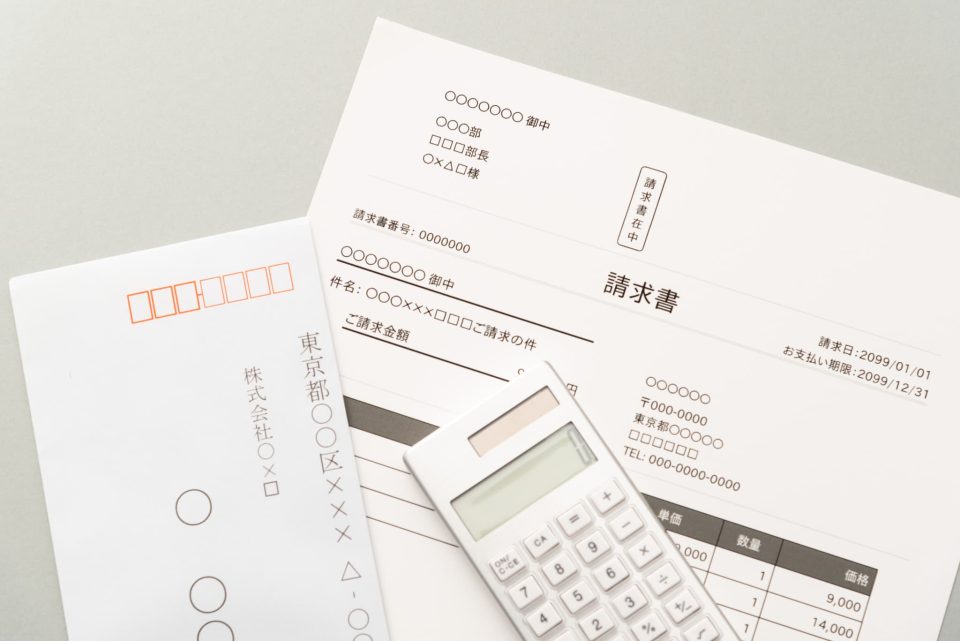
請求書の内訳を間違えると、トラブルにつながるリスクがあります。ここでは、内訳を記載する際の注意点を解説します。
わかりやすく明確に記載する
請求書の内訳は、業務内容をわかりやすく明確に記載する必要があります。取引先との請求書のやり取りが多く、直接業務に関わらなかった経理担当等が内容を把握していない可能性があるためです。誰でも請求書の内容がわかるように、一目で取引内容を把握できるようにしましょう。商品・サービスの内訳を明確にすることで、お互いの認識のずれを防止できます。
変更した内容も記載する
請求書の内訳は、取引内容を証明するものであるため、変更後の内容を明確に記載しなければなりません。請求書の内容は、途中で変更になる場合があります。たとえば、通常と異なるイレギュラーな対応があったり、担当者が変更したりするなどです。単価の変更をする場合は、変更後の取引内容を正確に記載しましょう。
請求書と請求明細書の違い
請求書には、取引の基本的な情報が記載されています。ここでは、請求書と請求明細書の違いを解説します。
請求明細書とは
請求明細書とは、内訳の詳細が書かれた補足資料です。金額の内訳を詳細に記載することで、取引の詳しい内容を把握できます。請求明細書を、請求書と一緒に送付することで、取引先が請求の詳細を確認しやすくなります。
請求書は、取引先に対して請求額の支払いを促すための書類です。取引の内容がわかれば、請求書のみを作成すれば請求には問題ありません。取引先から要望がある場合のみ、請求明細書を作成しましょう。
請求明細書を作成するケースとは
取引の内容がわかりにくい場合、請求明細書を作成する必要があります。たとえば、記載項目が多く、一定期間をまとめていたり、内容が包括的になっていたりするケースです。具体的な請求内容をイメージしにくい場合は、後で取引の内容を調べなければなりません。
請求明細書を作成しておけば、請求の漏れを発見しやすくなります。取引の内容がわかりにくくなりそうな場合を想定して、事前に作成するとよいでしょう。
請求明細書の内訳の記載内容
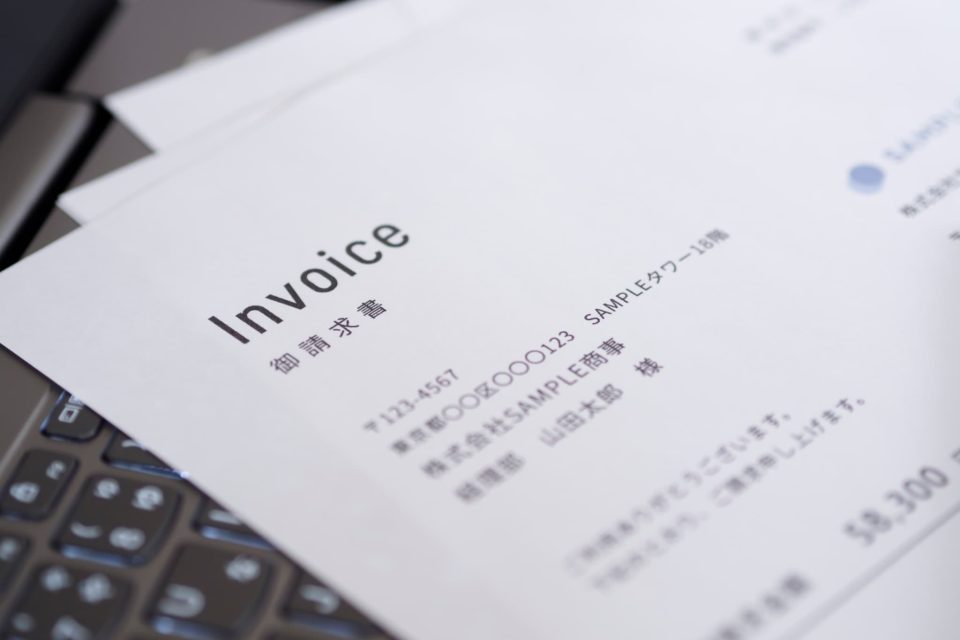
請求明細書には、商品の名称や種類、数量、単価、消費税を含んだ請求の合計額など、具体的な取引の内容が記載されています。書き方には明確なルールがなく、商品の詳細が記載されていれば問題ありません。ただし、ほとんどの企業が同じ書き方で作成しています。
請求明細書は、内訳書として、取引先に対し売上の情報を明確にする目的で作成されます。請求書と同じ金額であることを確認し、発行することが必要です。請求明細書に合計金額を記載しないケースもあるため、取引先のルールを確認しましょう。
工事ごとの請求書の内訳も見やすく管理!「ANDPAD請求管理」でペーパーレス化
「ANDPAD請求管理」は、建設業界に特化した請求管理を実現するツールです。請求書受領から査定業務、書類の保管までを電子化し、ペーパーレス化の推進につなげられます。電子帳簿保存法にも対応し、毎月の請求管理業務の大幅な効率化が可能です。明細書作成にかかる転記作業や工事ごとの整理といった手間も削減でき、バックオフィス業務の負荷を大きく軽減します。
組織全体で万全の体制を構築しており、充実したサポート体制によって導入や運用支援にも注力しています。お電話やチャットでも、直接ご質問ができ、操作方法をはじめとした困り事が発生した場合でも、すぐにご相談いただけます。
バラバラだった内訳情報を一元管理、脱Excelでミスも削減|友渡建設株式会社様
友渡建設株式会社様は、「ANDPAD請求管理」を導入し、紙の請求書を大幅削減、デジタル化を推進しました。紙や手書き作業が不要になり、ミスの削減や業務効率の向上などにつなげています。
また、現場で請求書の確認や査定業務を行い、請求査定のための移動を短縮し、業務の時間や負担も軽減しています。今後はDX化を推進し、関係者全員が効率よく働ける環境づくりに、挑戦するとのことです。
参考:請求書の振り分け・査定・保管がその場で完了、作業・移動にかかる時間を大幅削減|友渡建設株式会社 様

まとめ
請求書の内訳には、氏名や商品・サービスの名称、単価、数量などを記載します。一目で内容が把握できるように、詳細を明確にすることが必要です。請求書作成のテンプレートを活用し、ミスを防止すると、請求のトラブルを防止できるためおすすめです。
「ANDPAD(アンドパッド)」は、クラウド型の建設プロジェクト管理サービスです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。直観的で使いやすいUI・UXを実現する開発力や、年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートが特徴です。ぜひ利用をご検討ください。