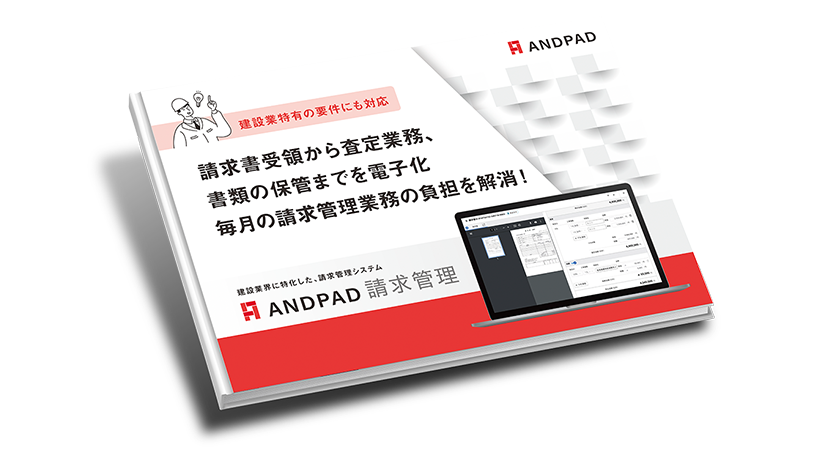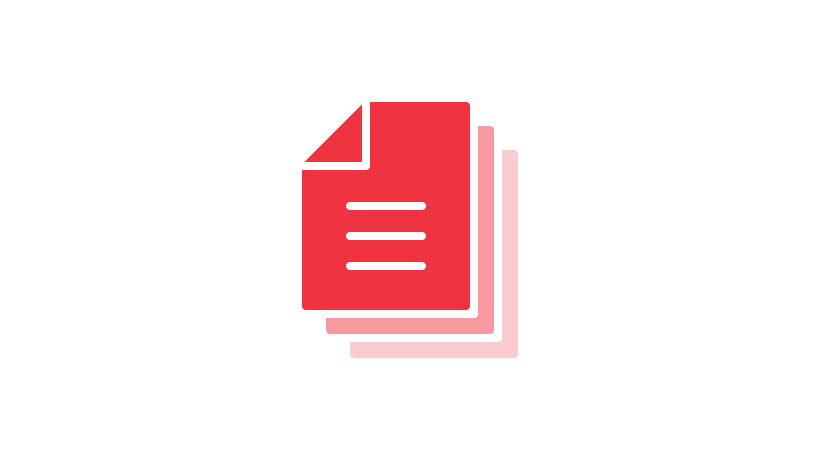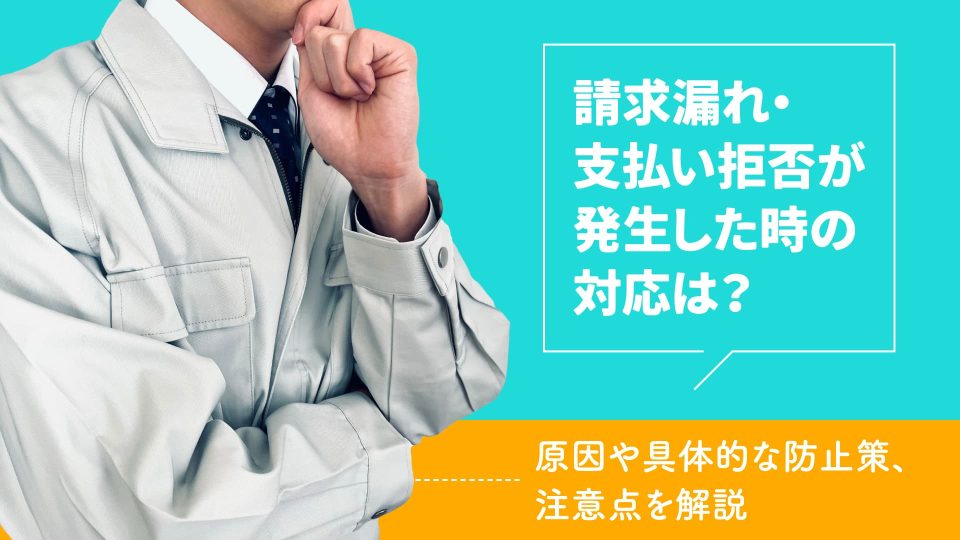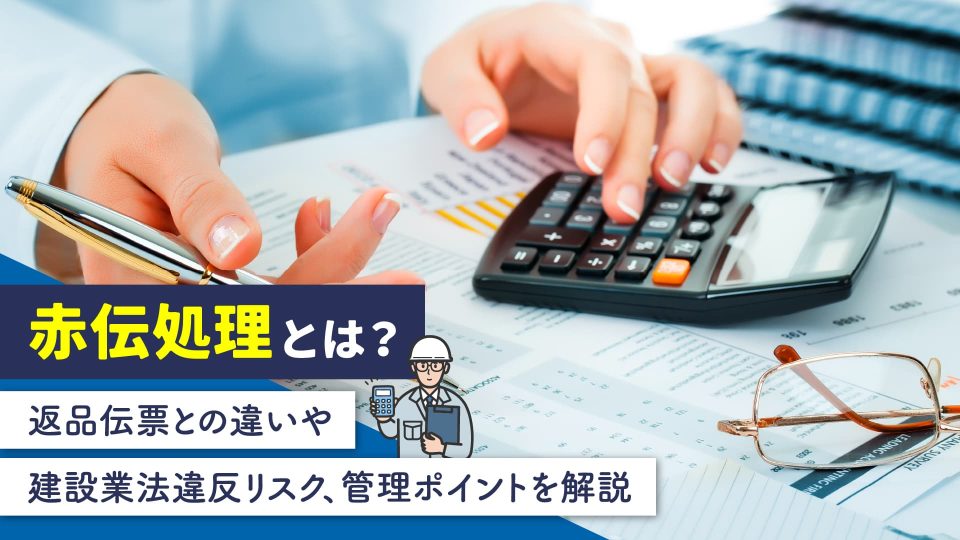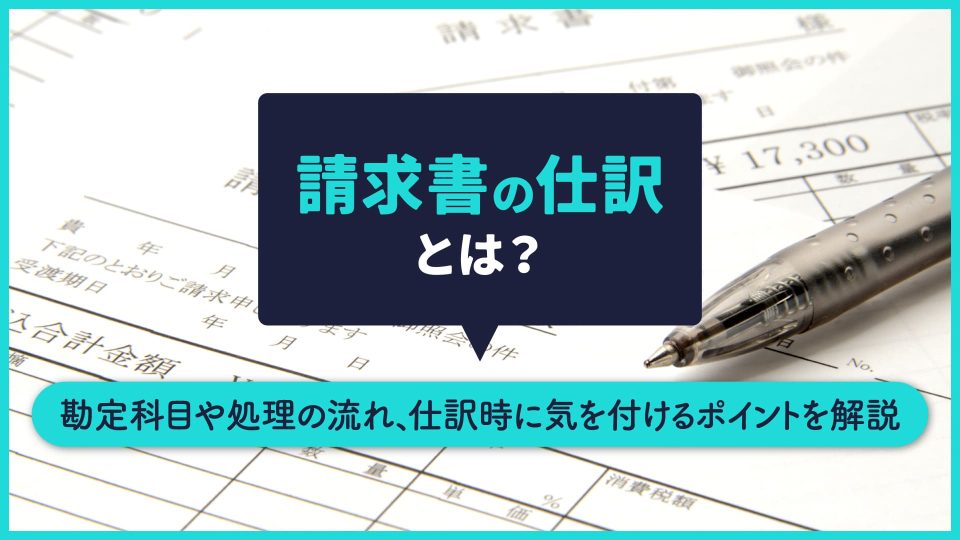請求漏れやそれに伴う支払い拒否が発生した際は、どのように対処すればよいのでしょう。また、そもそも請求漏れを起こさないためには、どのような対策が必要なのでしょう。この記事では、請求漏れや支払い拒否によるリスクをはじめ、その原因や対策について解説します。請求漏れにはさまざまなリスクがあるため、ぜひ参考にしてください。
請求漏れ・支払い拒否のリスクと影響

請求漏れ・支払い拒否のリスクや影響について解説します。キャッシュフローへの影響や未払いのリスクがあることについて解説するため、参考にしてください。
企業の信用低下・キャッシュフローへの影響が考えられる
請求漏れや支払い拒否により、企業の信用が低下したりキャッシュフローへ影響が及んだりします。手元にある現金・預金が減少することによって、事業に必要な資金が不足します。場合によっては、他の支払いができないリスクもあるでしょう。
速やかに代金を回収しなければ、事業に必要な資金が確保できないだけでなく、最悪の場合、帳簿上は黒字であっても、手元に現金がないために倒産する「黒字倒産」になりかねません。
未払いリスクがある
請求漏れによって、取引先から代金が支払われない恐れがあります。会社では請求書をもとに手続きを進めます。請求書がなければ、支払いの手続きが進められません。そのまま未払いに陥る可能性があります。
請求漏れ・支払い拒否が発生する主な原因と背景
請求漏れ・支払い拒否が発生する原因として、請求書の作成忘れ・投函忘れといったヒューマンエラーが考えられます。
自社でのヒューマンエラーによる請求ミス
請求漏れや支払い拒否が発生する原因として多いのは、社内でのヒューマンエラーです。請求書の作成を忘れていた、確認が漏れていたなど、人為的なミスが発生する可能性があります。請求すべき取引に漏れがあるケースや、電子メールにファイルを添付するのを忘れるケースも考えられます。
請求書の作成忘れ・投函忘れ
請求書の作成業務そのものを忘れることがあります。月末や月初などは、通常業務で忙しくタスクが漏れる可能性があります。商品やサービスが提供されてから請求書が必要になるまで期間が空く場合も、作成し忘れる可能性が高まるでしょう。
紙の書類でやりとりしている場合、作成済みの請求書を投函し忘れることもあります。チェックフローを見直したり、リマインド機能を活用したりする対策がおすすめです。
請求書の添付忘れ
請求書を作成したものの、メールで送付する際に添付し忘れることもあります。請求書をPDFやWordなどで作成する場合、添付忘れが発生しやすくなります。メールの送付自体を忘れることもあるでしょう。リマインド機能を活用しましょう。
取引先による要因
支払い拒否の要因として、以下2つが挙げられます。
支払えるけれど支払いたくないケース
支払いたくても支払えないケース
1つ目は、宛先に誤りがあった、郵送途中で何らかのミスがあったというケースです。催促をしても、取引先にはそもそも請求書が届いていないため、支払いを拒否されてしまいます。このケースは請求漏れに気付きにくく、そのまま長期間放置すると、支払いを拒否される可能性もあります。
2つ目は、取引先が財政的に苦しいことから、支払いたくても支払えないケースです。いつ支払いができるのかを取引先と話し合い、改めて支払い予定日を決めなければなりません。話がまとまらないと、最終的に法的な手続きが必要になる場合もあるでしょう。
請求漏れ・支払い拒否が発生した場合の対応
請求漏れ・支払い拒否が発生した場合、取引先への連絡や書面で催促するといった対応が必要です。それぞれの対応について解説します。
関連記事:未払い請求が発生した時の催促方法とは?例文付きで催促・督促状の書き方も解説
取引先への連絡をし、支払い依頼をする
請求漏れに気付いた時点で、速やかに事実確認をしてください。取引内容や請求対象の項目を確認したのち、入金されているか調べましょう。取引先との関係によっては、請求書を送付する前に入金されている可能性があり、入金に気付かず催促しては失礼です。
請求漏れがあり、入金も確認できない場合は、速やかに取引先に連絡します。請求漏れを謝罪し、支払いを依頼しましょう。
関連記事:【例文あり】請求書の催促メールの書き方とは?対処法や5つの催促ポイントも解説
書面での督促・法的措置を検討する
支払いが履行されない場合、書面での督促状を作成します。督促状の発送は時効の中断事由に該当し、時効期間の進行を6か月間止められます。6か月以内に裁判上の請求を行えば、売掛金の時効が更新されます。
督促状を送っても支払いがない場合、内容証明郵便で催告書を送付しましょう。催告書とは、債務の履行を促す最終通告であり、支払期限内の履行がなければ法的措置をとる意思を明記する書類です。
請求漏れが発生した際に送るお詫びメールの内容
請求漏れが発生した際は、速やかにお詫びのメールを送付しましょう。メールに記載する本文の内容は、以下の通りです。
- 冒頭は挨拶の言葉
- 請求漏れが生じた経緯の説明
- 発行日や送付日
- 今後の改善策や再発防止策
- お詫びの言葉
メール件名は、お詫びのメールであることがひと目で分かる「【お詫び】請求書の遅延につきまして」などと記載しましょう。
請求漏れの注意点

請求漏れにおいて、請求する側と請求される側、どちらにとっても注意すべきポイントがあります。ここでは支払い義務や時効について解説します。
請求漏れが発生しても支払い義務はある
請求書が発行されなくても、取引が成立した事実が明らかであれば、支払い義務が発生します。そもそも請求書とは、取引内容を確認し、金額や支払期日についての認識の相違を防ぐために発行される書類ですが、法的な発行義務はありません。
そのため売買契約を締結し、取引を行った時点で支払い義務は発生します。請求書が発行されなかった場合でも、支払い義務は存在し、取引先は代金を支払わなければなりません。
請求漏れは5年で時効になる
請求漏れがあっても、先方には支払い義務があります。ただし、5年経過すると民法166条により売掛債権は時効消滅します。請求漏れに気付いて請求書を発行しても、支払期限を過ぎて5年間経過すれば債権は消滅するため、注意してください。
債権を消滅させないためには、「時効の完成猶予」または「時効の更新」が必要です。「時効の完成猶予」とは、売掛債権に一定の完成猶予事由が発生した場合に、時効の完成が一定期間先延ばしになる制度です。
請求漏れを発生させない具体的な防止策
請求漏れを防ぐ手段として、管理システムを導入する、ダブルチェック体制にするなどの方法が挙げられます。どのように対策すべきか、解説します。
関連記事:請求書における相殺とは?相殺請求書の書き方や仕訳方法、処理の流れなども解説
請求管理システムを導入する
手作業による請求業務が原因で請求漏れが発生する場合、請求管理システムの導入を検討することが推奨されます。請求管理システムは、請求書の作成から発行、入金確認などを行えるシステムです。
自動化されたシステムは手作業による入力や金額計算を自動化し、締め日ごとの請求データを自動的に作成することが可能です。請求管理システムの導入により、請求業務の効率化が図れるとともに、人的ミスを減少させ、請求漏れを防止できます。
チェックリストを作成しダブルチェック体制を整える
請求書の発行には、売上データの入力、請求書の作成と印刷、請求書の発送作業などが必要です。業務の各段階を抽出し、チェックリストとして整理することで、作業の抜け漏れを防ぐことができます。チェックリストを複数の人や部署で共有することで、ミスの防止効果がさらに高まります。
関連記事:請求書に収入印紙は原則不要?必要なケースや注意点・金額・貼り方を解説
ナンバリングする
請求書には全てナンバリングを施し、取引と請求を一括管理します。書類に同一の番号を付与することで、全ての書類を関連付けた一括管理が可能です。データ管理が徹底され、業務が効率化されます。
ナンバリングによる書類の一括管理は請求漏れを防止するだけでなく、取引先とのコミュニケーションをスムーズにします。取引先からの問い合わせに対しても、請求書の番号を基に迅速に見積書や納品書を確認し、正確な情報を提供できます。
スケジュール管理など社内ルール・業務プロセスを見直す
請求作業は1人で行わず、複数人でチェックする体制を導入します。業務が属人化すると、1人の従業員が全ての作業を担当するため、請求漏れが発生しやすくなるでしょう。属人化によるリスクとして、担当者の急な欠勤や退職によって業務が滞る可能性があります。
請求業務においては、作業の各段階で複数人がチェックするフローを確立し、ミスが起こりにくい体制を整えることが重要です。
請求管理システムを選定する際のポイント

請求書管理システムを選定するポイントは、以下の3つです。
- 既存システムとの連携の可否
- 業務範囲の確認
- セキュリティ対策の水準
特に、請求管理システムは、単に請求書を管理するものから、請求後の入金履歴までを一元管理できるシステムもあります。自社に必要な業務範囲を明確にしたうえでシステムを選びましょう。
建設業の請求管理業務を効率化するなら「ANDPAD請求管理」
建設業界に特化した「ANDPAD請求管理」とは、請求書の回収や工事ごとの振り分けから、出来高査定や相殺、承認まで建設業特有の要件を満たした請求管理システムです。電子帳簿保存法にも対応しているため、毎月の請求管理業務を大幅に効率化が可能です。
まとめ
請求漏れが発生すると、キャッシュフローへ影響を及ぼすだけでなく、場合によっては取引先から支払い拒否される可能性もあります。チェック体制を見直す、請求書にナンバリングするといった対策が必要です。
請求漏れを防ぐには、請求管理システムの導入がおすすめです。どのようなシステムを導入すべきか悩んでいる方は、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」をご検討ください。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。誰でも使いやすい画面を意識して開発されており、導入支援にも注力しているのが特徴です。気になった人は、以下よりお気軽にお問い合わせください。