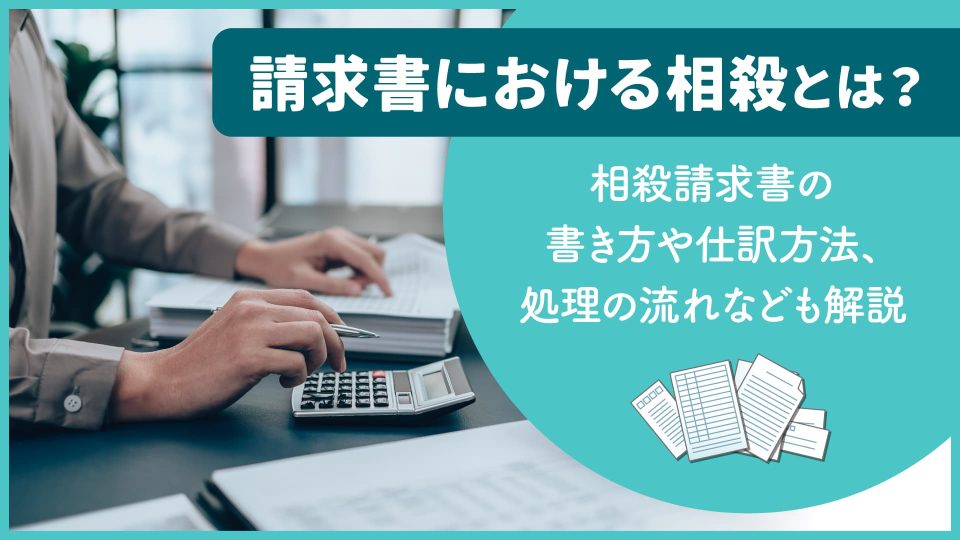相殺請求書は、企業間取引で債権と債務を相殺し、支払金額を減額する方法です。インボイス制度の導入により、適切な仕訳や処理方法には注意が必要です。この記事では、相殺処理の流れや書き方、メリット・デメリットを解説します。ぜひ役立ててください。
相殺請求書とは何か
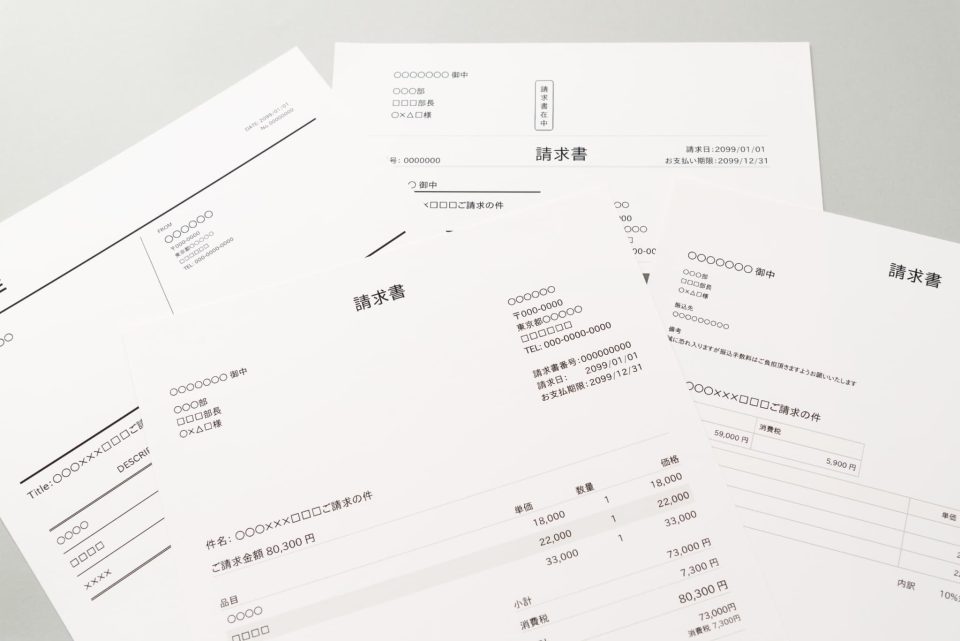
相殺請求書とは、取引先との債権と債務を相殺し、実際の支払いを減額するための請求書です。相殺請求書を詳しく解説します。
請求書における相殺とは
請求書における相殺処理とは、売掛金と買掛金を相互に差し引いて帳消しにする手続きです。実際の支払い額が減り、手数料や手間が軽減されます。返金や返品、値引きなどを反映させる際にも相殺処理が行われます。請求書には内容を正確に記載することが重要です。
請求書の相殺処理が可能なケース
取引先との間で売掛金と買掛金が発生している場合に、請求書の相殺処理が可能です。適格請求書を発行した場合にも、請求額を相殺できます。相殺処理は基本的に双方の合意が必要であり、事前に相手から許可を得ることが重要です。
条件を満たす場合は、弁済期を過ぎた債権に限り合意なしでの相殺も可能ですが、信頼関係を守るためにも、常に合意のうえで相殺処理を行いましょう。
相殺請求書に記載すべき項目
相殺請求書には、相殺する債権、債務の詳細、相殺額、取引先情報などの記載が必要です。記載すべき項目を解説します。
一般的な請求書に必要な記載項目
一般的な請求書には、発行日、請求金額、振込先情報、税率ごとの消費税額などを記載します。相殺処理を行う場合、相殺する案件の内容や金額、相殺前後の金額の明記も必要です。相殺請求書は、適格請求書に必要な項目を網羅し、相殺金額をわかりやすく記載することで、取引先に正確に伝えられます。
関連記事:請求書の内訳の書き方は?記載例や必要項目、請求明細書との違いをまとめて解説
相殺処理の際に必要な記載項目
相殺処理を行う請求書には、相殺前の請求金額、相殺金額、相殺後の実際の請求額を明記し、取引内容に応じて税率ごとの消費税額も記載します。インボイス制度に対応した請求書発行には、適格請求書に必要な項目を網羅することが求められます。
相殺請求書の書き方のポイント

相殺請求書の書き方では、相殺前後の金額や取引内容を明確に記載することが重要です。書き方のポイントを解説します。
相殺前と相殺後の金額、相殺内容を明記する
相殺請求書には、相殺前の取引金額、相殺金額、相殺後の支払金額を明確に記載します。記載場所は自由ですが、相殺前の金額の下段に「相殺」の項目を設け、相殺額と支払金額を記入したり、請求書の備考欄を活用したりする方法が主流です。
請求書を2枚に分けて、1枚に相殺前の金額、もう1枚に相殺後の金額を記載する方法もあります。取引先にとって理解しやすい形式を採用しましょう。
相殺金額の表記には「-」「▲」を使用する
相殺金額を記載する際には、「-(マイナス)」や「▲(黒三角)」、「△(白三角)」を使用し、差し引く金額であることを明確に示します。商習慣として広く使用されており、請求書で相殺を行う場合には、取引先に誤解なく伝えるために重要です。
記載方法に関する明確な法令はありませんが、一般的には「-」や「▲」、「△」の使用が推奨されています。取引先から指定された記載方法がある場合は、それに従うようにしましょう。
請求書の相殺処理をするメリット
請求書で相殺処理を行うことで、支払い手続きが簡略化され、コスト削減につながります。請求書の相殺処理をする主なメリットを解説します。
キャッシュフローの安定につながる
相殺処理を行うことで、現金のやり取りが減り支出を抑えられます。キャッシュフローが安定し、手元資金を確保しやすくなります。振込手数料や事務処理の手間も軽減され、金銭管理の効率化が図れるでしょう。相殺処理は、経営資源の最適化にも寄与するため、企業にとって重要なメリットがあります。
コスト削減(収入印紙代・振込手数料など)が可能
振込手数料や送金手数料が不要になり、企業の経費削減が可能です。入金確認や帳簿付けにかかる手間を減らすことで、人件費の削減にもつながります。収入印紙代や送金業務の負担も軽減され、コスト削減が期待できます。
未払いリスクの軽減・自社の損失防止が可能
未回収の売掛金や支払い遅延のリスクを軽減できます。掛け取引では、貸し倒れのリスクが常に生じるため注意が必要です。相殺処理により金銭のやり取りを減らすだけでなく、売掛金が回収困難な場合でも自社の損失を最小限に抑えられます。貸し倒れリスクを軽減し、キャッシュフローを守ることが可能です。
請求書の相殺処理をするデメリット
請求書の相殺処理には、取引先との合意が必要であり、手続きが煩雑になるデメリットがあります。請求書の相殺処理をする主なデメリットを解説します。
経理担当者の事務負担・手間が増加する
相殺処理を行うと、売掛金と買掛金を担当する経理担当者の連携が必要となり、業務の負担が増加します。相殺の件数が増えると、確認作業や調整に時間がかかり、事務負担が増す可能性があるでしょう。
資金繰りが一時的に苦しくなる可能性がある
相殺処理を行うと、資金繰りに影響を与える可能性があります。予定していた入金がなくなるため、キャッシュフローが一時的に悪化することもあります。
一方で、現金支出が減ることでキャッシュフローが安定するという面もあり、相殺の影響は取引内容や企業の資金状況によって異なります。相手方の資金繰りにも影響が及ぶ可能性があり、事前に相手の了承を得ずに相殺を行うと、トラブルにつながるでしょう。
自社の資金繰りが厳しい状況では、相手から相殺を提案された場合に応じない選択肢も視野に入れる必要があります。一方的な相殺はトラブルの原因にもなり得るため、事前に十分な調整と合意形成を図りましょう。
相殺請求書を発行する際の注意点
相殺請求書を発行する際は、正確な金額や相殺内容を明記し、双方の合意を得ることが重要です。発行時の主な注意点を解説します。
取引先の承諾を事前に得る(双方の合意が必要)
相殺処理を行う際は、事前に取引先の承諾を得ることが重要です。双方の合意がない、一方的な相殺処理はトラブルの原因となる可能性があります。商慣習として、相手の同意を得てから進めることが推奨されています。
相殺領収書の発行が必要な場合がある
取引先から相殺領収書の発行を求められる場合があります。金銭の授受がないことを証明するために重要な書類ですが、発行義務はありません。取引先との合意に基づいて発行し、適格請求書としての要件を満たすことが求められます。
関連記事:請求書に収入印紙は原則不要?必要なケースや注意点・金額・貼り方を解説
第三者が見て相殺内容が明確にわかるものにする
第三者が見ても相殺内容が明確にわかるようにしましょう。請求書には、相殺する案件の内容、相殺金額、相殺した事実を記載し、相殺金額には「△」や「▲」または「-(マイナス)」を付けます。取引先からの指定があれば、従うことが重要です。相殺処理後は帳簿に記録し、後日確認できるように保管することが大切です。
請求書の相殺処理の仕訳の方法
請求書の相殺処理では、仕訳を適切に行うことが重要です。仕訳の方法を解説します。
相殺仕訳の基本ルールと仕訳例
相殺仕訳の基本ルールでは、債権と債務を相殺する際に、適切な会計処理が求められます。たとえば、A社とB社の間で、A社がB社に対して20万円の売掛金を有しており、同時にB社もA社に対して15万円の売掛金を有している場合、相殺処理を行うとA社は差額の5万円を支払う必要があります。
仕訳計上の際には、売掛金や買掛金をそれぞれ借方と貸方へ記載することが必要です。相殺した旨を摘要欄に記載し、相殺後の処理も正確に行います。税額計算や消費税の適正な処理が重要です。
請求書で相殺処理をする際の基本の流れ
請求書で相殺処理を行う際は、事前に相手方と合意し、相殺内容を明確に記載します。基本の流れを解説します。
取引先の了承を得る
法律上、一方的な相殺も可能ですが、ビジネス上は双方の合意を得てから処理を行いましょう。無断で相殺を実施すると、取引先の資金繰りに影響を及ぼし、信頼関係を損ねる恐れがあります。トラブルを避けるためにも、事前にしっかりと連絡し、合意を得ることが必要です。
相殺請求書を発行する
取引先の了承を得た後は、相殺請求書を発行します。全額相殺の場合でも、取引内容を明確にするため、「お振込は不要です」と記載した請求書の作成が必要です。相殺請求書の記載方法として、金額欄に相殺前の金額、相殺金額、相殺後の金額を記入する方法や、備考欄に詳細を記載する方法などがあります。取引先と確認しながら、わかりやすく記載しましょう。
相殺領収書を発行・交換する(必要な場合のみ)
相殺処理が完了したら、必要に応じて相殺領収書を発行します。相殺領収書は、買掛金の支払い義務が消失したことを証明するための書類です。発行義務はありませんが、取引内容を明確にするために必要な場合があります。一方が発行すれば、もう一方も同様に発行します。収入印紙は基本的に不要ですが、金銭を受領した場合は収入印紙が必要です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)における相殺処理のポイント
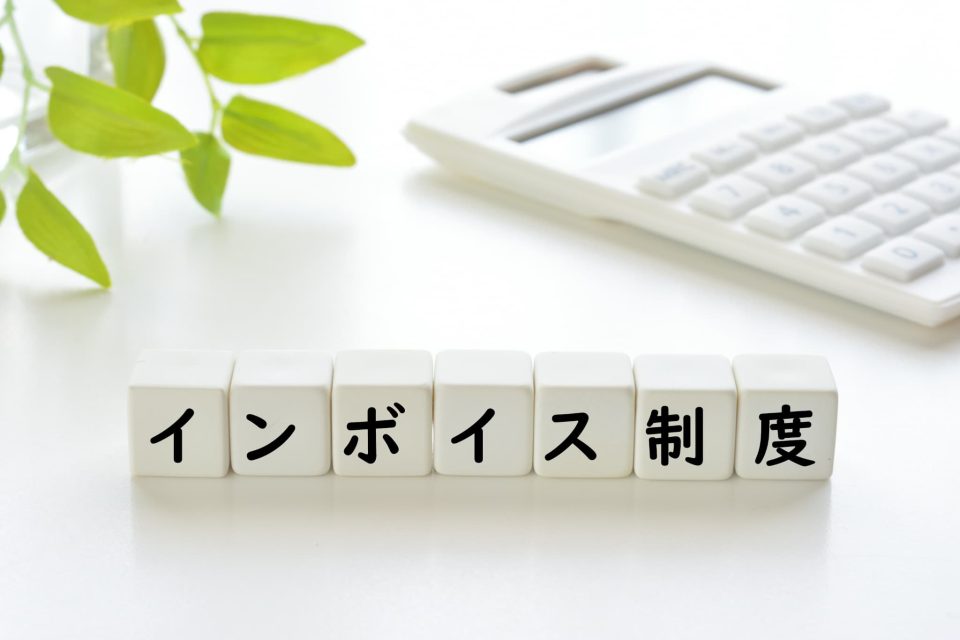
インボイス制度において相殺処理を行う際は、適格請求書の対応が必要です。相殺領収書には、税抜・税込価格や税率、消費税額、インボイス事業者の登録番号を記載し、相殺前後の金額も明記します。仕入税額控除を受けるためには、相殺前の金額の記載が重要です。
立替経費などを査定金額から相殺できる「ANDPAD請求管理」がおすすめ
ANDPAD請求管理は、建設業特有の請求管理業務を効率化するシステムです。請求書の回収や工事ごとの振り分け、出来高査定や立替経費の相殺、承認までを一元管理します。電子帳簿保存法にも対応し、手作業の入力や書類保管における手間の削減が可能です。現場からも査定業務が可能になり、業務分散し、経理や総務の負担も軽減します。
毎月の請求業務を大幅に効率化でき、導入後のサポートも充実しています。
ANDPAD請求管理の導入事例|友渡建設株式会社様
友渡建設株式会社様は、ANDPAD請求管理を導入し、請求書のデジタル化と業務効率化を実現しています。従来、毎月100枚以上の請求書を、手作業で管理や振り分けを行っていました。
ANDPAD導入後は、現場監督は移動せずにオンラインでの査定が可能となり、経理担当者も、瞬時に情報を呼び出せるようになり、検索や処理の迅速化につながっています。デジタル化により現場ごとに振り分けるなどの作業が短縮され、業務効率が大きく向上しました。
参考:請求書の振り分け・査定・保管がその場で完了、作業・移動にかかる時間を大幅削減|友渡建設株式会社 様

まとめ
相殺請求書は、企業間の債権と債務を相殺して支払金額を減額する手段です。相殺処理には事前の取引先の合意が必要で、インボイス制度に対応した適切な記載が求められます。コスト削減やキャッシュフローの安定がメリットですが、経理負担の増加や資金繰りへの影響は否めません。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1の実績を誇ります。使いやすいUI・UXを実現する開発力をもち、利用者がスムーズに操作できるように設計されています。年間数千回を超える導入説明会を開催し、手厚いサポート体制も特徴のひとつです。ぜひお問い合わせください。