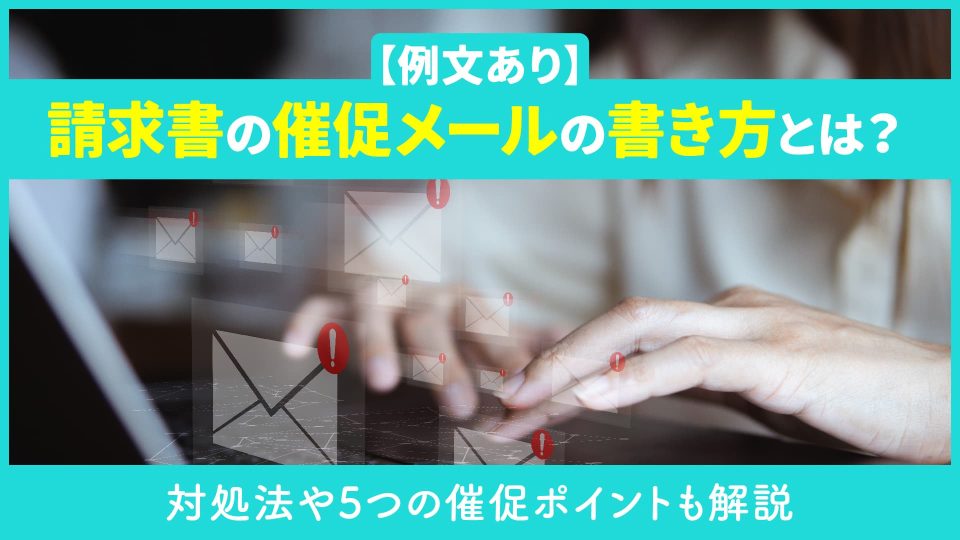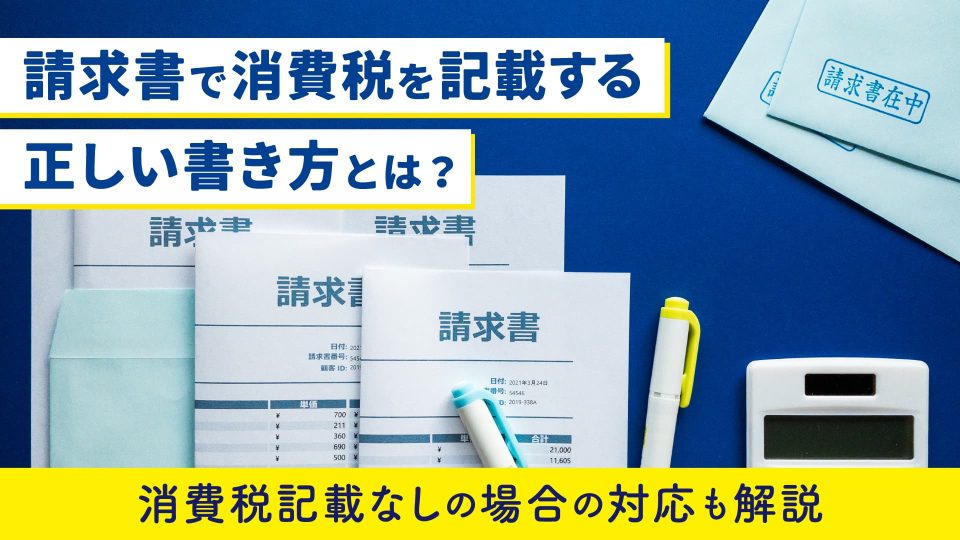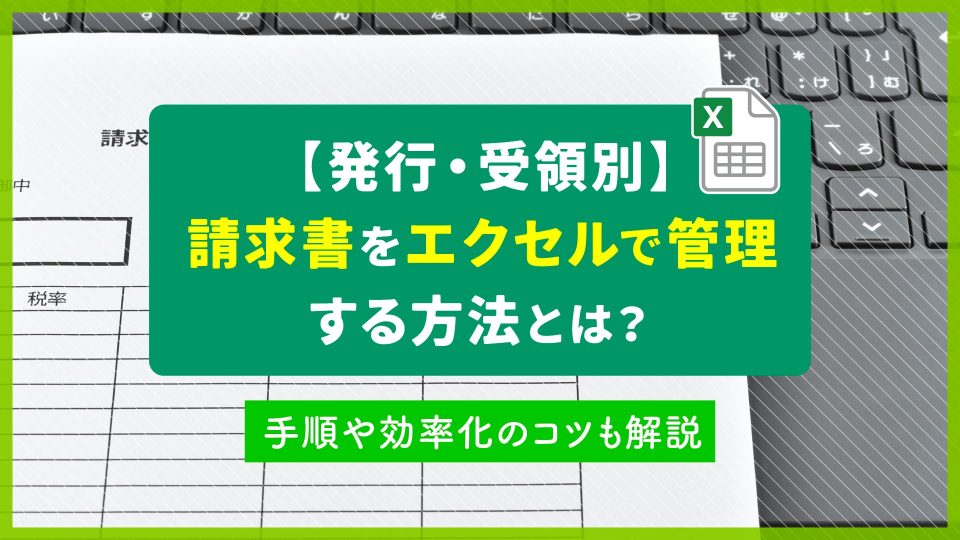締切の期日になっても、請求書が届かず困っている担当者もいらっしゃるでしょう。請求書が届かない場合、取引相手に催促することは問題ありません。この記事では、請求書をメールで催促する際の書き方や対処法、メールの文章を作る際のポイントを解説します。具体的な例文も掲載しているため、ぜひ参考にしてください。
請求書の催促メールが必要な場合
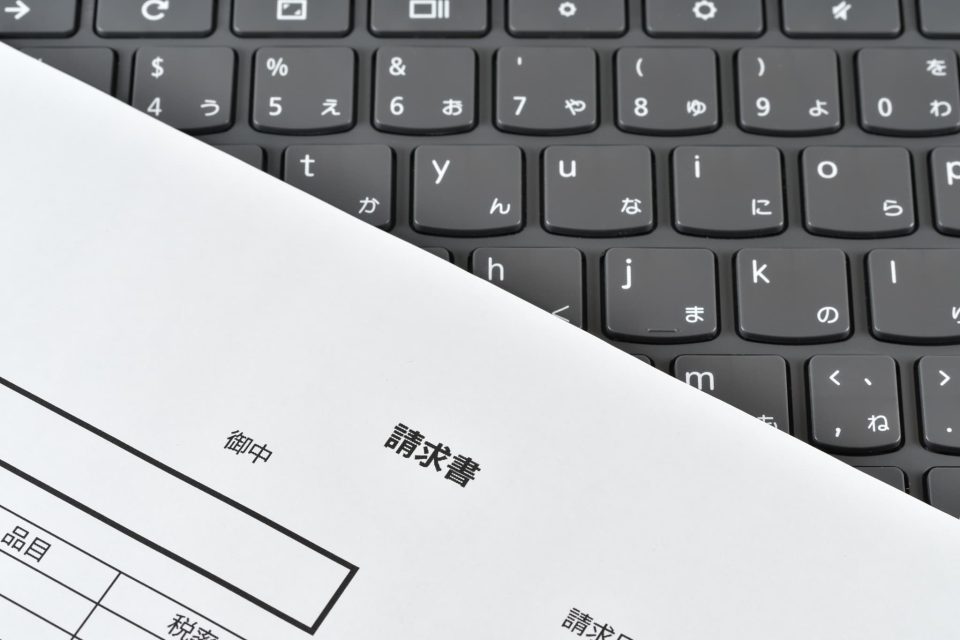
請求書の発行は法律で義務付けられてはいないものの、取引の記録を残し支払いを円滑に進めるために重要です。税務調査や会計処理において取引内容や支払状況を証明するために請求書が必要とされています。
支払期限が近づいているにもかかわらず請求書が届かない場合、取引先に直接連絡し発行を催促する必要があります。催促の方法としては、電話やメールを使用することが一般的です。請求書が届かない場合の対処法については後述します。
請求書が届かないときの対処法は?
請求書が届かない場合、送付を催促する必要があります。催促する方法は、メールか電話、どちらでも構いません。それぞれの方法や支払い義務について解説します。
メールで催促する
支払期限まで時間がある場合、メールで催促すると良いでしょう。メールは電話と異なり、双方の都合の良い時間に対応できるため、取引先に負担をかけずに済むからです。メールの冒頭で請求書がまだ届いていないことを伝えましょう。
電話で催促する
メールでの催促後、数日経過しても連絡がない場合や急ぎの場合には、電話での催促が選択肢となります。電話ではリアルタイムでのコミュニケーションが可能であり、即座に情報を整理できる利点があります。電話でのコミュニケーションでは声のトーンや反応が伝わるため、丁寧な態度を心がける必要があります。
取引先の都合により、請求書の発送に時間がかかりそうな場合は事前にメールやFAXでの送付を依頼すると良いでしょう。
請求書がなくても支払い準備はする
メールや電話で連絡が取れない場合は、一旦催促を中断し、支払いの準備を進めましょう。請求書が届かなくても法的には支払い義務があります。下請法によれば、下請代金の支払期日は「商品やサービスを受けた日から起算して60日以内」と定められています。そのため、請求書の有無や催促の結果に関わらず、支払いの準備を進める必要があります。
請求書の催促メールを「受け取ったとき」の対処は?
催促メールを受け取った場合は、速やかに対処しましょう。すぐに請求書を作成するのが好ましいですが、難しければまずお詫びの連絡をしましょう。
まずはお詫びの連絡をする
催促メールが届いた場合、まずはお詫びのメールを送ります。請求書の送付状況を確認し、行き違いがあった場合は説明と謝罪を含めた文面を考えます。文面では、発生した事象を簡潔に説明し、謝罪しましょう。その後、具体的な日付を示して請求書の送付予定を伝えます。できる限り早急な対応を約束し、取引先の不便を最小限に抑えるよう努めましょう。
速やかに請求書を送付する
お詫びのメールを送信した後、迅速に請求書を作成し、期日内に送付してください。速やかに送付する必要がありますが、記載漏れや誤りがあると訂正に時間がかかる可能性があるため、注意してください。
郵便で送付する場合、FAXやメールで先に送付することが推奨される場合があります。インボイスの対応が必要な場合、登録番号、税率ごとに区分した消費税額など、各項目に抜けている点がないかを確認してください。
請求書の催促メールにおける5つのポイント
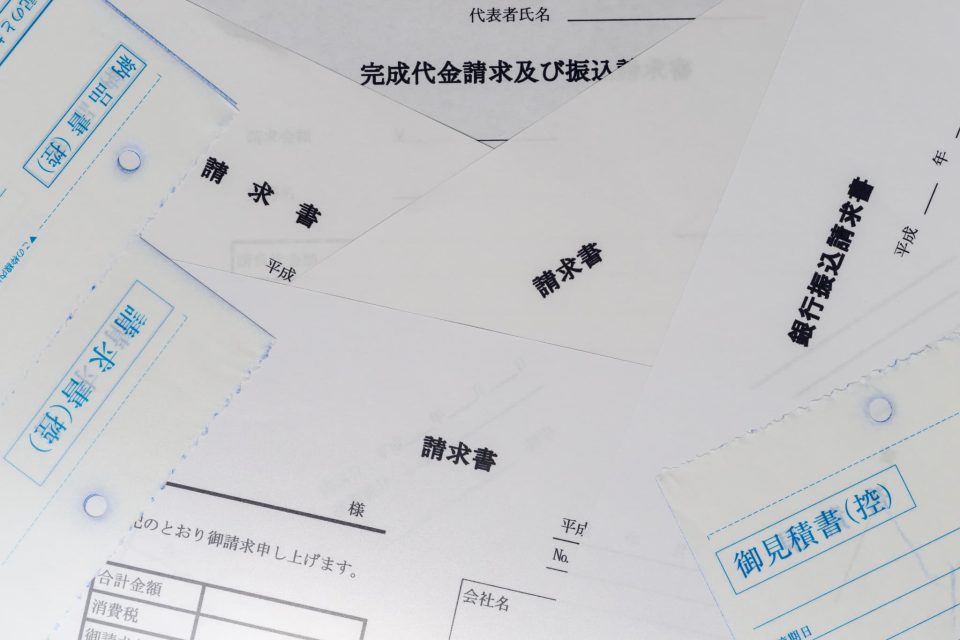
催促メールを作成する場合、5つのポイントに沿って文章を組み立てましょう。伝え方を誤ると、トラブルに発展する可能性があるため、注意してください。
1. 柔らかい口調を意識する
催促メールを送る際は、口調が強すぎないかを事前にチェックすることが重要です。相手側に不備があったとしても、高圧的な文面にならないよう注意しましょう。言い回しの微調整で受け取り側の印象が大きく変わることがあります。避けたい表現の例は、以下のとおりです。
忘れていませんか
届いておりません
催促メールとして適しているのは、丁寧で具体的な言葉です。
2. 件名は簡潔にする
メールの件名を簡潔にすることが重要です。例えば、「◯月分請求書 送付のお願い」など、内容がひと目見て理解できるような件名を使いましょう。「重要」や「至急」といった表現を使いすぎると、相手に不快感を与える可能性があります。必要に応じて使用し、適切な使い方に気を配りましょう。
3. 早めに連絡する
請求書催促メールを送る際の重要なポイントは、早めの連絡を心がけることです。取引先の担当者によっては、メールの確認頻度が低い場合があり、特に締め日が近い場合は注意が必要です。請求書の発行や送付には、取引先の内部での確認や手続きが必要であり、締め日が近づいてからの連絡では間に合わない可能性があります。
4. 入金が遅延する可能性を伝える
社内の業務フローによっては、即座に入金処理することが難しい場合があります。請求書の到着が遅れると支払いも遅れる可能性があるため、トラブルを避けるためには、先に伝えておくべきでしょう。取引先もできるだけ早い入金を希望している可能性が高いため、早急な対応を促すことが効果的です。
5. 相手への配慮を忘れない
自社の連絡と取引先の手続きがすれ違った場合に備えて、メールの末尾にお詫びの文言を含めることが推奨されています。請求書が届いていない場合でも、取引先がすでに手続きを済ませている可能性があります。
自社側のミスやチェック漏れの可能性もゼロではないため、メールの受信フォルダや郵便の確認を行い、取引先の対応を見逃していないか事前に確認する必要があります。良好な関係を維持するためには、相手の手続き漏れと決めつけず、誤解を避けることが重要です。
【ケース別】請求書の催促メールの例文
請求書の催促メールは、通常時と支払い日までに余裕がない場合、取引相手との付き合いの長さなどで異なります。それぞれのメールの例文を解説します。
メールの例文1|通常の催促の場合
通常の請求書を催促する場合は、幅広く使用できる以下の例文を参考にしてください。
件名「◯月分請求書 送付のお願い」 株式会社A 〇〇様 いつもお世話になっております。株式会社Bの△△です。 ◯月分の請求書につきまして、本日時点でまだ確認できておりません。 お手数をおかけいたしますが、念のため状況をご確認いただければ幸いです。 また、請求書の到着が◯日を過ぎた場合、お支払いが遅れる可能性がございます。 あらかじめ、ご了承ください。 未発送である場合は、早めのお手続きをよろしくお願い申しあげます。 なお、本メールと行き違いになった場合は、何卒ご容赦いただけますと幸いです。 |
メールの例文2|早急に請求書が必要な場合
支払期日までゆとりがなく、早急に請求書が必要な場合は、以下の例文を参考にしてください。
件名「【至急】○月分請求書のご送付をお願いします」
株式会社A 〇〇様
いつも大変お世話になっております。 株式会社Bの〇〇と申します。
さっそくですが、◯月分の請求書につきまして、弊社での受領を確認できておりません。 お忙しいところ恐縮ですが、請求書の送付をお願いできますでしょうか。
弊社の会計処理の都合上、◯日までに請求内容を確認させていただく必要がございます。 可能であれば、原本に先立ち、メール(PDF)またはFAXで、先に請求書をお送りいただけますと幸いです。
請求書の確認が◯日を過ぎますと、翌月のお支払いとなります。 本メールと行き違いで請求書をご送付いただいている場合は、ご放念くださいませ。 |
メールの例文3|いつもの取引先の場合
毎月取引を実施している会社への催促メールの例を紹介します。取引先に対して敬意を払いつつ、多少、砕けた表現が使える場合もあります。良好な関係を維持しつつも、催促の内容を明確に伝えるスタイルが好印象です。
件名「◯月分請求書 送付のお願い」 株式会社A 〇〇様
平素より大変お世話になっております。株式会社Bの△△です。
◯月分の請求書につきましてご連絡いたします。 毎月◯日までに頂いている請求書ですが、◯月◯日の時点で受領しておりません。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご確認をお願いします。
なお、本メールと行き違いになっている場合には、ご容赦いただけますと幸いです。
弊社の事務処理の関係により、原本が◯月◯日までに必要です。 ◯日を過ぎてしまうと、お支払いが翌々月になるため、あらかじめご了承ください。 よろしくお願いいたします。 |
請求書の送付漏れの防止方法
請求書の送付が漏れてしまうと、取引先に迷惑をかけてしまいます。請求書の送付漏れが生じにくい体制を整えておくことが重要です。
チェック体制を見直す
社内のチェック体制の強化が請求書の送付漏れを防止するための重要なポイントです。単独の担当者では見逃す可能性があるため、複数人でのチェックが推奨されています。請求書の発行が多い場合や、郵便で送付する場合は特に注意が必要です。郵送時には宛先の記載や封入作業でミスが発生しやすいため、入念なチェックが不可欠です。
業務フローを見直す
請求書の送付漏れを防止するためには業務フローの改善が重要です。請求書の送付漏れの原因として、書類管理の不備が挙げられます。請求書に通し番号を付けて管理することで漏れを防止する方法が推奨されています。
作業リストを作成し、請求書の発行や送付状況を確認できるようにすることが効果的です。ステータス別に管理することで業務効率が向上します。送付リストを作成し、送付が完了した案件にチェックを入れることで漏れを防止しやすくなるでしょう。
システム導入を検討する
ここまでで業務フローの改善と社内のチェック体制強化が重要であることを述べてきました。さらに請求書の自動作成・発行・送付などが一元管理できるシステムを導入することにより、手作業の時間と労力を大幅に削減できます。
請求書を一元管理することで、送付漏れを防止する効果が期待できます。またWeb上で送付できるシステムを利用すれば、郵送手続きが省略でき、業務効率化に寄与します。
請求書の催促メールでよくある質問

請求書の催促メールにおいて、送付のタイミングや注意点、請求書が届かない場合の対処法など、よくある質問に回答します。
催促メールを送るタイミングはいつ?
請求書を送ったにもかかわらず、数日経っても「届いているかどうか」の返信や確認が取れない場合は、送付後2~3営業日を目安に催促メールを送りましょう。特に初回の取引や、相手が請求書の確認フローに慣れていない場合は、請求書の到着有無や内容の確認を丁寧に尋ねることがポイントです。
また、メールを送る時間帯にも配慮が必要です。早朝や夜間、休日を避けて、業務時間内の午前中や午後早めの時間帯に送ると読んでもらえる可能性が高まります。
2回目以降の催促メールの注意点は?
2回目の催促メールを送る際の準備として、まず1回目の送信確認を行います。1回目が未送信だった場合は、その旨を伝えつつ、催促メールを送信しましょう。1回目が送信済みの場合、2回目の送信間隔が短すぎると好ましくないため、3日後を目安にすると良いでしょう。2回目のメールの内容は、行き違いを避けるために注意深く作成することが重要です。
請求書が届かない場合はどうする?
請求書が届かない場合、メールや電話で催促しましょう。また、請求書が届かなくても、下請法により商品やサービス受領後60日以内に支払うのが基本的な原則です。公正取引委員会・中小企業庁の資料に記載されています。
請求管理業務の負担を解消するなら「ANDPAD請求管理」
建設業における請求管理業務の負担を解消したいと考える人には「ANDPAD請求管理」がおすすめです。請求書の回収や工事ごとの振り分け、出来高査定といった建設業特有の要件を満たした管理システムです。毎月の請求書管理業務を大幅に効率化できるでしょう。導入時のサポート体制も充実しているため、安心して導入してください。
まとめ
期日を過ぎても、請求書が届かない場合は催促のメールを送付しましょう。その際は、トラブルにならないよう、表現には十分に注意してください。逆に、請求書を送る立場の場合は、送付漏れが生じないように注意してください。
請求書の管理には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーに利用されています。気になる人は、以下よりお問い合わせください。