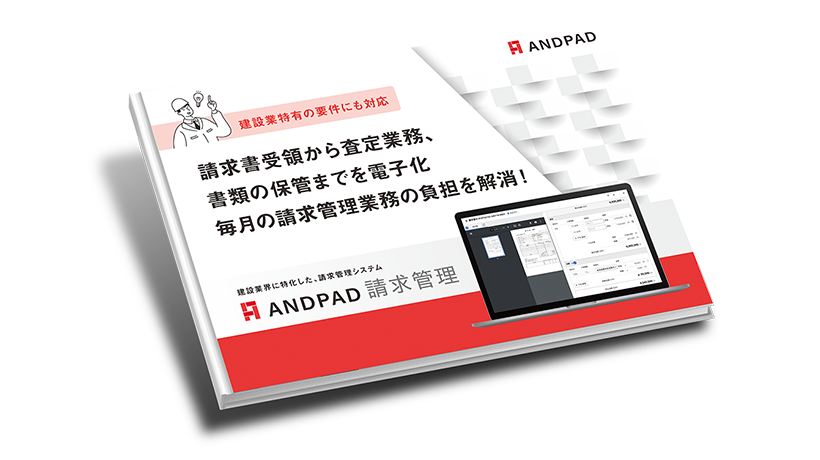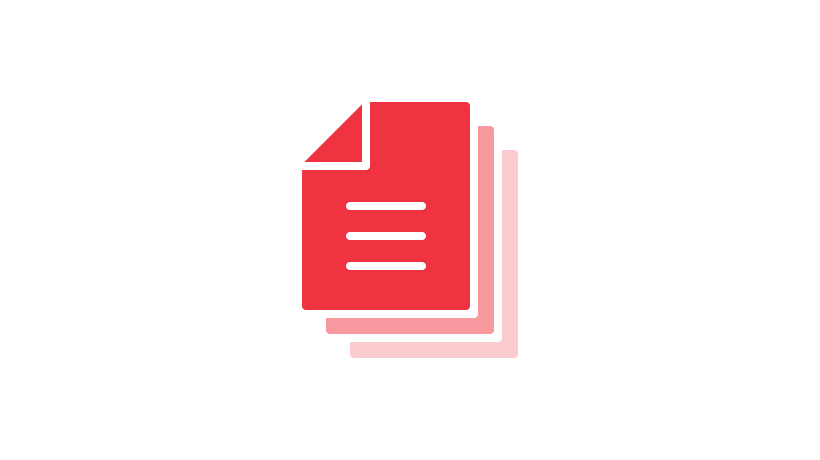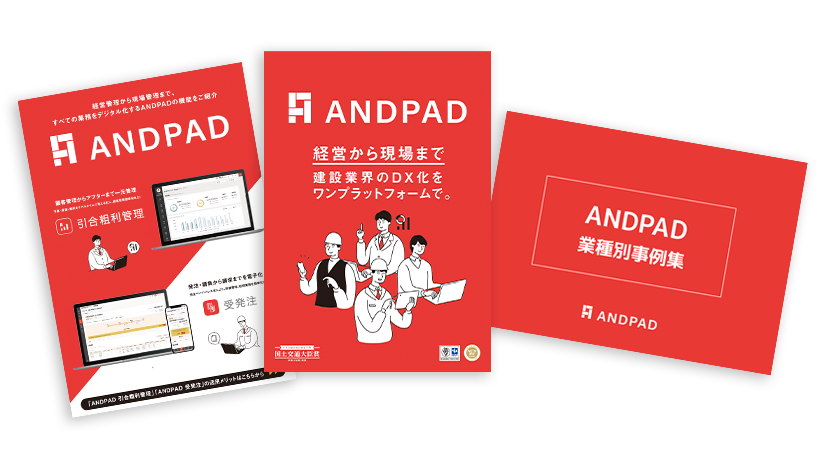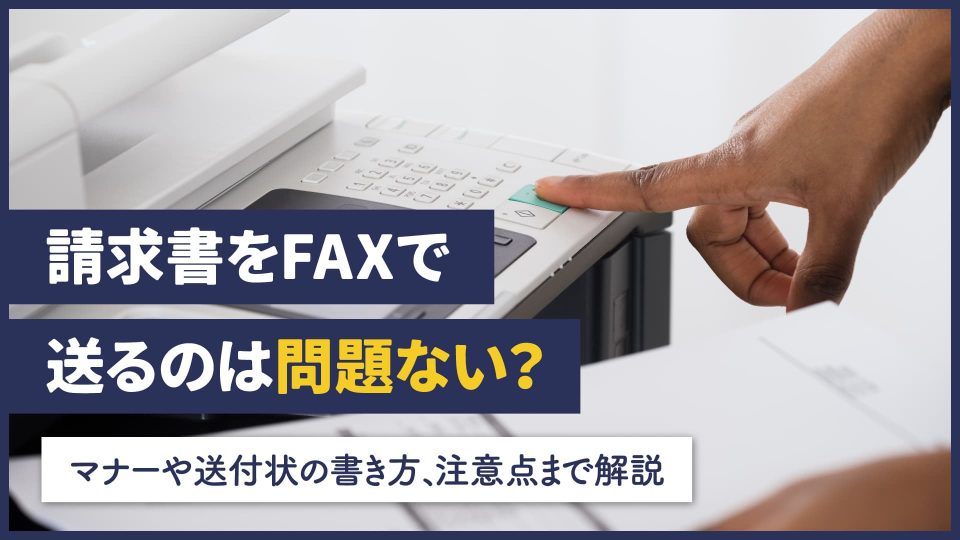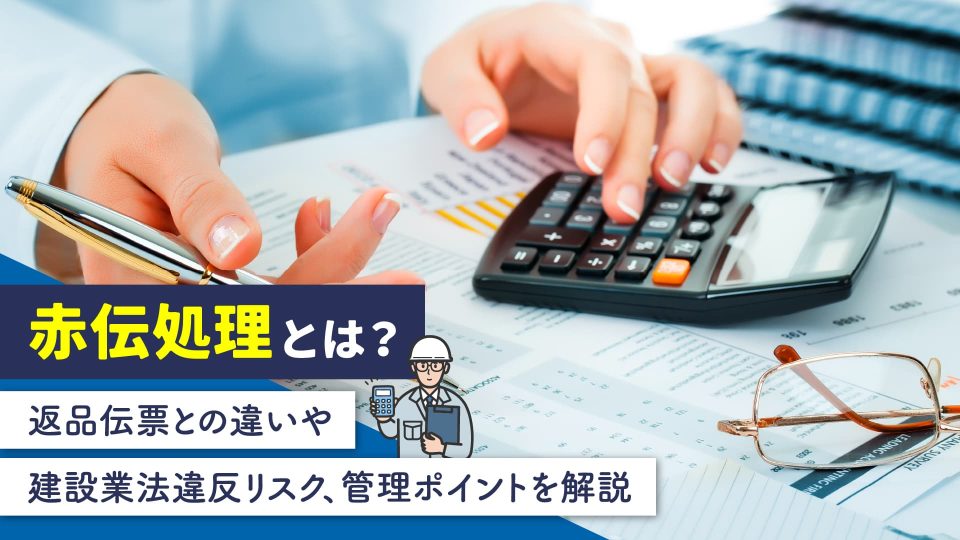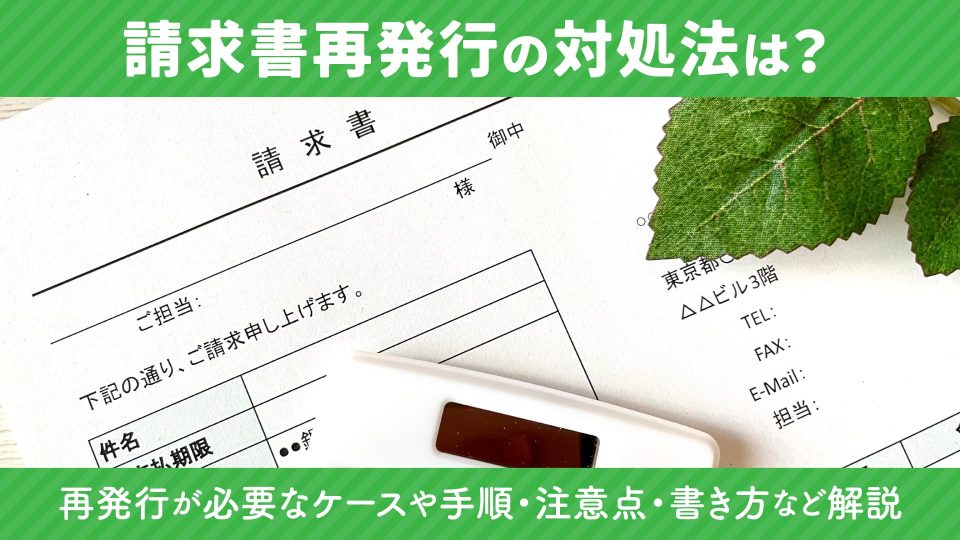請求書をFAXで送ることは、双方の合意があれば問題はありません。しかし、FAXを利用する場合は、送付状を添えて原本を別途郵送する必要があります。この記事では、請求書をFAXで送るメリットやデメリット、送付状の書き方と例文、電子請求書を利用するメリットについて解説します。
請求書をFAXで送付しても問題はない
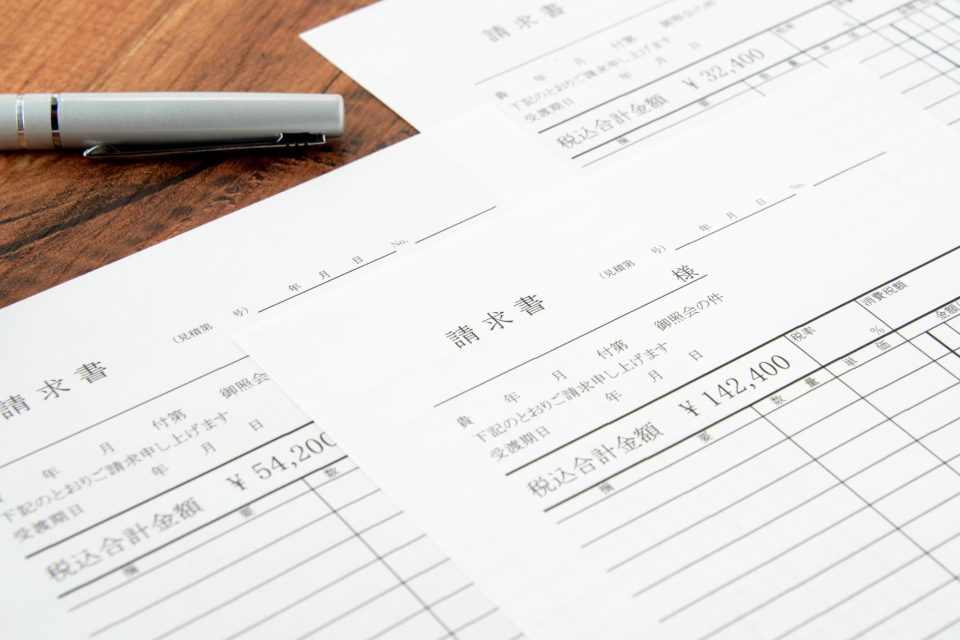
請求書をFAXで送ること自体は、取引先とのあいだに合意があれば、問題ありません。法律上、請求書の送付方法は決まっていないからです。ただしFAXでの送付は、あくまでも補足的な方法である点には注意が必要です。郵送やメールで送る方法と比べると一般的ではありません。
請求書をFAXで送る際のマナーと注意点
請求書はFAXで送れますが、送付時に注意すべき点があります。ここでは、送付時のマナーと注意点を解説します。
送付状の書き方と例文
FAXで請求書を送る場合、ビジネスマナーとして、送付状の添付が通例です。送付状は、以下の項目を満たしていることを確認しましょう。
請求書の送信日時
請求書の送付先
請求書の発信元
連絡先(発信元と異なる場合)
あいさつ文
請求書の件名
送付状を含めた書類の総数
送付状の例文を以下に示します。
送信日時 株式会社A B事業部 C様 発信元 株式会社D E事業部 F TEL:XX-XXX-XXXX FAX:XX-XXX-XXXX 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 さて、4月分の請求書を送付いたしますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。 敬具 記 請求書1通 以上 |
原本の取り扱い
FAXで請求書を送る場合、原本も別途、郵送しなければなりません。法律上、証憑書類と呼ばれる請求書や納品書は、紙あるいは電子データによる原本の保管が義務付けられているためです。紙で作成した原本がある場合、出力された紙データは、法的に原本と認められない可能性があります。
誤送信には気を付ける
FAXは送付先のFAX番号を入力するだけで、簡単に書類を送付できます。しかし、FAX番号を間違えたり、書類を取り違えたりといった誤送信には注意が必要です。誤送信は、個人情報や機密情報の漏洩につながりかねません。
FAXの誤送信が起こる原因は、主にヒューマンエラーです。それ以外にも、機器の不具合や紙詰まりなどのトラブルで送信できないケースもあります。FAXの誤送信は、その場で気が付かず、送付先から指摘されて判明することも考えられます。セキュリティ対策が不十分であると判断されて信頼を失い、事業にも影響を及ぼしかねません。
請求書をFAXで送るメリット

請求書をFAXで送るメリットを3つに分けて解説します。
送信者の情報が明確で信頼性が高い
請求書に限らず、契約書や注文書など、さまざまな書類がFAXでやり取りされています。多くの場合、業務フローに組み込まれており、効率のよさと信頼性の高さは、以下のように周知の事実です。
送信元の情報が明らかである
メールと異なり、スパムメールのような膨大な量のFAXが送られることが少ない
インターネットを経由したサーバー攻撃を受ける危険性が低い
IT知識やスキルがない人でも使える
FAXは書類を機械に挿入し、番号を入力して送信するだけで完了します。難しいパソコンの操作や高度なITスキルは不要で、年齢を問わずアクセスしやすいメリットがあります。FAXを送るための特別な研修も不要です。メール、チャットやITツールの場合、使いこなすために操作を覚えなければなりません。
緊急時にも対応できる
FAXの送付時に担当者が不在であっても、ほかの従業員が確認して、適切な対応をとることが可能です。文書は目につきやすく、送付先の注意を惹きます。物理的な記録として残ることもメリットとして挙げられるでしょう。また、メール作成の手間がかからず、緊急時も即座に情報を共有できます。
請求書をFAXで送るデメリット
請求書をFAXで送ることで、どのようなデメリットが生じるのかについて解説します。
コストがかかる
請求書をFAXで送る場合は、書類の印刷には、用紙やインクなどの消耗品が必要です。これらの消耗品は定期的に補充しなければならず、FAXの使用頻度が高いほど、経費も増えます。コストは短絡的に考えるのではなく、中長期的な視点で考えることが重要です。FAX機器の購入またはレンタル費用、維持費、電話回線の利用料金もかかります。
返信までのタイムラグがある
FAXを送ったタイミングで、相手がすぐに確認するとは限りません。FAXは物理的な手段であるため、見落とされる可能性は低くなりますが、相手が不在の場合には、確認までにタイムラグが発生することは避けられないでしょう。
返信をする場合、新たに書類を用意したり内容を記載する手間と時間がかかります。特に繁忙期には、FAXが見落とされたり対応を後回しにされたりするリスクがあり、機会損失になりかねません。
保管の手間がかかる
FAXで送られた請求書は、紙ベースで管理することになります。紙ベースでの書類の管理は、デジタル化を推し進める世間の流れに相反するものです。業務効率の低下や環境への影響など、弊害が浮き彫りになるでしょう。また、書類の管理や整理には、多くの時間と手間がかかります。電子ファイルと比べると検索やアクセスがしにくいでしょう。また、紙は経年劣化するリスクもあります。
電子請求書のメリット

FAXの代わりに電子請求書を利用する方法もあります。ここでは、電子請求書を利用するメリットを解説します。
手間とコストが削減できる
電子請求書は、印刷したり郵送したりする手間と、紙やインク、電話回線使用料といったコストがかかりません。請求書をデータのまま、メールやクラウドで送ることも可能です。また、紙の請求書とは異なり、1枚ずつ綴じて保存する必要もなく、受け取る側も管理の手間が省けます。保存スペースも不要であるため、管理場所にコストをかける必要がありません。
初期設備投資のコストも抑えられることから、財務負担も軽減します。
業務効率化につながる
請求処理をはじめ、経理業務は煩雑なことが多く、作業工程は膨大です。電子請求書を利用することで、書類をスキャンして読み込んだり、誤送信を防ぐためのダブルチェックをしたりする手間を省けるため、業務効率化につながります。また、原本を郵送する必要がないため、請求書の発行から受領までの時間も短縮できます。
場所を選ばず業務ができる
電子請求書は、パソコンと通信環境があれば、場所を問わずに発行、送信が可能です。データでやり取りが完結するため、テレワークでも請求書の発行・受領業務ができます。テレワークでも対応しやすいため、働く場所の自由度が高まり、従業員のワークライフバランスの向上にもつながります。
最新の電子帳簿保存に対応できる
電子帳簿保存法の改正により、2022年1月から電子上で行われた取引に関する書類は、電子データでの保存が義務付けられました。電子データで受領した請求書は印刷せず、電子データのまま保存しなければなりません。
法人の場合の保存義務期間は、法人税法では7年、欠損金の繰越控除適用は10年です。個人事業主の場合、保存義務期間は、所得税法で5年、消費税納税業者は7年です。請求書の写しを作成した場合も、受領した請求書と同様に保存義務が生じます。
参考:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
建設業の請求書をFAXで送る手間をなくすなら「ANDPAD請求管理」
ANDPAD請求管理は、建設業界に特化した請求管理システムです。建設業界特有の出来高査定、立替経費の相殺といった要件にも対応可能です。請求書受領から査定、管理までを電子化するため、請求業務の負担の解消につながります。
受領した請求書をPDF化した後、システム側へアップロードし、自動的に振り分け作業をします。査定項目や工種を自由に入力できるため、請求書の紐付けや管理もスムーズです。請求額とは別に、出来高の査定額を入力、立て替え経費などの相殺金額も入力可能です。電子帳簿保存法にも対応しています。
まとめ
FAXは、ITスキルや知識が不要で、緊急時でも請求書を送れるメリットがあります。一方で、紙やインクなどのコストや、管理の手間がかかるといった点がデメリットとして挙げられるでしょう。電子請求書の利用は、手間とコストの削減、業務効率化につながります。
建設業界の業務効率化には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」をご利用ください。使いやすいUI・UXを実現する開発力と、年間数千を超える導入説明会を実施する手厚いサポートが強みです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。詳しくは、お問い合わせください。