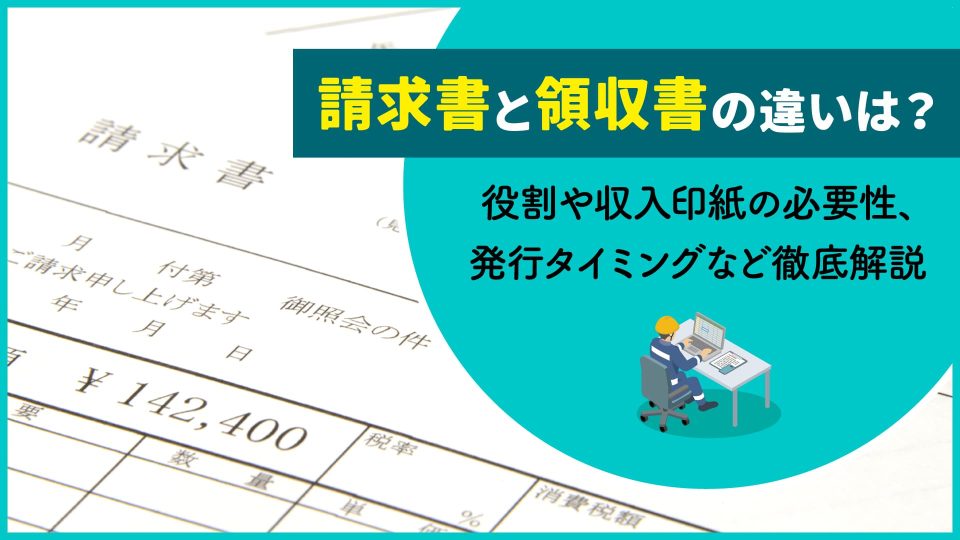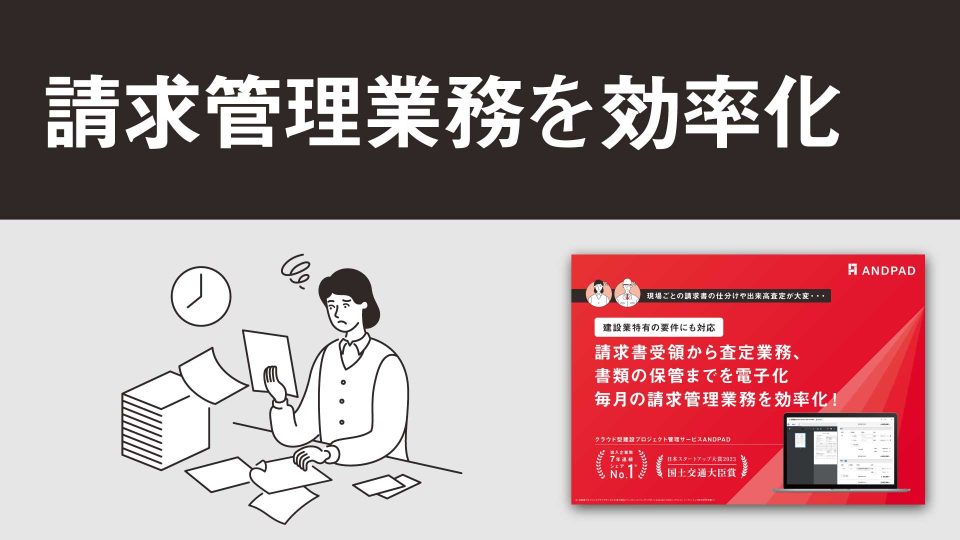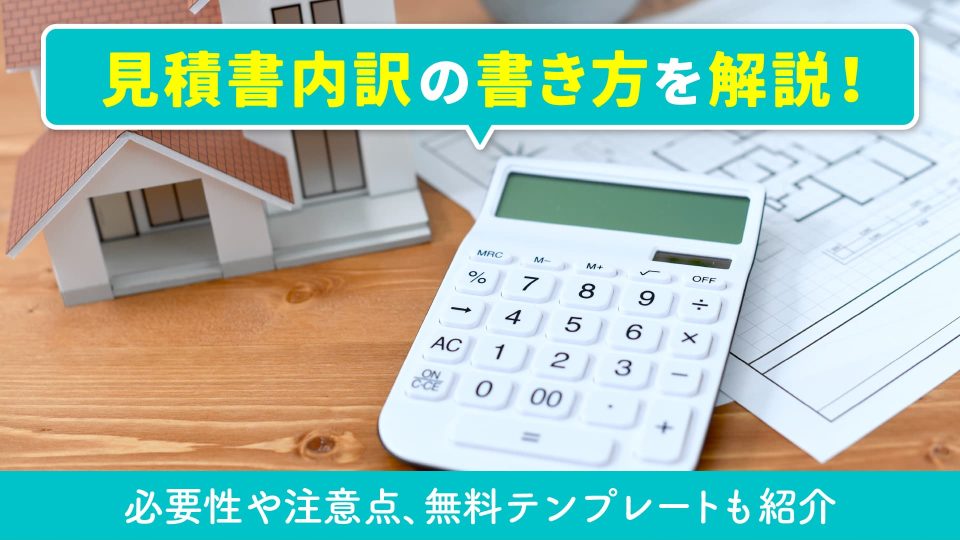請求書と領収書は「収入印紙の有無」や「紛失した場合の再発行の可否」に違いがあります。この記事では、請求書と領収書の違い、収入印紙が必要か否か、書類の保管期間などについて解説します。請求書と領収書の違いや使い分けが知りたい経理や税務担当者は、ぜひ参考にしてください。
請求書と領収書の違い

請求書には請求金額や支払いの内容、支払い日などが記載されています。請求書が金銭を受け取る前に発行されるのに対し、領収書は対価を受け取ったことを示す書類であるためです。請求書と領収書は、発行するタイミングが金銭を受け取る前か後という違いがあり、記載項目も異なります。
請求書と領収書の役割を解説
請求書と領収書の役割、記載すべき項目について解説します。
請求書とは
請求書は、商品やサービスなどに対する金銭の支払いを要求する書類です。請求書には、主に以下の項目を記載します。
- 請求書作成者の氏名あるいは名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名あるいは名称
- 請求書番号
- 請求者の捺印
- 請求合計額と消費税額
- 備考
- 振込先
- 振込手数料
- 支払い期限
領収書とは
領収書は、商品やサービスの対価として金銭を受け取ったことを明示する書類で、金銭のやり取りが完了したことを証明します。領収書には、以下の項目を記載します。
- 発行日
- 領収金額
- 但し書き
- 宛名
- 発行者名と連絡先
- 収入印紙
請求書兼領収書とは
企業同士の取引では、一般的に以下の流れで請求書と領収書を発行します。
- 請求書を発行する
- 期日までに支払いが行われる
- 領収書を発行する
ただし、請求と支払いが同時に行われる場合には、請求書兼領収書を使用します。請求書兼領収書は、請求書と領収書両方の役割を持つものです。請求書の下に領収書がついていたり、請求書に領収済みと記載されていたりと形式はさまざまですが、経費申請上、金銭を領収したことがわかることが重要です。
請求書は領収書の代わりになる?
原則として、領収書は発行義務があります。ただし、以下が記載されている請求書は、領収書の代わりとすることができます。
- 日付
- 支払った人と受け取った人がそれぞれ誰であるか
- 金額
- 支払った内容
- 収入印紙と割印(※5万円を超える場合)
領収書が発行されないときの代用手段
支払いが完了したにもかかわらず、領収書が発行されない場合もあるでしょう。ここでは、請求書が領収書の代わりになるケース、利用明細が利用できるケースなどについて解説します。
銀行振込
ビジネスにおいては、領収書を受け取るのが原則ですが、銀行振込は領収書が発行されません。銀行振込で支払いをした場合には、振込明細書や銀行口座の利用明細のコピーなどと請求書をセットにすることで、経理上は認められます。ただし、請求書が発行されない場合には、領収書が必要です。
クレジットカード払い
領収書が発行されない代表的なケースとして、クレジットカード払いが挙げられます。クレジットカードは信用取引に該当するため、決済時点ではまだ実際の支払い(弁済)は完了していません。そのため、店舗やサービス提供者には領収書を発行する法的義務はありません。
ただし、経費精算や税務処理の際には、クレジットカードの利用明細書や売上票(お客様控え)、購入時のレシートなどが、領収書の代わりとなる証憑として認められることがあります。これらの書類には、以下の情報が記載されている必要があります。
- 書類の発行者名と受領者名
- 日付
- 金額
- 支払内容(但し書きなど)
領収書が発行されづらいケース(交通費・冠婚葬祭など)
公共交通機関の利用や、取引関係の冠婚葬祭における祝電や香典など、領収書を受け取れないケースもあるでしょう。公共交通機関の利用は、Webの利用明細が領収書として代用できます。冠婚葬祭の場合には、招待状やお礼状などが金銭支払いの証拠となります。これらの書類に加えて、日付・支払先・金額・内容を記載した明細書を提出しましょう。
【原則】現金払いの請求書は領収書として代用不可
原則として、現金で支払った場合に請求書を領収書の代わりにすることはできません。現金払いは履歴が残らないため、請求書だけでは支払いの証明にならないからです。
そもそも請求書は「支払い前」に発行される書類で、代金を請求する役割があります。一方、領収書は「支払い後」に発行され、実際に代金を受け取った証明として使われます。そのため、現金払いでは請求書を領収書の代わりに使うことはできません。
請求書と領収書の収入印紙の違い
請求書と領収書には、収入印紙の要不要に違いがあります。以下では、それぞれについて解説します。
基本的には請求書に収入印紙は不要
印紙税は金銭のやり取りが生じた取引に対して支払う税金です。請求書を発行した段階では、まだ支払いが行われていないため、基本的には請求書に収入印紙は不要です。
領収書には原則として収入印紙が必要
領収書は国が定める課税文書のひとつであり、原則として収入印紙が必要です。ただし、以下の場合は収入印紙は不要です。
- 受領した金額が5万円(税抜き)以下の場合
- クレジットカードの利用明細を領収書として提出する場合
収入印紙の金額は、受取金額が増えるほど高くなります。
参考:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
支払い方法の違いによる領収書の発行タイミング

支払い方法がクレジットカードか、振り込みや振替、現金払いかによって、領収書の発行タイミングは異なります。
クレジットカード払い
前述のとおり、クレジットカードによる支払いは信用取引であるため、サービスや商品の提供者に領収書を発行する義務はありません。ただし、クレジット決済の際に、売り手に領収書の発行を依頼すると対応してもらえる場合があります。ECサイトなどオンラインで商品を購入した場合は、領収書発行ページからダウンロードして印刷できるサイトもあります。
振り込みや振替、現金払い
現金払いにおいては、金銭を受け取った側に領収書を発行する義務があるため、金銭のやり取りが発生したタイミングで、領収書の発行を請求できます。振り込みや振替の場合、対面での取引ではないため、その場で領収書を発行することができません。振り込み後に領収書の発行を支払先に請求しましょう。
請求書と領収書の保管期間
法人が受け取った請求書や領収書は、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えて、7年間の保管義務があります。また、繰越欠損金の控除を受ける場合は保管義務が10年間に延長されます。個人事業主で青色申告をしている場合の保管義務は、法人と同様に、確定申告の提出期限日の翌日から数えて7年間です。
ただし、前々年分の所得が300万円以下の場合に限り、保管義務は5年間に縮小されます。白色申告の個人事業主は、前々年分の所得額にかかわらず、保管義務は5年間です。
参考:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
参考:国税庁標準文書保存期間基準(保存期間表)
請求書と領収書を紛失した際の違い
請求書や領収書を紛失したり、記載項目が間違っていたりして、取引先に請求書や領収書の再発行を依頼することも考えられます。ここでは、請求書や領収書の再発行について解説します。
請求書は再発行してもらえる
請求書は証憑の一種で、法人・個人事業主にかかわらず、一定期間の保管義務が発生します。紛失したまま放置すると、取引先が税務調査で指摘を受ける恐れがあります。正当な理由がある場合は、請求書の再発行を依頼しましょう。ただし、二重発行によるトラブルには注意が必要です。
領収書は再発行してもらえない場合もある
領収書も、発行元に再発行を依頼できます。ただし、領収書の再発行に法的な義務はないため、必ずしも再発行してくれるとは限りません。再発行してもらえない場合は、領収証明書や支払証明書などの書類を有料で発行してもらうか、レシートや請求明細書での代用を検討しましょう。
請求書や領収書は電子化ができる

請求書や領収書は、発行や管理に手間がかかり、紛失するリスクもあります。請求書や領収書を電子化することで、請求書管理に関する業務を効率化し、手作業の負担も軽減できます。また、請求書や領収書の電子化は、資源保護の面でも推奨されています。電子化の方法としては、スキャナの利用や専用システムの導入などが挙げられます。
建設業の請求管理はANDPADがおすすめ
建設業の請求管理には、建設業界に特化した「ANDPAD請求管理」がおすすめです。請求書の回収、工事ごとの振り分け、出来高査定や相殺・承認といった、建設業特有の要件を満たしています。
電子帳簿保存法にも対応しており、毎月の請求業務を大幅に効率化できるでしょう。紙の請求書や領収書の保管スペースを確保する必要がなく、データ検索もスムーズです。また、自社独自の査定項目を自由に追加できるカスタマイズ性もあります。
まとめ
請求書と領収書は役割が異なります。請求書は金銭の支払いを請求する書類で、領収書は金銭の受領が完了したことを示す書類です。請求書と領収書は、いずれも法人は7年間、個人事業主は状況に応じて5年または7年間の保管が義務付けられています。
請求書の管理には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」をご利用ください。年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートを実施しており、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力が特長です。詳しくは、資料をご覧ください。