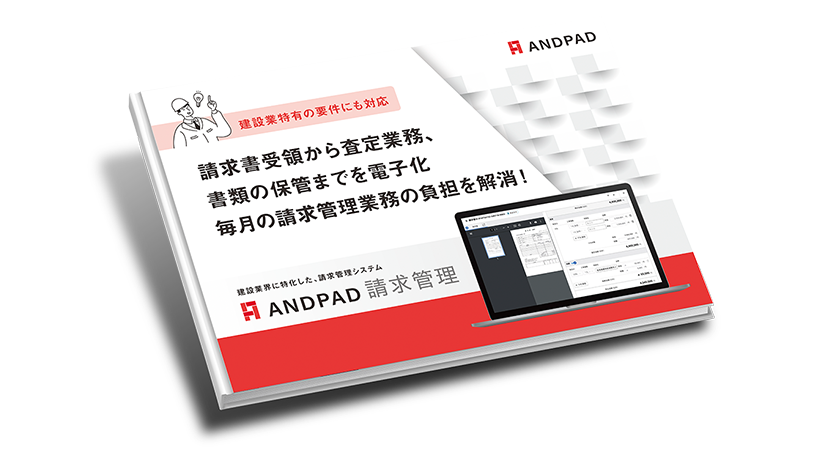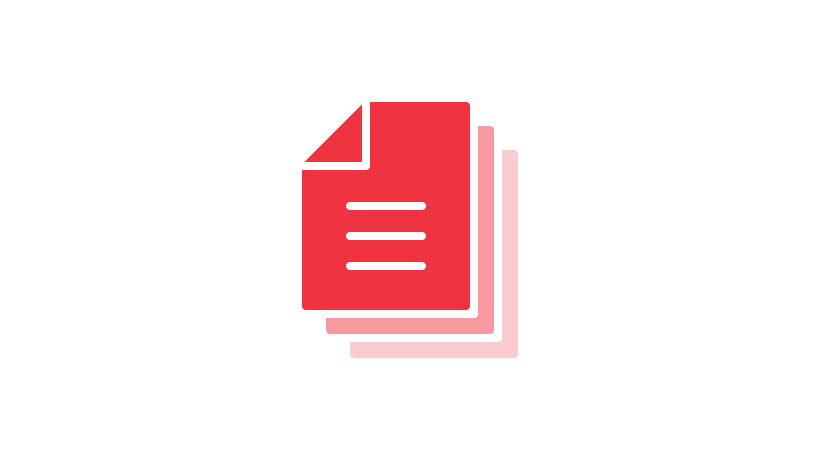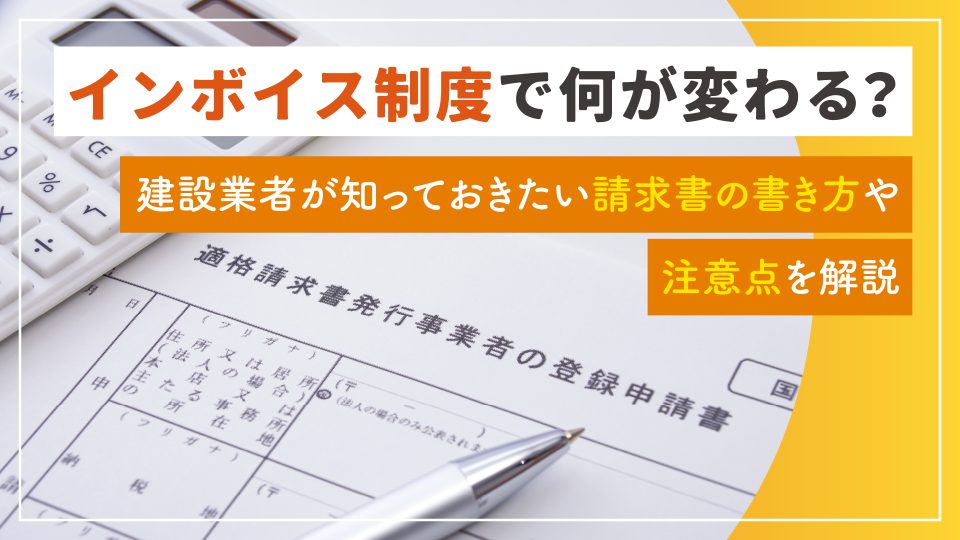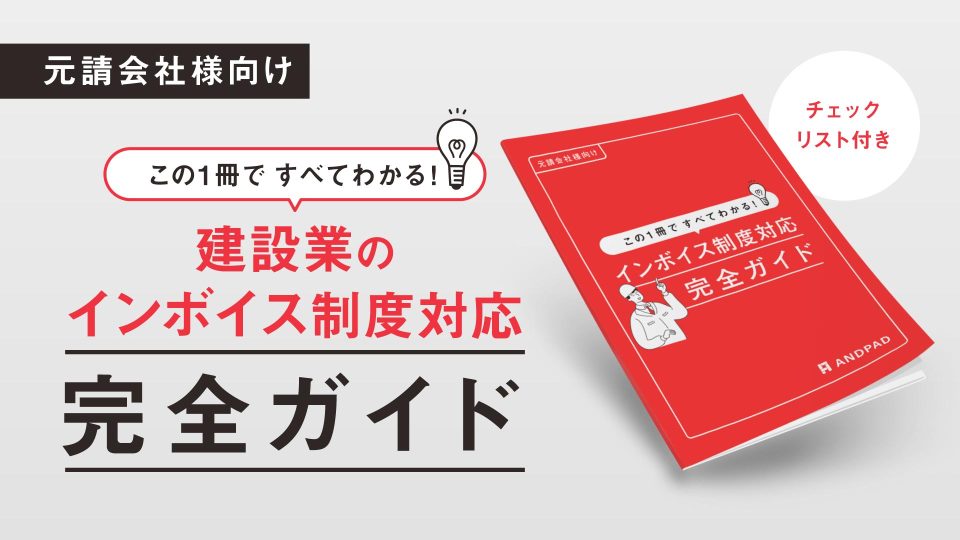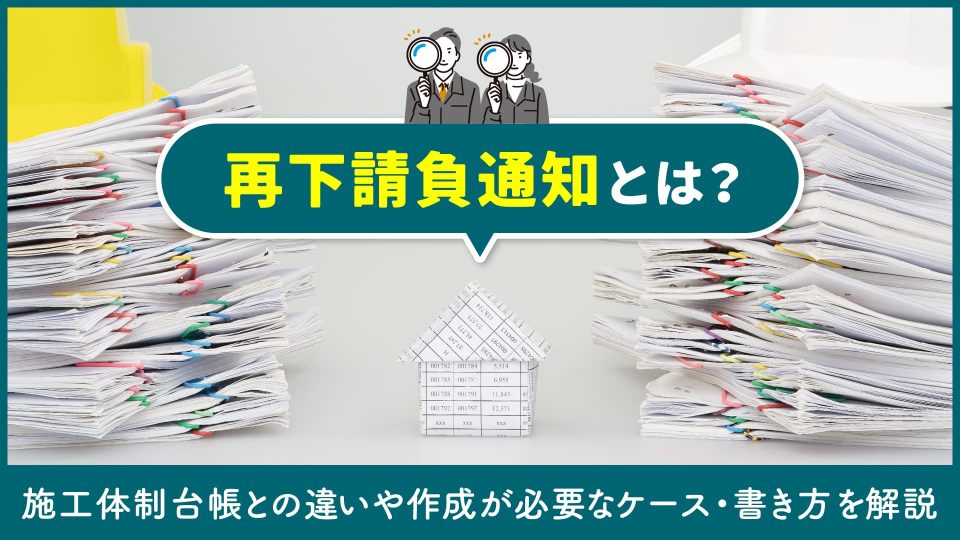2023年10月よりインボイス制度がスタートしました。インボイスに対応しないことは、買い手側にも売り手側にも不利益が生じる可能性があります。この記事では、2023年12月時点の情報をもとに、建設業におけるインボイス対応の重要性や請求書の書き方について解説します。インボイスの保存期間や修正方法などの注意点を知り、スムーズな運用を目指しましょう。
建設業における請求書の書き方やテンプレートについて以下の記事でも解説しています。、是非あわせてご覧ください。
関連記事:【建設業】工事の請求書の書き方とは?テンプレートや送付方法、注意点まで解説
インボイス制度とは
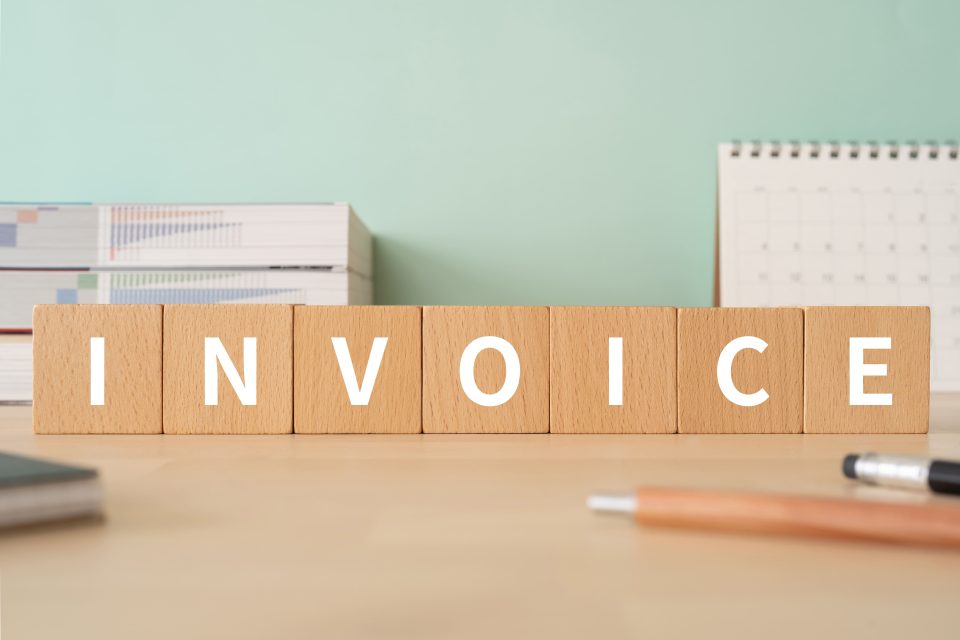
まずは、インボイス制度の基本知識と対応するための準備や対策を見ていきましょう。
インボイスの基本知識
インボイスは、直訳すると「送り状」「請求書」となります。インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を発行することで消費税額を正確に把握し、買い手側が仕入税額控除を受けられる制度です。イギリスやドイツ、フランスなどの海外でも広く導入されており、日本でも2023年10月1日より開始となりました。インボイス制度は、適格請求書保存方式と呼ばれることもあります。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、消費税が二重三重に課税されないように、仕入にかかる消費税額を控除する仕組みです。2023年10月以降はインボイスを発行しないと、原則として買い手側は消費税の仕入税額控除ができなくなります。ただし、インボイス制度の開始後6年間は経過措置が設けられており、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除が可能です。
インボイスに対応するためには
インボイスに対応するためには、買い手側・売り手側それぞれに準備や対策が求められます。まず、買い手側はシステムを導入するなどして、インボイスに対応できる環境を整備しなければなりません。売り手側もインボイス発行事業者の申請を行い、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。
建設業におけるインボイス対応の重要性
インボイス制度は、売上1,000万円以下の免税事業者だけでなく、取引先の企業にも影響を及ぼします。ここからは、建設業におけるインボイス対応の重要性を解説します。
買い手側
建設業における買い手とは、「工事の発注元の企業(元請会社)」のことです。買い手側がインボイス登録していない事業者に仕事を発注した場合、適格請求書が発行されないため、仕入税額控除が受けられなくなります。その結果、納税額が増えて利益を圧迫する可能性が出てきます。
売り手側
建設業における売り手とは、「工事の発注先の企業(協力会社)」のことです。売り手側がインボイスに対応していないと、工事の発注元の企業は仕入税額控除が受けられず、損をしてしまうことになります。そのため、適格請求書発行事業者に仕事が流れてしまい、インボイス登録していない事業者は不利益を被る可能性があります。
インボイスの登録は任意
買い手側の課税事業者からの求めがあれば、原則としてインボイスを発行しなければなりません。ただし、インボイスの登録は強制ではないため、リスクを承知したうえで「対応しない」という判断を下すことも可能です。また、インボイス対応が必要ではないケースも存在します。
インボイスが必要ないケース
次のケースでは、インボイスに対応しなくても業務に大きな影響はないと考えられます。
- 顧客が一般消費者のみ
- 取引先が簡易課税事業者または免税事業者のみ
- 取引先が仕入税額控除をしない事業者のみ
ただし、取引先の状況によっては、将来的にインボイスへの対応が求められる場合もあります。また、新規の取引先を開拓したいときも、適格請求書発行事業者に登録していた方がスムーズです。
建設業における請求書の書き方
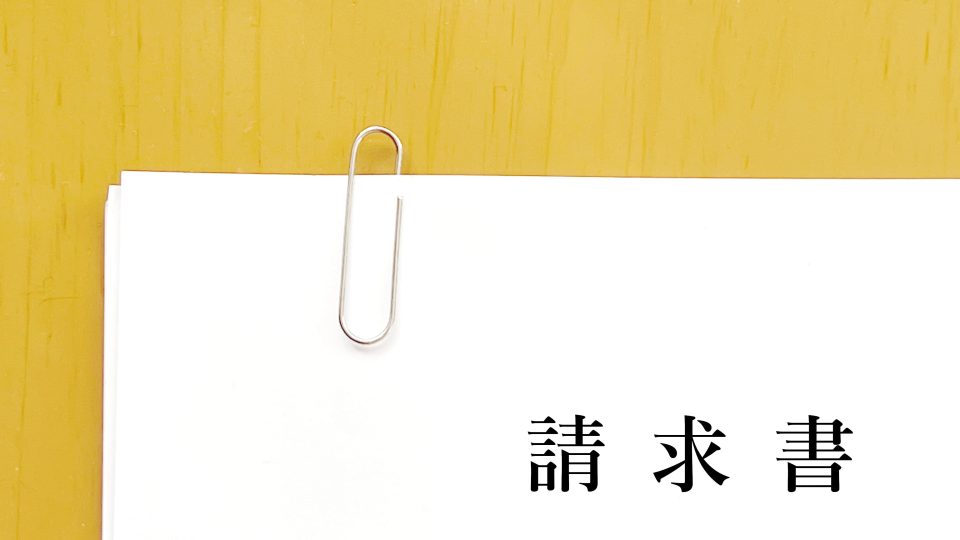
適格請求書(インボイス)とは、これまで使用されていた「区分記載請求書」に、登録番号や適用税率などを追加した書類やデータを指します。ここでは、建設業における請求書の具体的な書き方を紹介します。
以下では、一人親方の請求書の書き方について詳しく解説しています。
関連記事:一人親方の請求書の書き方|必須項目やインボイス制度の影響も解説
関連記事:請求書における相殺とは?相殺請求書の書き方や仕訳方法、処理の流れなども解説
請求書のフォーマットは決まっていない
建設業の請求書に決まったフォーマットはありません。ただし、記載すべき項目は決まっており、不備があった場合は再発行が必要となります。手続きや管理の手間を削減するためにも、会社内でフォーマットを統一しておくことが重要です。
請求書に記載すべき基本項目
請求書に記載すべき基本項目は、次のとおりです。
- 請求書発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
- 請求書受領者の氏名又は名称
基本項目は、従来の「区分記載請求書」の内容を引き継いでいます。必須ではありませんが、振込先や支払期日などの記載もあると便利です。また、請求先の情報は省略せずに、正式名称で書く必要があります。
関連記事:請求書の内訳の書き方は?記載例や必要項目、請求明細書との違いをまとめて解説
インボイス対応で必要な追加項目
インボイス対応で必要な追加項目は、次のとおりです。
- 登録番号
- 税率ごとに区別して合計した対価の額(税抜き又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区別した消費税額等
登録番号は、適格請求書発行事業者の「登録通知書」にて確認できます。適用税率と消費税額等については、合計が12万円(税抜き)の請求書の場合、「8%対象 4万円(消費税3,200円)」「10%対象 8万円(消費税8,000円」と記載します。
請求書を作成する方法
請求書を作成する方法は、「手書き」「エクセルやワード」「請求書管理システム」の3種類があります。それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
1. 手書き
パソコンがない場合は、手書きでインボイスを発行するケースもあります。「自動計算ができない」「修正に手間がかかる」など、デメリットも多いため、採用している事業者は少数です。
2. エクセルやワード
適格請求書は、エクセルやワードでも作成可能です。インターネット上のさまざまなサイトでも、無料で使えるテンプレートが配布されています。エクセルやワードが標準で搭載されているパソコンも多いので、コストをかけなくてもインボイスの発行は可能です。ただし、インボイスは原則7年間の保管義務があるため、管理方法を考える必要があります。
3. 請求書管理システム
請求書管理システムを導入することで、請求書の作成や管理が最適化できます。システムで自動化することで、インボイス対応の負担が軽減でき、業務の効率化もできるでしょう。ただし、導入コストがかかるため、自社に合ったシステムを選ぶことが大切です。
関連記事:請求書受領サービスとは?6つの比較ポイント、5つの導入メリットまで徹底解説!
インボイスの注意点

ここからは、インボイスの注意点を3つ紹介します。事前に対策を行うことで、スムーズな運用を目指しましょう。
保存義務は原則7年間
法人の場合、原則として7年間は適格請求書の控えを保存する義務があります。7年間の起算点は、「事業年度の確定申告の提出期限の翌日」です。請求書の発行日や受領日を基準として考えないよう注意しましょう。また、欠損金の繰越控除を適用している場合など保存期間には例外もあり、10年間に延長されるケースもあります。
記載ミスは修正インボイスの作成が必要
適格請求書に不備があった場合は、修正インボイスの作成が必要です。買い手側がインボイスを修正することはできないため、売り手側が再交付しなければなりません。修正インボイスを作成する場合は、次の2つの方法があります。
- 修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する
- 当初に交付した適格請求書との関連性を明らかにした上で、修正した箇所のみを明示した書類を交付する
請求書が複数になると混乱しやすいため、「どのようなフローで修正を行うのか」といった認識を買い手側・売り手側で擦り合わせておきましょう。
経理担当者の負担増加
インボイス制度により、経理業務の負担が増大することが懸念されています。スムーズな運用を実現するには、システムの導入がおすすめです。建設業界に特化したANDPAD(アンドパッド)なら、非効率な適格請求書のやり取りを解消し、適切な保存・管理が行なえます。
まとめ
インボイスの登録は任意ですが、取引先が流動的な建設業では、対応しないことで売上が大きく減少するリスクがあります。買い手側も適格請求書を受領できないことで、仕入税額控除が受けられなくなり、経営に悪影響を及ぼします。インボイス制度では、保存期間や修正方法なども細かく定められているため、適切な運用方法を検討しなければなりません。
クラウド型建設プロジェクト管理サービスのANDPADは、インボイスに関わるさまざまな業務の効率化を実現します。導入企業数No.1のサービスとして、業種を問わずさまざまな企業・ユーザー様にご利用いただいております。導入後もさまざまなサポートをご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2023年12月28日時点の法律に基づき執筆しております。