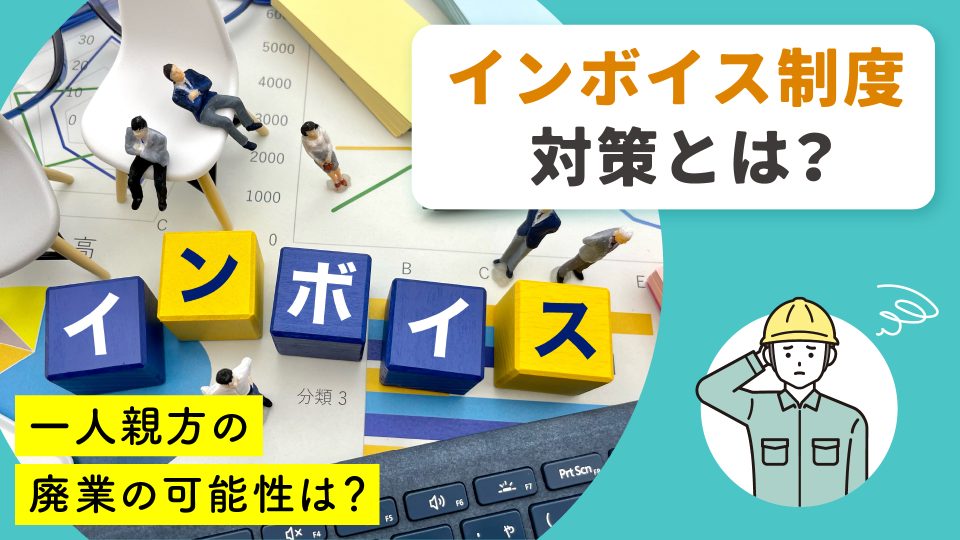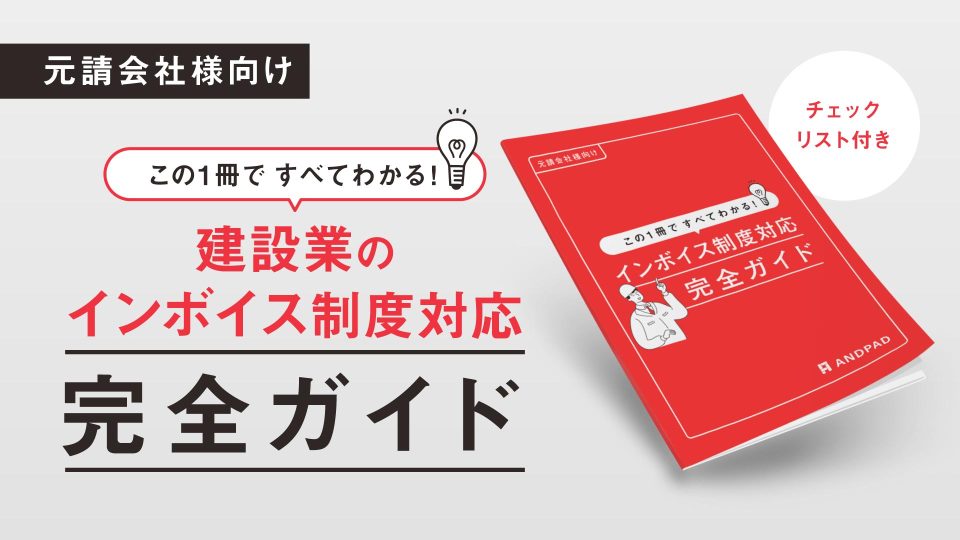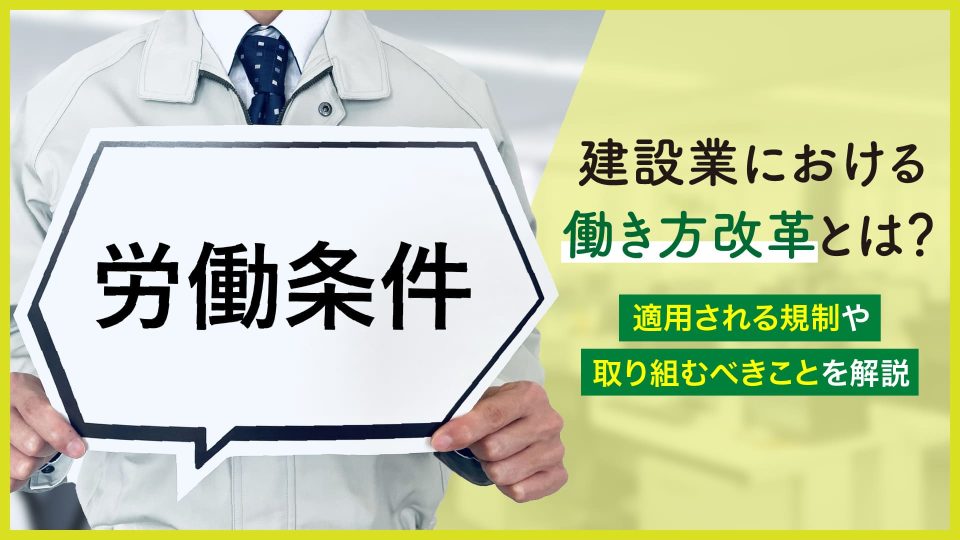インボイス制度は、2023年10月に導入されました。インボイス制度の目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。ただし、免税事業者は大きな影響を受けることになります。建設業における一人親方も例外ではなく、なかには廃業を検討する一人親方も珍しくありません。
本記事では、インボイス制度の概要や、課税事業者になるメリット・デメリットなどを解説します。ぜひ参考にしてください。
インボイスの全体像を把握したい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:インボイス制度が建設業に与える影響とは?導入を検討する際の注意点も解説
そもそもインボイス制度とは

まずは、インボイス制度の概要や、インボイス制度の元となる消費税の仕組みについて解説します。インボイス制度は、一人親方への金銭的な負担が増える可能性が高く、取引にも大きな影響を与えるため、インボイス制度についてしっかり知識を深めておきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は、適格請求書等保存方式です。消費税を受け取った事業者が、正確に消費税を納めるために必要な適格請求書(インボイス)を発行する制度を指しています。インボイス制度を建設業に当てはめれば、元請け企業の大半は、これまでも消費税を納めてきた課税事業者であるため、申請すればインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になれます。
一方で、一人親方のような免税事業者はこれまで消費税を納税していないケースがございます。インボイスを発行するためには、まず課税事業者になって、消費税を納めることになります。一人親方がインボイスを発行できなければ、元請け企業が消費税を負担する必要が出てきます。負担を嫌う企業は免税事業者へ仕事を依頼しにくくなり、一人親方の免税事業者は仕事が減る可能性があります。
インボイス制度における消費税の仕組み
現在の消費税率は、通常の税率である10%と軽減税率の8%があります。これまでの課税事業者は、仕入れで支払った消費税を仕入税額控除してから消費税を申告し、納税する仕組みでした。インボイス導入後は、仕入税額控除するためにインボイスが必要になっています。インボイスは、課税事業者が適格請求書発行事業者に登録することで発行できます。
適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を納税地の税務署に提出しなければなりません。取引先が免税事業者の場合は、インボイスを発行できないため、インボイスを受け取れません。インボイスがなければ、仕入れした分の仕入税額控除を受けることができなくなり、その分の消費税を負担することになります。
これを建設業に当てはめると、元請け企業が一人親方などの免税事業者に発注した分の消費税は、元請け企業の負担となります。免税事業者の一人親方にとって、インボイス制度は大きな影響を及ぼす可能性があります。
一人親方が課税事業者を選択するメリット・デメリット

インボイス制度の導入により、建設業では一人親方の多さが論点となっています。一人親方で免税事業者の場合は、免税事業者のままでいるのか、課税事業者となるのかを選択しなければなりません。
ここでは、課税事業者となり、適格請求書発行事業者となる場合のメリットやデメリットを解説します。
関連記事:インボイス制度が一人親方に与える影響とは?課税事業者の税負担軽減特例も解説
課税事業者を選んだ一人親方のメリット
一人親方が、課税事業者を選んだ場合のメリットは、取引先や仕事が減るリスクを軽減できることです。
元請け企業からの視点でいえば、消費税の負担リスクがないため、これまでと同様、仕事を依頼しやすくなります。場合によっては一人親方で免税事業者へ回していた仕事を受注できるようになり、売り上げにつながるかもしれません。仕事が減るリスクを軽減できることは大きなメリットになります。
課税事業者を選んだ一人親方のデメリット
これまでは、年間の売上が1,000万円以下であれば免税事業者となるため、消費税を申告する必要はありませんでした。課税事業者を選んだ場合、消費税を申告・納税することになるため、納税分の負担が増えることになります。
適格請求書発行事業者への登録までの手続きや、適格請求書の発行など、課税事業者であることで発生する事務作業が増え、普段の業務を圧迫する可能性もあります。
一人親方が免税事業者を選択するメリット・デメリット
一人親方が、免税事業者を選択する場合も、メリット・デメリットが生じます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
免税事業者を選んだ一人親方のメリット
免税事業者を選んだ一人親方の大きなメリットは、これまでと変わらず消費税を納めなくて済むことです。納税額が増えないため、キャッシュフローも悪化しません。
ただし、免税事業者の免税分は、取引先が代わりに納めていることを認識しておかなければなりません。建設業では、主に元請け企業が免税事業者の消費税を納めることになります。元請け企業は、消費税の納税額が増えるため、免税事業者の一人親方への仕事の依頼を検討するようになるかもしれません。
免税事業者を選んだ一人親方のデメリット
免税事業者を選んだ一人親方のデメリットは、仕事が減るリスクです。免税事業者分の納税負担が増えれば、元請け企業のキャッシュフローは悪化します。資金繰りにマイナスの影響を与える可能性を考慮する取引先も出てくるでしょう。
仕事を依頼したとしても、これまでの報酬よりも10%以上安価な報酬を提示される可能性があります。加えて、一人親方同士の仕事の依頼であっても、インボイスを発行できなければ仕事を依頼しづらくなってしまいます。
一人親方ができるインボイス制度対策
免税事業者であった一人親方が、課税事業者となり適格請求書発行事業者になる選択をする場合は、インボイス制度への対策が必要です。主な対策は、簡易課税制度の利用とインボイス発行の準備です。ここでは、その2点について解説します。
簡易課税制度の利用
年間売上が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を利用して消費税を納税できます。簡易課税制度とは、中小零細企業などの消費税の計算方法に関する特例です。
簡易課税制度では、みなし仕入率を使って消費税の納税額を簡単に算出できるようになっています。建設業の場合は、第三種事業に区分されていて、仕入率は70%に設定されています。簡易課税制度の消費税の算出方法は、次のようになります。
| 消費税 = (課税売上高 × 0.1) – (課税売上高 × 0.1 × みなし仕入率) |
一般的な算出方法である原則課税方式と比較して、簡易課税制度を利用した方が消費税額が少なくなる可能性があるため、試算してから利用することをおすすめします。なお、この制度を利用するためには、届け出が必要です。
インボイス制度に対応した請求書を準備
一人親方が課税事業者になり、適格請求書発行事業者に登録すれば、適格請求書を発行しなければなりません。適格請求書とは、これまでの区分記載請求書に加えて、制度導入で新たに追加された項目を加えた適格請求書のことです。新たに加えられる3項目は次のようになります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
一人親方が課税事業者になれば、適格請求書発行事業者に登録するために登録申請書を提出します。登録通知書が届けば、取引先に登録番号と交付や受領方法を伝えましょう。登録通知書が届くまでにインボイス発行のためにフォーマットやシステムを導入し、発行と管理の準備を進めます。
関連記事:インボイス制度で何が変わる?建設業者が知っておきたい請求書の書き方や注意点
関連記事:一人親方の請求書の書き方|必須項目やインボイス制度の影響も解説
インボイス制度の影響で一人親方を廃業する場合の手続き

場合によってはインボイス制度導入の影響を受けて、一人親方を廃業する人もいます。一人親方を廃業する際にも手続きが必要です。一人親方の廃業を決めれば、まずは廃業する日を決定します。廃業日とは、税務署に提出する廃業届に記入する廃業した日のことです。廃業に必要な書類は、次の3種類です。
- 個人事業の開業届出・廃業等届出書
- 青色申告の取りやめ届出書
- 廃業の届出書(各都道府県税事務所)
まとめ
インボイス制度の導入により、多くの一人親方が消費税に関する影響を受けています。免税事業者のままでは、仕事が減る可能性があります。すでに、仕事が減ってしまった一人親方もいるのではないでしょうか。消費税納税の負担や適格請求書の発行が難しく、廃業を余儀なくされるケースもあります。
一方、課税事業者となり、適格請求書を発行するためには、新たなフォームやシステムの導入を検討しなければならず、手間に感じる人も多いでしょう。
インボイス制度に対応したシステムの導入をお考えなら、業界シェアNo1の「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。ANDPADの受発注機能の活用で、インボイス制度に対応した、発注・請負・請求までの電子化が可能となり、受発注関連業務を大幅に効率化できるでしょう。
今なら、インボイス制度に関して分かりやすく解説した完全ガイドブックも公開中です。興味のある方は、ぜひ、以下から無料ダウンロードにお進みください。
※本記事は2023年12月22日時点の法律に基づき執筆しております。