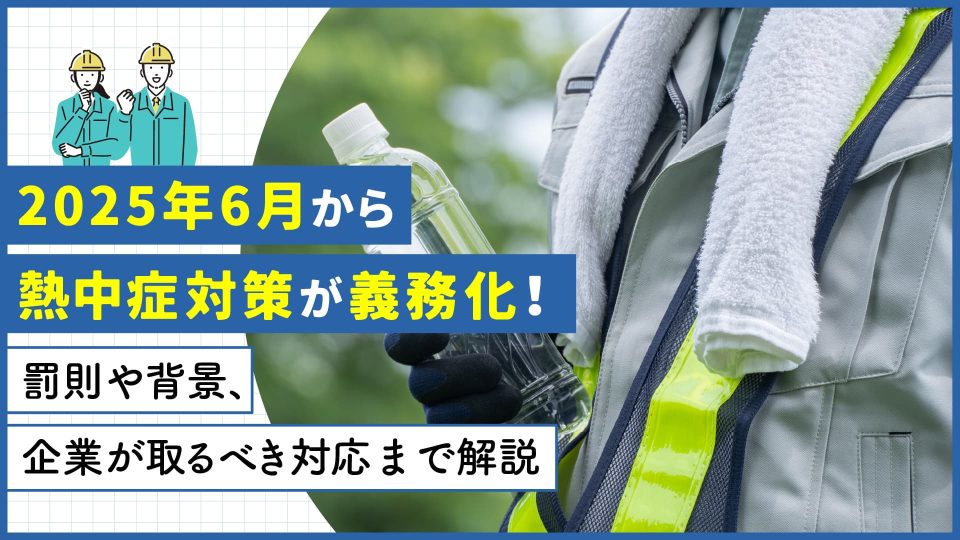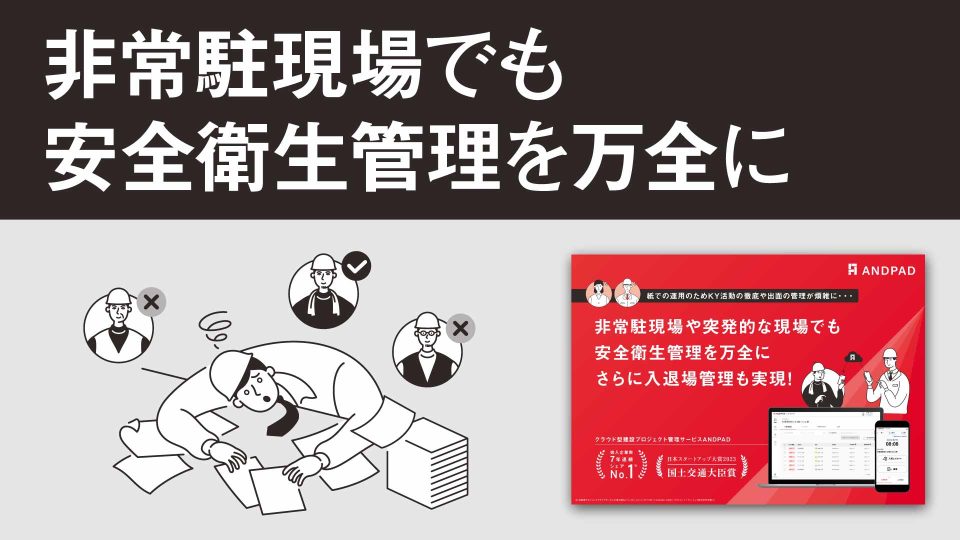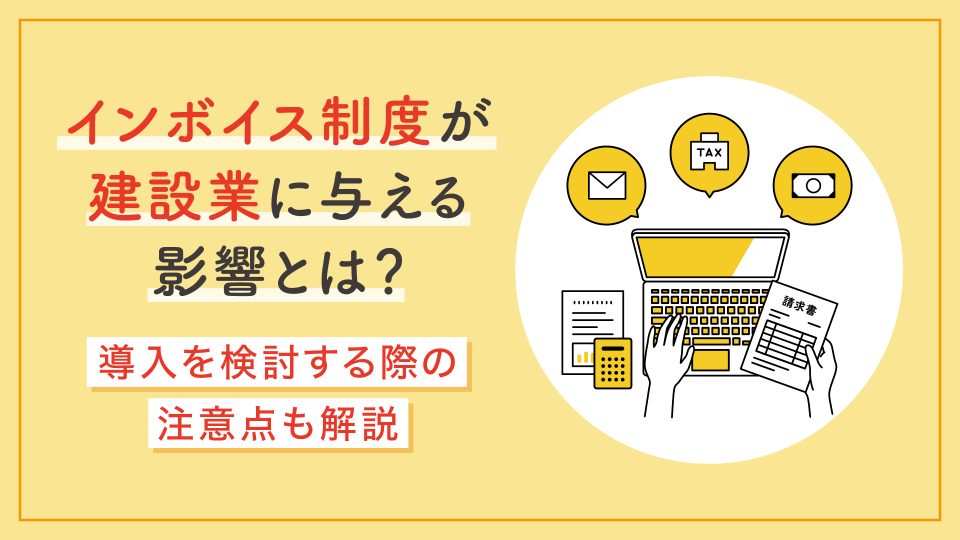この記事では、2025年6月1日から施行される「労働安全衛生規則」の改正について、具体的には義務化される熱中症対策について解説します。この義務化には罰則もあるため、企業は計画的に対応を進めることが求められます。具体的な改正内容や熱中症の定義や熱中症対策が義務化される背景などを知りたい人は参考にしてください。
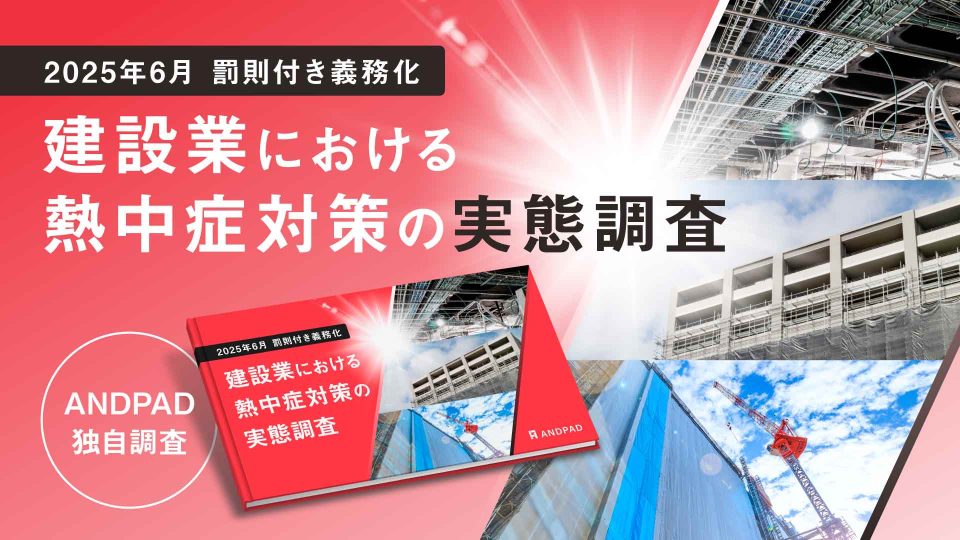
【建設業向け・熱中症対策にまつわる独自調査レポート】2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が強化されました。本調査は、この法改正に関連して、建設業における熱中症対策の実態を把握することを目的に実施しました。建設業界における各業種、現場規模、管理者の常駐有無といった切り口から、リアルな対応状況を考察します。
【2025年6月施行】熱中症対策が義務化
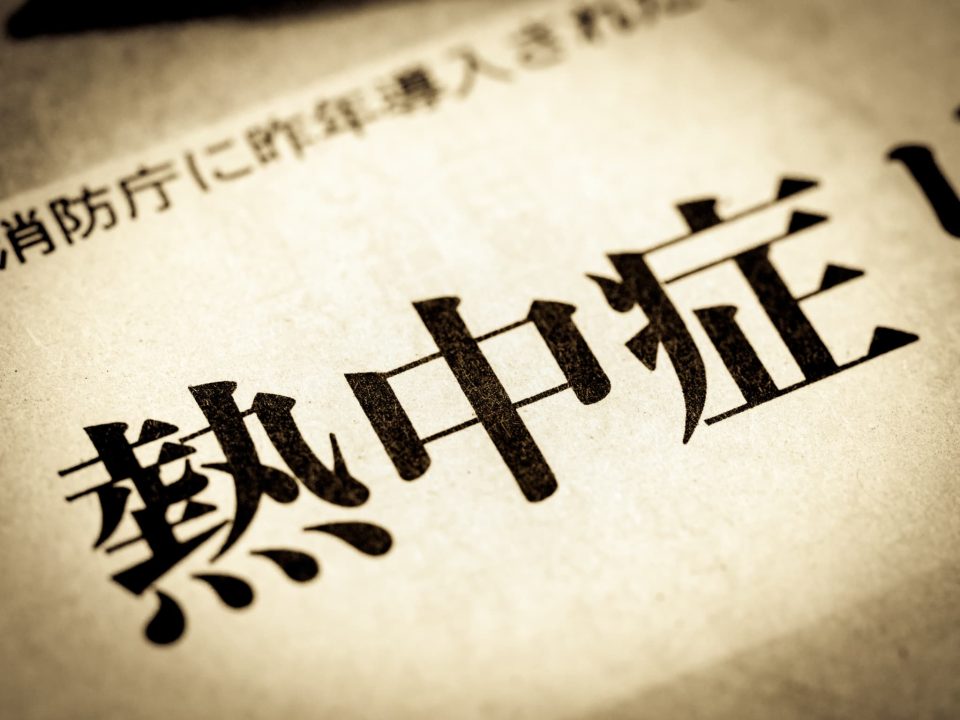
2025年6月から、事業者の熱中症対策が義務化されています。以下では、その内容を解説します。
労働安全衛生規則の改正が施行
2025年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行されます。具体的には、熱中症患者の報告体制整備、熱中症のおそれがある従業員を把握した場合の手順作成、関係する各作業従事者への周知の3点です。以下では具体的な内容を解説します。
熱中症患者の報告体制整備・周知
熱中症は、早期発見が重要です。企業は、熱中症の自覚症状がある従事者や熱中症のおそれがある従事者を見つけた際に、その旨を報告するための体制を整備しなければなりません。
具体的には、報告を受ける責任者の氏名・連絡先・連絡方法を定めたうえで、事業場内の見やすい場所への掲示や、メール・文書の配布などにより明示し、関係者に周知する必要があります。また、報告先として定めた責任者は、従業員から随時報告を受けられる体制を維持しておくことが求められます。
さらに、熱中症のリスクがある従業員を積極的に把握するためには、事前にそのための仕組みを整備しておくことが重要です。
熱中症発生時の手順作成・周知
熱中症のおそれがある従業員を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、以下のような実施手順を作成し、関係者への周知が必要です。
まずは熱中症の恐れがある作業者を当該作業から速やかに離脱させ、身体を冷却します。必要に応じて医師の診察や処置を受けさせ、その他の熱中症症状の悪化防止のための措置を実施しなければなりません。
また、事業場における緊急連絡網や、緊急搬送先となる医療機関の連絡先・所在地などをあらかじめ定めている場合は、それらの情報も手順内に明記しておくことが望ましいとされています。
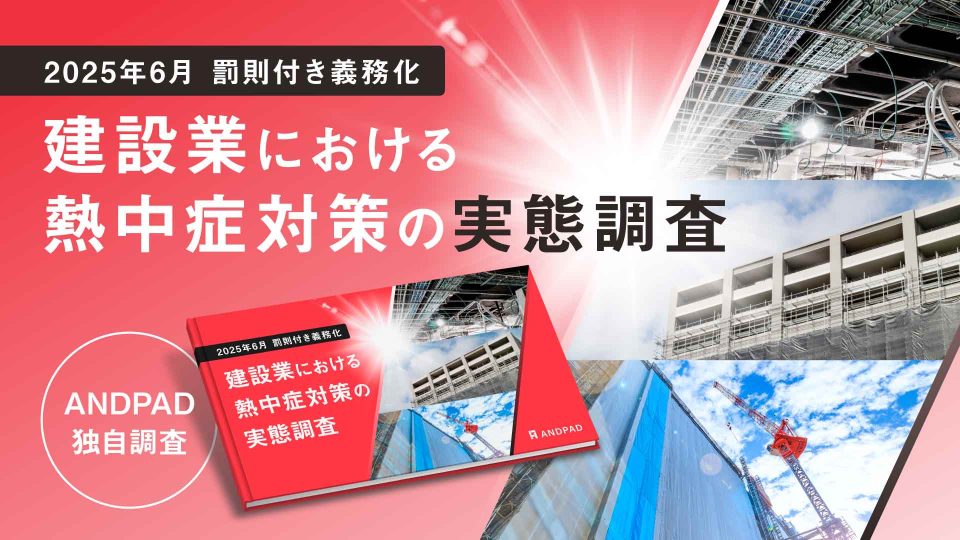
【建設業向け・熱中症対策にまつわる独自調査レポート】2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が強化されました。本調査は、この法改正に関連して、建設業における熱中症対策の実態を把握することを目的に実施しました。建設業界における各業種、現場規模、管理者の常駐有無といった切り口から、リアルな対応状況を考察します。
事業者が熱中症対策を怠った場合の罰則
熱中症対策を怠った事業者には、都道府県労働局長または労働基準監督署長から使用停止命令を受ける可能性があります。また、熱中症対策の実施義務に違反すると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
熱中症対策とは、報告体制の整備、実施手順の作成、関係者への周知のことです。熱中症対策義務化の対象外となる業務でも、状況によっては熱中症を発症するおそれがあるため、自社全体で対策を意識しましょう。
熱中症の定義

熱中症とは、体温が上昇し臓器が高温にさらされることで発症する障害です。人間の身体は体温を平熱に保つために汗をかき、その際に体内の水分と塩分が減少します。その状況が続いた結果、血液の流れが滞って体温が上昇し、重要な臓器が高温にさらされます。救急搬送されたり、最悪の場合死亡したりするケースもあります。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義
「熱中症を生じるおそれのある作業」は具体的に定義されています。WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えた実施が見込まれる作業のことです。
WBGT(湿球黒球温度)とは熱ストレスを評価する暑さ指数を指し、熱中症予防対策を取る際の作業環境管理の指標となります。また、前述した条件に該当しない作業でも、作業強度や着衣の状態によってWBGT基準値を超える場合は熱中症リスクが高まるため、同様の措置が必要です。
熱中症対策が義務化される背景
なぜ、2025年6月から熱中症対策が義務化されることとなったのでしょうか。2つの背景を解説します。
職場における熱中症の死傷者数が増えている
近年の日本では、職場での熱中症による死傷者の数が年々増えています。気候変動の影響から、夏場に異常な気温となる日が増えていることが大きな原因です。2022年から2024年にかけて、3年連続で年間30人以上の死亡が報告されました。労働災害による死亡者数は全体の4%を占めており、熱中症対策がいかに重要かを示しています。
熱中症の初期症状の放置や対応の遅れがみられる
熱中症に関する労災事故では、初期症状での放置や対応の遅れが問題になっています。これまでの法令では、熱中症を原因とする健康障害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応について明確な規定が定められていませんでした。
このたび労働安全衛生規則が見直され、事業者に対する、熱中症による健康被害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応が義務化されました。
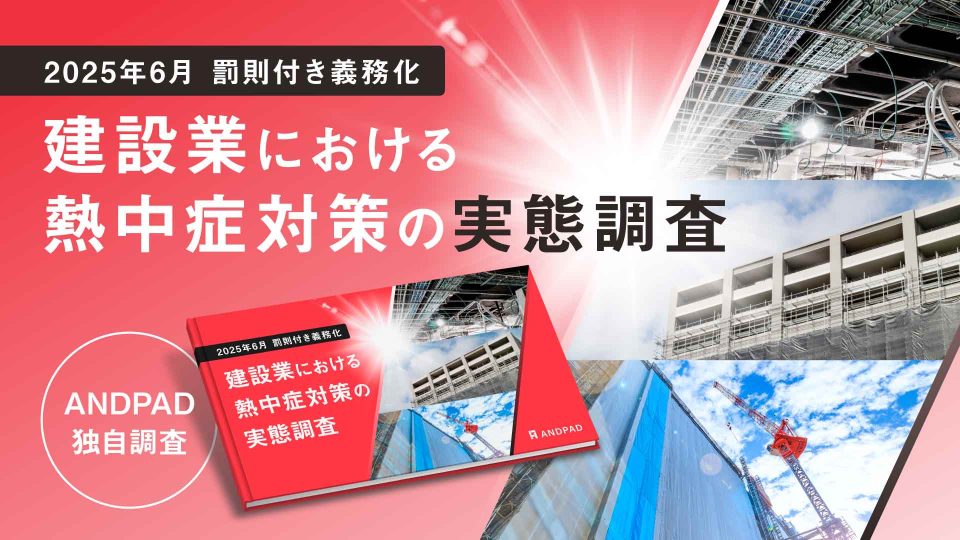
【建設業向け・熱中症対策にまつわる独自調査レポート】2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が強化されました。本調査は、この法改正に関連して、建設業における熱中症対策の実態を把握することを目的に実施しました。建設業界における各業種、現場規模、管理者の常駐有無といった切り口から、リアルな対応状況を考察します。
建設業は熱中症が起こりやすい環境
建設業は野外作業が多く、高温多湿な夏場は熱中症が発生しやすい環境です。具体的には、屋外作業は外気温の影響を直接受けるうえ、身体を動かすことで体温がさらに上昇します。また、水分や塩分の不足が発生しやすい状況という要因も挙げられます。
現に、職場における熱中症の死傷者数は、常に建設業が上位です。作業従事者の健康と安全のためにも、熱中症対策は必要不可欠です。
事業者に求められる熱中症対策の内容と方法、注意点

事業者にはどのような熱中症対策が求められるのか、内容や方法、注意点を解説します。
報告フローを明確にする
まず、報告フローを明確にしなければなりません。作業従事者自身が異変を感じた際や周囲が異変に気付いた際に、どこへ連絡するかを明示した連絡網を作成し、周知徹底することが重要です。体調は急変するケースもあるため、その場合の対応もあらかじめ定めておきます。
報告フローを作成する際は、本社や上長だけでなく、現場責任者が早期に対応できる部署や担当者を設定しましょう。
作業離脱をルール化する
熱中症の初期症状の疑いがある作業従事者を発見した場合は、即座に作業から離脱させなければなりません。あらかじめ、その場合のルールを決めておきましょう。まず、ふらつきや痙攣など熱中症と思われる症状がある場合は離脱させます。
離脱させたあとは、意識確認を実施しましょう。返事がおかしかったり、ぼーっとしていたりするなど普段と様子が違う場合は救急隊を要請します。この間、一人にしないよう注意します。単独で作業を行っている場合は、即座に連絡が取れる体制にしておきましょう。
応急処置・医療機関への搬送ができる環境を整える
熱中症の疑いがある人の意識がはっきりしない場合は、即座に医療機関へ搬送しなければなりません。あらかじめ救急車を呼ぶタイミングや搬送先を決めておき、万が一の場合に備えましょう。
意識がある場合は涼しい場所へと移動し、衣服を緩めて身体を冷やします。この時、氷や冷却パックを使用して身体を冷やしましょう。加えて、経口補水液やスポーツドリンクなども準備し、こまめに水分補給できるようにします。もし自力で水分補給ができそうになければ、すぐに救急隊の要請をしましょう。
作業環境を管理する
作業場のWBGT値を測定し、基準値を超えてしまいそうな場合はWBGT値を下げるための対策を実施しましょう。WBGT値が下がると、熱中症の予防にもつながります。
たとえば、日陰が少なかったり、休憩所から離れていたりする現場には、熱を遮るための屋根または遮光ネットを設置するとよいでしょう。また、冷房や大型扇風機、ドライミストなどを導入し、できるだけ涼しい環境で作業できると予防になります。
作業員の健康管理に努める
作業員の健康管理も、熱中症対策の1つです。施工管理や現場監督が熱中症対策の役割を担い、健康チェックシートの記入や、健康状況の聞き取りを実施しましょう。脱水症状がないか、尿の色でチェックすることもできます。
トイレ内に尿の色によって補給する水分量の目安を提示し、水分補給や塩分補給を促します。また、熱中症になりやすい天候や気温の日は、こまめなWBGT値の測定も重要です。
ANDPAD導入で建設業の安全衛生対策も可能
ANDPADを導入すると、チャット機能を活用できます。このチャット機能を利用すると、メンバー全体への情報共有が可能です。そのため、熱中症対策の報告体制構築に役立ちます。
また、業務指示や安全確認、改善点の反映などの打ち合わせがスムーズになるでしょう。現場にいる従業員に対して、作業する際の安全上の注意事項や、災害事例などの伝達も可能です。
【導入事例】チャット機能活用で熱中症対策も
香川県⾼松市に本社がある新日本建工株式会社では、ANDPADのチャット機能を活用してスムーズな情報共有を実施しています。暑い時期には気温上昇への注意喚起や塩分・水分補給の推奨を伝達し、熱中症の予防に役立てています。また、業務指示や安全確認、改善点の通知などを的確に実施できているそうです。ANDPADのチャット機能は安全衛生にも十分な効果を発揮するといえます。
参考:ANDPADをハブにして、番頭に集中していた業務負荷を大幅に軽減|新日本建工株式会社 様

まとめ
労働安全衛生規則改正が2025年6月1日に施行され、熱中症対策が義務化されています。各企業は報告体制の整備や手順の作成、悪化防止の措置への準備を実施し、作業従事者に周知しなければなりません。なかでも建設業は熱中症が発生しやすい環境であるため、念入りな対応を実施しましょう。
建設の現場には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーにご利用いただいています。熱中症対策の報告体制を構築したいと考えている企業は、ぜひお問い合わせください。