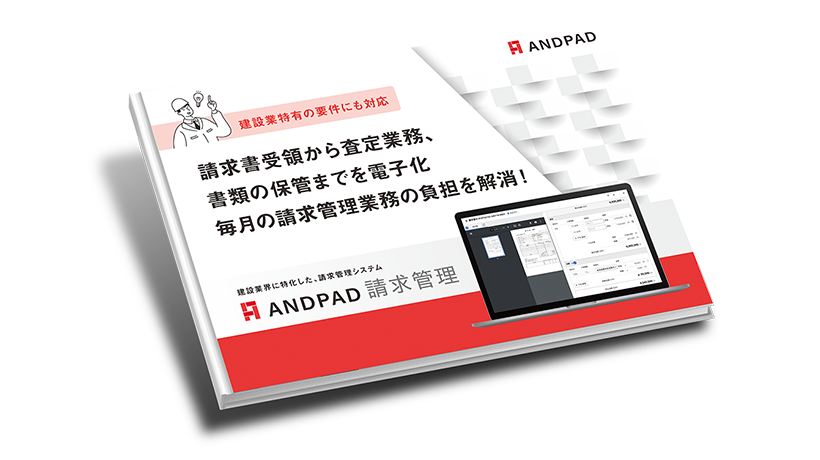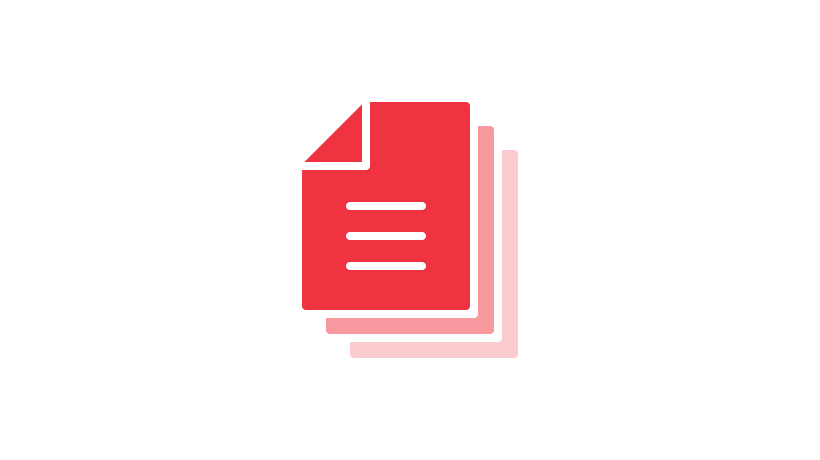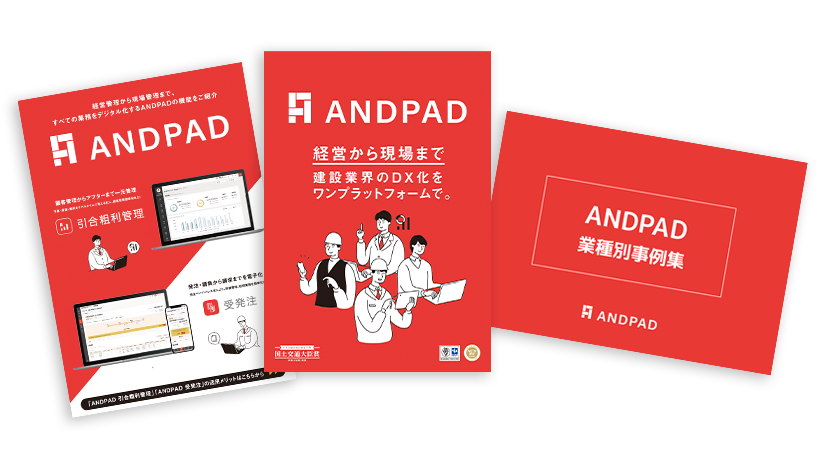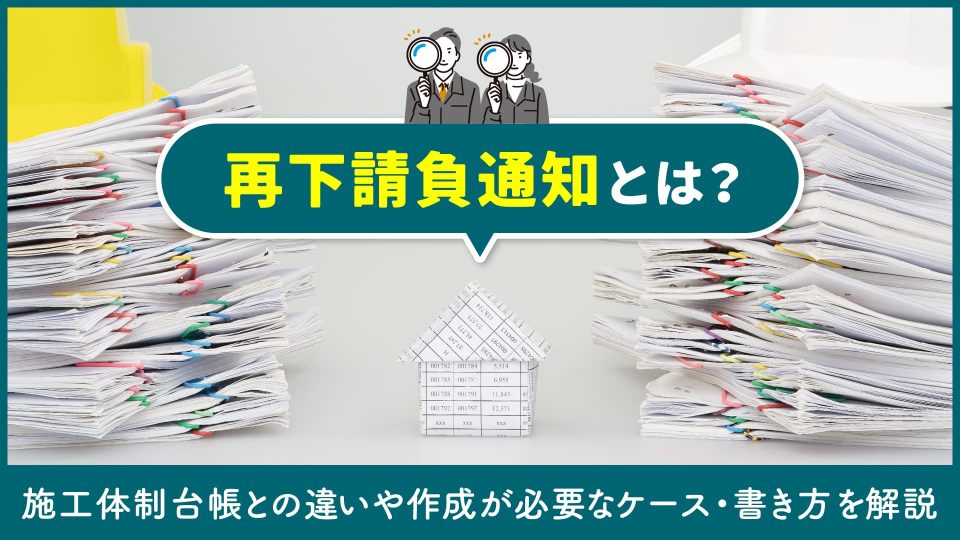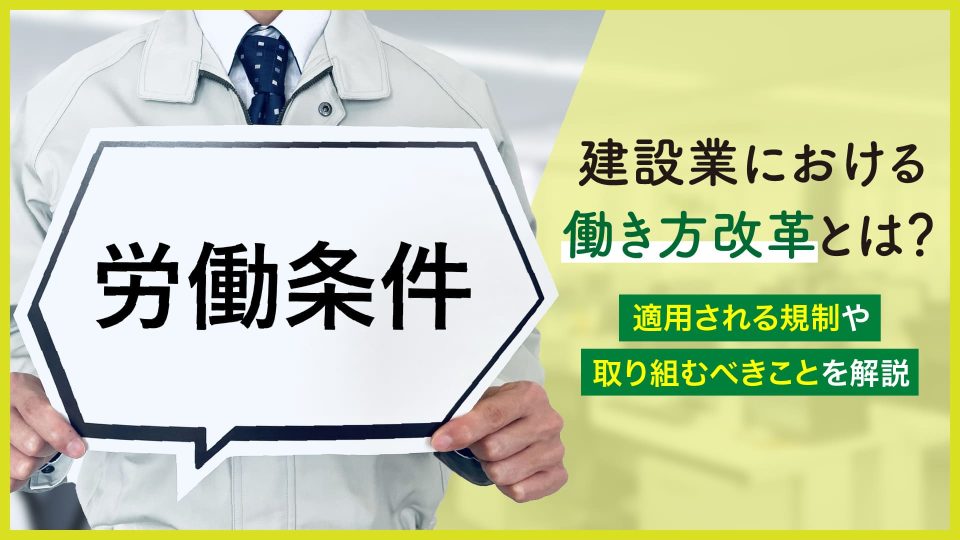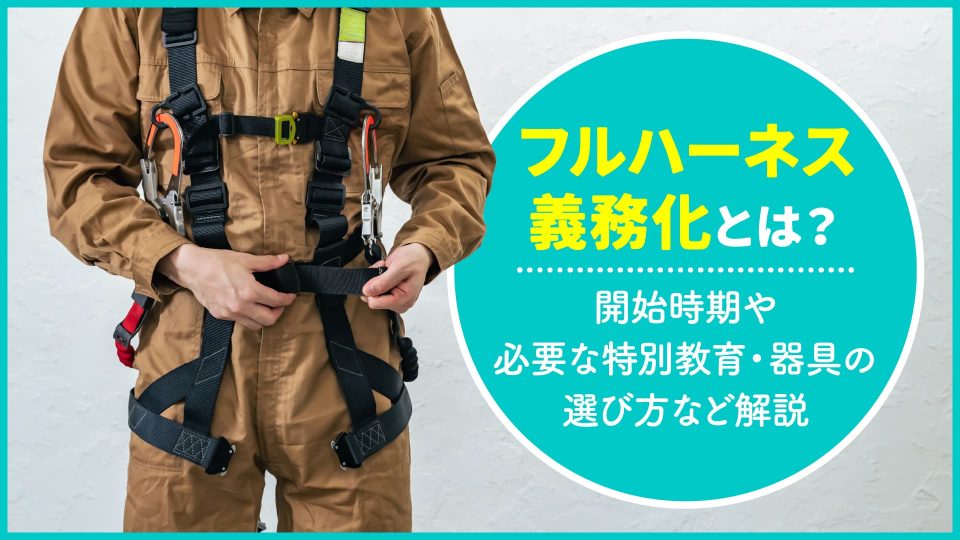建設工事をスタートするにあたって欠かせない書類の1つに、再下請負通知書があります。ただし、名称からはどのようなものか分かりにくいでしょう。この記事では、作成が必要となる条件や記入すべき内容などについて解説します。業務で作成する可能性があり、知識を得ておきたい人は参考にしてください。
再下請負通知書とは

施工体制台帳に含まれる書類の1つで、元請会社が一次協力会社以下との、下請契約の内容を確認するための書類です。どのような企業と協力し、請け負った工事を進めるかを示しており、工事に関わる企業が安全かつ適切に業務を進めているかを確認できます。
施工体制台帳の作成は元請会社の役目ですが、再下請負通知書の作成は一次協力会社以下、下請工事を請け負った企業の役目です。
再下請負通知書が必要なケース
作成が必要なケースは、おもに2つあります。1つ目は、元請会社より工事を委託された協力会社が、別の企業に工事の一部を委託する場合です。2つ目は、二次協力会社が別の企業の工事の一部を委託した場合です。
民間工事では下請金額の総額が4,500万円以上であることが作成条件ですが、公共工事では下請契約を結んだ時点で作成義務があります。
再下請負通知書と施工体制台帳の違い
施工体制台帳も、同じくグリーンファイルに含まれる書類の1つです。2つの書類の大きな違いは、作成する企業です。施工体制台帳は元請会社が作成するのに対し、再下請負通知書は協力会社が作成します。元請会社は協力会社がまとめた情報を再下請負通知書で確認し、建設会社の状況を把握します。
関連記事:施工体制台帳とは?項目別の書き方・記入例、作成義務などの注意点まで解説
関連記事:施工体系図とは?施工体制台帳との違いや作成・保存義務、書き方や記入例を解説
再下請負通知書の欄外部分の項目の書き方
欄外部分は、どのように記入すればよいのでしょうか。項目ごとの書き方を解説します。
関連記事:安全書類の記入例をわかりやすく解説!全建統一様式を採用するメリットもご紹介
日付
書類の作成日を記入します。年の部分は西暦でも和暦でも問題ありませんが、多くの場合和暦で記入されます。
直近上位の注文者名
直近上位となる企業名を記入します。直近上位とは、下請工事を自社へと委託した企業です。一次請負が自社のケースでは、元請の企業名を記入します。
現場代理人名(所長名)
直近上位企業の、現場代理人の氏名を記入します。法的な決まりはないため、元請の現場代理人の氏名を記入することもあります。
元請名称・事業所ID
元請の企業名を記入します。元請会社が建設キャリアアップシステムに登録していれば、事業者IDも記入しましょう。
報告下請負業者
報告下請負業者は自社のことです。自社の住所や電話番号などを記入します。自社が建設キャリアアップシステムに登録していれば、事業者IDも記入しましょう。
自社に関する事項の項目と記入例
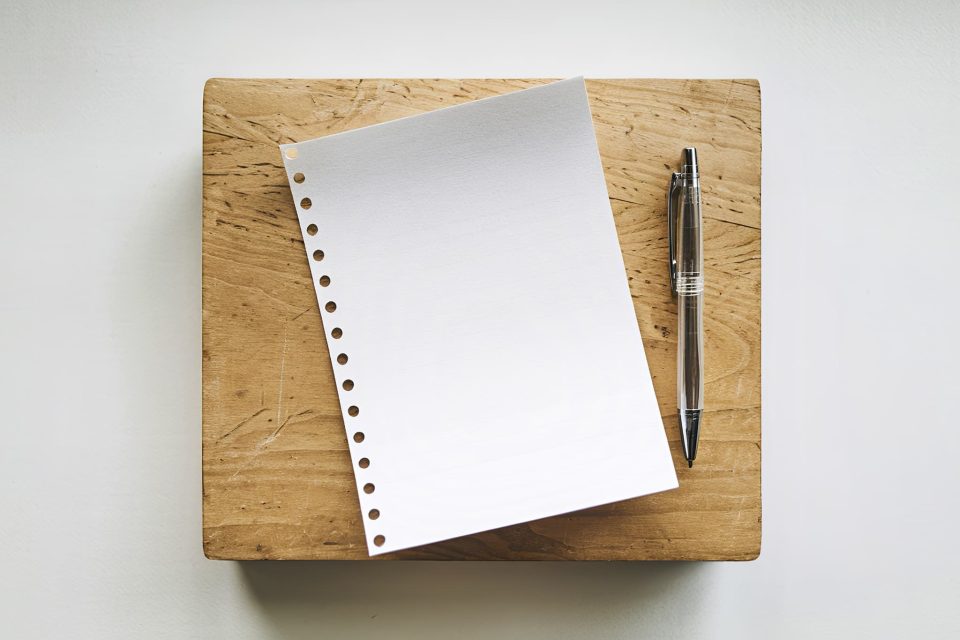
自社に関する事項の項目は、多岐にわたります。それぞれの項目ごとの記入例を解説します。
工事名称及び工事内容
自社で実施する工事内容を記入します。形式は、「(工事名称)に係る(自社の工事内容)」です。
工期
自社が実施する、工事の期間を記入します。工事のスタート前に見込みの期間を記入し、工事のスタート後に工期が伸びた際は、再度作成しましょう。
注文者との契約日
自社と直近上位の企業との間で、実施する工事の下請負契約を結んだ日付を記入します。
建設業の許可について
工事に欠かせない許可業種において、自社が所有している内容について記入します。土木工事業や建設工事業、大工工事業など施工に欠かせない業種、許可業種の許可番号、許可を受けた年月日を記入しましょう。
ただし、請負金額が500万円未満、建築一式では1,500万円未満の工事では建設業の許可を得ていなくても施工可能で、その際は斜線で記入欄を消します。
監督員名・権限及び意見申出方法
自社に所属する監督員の氏名を記入します。権限及び意見申出方法の欄には、協力会社と交換した施工に関する意見のやりとりについて記入しましょう。記入例は、「下請負契約書第◯条記載の通り。文書による。」です。
現場代理人名・権限及び意見申出方法
自社に所属する現場代理人の氏名を記入します。権限及び意見申出方法の欄には、直近上位の注文者と交換した施工に関する意見を記入しましょう。
主任技術者名・資格内容
自社に所属する主任技術者の氏名を記入します。主任技術者とは、工事現場で技術的な管理をする、一定水準以上の知識や経験を持つ人材のことです。原則、主任技術者は常駐することになるため「専任」に〇を記入します。他の工事と兼任しているのであれば「非専任」に〇を記入しましょう。資格内容の欄には、主任技術者が持つ資格を記入します。
安全衛生責任者名
安全衛生責任者の氏名を記入します。労働安全衛生法で定められている事業所の安全管理をする人材のことを指します。資格は義務ではありませんが、現場に常駐する現場代理人か主任技術者、または職長から選ぶことが条件です。
安全衛生推進者名
安全衛生推進者の氏名を記入しましょう。下請企業の安全衛生管理を担当する人材のことを指します。現場に10人以上49人以下の従業員が常駐しており、加えて自社の現場事務所が現場に位置するケースでは自社から選びます。その他の場合は、直近上位企業の安全衛生推進者の氏名を記入します。
雇用管理責任者名
雇用管理責任者の氏名を記入します。役職に就いている際は、役職も記入します。建設労働者が自社に1人以上いる場合は、雇用管理者を選任することが義務付けられています。資格は不要ですが、企業の代表か労務管理担当から選ぶことが一般的です。
専門技術者名・資格内容・担当工事内容
自社が担当する工事を始める際、内容次第では他の専門工事と合わせ、自社で直接施工することがあります。その際は、現場ごとや担当業種ごとに専門技術者を置かなければなりません。
なお、「主任技術者」の条件を満たす必要があります。そのため「資格内容」の欄には、主任技術者の条件を記入します。「担当工事内容」の欄には、附帯する工事の内容を記入しましょう。
登録基幹技能者名・種類
登録基幹技能者が工事に関わる場合、氏名と種類を記入します。登録基幹技能者とは、現場での作業を円滑に進める役割を担い、その資格を所有する人材のことを指します。
一号特定技能外国人の従事状況
一号特定技能外国人は、特定産業分野において相当程度の知識か経験を持ち、在留資格を持つ外国人です。在留資格を持つ就労者が自社に関わっている場合は「有」に〇を、そうでなければ「無」に〇を記入します。
外国人建設就労者の従事状況
外国人建設就労者が自社に携わっている、または携わる予定がある場合は「有」に〇を、そうでない場合は「無」に〇を記入します。該当する就労者がいる際は、外国人建設就労者建設現場入場届出書の提出が必須です。
外国人技能実習生の従事状況
外国人技能実習生とは、母国のために日本企業で技術を学びに来た外国人のことを指します。自社に外国人技能実習生が携わっている場合は「有」に〇を、そうでない場合は「無」に〇を記入します。
健康保険等の加入状況
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各保険の企業加入状況を確認します。併せて事業所整理番号等も記入します。
再下請負関係の項目と書き方
自社が再下請負を委託した、建設工事に関する情報を記入します。「自社に関する事項」とおおむね似通っていますが、自社が再下請負人に委託した工事の詳細を記入することがポイントです。また「工事名称及び工事内容」や「工期」、「契約日」は間違いやすいため、注意しましょう。自社より下に協力会社がいない場合は、項目全体に斜線を引く必要があります。
再下請負通知書に関するよくある質問
再下請負通知書に関して、疑問に感じやすく、頻出する2つの質問について解説します。
再下請負通知書に押印は必要?
再下請負通知書には押印欄がありますが、内閣府が進める押印手続きの見直しにより、押印は不要としている自治体もあります。例として、青森県では規則改正が行われ、再下請負通知書への押印は不要になりました。押印が必要な場合は、個人印ではなく企業印の押印が求められるため、注意が必要です。
再下請負通知書は一人親方でも必要?
一人親方でも、他の協力会社と同じく元請会社から仕事を受ける立場であるため、提出が義務付けられています。企業が作成する場合と内容はさほど変わりませんが、以下の点について注意が必要です。まず、企業名がない場合は個人名を、営業所の名称には、自分の氏名を記入します。次に、健康保険等の加入状況はすべて「適用除外」に〇を記入しましょう。
再下請負通知書を作成した後の流れ

原則として、作成した書類は直近上位の企業に提出します。提出された書類は、一次協力会社が集めたのち、「下請負業者編成表」を作成して元請会社に提出します。工事着工前に、メールや郵送、持参するなど、元請会社の指示に従い提出しましょう。
提出期限は工事着工の2週間前までが一般的です。提出が遅れると、着工に影響が出る可能性があるため注意しましょう。
まとめ
グリーンファイルの1つである再下請負通知書は項目が多く、書き方が分かりにくいと感じる人も珍しくありません。元請会社から工事を委託された協力会社がさらに別の企業に工事の一部を委託した場合、再協力会社がさらに別の企業の工事の一部を委託した場合に作成します。各項目に記入すべき内容を確認し、間違いがないよう作成しましょう。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1のサービスであり、業種を問わず幅広い導入実績があります。使いやすいUI・UXを実現する高い開発力と、年間数千回以上の導入説明会を実施する手厚いサポート体制が特徴です。まずはお気軽にお問い合わせください。