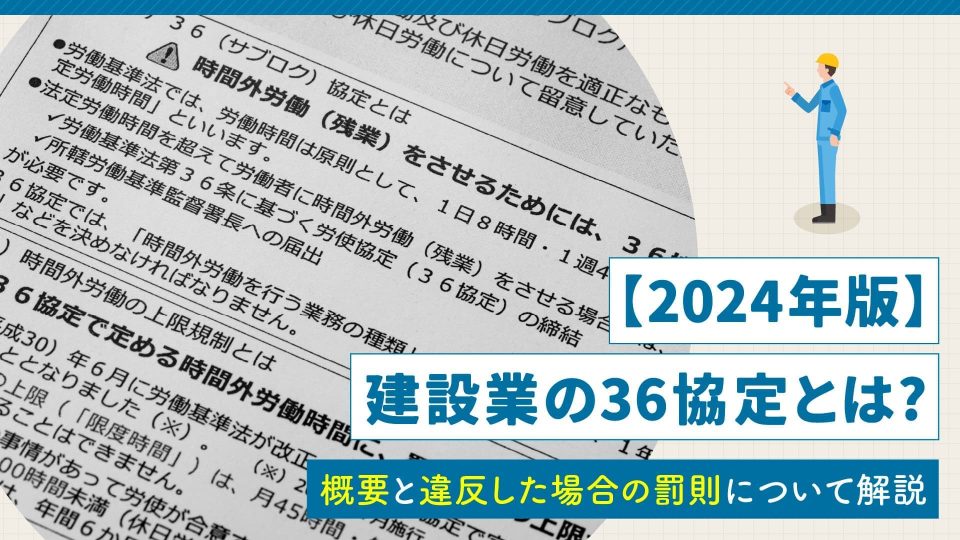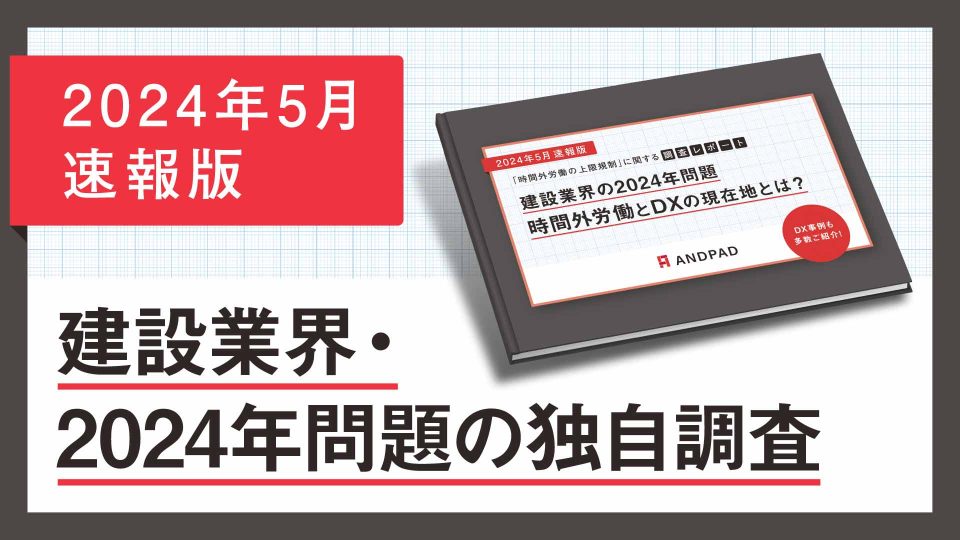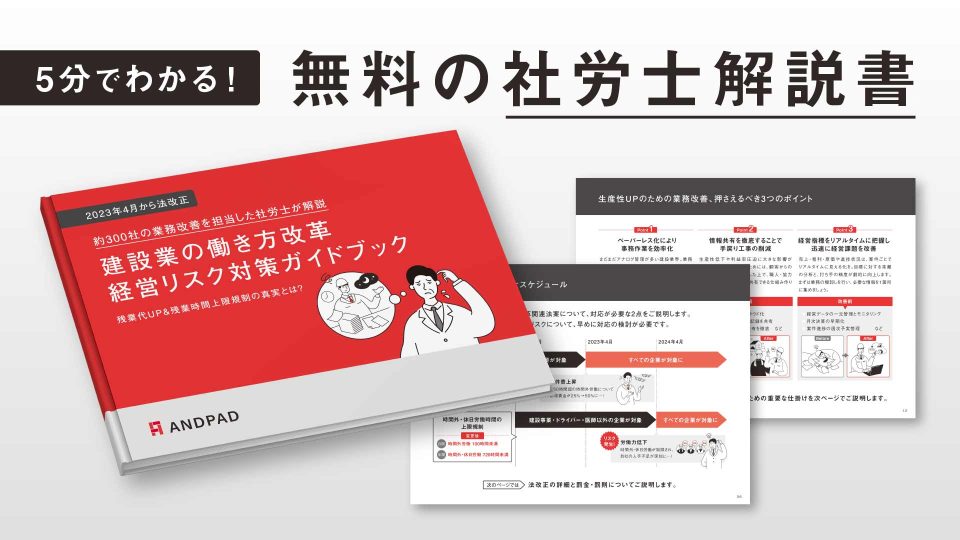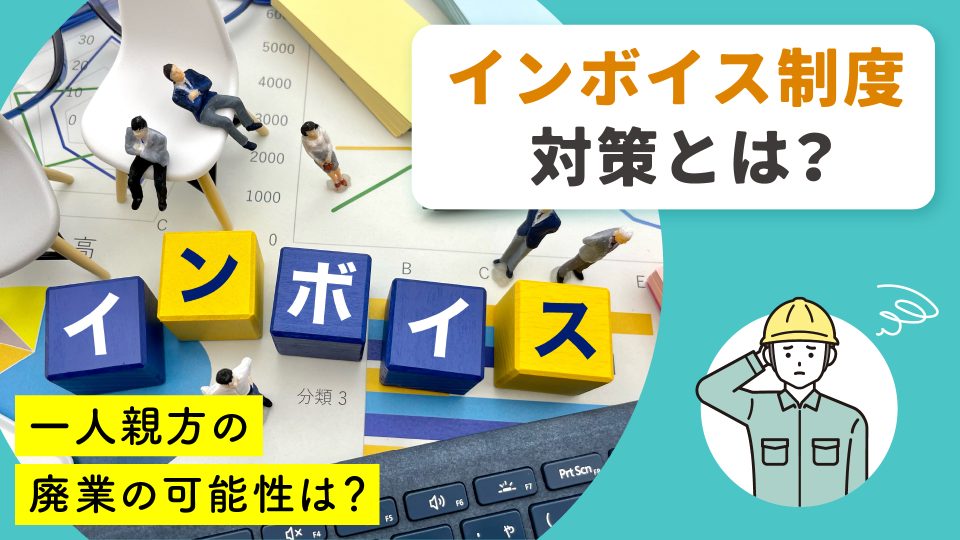建設業において、2024年4月から、36協定の時間外労働が適用となりました。この記事では、36協定について改めて確認したい担当者に向けて、36協定の基礎知識や2024年に変更されたポイントなどについて、わかりやすく解説します。違反した場合の罰則や届出書についても解説するため、ぜひ役立ててください。
36協定とは

2024年4月から、建設業でも他の業種と同じ上限基準が適用となった「36協定(サブロクきょうてい)」は、時間外・休日労働に関する協定を指す通称です。労働基準法36条にもとづく労使協定であることから、略して36協定と呼ばれています。36協定で定められている時間外・休日労働の条件については、次の項目で詳しく述べます。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
労働時間の上限
労働基準法により、1日・1週の労働時間が決められています。法定で定められた労働時間の上限は、1日8時間および1週40時間です。これを、法定労働時間といいます。また、企業は従業員に対して、少なくとも週に1日以上または、4週に4日の休日を与えなくてはなりません。これを法定休日といいます。
時間外労働および休日労働には36協定の締結が必要
法定労働時間や法定休日を超えて労働者に労働をさせる場合には、36協定の締結が必要です。企業は、所轄の労働基準監督署に、36協定で締結した内容を記載した「時間外労働・休日労働に関する協定届」を、提出します。
所轄の労働基準監督署に持参、郵送する以外に、電子申請することも可能です。36協定があれば、際限なく時間外労働や休日出勤をさせられるわけではありません。「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」など、定める必要があります。
時間外労働の上限規制とは
時間外労働の上限規制は、働き方改革関連法による改正後の労働基準法により、法定化されました。特別な事情や臨時的な事情がない限り、原則として、企業は、従業員に月45時間・年360時間を超える、時間外労働をさせることができなくなりました。上限規制は、2019年4月から施行されています。なお、中小企業には1年間の猶予が与えられ、2020年4月1日から施行となりました。
建設業界には5年間の猶予
時間外労働の上限規制は、前述の通り、2019年4月に施行されました。建設業や自動車運転者、医師など、一部の業種において設けられていた5年間の猶予期間は、2024年4月に終了し、労働時間の上限規制の対象になりました。時間外労働の上限規制の適用が猶予されている建設業界の事業範囲は、労働基準法第139条で定められています。
建設業界に5年の猶予期間が設けられた背景
建設業界の猶予期間が5年と長く設けられた背景には、建設業界が抱える問題が影響していると、考えられています。建設業界では、長時間労働や休日出勤が課題です。1週間の労働時間が長く、休日が十分に取れない労働者は少なくありません。その理由として、人手不足や短期的な案件の多さ、天候や資材の入荷時期などによって、スケジュールが左右される点があげられます。
36協定の時間外労働の上限内では、定められた工事の完成時期を遵守することが困難であると判断されて、施行から5年間の猶予期間が設けられました。
【2024年4月適用】時間外労働の上限時間

時間外労働の上限期間は、36協定を結べば、法定労働時間を超えた労働が可能です。建設業界においては、2024年4月以前は、時間外労働の上限時間は定められていませんでした。2024年4月以降は、時間外労働の時間数が原則月45時間・年360時間以内に制限されます。なお、臨時的な特別な事情がある場合に限り、時間外労働の上限期間を超えて労働させてよいとされています。
臨時的な特別の事情がある場合
労働基準法第36条第5項では、臨時的な特別の事情があって、労働者と使用者のあいだで合意に達した場合に限り、月45時間・年360時間を超えてもよいとしています。ただし、臨時的な特別の事情がある場合でも、以下の条件は、すべて遵守することが必要です。
- 時間外労働が、年間で720時間以内であること
- 時間外労働と休日労働の合計が、月に100時間未満であること
- 時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が80時間以内であること
- 時間外労働が月45時間を超えてよい回数は、1年間に6回が限度である
建設事業のうち、災害の復旧および、災害復興事業の場合にあたるものについては、2024年4月以降も、2と3の条件は適用されません。
36協定に違反した場合の罰則
36協定に違反した場合、労働基準法違反として、企業には6か月以内の懲役、もしくは30万円以内の罰金が科されます。建設業界では、2024年4月まではこの罰則が適用されず、月45時間・年で360時間を超える労働については、厚生労働大臣の告示による行政指導にとどまっていました。
今後は、36協定に違反した場合に罰則があるだけでなく、悪質なケースと認定されると、企業名が公表されます。企業名が公表された場合、36協定に違反しているとして、社会的な信用を失い、事業の継続が困難となる恐れもあるでしょう。
36協定における届出書の種類
時間外労働の上限時間が設けられたことにより、36協定の書式が変更になりました。以前の書式から変更となった点について、ケースごとに必要な届出書を以下で解説します。
月45時間超の時間外・休日労働・災害時の復旧・復興の対応の全てにおいて見込まれない
このケースにおいて提出する必要がある届出書は、「時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)様式第9号」です。
月45時間超の時間外・休日労働が見込まれる、災害時の復旧・復興の対応は見込まれない
この場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)様式第9号の2」を提出します。1枚目は、前項の「様式第9号」と同じく「一般条項」、2枚目は「特別条項」を締結する様式です。
災害時の復旧、復興の対応が見込まれる
月45時間超の時間外・休日労働が見込まれる場合は、「様式第9号の3の3(特別条項)」を締結します。見込まれない場合は、「様式第9号の3の2(特別条項)」を締結します。
建設業の36協定は「事業場」ごとに届け出る

建設業の36協定は、工場や支店、営業所など、労働管理している「事業場」ごとに、届け出なくてはなりません。比較的大きな建設現場や工場など、現場で労働管理をしている場合は、現場ごとに36協定の届け出が必要です。現場で労働管理をしていない小規模な建設現場は、本社や総括事務所など、労働管理をしている直結上位の組織が、36協定を届け出ます。
なお、現場が複数ある場合は、現場ごとか、事業所でまとめて提出するか、いずれかを選びます。その場合の判断基準は、労働管理をしている場所がどこであるかです。
36協定以外にもある知っておくべき制度
従業員を雇用するにあたって、確認しておきたい2つの制度について解説します。
正規・非正規社員の同一労働同一賃金
正規・非正規社員の同一労働同一賃金とは、同じ職場で同じ業務内容の従業員に対して、同一の賃金を支払うことを定めた法律です。正規社員と非正規社員とのあいだで、非合理な待遇格差をなくし、公平な労働条件を確保する目的で制定されました。正社員にも出勤手当や危険手当などが支給されている場合は、雇用形態に関わらず、支給しなくてはなりません。
月60時間超の時間外労働における割増賃金率の引き上げ
2023年4月から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金が、引き上げとなりました。労働時間が月60時間を超えると人件費が大きく増加するため、勤怠管理をしっかりと行いましょう。時間外労働のみが引き上げの対象であるため、休日労働と深夜労働の割増賃金率に、変わりはありません。
建設業の業務改善を進めるための方法
建設業においては、労働時間の上限制限や時間外賃金の割増など、業務改善の推進は急を要します。業務改善をスムーズに進めるための方法を、2つ解説します。
正確な勤怠管理
勤怠管理システムを利用することで、従業員1人ひとりの正確な労働時間が把握できます。36協定の上限を超えそうな労働者がいるか一目瞭然です。建設業は、会社や事業所によらず、自宅から直接建設現場に向かい、また自宅に帰るという直行直帰のシステムを取ることが多く、労働時間を正確に把握することが困難でした。
従業員の労働時間を正確に把握することが、労働時間上限への対応の第一歩です。正確な勤怠管理をすることで、36協定の罰則を避けられるだけでなく、業務改善にもつながるでしょう。
DX化による生産性向上で業務改善
DX化により労働時間を削減することで、生産性を向上させる方法があります。建設業におけるDX化は、AIやドローンの活用、情報通信技術を取り入れたICT重機の導入など、多岐にわたります。現場の効率化を進めるクラウドサービスの導入から始めることが、自社や現場にデジタル技術を普及させる近道です。
まとめ
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定を指す言葉です。5年の猶予期間を経て、2024年4月から建設業でも適用されました。時間外労働や休日出勤が常習化している建設業において、労働時間の上限制限や、時間外賃金の割増など業務改善は急ピッチで進めなくてはなりません。スムーズな業務改善のために、まずはクラウドサービスを導入し、現場の効率化に努めましょう。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、使いやすいUI・UX、年間数千を超える導入説明会を実施するサポート力などを有し、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。まずは、以下からお気軽にお問い合わせください。