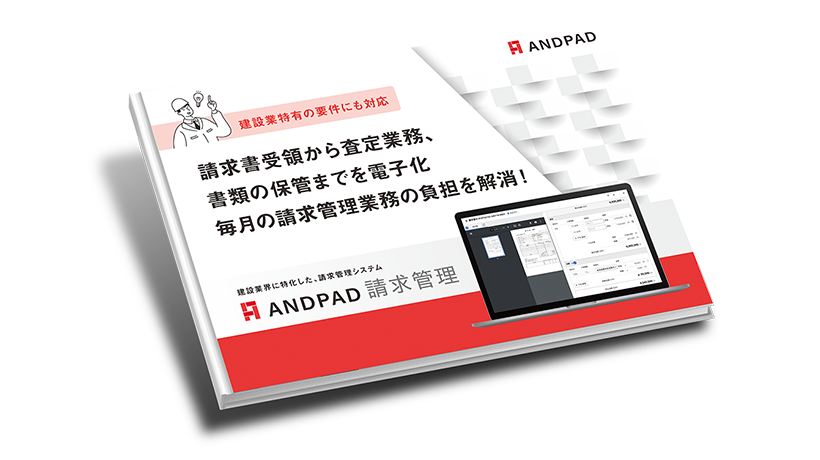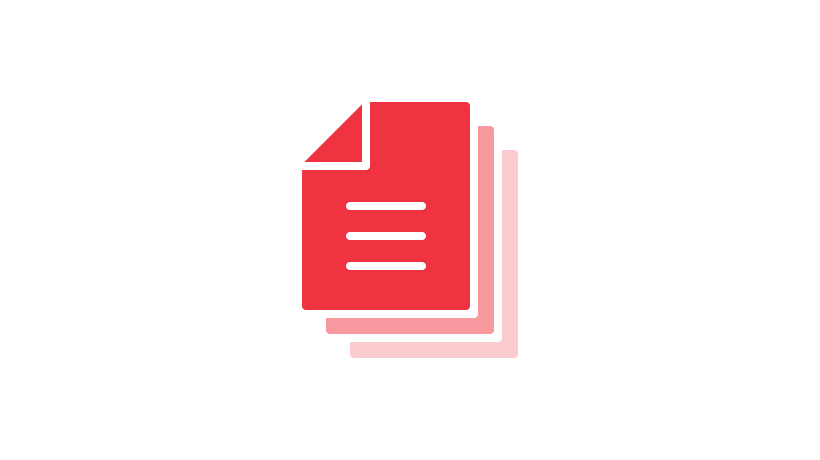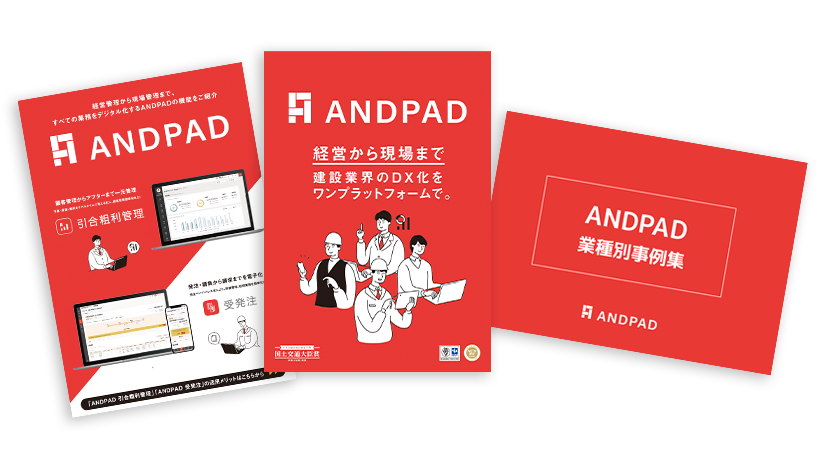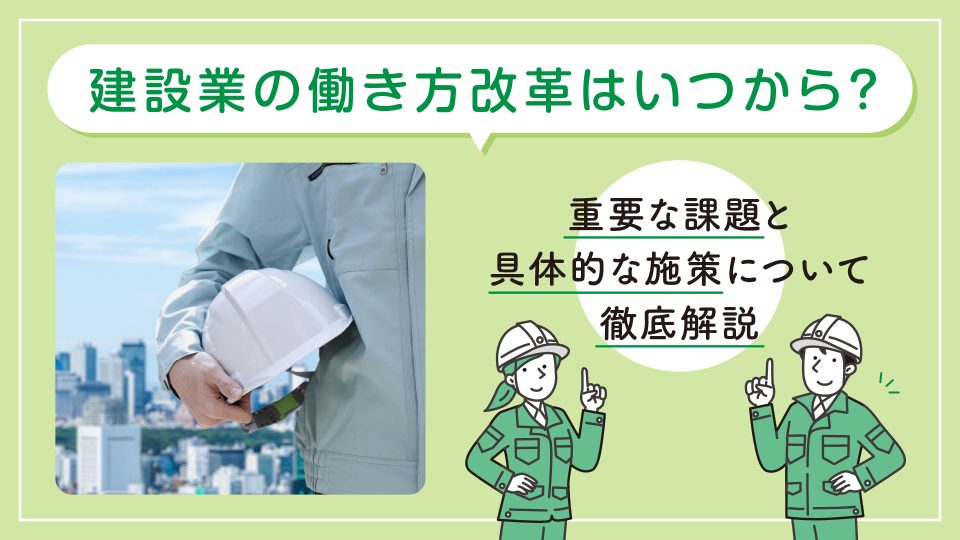昨今は、さまざまな業界で働き方改革が推進されています。しかし、建設業をはじめとする一部の業界では、実現にいくつかのハードルがあるとされています。一体、どのような点が働き方改革の実現を困難にしているのでしょうか。本記事では、建設業における働き方改革の問題点、および実現するためのポイントを解説します。興味関心を持った方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
2024年4月より施行された「働き方改革関連法」で生じる2024年問題。以下では、2024年問題について詳しく解説しています。全体像を理解したい方はご覧ください。
関連記事:2024年問題で建設業界がすべきことは?具体的な課題と対応策を解説
働き方改革とは

昨今は、少子高齢化や働き手の志向性の多様化により、働き方の自由度が高まっています。働き方改革とは、働く人々がそれぞれの事情に応じて働き方を選択できる社会を実現するための改革です。具体的な改革内容として、時間外労働の上限規制や月60時間を超える残業に対する割増賃金率引き上げなどが挙げられます。
働き方改革関連法は2019年4月1日から順次施行されており、2024年以降は建設業でも本格的に取り組みが実施される予定です。
関連記事:建設業における働き方改革とは?適用される規制や取り組むべきことを解説
関連記事:建設業の残業規制が2024年4月から施行!現状と課題、企業がとるべき対策は?
建設業界における2024年問題とは
各業界で進められている働き方改革ですが、建設業においては2024年問題が各種改革案を導入する障壁となっています。建設業の2024年問題とは、働き方改革関連法が適用される2024年4月までに、建設業界が解決する必要がある労働環境問題のことです。2024年4月から施行される建設業の働き方改革の具体例として、時間外労働の規制が挙げられます。
しかし、現状では一部の企業が時間外労働の上限規制への対応ができている状態に留まっています。
建設業で働き方改革の実現にハードルがある理由

政府主導の取り組みである働き方改革を、建設業で進めることの難しさについて解説します。
少子高齢化を原因とする人材不足
働き方改革の実現におけるハードルとして挙げられるのが、少子高齢化による人材不足です。少子高齢化が進んでいる昨今、建設業界では人手が足りずに従業員1人当たりの稼働時間が増えている企業が増加しています。国土交通省の調査によると、2022年の建設業に従事している労働者の数は479万人です。これはピーク時(1998年)の685万人と比較して、大きく減少しています。
終身雇用制度を採用している企業もありますが、今後ベテランが退職していくと、さらに人手不足が加速するでしょう。
関連記事:建設業界における人手不足の現状
関連記事:施工管理の人手不足が深刻化
後継者問題
建設業界における人材不足の問題以外にも、次世代への技術継承も課題に挙げられます。建設業界で働いている人材のうち、55歳以上の割合は約36%で、29歳以下の割合は約12%です。若い人材が少ないため後継者がおらず、代表者の引退等によって、建設会社が解散、倒産するケースも最近では珍しくありません。
働き方改革を進めるにあたって、熟練工のもつ深い知識と高度な技術を、若手人材がスムーズに継承できる仕組みを構築する必要があります。
長時間労働
働き方改革を進めるにあたって、建設業が抱えている最も大きい問題の1つが長時間労働です。建設業は、他の業種と比較しても年間労働時間は長いといえます。労働時間が長くなる原因として、人手不足や納期の変更をはじめとする各種調整業務などが挙げられます。繁忙期には多くの案件を抱えるため、人手不足になり長時間労働を強いられるケースも少なくありません。
現状のまま働き改革に関連した社内制度を各社が導入すると、従業員の労働時間が制限されてしまい、建設業全体の作業工程に大きな影響が出ることが予想されます。
建設業における働き方改革の進め方

さまざまな課題を抱えている建設業ですが、働き方改革を進めるためにはどうすればよいか解説します。
長時間労働の改善
働き方改革を進めるにあたって、まずは建設業界で常態化している長時間労働を改善する必要があります。現状、義務ではないものの、働き方改革においては、休みの頻度は週に2日が望ましいとされています。労働者の心身の健康を守るためにも休日数を増やすのは重要ですが、単純な就業時間の減少は工期へのしわ寄せを招く要因となりかねません。
休みを確保した上で、各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進できるかが重要な課題といえるでしょう。
従業員の待遇改善
従業員の待遇改善も、建設業界で働き方改革を進めるにあたって解決しなければならない課題です。建設業界は長年きつい、危険、そして汚いという3Kの業種といわれてきました。特に健康保険や厚生年金保険など、一般的な福利厚生制度が整っていない企業が存在しているのは問題です。また、法定福利費を適正に負担しない企業も中にはあります。
技能や経験にふさわしい処遇や社会保険への加入を義務づけるなど、労働環境の抜本的な変革が必要です。
生産性の向上
就業時間の減少による成果物の減少は、働き方改革の推進における懸念事項の1つです。働き方改革が進められ就業時間が減少しても、従業員のスキルアップや、ITツールを導入するなどして生産性が向上できれば、大きな問題にはなりません。
そのためには限られた人材や資機材の効率的な活用に取り組み、事業活動のIT化を推進する企業文化と組織風土を醸成する必要があります。従業員に積極的に社内教育を実施し、スキルの平準化を進めるのも生産性を向上させる方法として有効です。
下記では、施工管理業務を効率化する手順やITツールなどの手段4選をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:施工管理業務を効率化する手順
キャリアアップのサポート
働き方改革を進めるにあたって、キャリアアップのサポートを無視することはできません。経験やスキルに相応しい評価が得られれば、従業員の満足度も向上し、将来的には人手不足の解消にもつながるでしょう。国土交通省が策定した建設業働き方改革加速化プログラムでは、建設キャリアアップシステムへの加入が推奨されています。
建設キャリアアップシステムとは、日本の建設業界におけるクラウドシステムです。保有資格や就業履歴をデータとして蓄積できるため、自分の経験やスキルを客観的に証明できます。
働き方改革を建設業で進める際の注意点
働き方改革を進めるにあたって、いくつか押さえておきたい注意点があります。どのような点に気をつけるべきか、順番に解説します。
発注者から理解を得る
働き方改革を進めるためには、発注者からの理解や協力を得なければなりません。これは工事を進めるにあたって、自社の従業員はもちろん発注者の存在も欠かせないためです。新しい仕事のやり方を採用するとしても、自社の都合でプロジェクトを進めることはできません。最悪の場合、相手の信頼を失う可能性もあるでしょう。
受注者と発注者双方がお互いの立場を理解し、無理のない働き方改革を進める必要があります。
36協定届の新様式を正しく理解する
36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定のことです。従業員に時間外労働をさせる場合、36協定届を提出する必要があります。この36協定届の様式は、働き方改革を推進するために定められた働き方改革関連法案によって変化しています。
主な変更点は特別条項付と一般条項での様式の分化や、押印・署名の廃止などです。従来のものと間違えないように、あらかじめ厚生労働省の公式などで新しい36協定届の様式を確認しておきましょう。
まとめ
生産性の向上や労働環境の改善など、建設業が抱えている課題は少なくありません。働き方改革を進めるにあたって、業界全体で積極的に問題に取り組む必要があります。ANDPAD(アンドパッド)は、導入企業数No.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。工事写真、工程表、図面、資料などの最新情報をクラウドで一元管理し、施工に関わる方の業務効率化をサポートします。
年間数千を超える導入説明会を実施するなど、各種サポートも充実しています。興味を持っていただいた方は、ぜひ無料資料のダウンロード、および公式サイトから問い合わせてください。
※本記事は2024年3月1日時点の法律に基づき執筆しております。