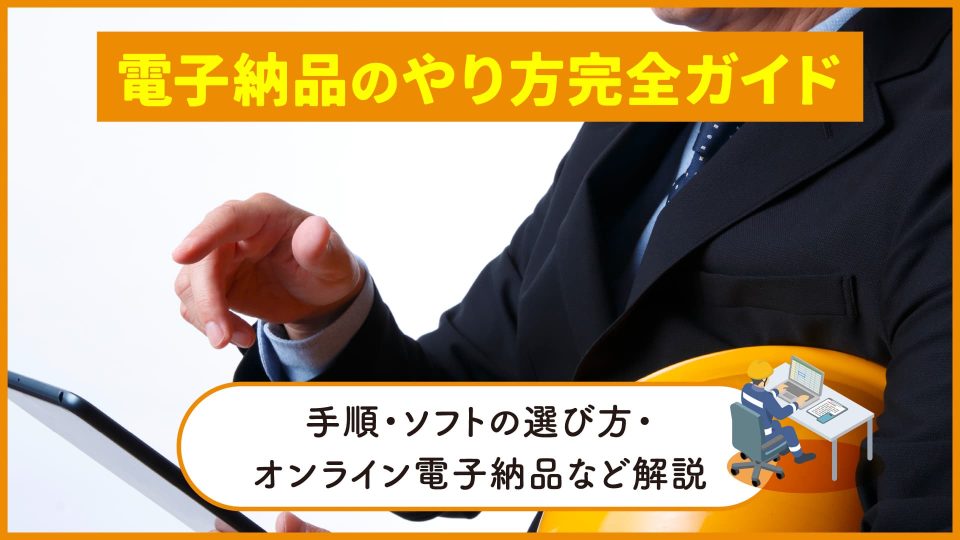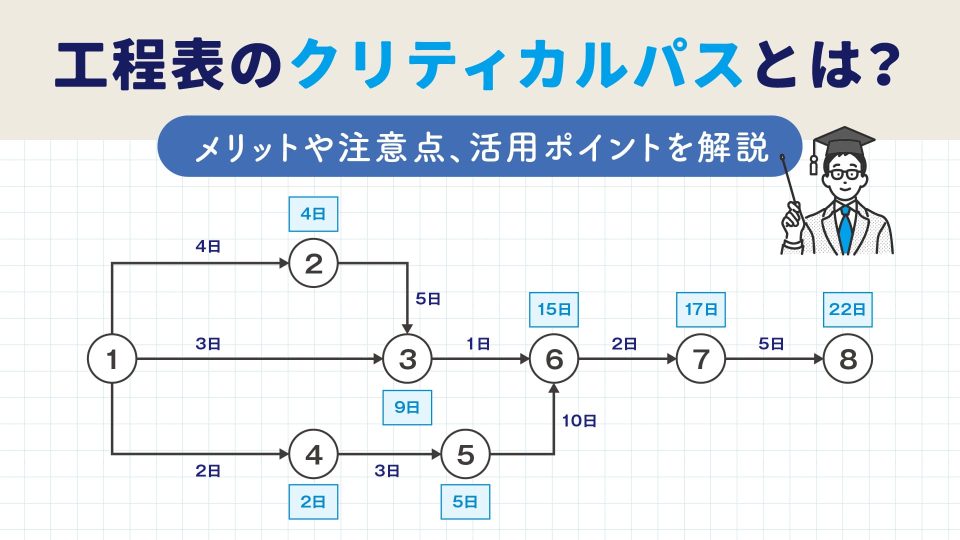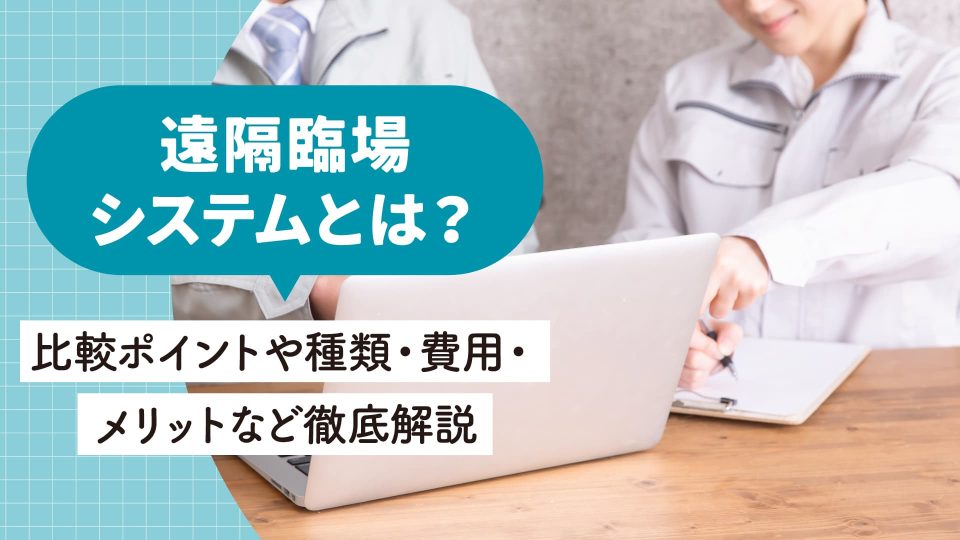電子納品とは、工事や業務の成果物を電子データとして納品する方法のことです。一見シンプルに感じられますが、納品する成果物にはさまざまなルールが定められています。この記事では、電子納品のやり方やメリット、使用するソフトの選び方について解説します。後半ではおすすめのソフトも紹介しているので、参考にしてください。

ANDPAD(アンドパッド)は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。ANDPADの「サービス概要」「導入メリット・導入事例」「サポート体制」がわかる資料3点セットをご用意しています。
電子納品とは

電子納品とは、成果物を電子化しただけという単純な方法ではありません。ここでは電子納品とは何なのか、概要を解説します。
電子納品は単に成果物を電子で送ることではない
電子納品と聞くと、単純に成果物を電子化しただけと思われがちですが、実際はそうではありません。確かに納品方法自体は、成果物をCD-RやDVD-Rに書き出してラベリングし郵送するか、オンライン上でデータを送信するかというシンプルなものです。しかし、納品できる電子データ自体には、細かいルールが定められています。
電子納品には細かいルールが複数ある
電子納品を導入することで、関係者間でスムーズにデータのやりとりができるようになります。ただし、統一的な運用を実現するため、電子納品には細かなルールが定められています。成果物は自分で作成できますが、ファイルの形式やファイル名の命名規則、格納するフォルダ構成まで、すべて電子納品要領・基準に則ったものにする必要があります。
国土交通省のガイドラインについて
電子納品の詳細なルールは、国土交通省の「電子納品等運用ガイドライン」で定められています。このガイドラインでは、以下の事項を定めることで、統一的で安定した運用を実現しています。
- 電子成果物の作成において、対象となる範囲
- 電子納品が適用される基準
- 発注する側と受注する側、それぞれが注意すべき点
電子納品の対象となる書類は、以下です。
- CADデータ(工事完成図)
- 施設管理台帳データなど(台帳)
- 地質データ(地質・土質調査成果)
- 工事帳票(施工計画書、工事打合せ簿、段階確認書等)
- i-Constructionデータ
参照元:国土交通省ガイドライン
オンライン電子納品とは?これまでとの違いは?
オンライン電子納品とは、インターネットを通じて電子成果物を納品する方法です。従来の電子納品との主な違いは以下の通りです。
- 納品方法:電子媒体(CD-R・DVD-R)への書き出し → オンライン上でのデータ転送
- コスト:CD-R・DVD-R代、郵送費が発生 → 物理的なコストが不要
- 納品スピード:郵送による時間が必要 → リアルタイムでの納品が可能
- 保管:物理的な保管スペースが必要 → クラウド上での管理
オンライン電子納品の普及により、より効率的でコストを抑えた成果物の納品が実現できます。
電子納品の流れ

電子納品を行う流れについて解説します。電子納品の基本的な流れに加えて、オンライン電子納品では新しい作業工程があります。
基本的な工程
電子納品において、従来から変わらず必要な工程について解説します。電子成果物の作成や品質管理体制の整備は、従来型・オンラインを問わず重要な作業です。
電子成果物を作成
まずは電子成果物を作成します。ここでポイントとなるのは、納品するデータをフォルダごとに整理しておくことです。電子成果物の作成を支援するソフトを活用するのがおすすめです。
チェック体制を利用する
チェック体制についても、従来通りに整えておく必要があります。チェック項目は従来と変わりませんが、国土交通省が公開しているチェックシステムに則って確認作業を行いましょう。
オンライン電子納品の場合に新しく行う作業
オンライン電子納品では、従来の電子媒体による納品にはなかった新しい作業工程があります。情報共有システムへの登録やオンライン納品特有のルールへの対応が必要です。
情報共有システムに登録
オンライン電子納品では、情報共有システムに成果物を登録する必要があります。具体的には、電子納品の成果物と、チェックリストに沿って行ったチェック結果を、それぞれシステムに登録します。発注者による再チェックやデータ転送などの作業を、すべてインターネット上で完結できます。細かくはシステムごとに異なるため、確認してください。
フォルダ名を指定
パソコンに保存する成果物のフォルダ名にはルールがあります。オンライン電子納品では、情報共有システムに登録する成果物のフォルダ名は「PRODUCT」とすることが定められています。
PDFで出力
チェックシステムを使用し、成果物に問題がないかチェックします。さらに、その結果はPDFで出力しなければなりません。従来の方法では、発生しなかった作業工程なので注意してください。
電子納品を利用するメリット
電子納品を利用することで、以下のメリットが得られます。
- コストを削減できる
- 保管スペースが不要になる
- 作業時間を短縮できる
従来の紙ベースでは印刷費用や製本費用がかかりますが、電子納品ではこれらの費用を大幅に削減できます。また、長期間にわたる工事や関係会社が複数にわたる場合、膨大なファイルを保管するスペースが必要です。電子納品であれば、省スペースで済みます。
これまでは成果物を紙にプリントしたうえで、それを1つずつファイリングする作業が必要でした。電子納品であればこのような作業も不要になり、作業時間を短縮できます。特にオンライン電子納品では、電子媒体への書き出しも不要になるため、さらなる効率化が期待できます。
電子納品で使用するソフトの選び方
電子納品を行う際には、情報を保存・管理できるソフトを使用します。しかし、そのソフトも、何でもよいわけではありません。
国土交通省に認定されたソフトを選ぶ
電子納品はコストや保管スペースの節約など、便利な反面、細かなルールもあります。使用するソフトも気をつけなければなりません。電子納品に使用するソフトは、国土交通省に認定されたものを選びましょう。
定期的に、要領・基準が更新されるため、それに対応できるソフトが望ましいです。国土交通省に認定されたソフトを使用する際は、常に最新のバージョンにしておきましょう。
図面・書類・写真の電子納品ソフトを選ぶ
電子納品ソフトは、種類によっては書類だけに対応している場合と、写真だけに対応している場合があります。書類や図面、写真すべてに対応していないソフトを選んでしまうと、複数のソフトを並行して使用しなければなりません。複数のソフトで成果物を管理することになり、余計なコストがかかってしまいます。
無料ソフトには注意する
電子納品対応ソフトのなかには無料のものもありますが、選定時は注意が必要です。特にセキュリティ面におけるリスクが懸念されます。ソフトの最終更新日やサポート体制を必ず確認し、継続的なメンテナンスが行われているかを見極めましょう。無料ソフトには、サポート体制が不十分なものもあるため、実績を見ることが大切です。
電子納品時の注意点

電子納品時には、チェックシステムや要領・基準を確認するなどの作業が必要です。また、電子成果物の納品方法の確認も必要なので、忘れずに行いましょう。
チェックシステムを確認する
電子納品をする前に、必ず事前チェックを行いましょう。国土交通省などが公開している「電子納品チェックシステム」を使用して、作成した電子成果物にエラーがないかを確認してください。チェックを行わずに納品すると、発注者の検査時にエラーが生じ、成果物が差し戻される可能性があります。
要領・基準を確認する
電子納品には細かな決まりごとがあります。電子納品の要領・基準に従った確認作業は必須です。定期的に内容が見直され、改良されていることにも注意してください。これまでに電子納品を実施した経験があっても、以前と同じ基準とは限りません。新たな工事を始める際は、必ず改定されている部分はないか確認しておきましょう。
子成果物の納品方法を確認する
電子成果物を納品する方法も、事前に確認しましょう。現在、電子納品の方法には、2つのパターンがあります。1つは、CD-RやDVD-Rに書き出して提出する従来の方法です。もう1つは、データをオンライン上で提出するオンライン電子納品です。発注者が指定していない納品方法では受け付けてもらえない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
電子納品ソフトは「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめ!
電子納品を行う際は、「ANDPAD電子納品」がおすすめです。電子納品のための黒板作成や写真の整理、電子納品要領に合わせた納品データの作成など、煩雑になりがちな電子納品業務を一元管理できます。
また、要領に合わせた電子納品ツリーを自動で作成できます。官公庁や自治体が指定する要領に合わせ、以下のような電子納品ツリーを自動作成できる点も魅力です。
- 大分類
- 写真区分
- 工種
- 種別
- 細別

ANDPAD(アンドパッド)は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。ANDPADの「サービス概要」「導入メリット・導入事例」「サポート体制」がわかる資料3点セットをご用意しています。
ANDPADで電子納品の成果物準備・整理を効率化した事例
ANDPADで電子納品の成果物準備・整理を効率化した事例を解説します。
「1,000枚を超える工事写真を効率管理。成果物整理の属人化を解消」株式会社GOOD PLACE様
株式会社GOODPLACEは、1990年に東京で創業し、当初はリクルートグループにおけるリフォーム事業を担う目的で設立されました。工事現場での写真撮影は、施工担当者にとって大きな負担となっていたそうです。1つの現場で撮影される写真は1,000枚を超えることもあり、撮影作業に加え、その後の整理や管理にも多くの人手が必要で、効率が悪かったそうです。
そこで、この課題を解消するために、電子小黒板を用いて撮影から管理まで行える「ANDPAD黒板」が2021年から導入されました。
参考:工事写真の撮影において「ANDPAD黒板」がもたらした“大革命”
「資料・写真の共有をクラウド化し、納品前チェックの精度を向上」内外建設株式会社様
1941年、旧東京銀行の前身である横浜正金銀行の関連会社として「綜通」が誕生しました。その綜通グループに属する企業のひとつが、1975年に創業した内外建設株式会社です。銀行の有人店舗工事を担当する、金融機関事業部でANDPADを導入しました。
参考:施工管理と受発注のデジタル化で社員も協力会社も働きやすい環境作りを実現
「写真整理を効率化し、残業時間を削減。納品データ作成もスムーズに」星野管工株式会社様
昭和3年(1928年)3月3日に創業した星野管工は、約1世紀にわたる歴史を持つ企業です。同社がANDPADを導入したのは2022年初頭のことです。同社にとって「働き方改革」への最初の取り組みでした。
当時、改革の必要性が高まる中で、営業事業部の牧佑一次長が独自に導入を提案したそうです。ANDPADを使えば、スマートフォンやタブレットで黒板付き写真を撮影し、そのまま案件ごとのフォルダに自動保存・整理が可能であるためでした。
参考:写真管理業務を大幅軽減、残業時間を半減、ANDPADが貢献
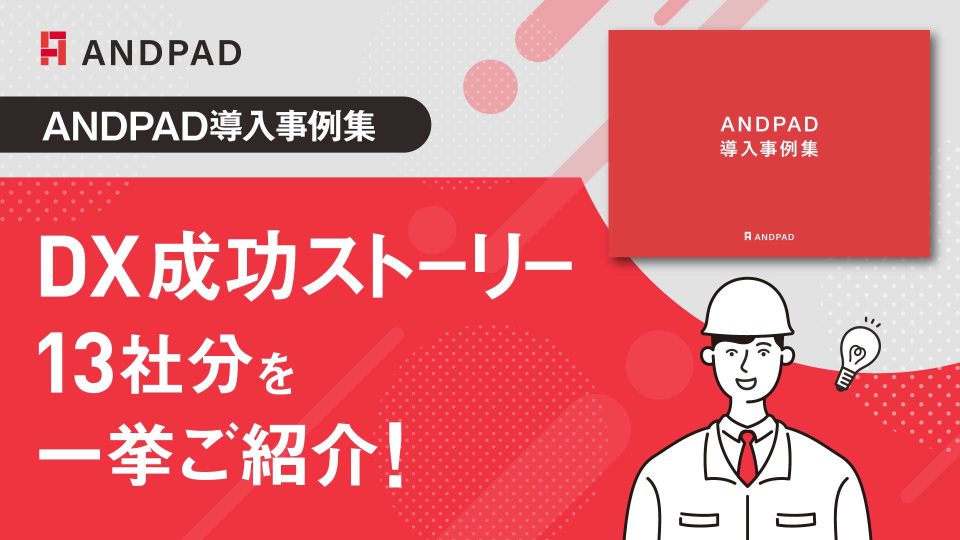
ANDPADをご検討中の方向けに、各社が抱えていた課題、DX成功に至るまでの導入事例をまとめてご紹介しています。ゼネコン、設備工事、太陽光、注文住宅、リフォームなど、幅広い業種の事例をピックアップしています。
まとめ
電子納品とは、工事や業務の成果物を電子データとして納品する方法です。従来のCD-RやDVD-Rによる納品に加え、近年はオンライン電子納品も普及しています。電子納品を成功させるには、国土交通省の要領・基準に準拠することが重要です。専用のソフトを活用することで、これらの複雑なルールに対応し、確実な電子納品を実現できます。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」が提供している「ANDPAD電子納品」を検討してみてください。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力や手厚いサポートが特長です。気になる人は、ぜひ以下よりお問い合わせください。