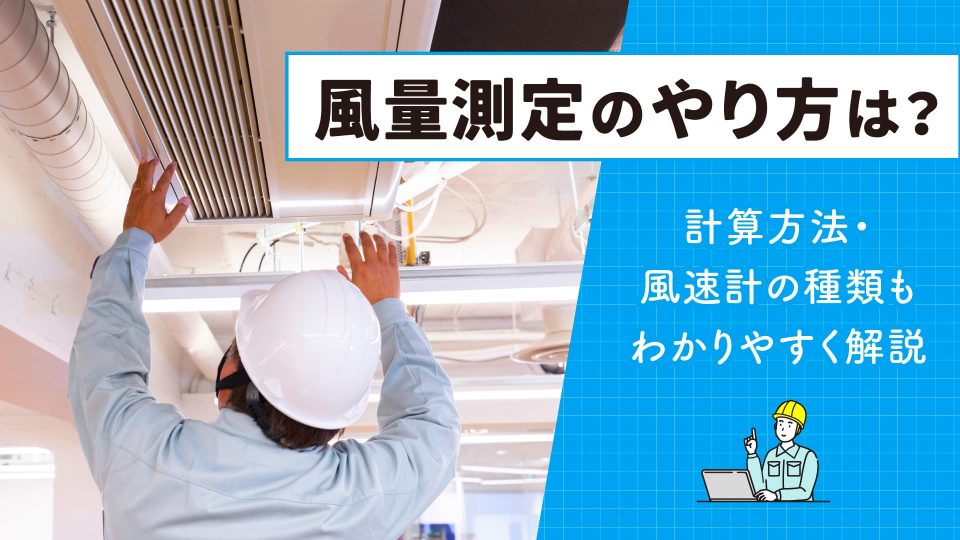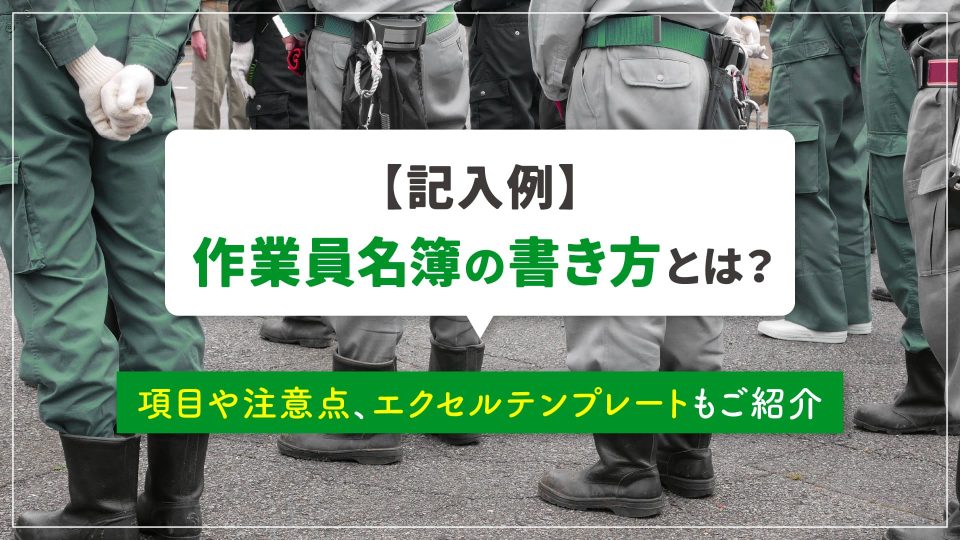風量測定は、空調設備や換気設備が設計通りに正常に動いているかを、確認するための測定です。この記事では、施工管理の担当者に向けて、風量測定のやり方や計算方法、風速計の種類などについて解説します。測定する際に、役立ててください。
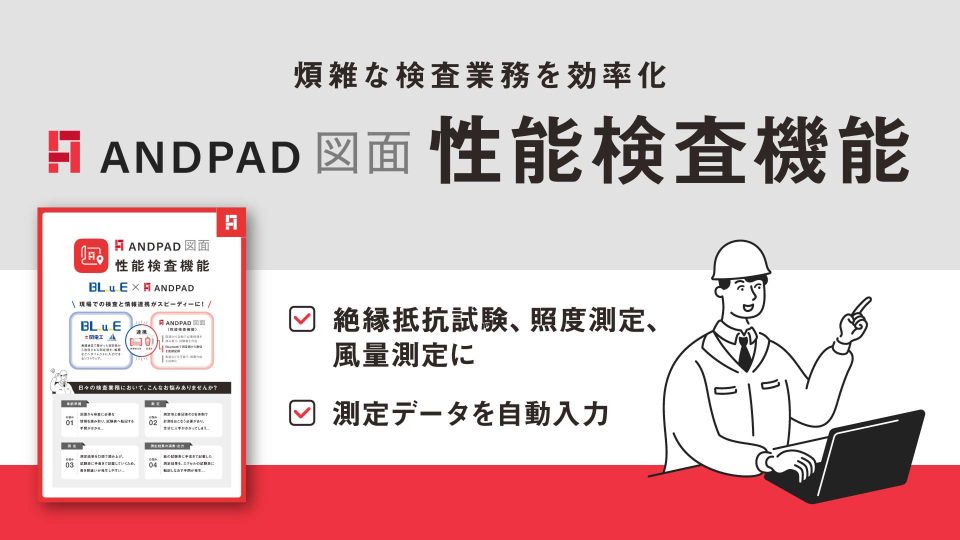
電気工事や空調設備工事における検査業務(風量測定・絶縁抵抗試験・照度測定)を効率化。具体的なサービス内容やメリット、導入効果をご紹介しています。
風量測定とは
風量測定は、空調機器や換気機器が設計通りに正常に稼働しているかを、確認するための作業です。風量や風速が設計通りに確保されているか、風量・風速の強弱を確認し、空調機器・換気機器に異常がないかを確認します。風量測定は、マンションやビル、地下施設、大型施設などでは欠かせません。
風量測定が重要な理由
換気を適切に行い、快適な環境を維持するためには、定期的な風量測定が欠かせません。適切な換気が行われないと、「冷暖房の効きが悪くなる」「空気が不衛生になる」「酸素不足が起こる」「ニオイやカビが発生する」など、あらゆる問題が発生します。
さらに、コロナ禍以降、感染症リスク対策としても必要とされています。また、ダクト内に溜まった脂分やホコリが原因となる火災のリスクもあるため、安全管理の面でも重要です。
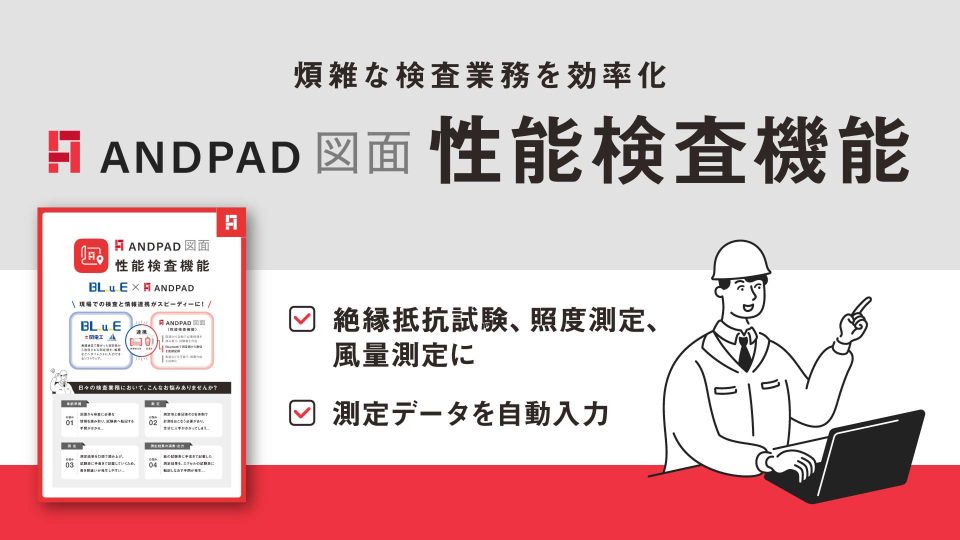
電気工事や空調設備工事における検査業務(風量測定・絶縁抵抗試験・照度測定)を効率化。具体的なサービス内容やメリット、導入効果をご紹介しています。
風量測定に関連する設備の名称
風量測定を実施する際には、関連する設備の名称や特徴を知ることも大切です。風量測定に関して知っておくべき設備の名称とその特徴は、以下の通りです。
ダクト:気体を運ぶための管
制気口:空調用の吹出口や吸込口、換気用の給気口や排気口など、空気の出入り口全般
ダンパー:ダクト内に取り付けた可動板で、空気の流れを調整する装置
排煙口:火災時に煙を屋外に排出し、避難を支援する装置
ブリーズライン(ライン型吹き出し口):細長い形状をした空調用吹き出し口
風量測定口:ダクト内で風量測定を行うための開口部
換気扇:室内の空気を排出し、外気と入れ替えるための装置
送風機:羽根車の回転で気体にエネルギーを加える機械
フード:外壁に取り付け、風雨や虫の侵入を防ぎながら換気するカバー
防鳥網:鳥の侵入を防ぐためにダクトやフードに取り付ける金網
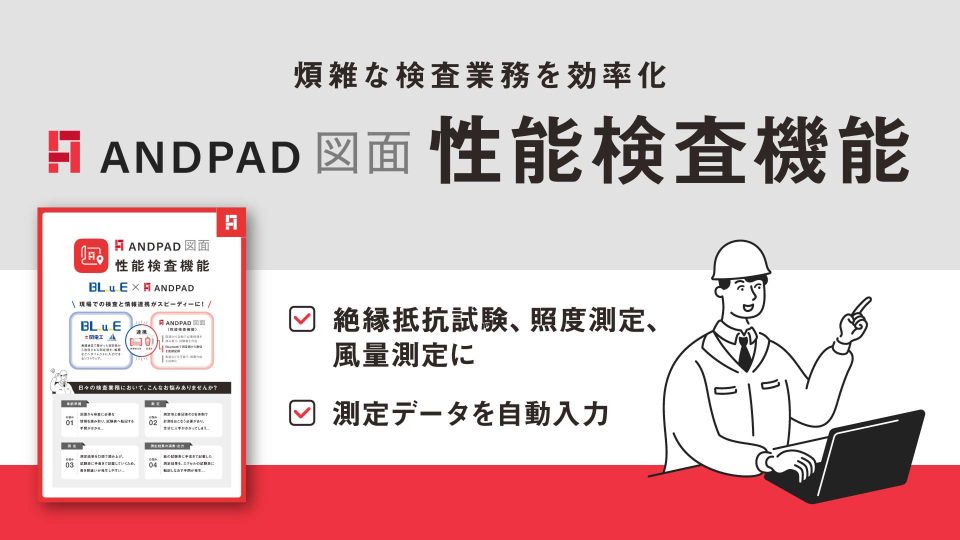
電気工事や空調設備工事における検査業務(風量測定・絶縁抵抗試験・照度測定)を効率化。具体的なサービス内容やメリット、導入効果をご紹介しています。
風速計の主な種類と特徴
風量測定を行う際には、風速計を用いる必要があります。風速計で風速を測定した後、計算して風量に換算します。ここでは、風速計の主な種類と特徴について解説します。計算方法については後述します。
関連記事:風速計の使い方と注意点、種類について徹底解説!用途別の選び方もご紹介
熱式風速計
熱式風速計は、センサーの先端で風を受け、温度が下がった分を風速に換算する仕組みの風速計です。安定性が高く強度もある「プラチナ線」がセンサーに使用されており、長期間にわたって高い精度を維持できます。
また、小型であるため、温度変化が少ない屋内での測定に適しており、狭い場所でも使いやすい点が特徴です。室内設備の点検や、製造現場・クリーンルームでの室内環境調査などの利用に適しています。
風車式(ベーン式)風速計
風車式(ベーン式)風速計は、ベーンに風を受けて、ベーンの回転数を風速に変換する仕組みを持つ風速計です。ベーンは、風車を意味します。
風車式(ベーン式)風速計は、温度変化の影響を受けにくく、屋外でも使用可能です。熱式風速計と比べると、微風速域や風速が細かく変化する場所には適していません。主な用途は、換気扇の風量測定や室内の対流測定、空調設備の排気測定、気象観測用です。
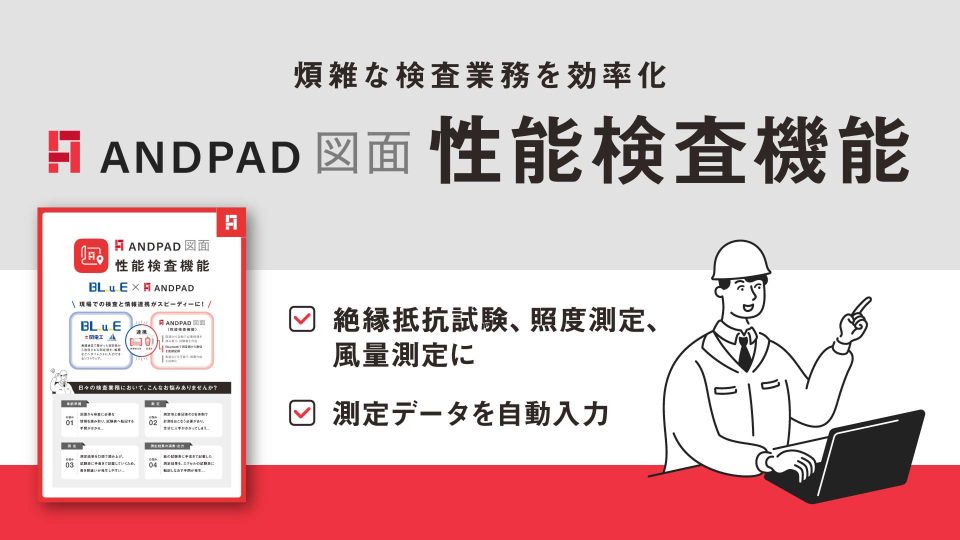
電気工事や空調設備工事における検査業務(風量測定・絶縁抵抗試験・照度測定)を効率化。具体的なサービス内容やメリット、導入効果をご紹介しています。
風量測定のやり方
風量測定のやり方について、順を追って解説します。なお、風量測定に関しては、日本産業規格 JIS B 8330:2000「送風機の試験及び検査方法」で規格されています。
1. 必要な道具を用意する
まず、風速を測定するために必要な道具を用意しましょう。風速を測定するためには、風速計、メジャー(スケール)、脚立が必要です。メジャーは、制気口の長さを測るために使用します。高い場所での測定が必要な場合は、脚立を使って安全に配慮しながら測定を行います。
2. 制気口の面積を測る
必要な道具を用意したら、制気口の面積を測定します。角ダクトの場合は、制気口の高さと幅を測定し、それらをかけ合わせて面積を求めます。円管ダクトの場合は、直径Dを測定し、半径r = D/2として求めます。その後、半径×半径×3.14で面積を計算します。
計算の際、単位はすべてメートル(m)で統一します。例えば、高さ800mm、幅500mmの制気口の場合、0.8m × 0.5m = 0.4m²が面積です。
3. 風速を測る
制気口の面積を測ったら、次に風速計を使用して風速を測定します。風速は場所によって異なるため、複数の箇所で測定し、その平均を取ります。測定箇所が多いほど、より正確な風速を算出できます。また、風速計を制気口にまっすぐ向けて測定することが重要です。例えば、4か所で測定し、8.4m/s、6.2m/s、3.0m/s、5.6m/sの場合、平均の風速は5.8m/sになります。
吹き出し口の風速を測る方法
角ダクトの場合、断面の長方形を16以上の等面積に分類し、それぞれの中心点で風速を測定します。各長方形の辺の長さが150mm以下になるように区分し、64以上に区分しなくて構いません。円管ダクトの場合は、測定する管路の断面で、互いに直角な直径上で10点ずつ、合計20点を測定します。
吸い込み口の測定方法
吸い込み口には、内寸と同じ断面のダクトをつなぎます。ダクトの長さは、ダクトの直径もしくは長辺の2倍に設定します。その後、ダクト入口の中央1点で風速を測定します。
4. 計算して風量を算出する
風速の平均値をもとに風量を計算します。計算式は、次の通りです。
風量(m³/min) = 風速(m/s) × ダクト断面積(m²) × 60(sec)
風量(m³/h) = 風速(m/s) × ダクト断面積(m²) × 3600(sec)
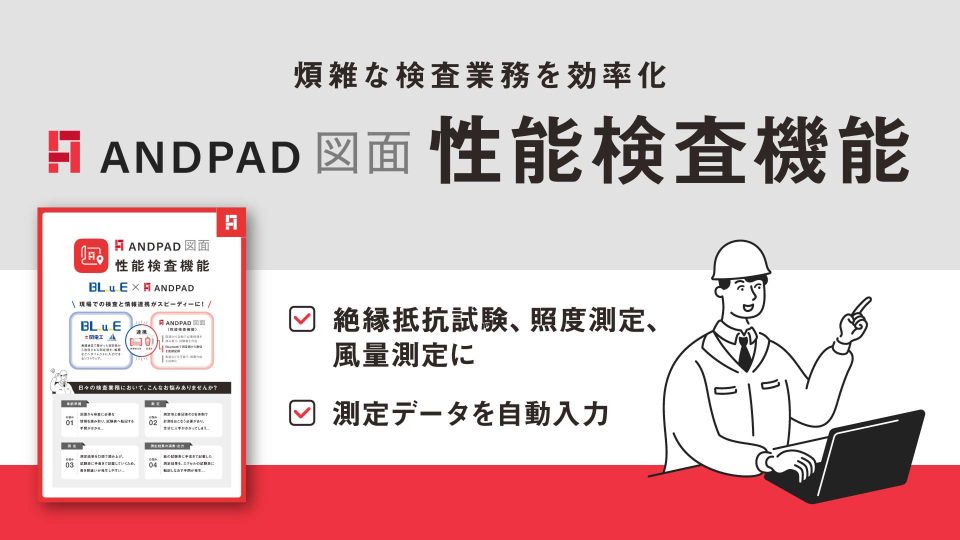
電気工事や空調設備工事における検査業務(風量測定・絶縁抵抗試験・照度測定)を効率化。具体的なサービス内容やメリット、導入効果をご紹介しています。
まとめ
風量測定は、空調設備や換気設備の正常動作を確認する重要な作業です。風速計を使って風速を測定し、制気口の面積と組み合わせて風量を算出します。正しい測定を行うことで、快適で安全な環境を維持できます。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1のサービスとして、さまざまな業種の企業やユーザーに利用されています。使いやすいUI・UXを実現し、開発力にも定評があります。年間数千回を超える導入説明会を実施しており、手厚いサポートも特徴です。ぜひご検討ください。