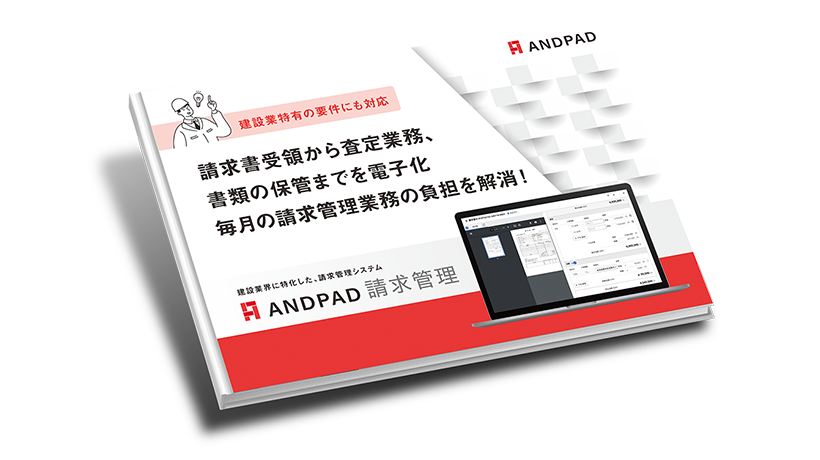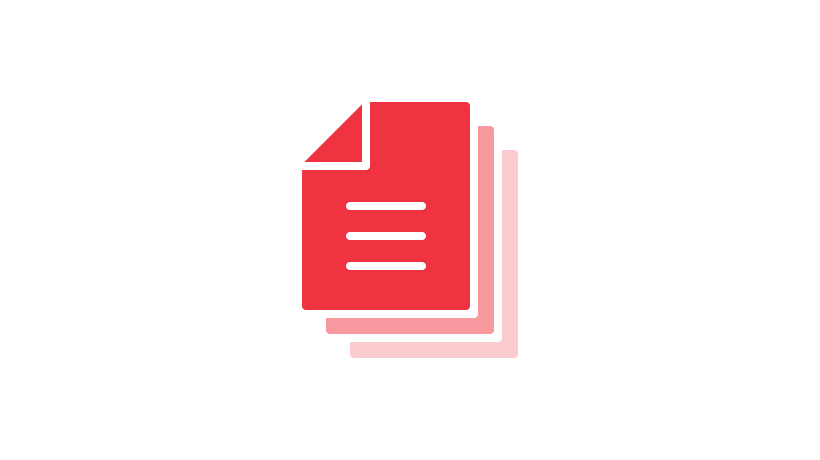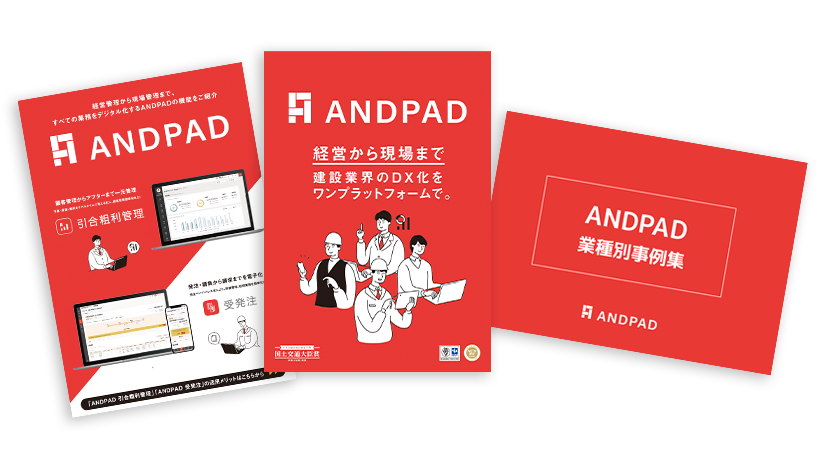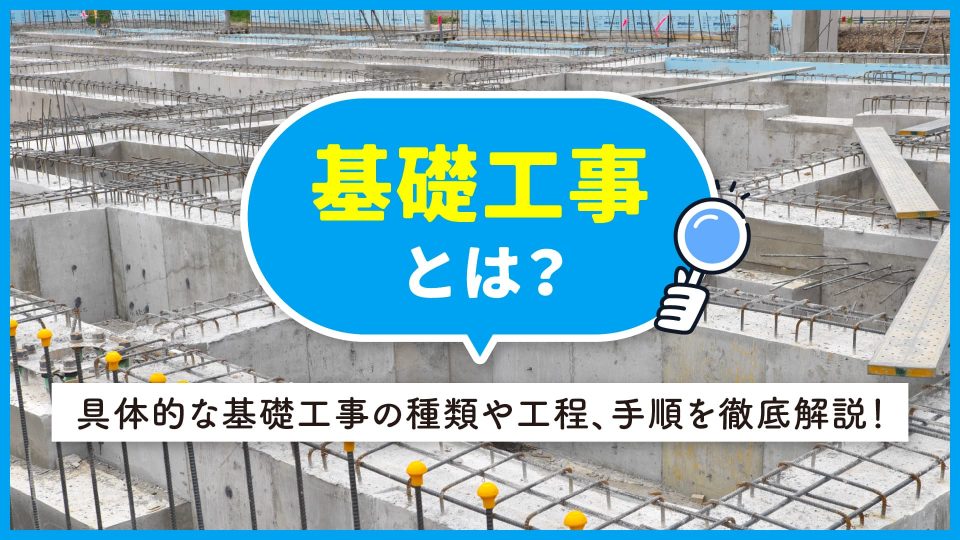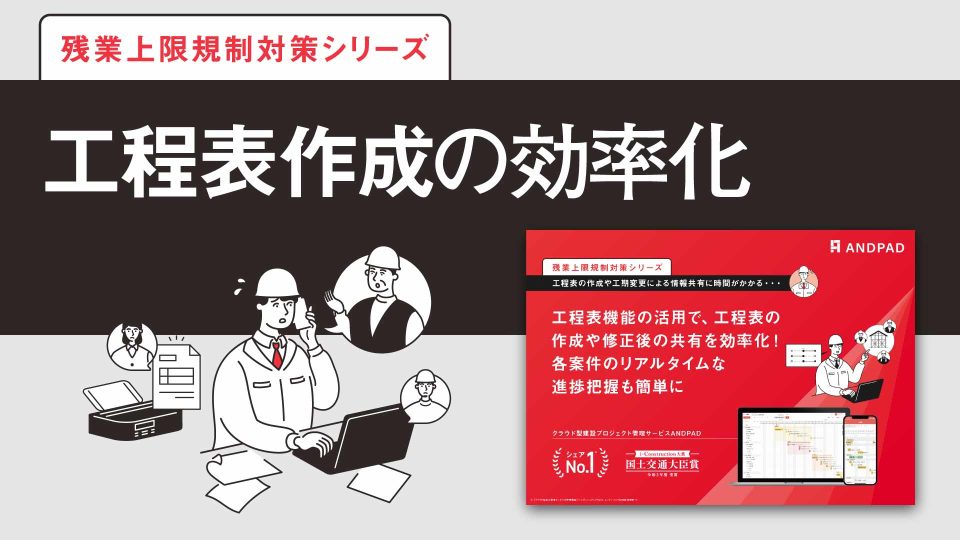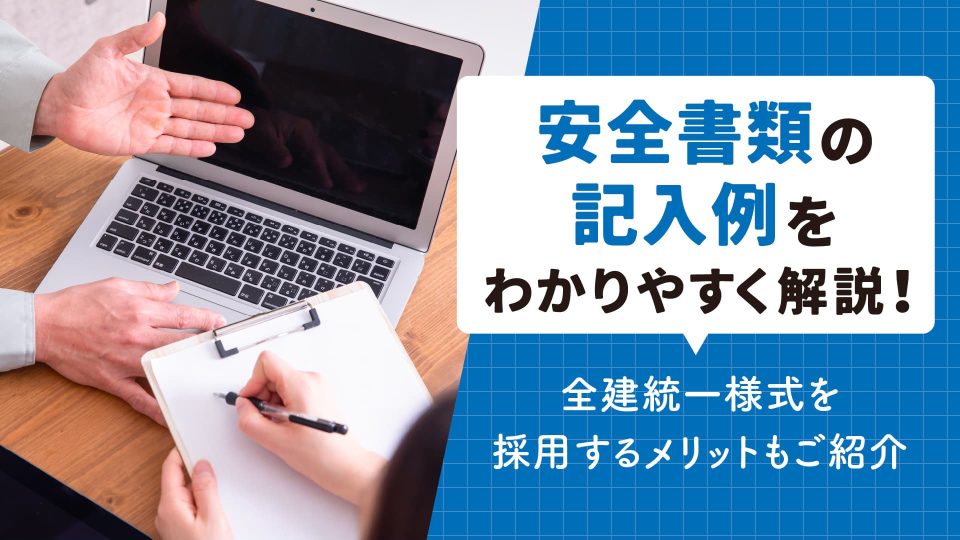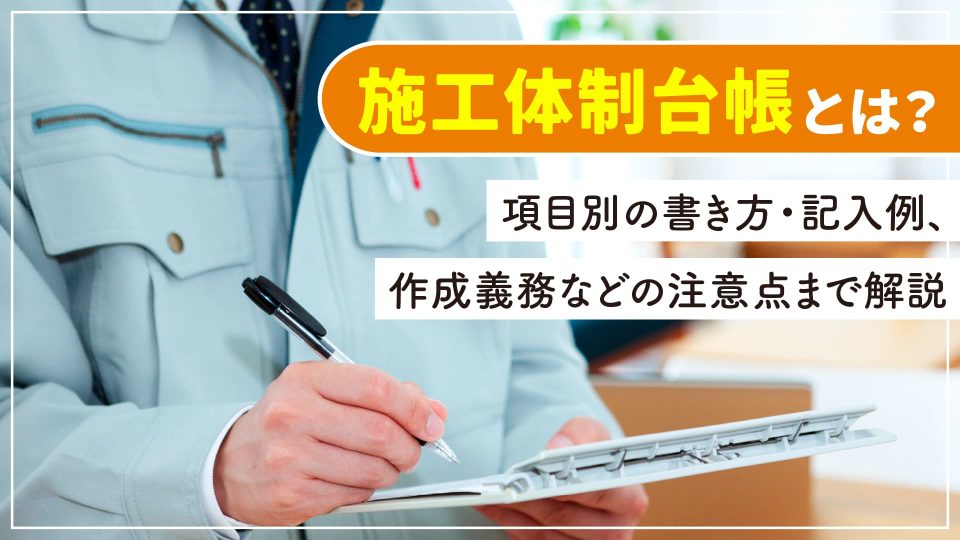基礎工事は、建物が不同沈下(ふどうちんか)することを防ぐために行われます。この記事では、基礎工事の種類や手順、品質を維持するための検査基準やチェックポイントについて解説します。あわせて、基礎工事の遅延を防ぐための管理方法についても解説するため、基礎工事の工程表を正確に管理し、スムーズな進行を目指す現場監督や施工管理者は、参考にしてください。
基礎工事とは?

基礎工事とはどのようなものか、またそれが必要である理由を解説します。
基礎工事が重要な理由
基礎工事には、不同沈下を防ぐ目的があります。また、地面と建物のつなぎの役割もあります。不同沈下とは、家全体が均等に沈下せず、一方向に斜めに傾くような状態を表す言葉です。
地面に直接建築物を建てた場合、建物自体の重さで地盤沈下が起こります。基礎工事を行い、建物の重さなどの縦向きの力や、地震の揺れなどによる横向きの力を建物から地盤に伝えることは、耐久性にも影響を与えます。
基礎工事の種類の概要
基礎工事の種類について、解説します。
ベタ基礎
ベタ基礎は、地盤に基礎を直接設置させる工程です。直接基礎の1つであり、床下全面をコンクリートで覆い、面で建物と地盤をつなぎます。地盤の強度が小さくても利用ができ、土を掘る量や型枠使用量が少なく、施工がしやすいメリットがあります。地震の揺れにも強い特徴がありますが、使用するコンクリート量は多めです。
杭基礎
杭基礎は、杭を直接地面に差し込む方法です。住宅を安定させるだけでなく、地震などによる液状化防止も可能です。地盤が軟弱な建物に使われることが多く、杭の種類は、支持杭(しじぐい)と摩擦杭(まさつぐい)に分けられます。使い分けは、予算や建物の種類、地面の状態によります。杭基礎が単独で施されることは少なく、杭基礎のあとにはベタ基礎や布基礎を施すことが一般的です。
布基礎
布基礎(ぬのきそ)は、直接基礎の一種で、建物の負荷が集中する主な柱や壁の下に連続して基礎を設置する方法です。地盤が強く、比較的広い土地向きです。日本の木造住宅において、古くから使われてきました。ベタ基礎よりも地盤に接する面積が小さく、地盤への負担も少なくて済むメリットがあります。ただし、床下に土がむき出しになる場合は、湿気対策、シロアリ対策が必要です。
基礎工事の工程と手順

基礎工事の工程と手順を解説します。
地盤調査
基礎工事に着手する前に、地盤調査を行います。地盤調査とは、地盤の硬さや強度、軟らかさ、どのくらいの建物の重さに耐えられるか、沈下に抵抗できるかを調査することです。沈下の恐れがある場合は、地盤改良が必要です。なお、建築基準法により地盤調査は義務づけられています。
遣り方工事
遣り方工事(やりかたこうじ)は、地縄張りの外側に木の杭や板などを張り、建物の正しい位置や基礎の高さなどを明確にする仮設工事です。この作業を「遣り方を出す」といい、建物の正確な位置を決めるために欠かせません。
地縄張りは、敷地内に縄やビニール紐などを張る仮設工事です。建物の位置や部屋の配置などを確認する目的で行います。コンクリートをはじめ、動かないものに目印である基準墨をつけたら、地縄張りと遣り方は撤去します。
掘削工事
掘削工事とは、根切りと呼ばれる基礎の作成のために、地盤を掘り起こすことです。基礎を敷設したい場所に、パワーショベルや油圧ショベルなどを用いて、地盤まで土を掘り起こします。基礎工事のなかでは、最も時間がかかり、数回に分けて土留め工事・排水などと同じタイミングで実施することが一般的です。作業中に、既存配管が見つかった場合は手掘りでの作業が必要です。
砕石敷き
砕石敷き(さいせきしき)とは、建物の基礎を配置する地面に砕石を敷き詰めることです。その際、ランマーと呼ばれる機械で締め固める(転圧)ことで、石の密度が高まり地面が固くなります。これにより、建物がすぐに沈むことを防げるでしょう。地盤を固める作業のことを地業といいます。
配筋工事
配筋工事とは、格子状の鉄筋を図面通りに組み立てることです。基礎を鉄筋コンクリートで作るために欠かせない、基礎の寿命や強度にも大きく関わる重要な工程です。そのため、手順や内容が建築基準法で細かく定められています。配筋工事が終了したら、基準墨をもとにコンクリートを流し固めるための型枠を組みましょう。
その後、アンカーボルトと呼ばれる建物の構造材と基礎をつなぐ金属製の部材を設置します。
コンクリート打設
コンクリート打設は、型枠の中にコンクリートを流し込む工程です。その際、振動を発するバイブレーターと呼ばれる機械を利用し、コンクリートの中に入っている空気を抜き、隙間なく敷き詰めます。空洞が少ないほど、強度が増すためです。コンクリートが乾いたら、基礎内部に打設していきます。
型枠撤去
コンクリートが乾き、上を歩けるようになるまでには3〜10日ほどを要します。完全に乾くまでには、1か月ほどかかります。ブルーシートでコンクリートを覆う養生を行い、外部の衝撃や風雨からコンクリートを守りましょう。完全に乾いたら、型枠を外し(脱型)、コンクリートに不良やひび割れがないか、アンカーボルトがずれたり曲がったりしていないかなどを確認します。
基礎工事の品質を確保するためのチェックポイント
基礎工事の品質を確保するために、チェックすべきポイントを確認しましょう。
配筋検査の基準とチェックポイント
配筋検査は、鉄筋が設計図面に基づき正確に配置されているかを確認する検査です。設計監理者あるいは、第三者機関により実施されます。チェックすべき8項目は以下のとおりです。
鉄筋の配置:鉄筋の網目の幅
鉄筋のかぶり厚さ:コンクリートの表面から鉄筋表面までの最短距離
鉄筋の波打ち:鉄筋が水平に保たれず波打っている状態
鉄筋定着の長さ:継ぎ足して重なっている部分
鉄筋の径(太さ):建築基準法に基づき、基礎の鉄筋は径9mmや径13mが使用されているか
防湿シート:隙間なく敷き詰められているか
ホールダウン金物の位置・本数・状態:位置、本数が図面とあっているか、ゆがんでいないか
アンカーボルトの位置・本数・状態:位置や本数が図面とあっているか
関連記事:配筋検査とは|検査項目のチェックリスト・写真撮影のポイントを徹底解説
コンクリート品質検査の基準とチェックポイント
コンクリートの品質検査方法は、以下の3種類です。
スランプ試験:コンクリートの軟らかさを調べる調査。スランプ量の許容範囲は、種類により異なる
空気量測定:空気が適正な量だけ入っているかを測る検査。既定の空気量は、普通コンクリートと舗装コンクリートで4.5±1.5%、軽量気泡コンクリートで5.0±1.5%である
塩化物イオン濃度測定:塩化物イオンの濃さを測る。濃すぎるとコンクリートを支える鉄筋が錆びやすくなる
工程の遅延を防ぐための管理方法

工程はさまざまな要因で、遅延しかねません。遅延を防ぐ管理方法を解説します。
工程表通りに作業が進んでいるか日々チェックする
工程が予定通りに進行しているかを日々確認しましょう。細やかな進捗管理は、問題の原因究明に役立ちます。怠慢な管理は、工期の遅れ、ひいては納期の遅れにつながります。
関連記事:工程管理とは?建設業で重視される理由・チャート種類・管理方法などを解説
問題が起きたとき即時に解決策を検討する
問題の発生により工程が遅延した場合は、原因を素早く究明し、適切にスケジュールの遅れを取り戻します。解決法には、以下のものがあります。
各作業員の業務内容が適切かを再確認し、リソースを割り当てる
場合によっては残業や休日出勤を依頼する
現在進行中のタスクと後続のタスクを同時並行で着手するファスト・トラッキングを実施する
解決策に応じてスケジュールを修正する
解決策に合わせ、スケジュールを修正し、遅れを取り戻しましょう。残業や休日出勤を依頼する場合は、法定労働時間を超えないようにします。また、作業員の体調にも配慮します。ファスト・トラッキングによるスケジュール修正は、複数のタスクを同時に管理する手間や負担が増えることに注意しましょう。
ANDPADなら工程表を一元管理できる
工程表の管理には、一元管理ができるクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。テンプレートで誰でも簡単・効率的に作成できるうえ、最新の工程表がリアルタイムに社内外の関係者へ共有可能です。スマートフォンからの修正にも対応しています。要件を一覧で把握できるため、スムーズに作業員や重機を手配できるでしょう。
まとめ
基礎工事は、不同沈下(ふどうちんか)を防ぐために重要な工程です。基礎工事は、複数の作業があり、さまざまな要因で遅延することがあります。工程表を確認し、スケジュール通りに工程が進んでいるかを都度チェックしましょう。
基礎工事が工程表通りに進んでいるかを確認するためには、管理サービスの利用がおすすめです。クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、使いやすいUI・UXで、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。年間数千を超える導入説明会を実施しており、サポートも充実しています。まずは、資料請求からお試しください。