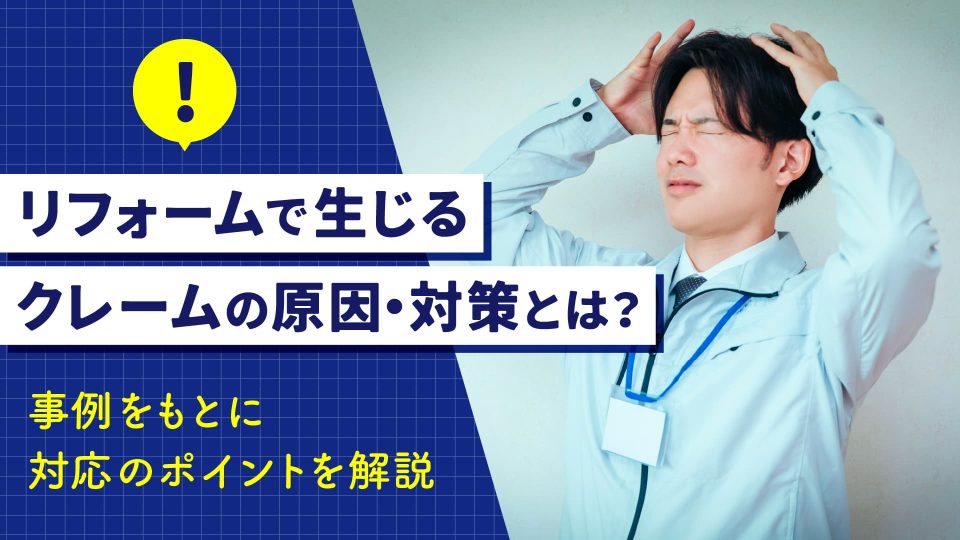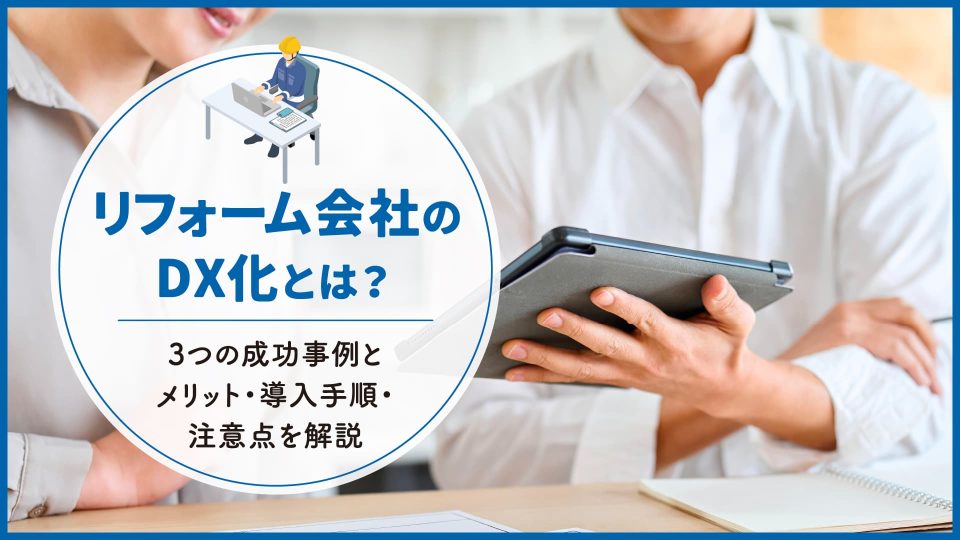作業日報は、会社全体で管理すべきであり、保存期間は法律で定められています。作業日報を管理し、効率的に運用するには、定期的な棚卸しや保存期間が過ぎた日報の取り扱いがポイントです。この記事では、作業日報の保存期間や保存する際のポイントを解説します。作業日報の保存方法によるメリットとデメリットについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
作業日報の全体像を把握したい場合は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:【建設業】作業日報の目的やフォーマットとは?記載内容やメリットについても解説
作業日報の管理方法・保存期間は?
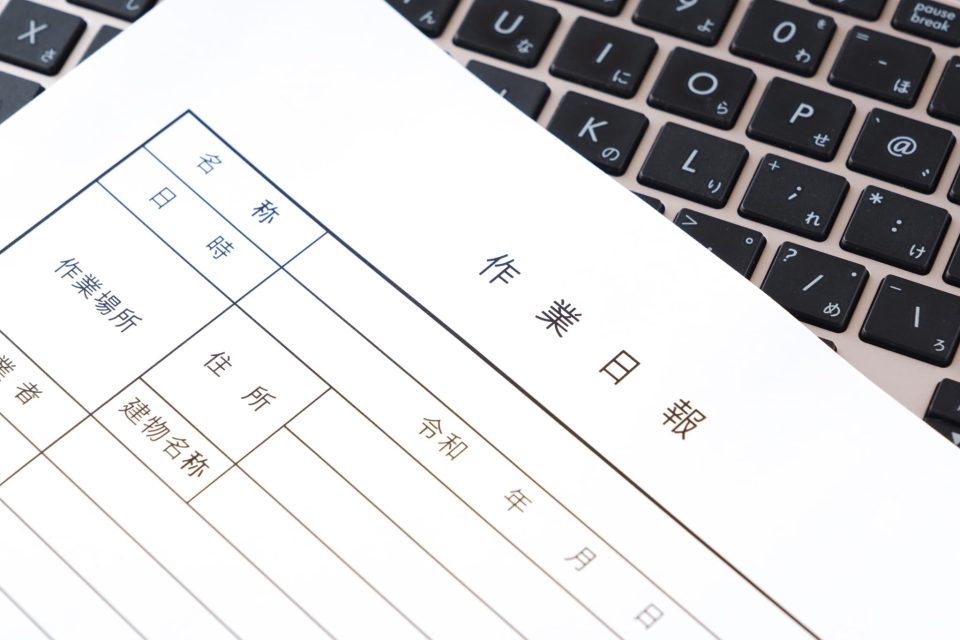
作業日報は、業界ごとに法律で定められた期間は保存する必要があるため、保存場所や方法が重要です。概要や記入項目とともに解説します。
作業日報の概要・記入項目
作業日報とは、1日の終わりにその日を振り返って作成する日誌です。業務内容や1日の反省を記します。上司や他のメンバーへの共有も目的の1つです。記入項目は以下の通りです。
1日の業務の振り返り
労働環境
進捗状況
共有すべき情報
関連記事:【例文あり】作業日報の書き方とは?作業日誌との違いや書き方のコツを解説
上司は日報を通して作業の進捗を確認できるため、スケジュールの変更が必要な場合や、トラブルで作業が停滞している場合に気づきやすいでしょう。作業日報は、組織にとって重要な役割を担います。作業日報を作成する際は、以下のPDCAサイクルを回します。
目標をたてる (Plan)
作業に取り組む(Do)
評価する(Check)
改善する(Action)
作業日報の保存方法
作業日報は、保存期間が法律で定められた書類です。必要時に速やかに取り出せるよう、個人ではなく会社全体で管理し、保存場所や方法を社内ルールとして定めます。保存スペースが不足する場合は、記録方法自体を見直す必要があるかもしれません。
法律で定められた作業日報の保存期間
会社で扱う書類は、書類ごとに保存期間が法律で定められています。作業日報は、金融商品取引法第25条により3年間の保存が義務付けられています。会議記録や軽易な契約書類も同様で、起算日は記録・作成日です。
速やかに提出できる状態で保管し、期間経過後は廃棄しても問題ありません。廃棄の方法については定められていませんが、個人情報の取り扱いには十分、注意してください。
業界別、作業日報の保存期間
作業日報の保存期間は、製造業が3年、建設業が5年、運輸業が1年と業界ごとに異なります。各業界の保存期間は、製造業は「労働安全衛生規則」、建設業は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、運輸業は「旅客自動車運送事業運輸規則」に記載されています。
作業日報を管理する4つのポイント

作業日報の管理に重要な、定期的な棚卸し、適切なタイミングでの廃棄、管理場所、電子化の4つのポイントについて解説します。
関連記事:日報はエクセル管理で業務効率化!自動化の方法や作り方を解説
1. 定期的な棚卸しが必須
作業日報は、どこに何があるかの確認作業も兼ねて、定期的な棚卸しが必要です。それにより、書類が整理された状態を維持できます。棚卸しの際は、書類ごとに保存期間を把握し、書類の分類についても見直しましょう。法律で定められた保存期間を経過したあとも、何らかの理由から保存したい場合は、電子化も有効です。
2. 保存期間が過ぎた日報は廃棄する
書類ごとに定められた保存期間を把握し、期間が過ぎたら破棄します。作業日報に限らず、書類の廃棄を怠ると社内に不要な書類・ファイルが増え続け、オフィスのスペースを圧迫する恐れがあります。
3. 管理場所を細かく決め過ぎない
書類を整理する際は、綺麗に分類しようとするあまり、管理場所や分類項目を細かくしすぎないよう注意が必要です。過度に複雑な分類は、かえって未分類の書類を大量に生み出し、本末転倒な結果を招きかねません。効率的な方法として、ファイルは大まかに分類し、そのなかでやや詳細に分けることをおすすめします。また、書類の電子化をすると、より柔軟な整理が可能になるでしょう。
4. 電子化を検討する
作業日報は電子化がおすすめです。紙での管理では、法定保存期間である3年を経過した書類を順次廃棄しても、常時保存する3年分の書類は相応のスペースを必要とします。ファイルの検索、取り出し、収納といった作業も発生します。
電子化することで、書類の検索作業が迅速化され、物理的な保存場所も不要になります。書類作成や複数人での共有作業が効率化され、印刷費の削減にもつながります。ただし電子化しても、放置すればパソコンやクラウドの容量を圧迫するため、定期的な棚卸しは欠かせません。
作業日報を保存するメリット4つ
電子と紙、それぞれの作業日報の保存には、以下のようなメリットがあります。
| 電子日報 | 紙の日報 |
・事故やトラブルを防げることができる ・自社のノウハウが蓄積される ・モチベーションが維持できる ・健康管理ができる | ・コストを削減できる ・自社のノウハウが蓄積される ・モチベーションが維持できる ・健康管理ができる |
電子と紙、共通しているメリットもあれば、異なる部分もあります。
1. コストを削減できる
作業日報は、コスト管理の最適化にもつながります。現場作業員の働き方を把握することで、人材の最適配置に転換できます。作業員の割り振りが偏っている箇所を調整することで、人件費の削減につながるでしょう。また、作業員の無駄やミスの削減により、資材や設備のコストも節約できます。
2. 事故やトラブルを防ぐことができる
作業日報を導入することで、事前に事故やトラブルを防げます。天候で計画通りに進まないこともあるものの、作業日報があれば作業の遅延にも対応できます。状況を細かく把握できていれば、工期遅延のトラブルも回避できるでしょう。作業日報に書く内容は、些細なことで構いません。また、作業における危険個所や問題点を洗い出すことも可能です。
3. 自社のノウハウが蓄積される
作業日報は、個々のスキルや会社のノウハウを蓄積する貴重な情報資産です。従業員の日々の気づきが詳細に記録されるため、実用性が高く、社内で共有すれば効果的な人材育成にもつながります。いわば、従業員それぞれが得た知識や技術を集めたデータベースといえます。
4. モチベーション・健康管理ができる
各従業員が書く作業日報は、職場のコミュニケーションを促進します。上司は部下の業務内容や成果を把握しやすくなり、適切な指導や支援もできるでしょう。同時に、部下の悩みにも早期に気付けるため、従業員のモチベーション維持につながります。さらに、労働環境や従業員の健康状態の把握も容易になることがメリットです。
作業日報を保存するデメリット4つ
電子と紙、それぞれの作業日報の保存には、以下のようなデメリットがあります。
| 電子日報 | 紙の日報 |
・サービスを導入しなければならない | ・過去の日報を探しにくい ・記載内容が読み取りにくい ・提出が難しい ・一元管理ができない |
1. 過去の日報を探しにくい
作業日報は日々蓄積され、3年分では膨大な量になります。特に新入社員にとって過去の作業日報は役立ちますが、紙媒体では検索に時間がかかります。電子化することで、速やかに必要な情報を探せます。
2. 記載内容が読み取りにくい
手書きの作業日報を採用している場合は、人によって読みづらいことがあります。印字された書類と比べ、手書きの場合は時間とともに読みづらくなってしまいます。特定のフォーマットがない場合は、従業員によって書き方も異なるため、他の人からは読みにくい可能性があるでしょう。この場合、進捗管理や改善点のフィードバックにも、影響を及ぼします。
3. 提出が難しい
紙で作業日報を管理している場合、提出が面倒になる可能性があります。営業や出張で社外にいる場合でも、日報を提出するために帰社しなければなりません。日報自体が形骸化してしまう恐れもあります。また作業日報を確認する上司も、フィードバックがしにくくなるでしょう。
4. 一元管理ができない
紙の作業日報を採用している場合、一元管理できない点がデメリットです。エクセルにデータを移す場合でも、案件によって進捗や成果、顧客情報をそれぞれ紐付ける必要があります。これは、手間がかかり非効率です。データ移行にともない、データを誤って削除してしまったり入力ミスをしたりするリスクもあります。
作業日報の一元管理ならANDPADがおすすめ!

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」は、検索作業や記載内容の読み取り、提出の手間や保存場所など、作業日報のデメリットを効果的に解消します。クラウド型のため、過去の作業日報を瞬時に検索でき、提出やフィードバックも場所を選びません。作業日報に関する業務の効率化と生産性向上に役立ちます。
まとめ
作業日報は、法律によって保存期間が定められた重要書類です。社内のノウハウが蓄積された重要な情報資産として人材育成にも活用できますが、3年と定められた保存期間中の管理方法に課題があります。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しているサービスです。使いやすいUI・UXを実現する開発力と手厚いサポート体制で、安心して作業日報の電子化ができます。ぜひ以下よりお問い合わせください。