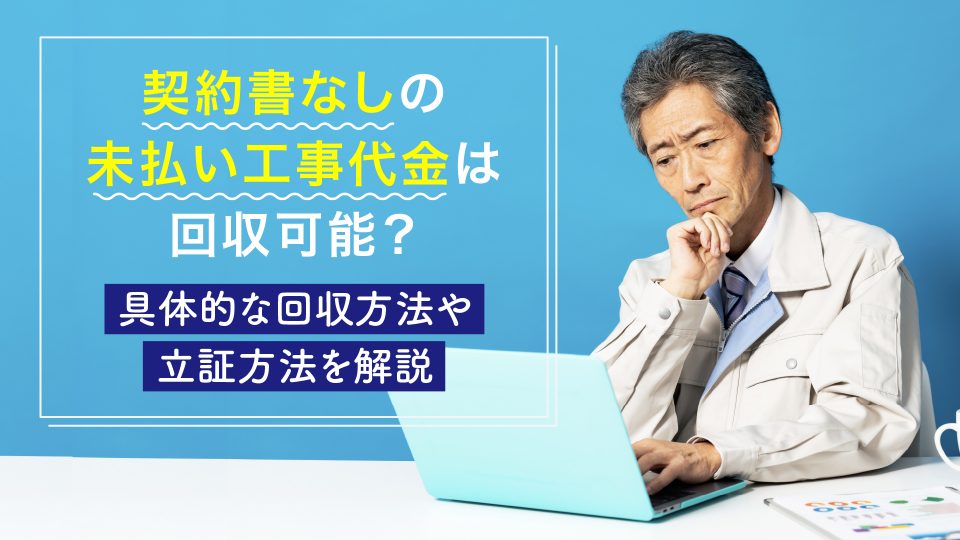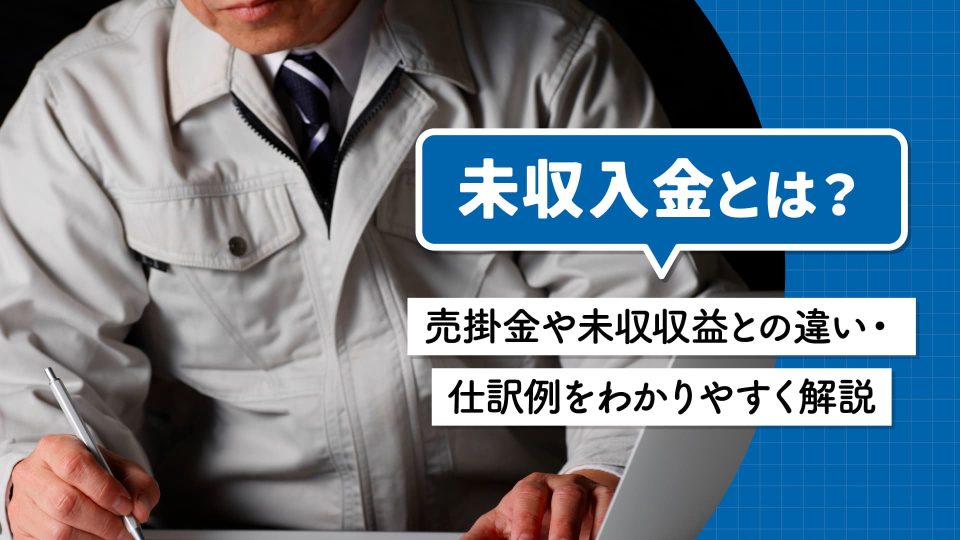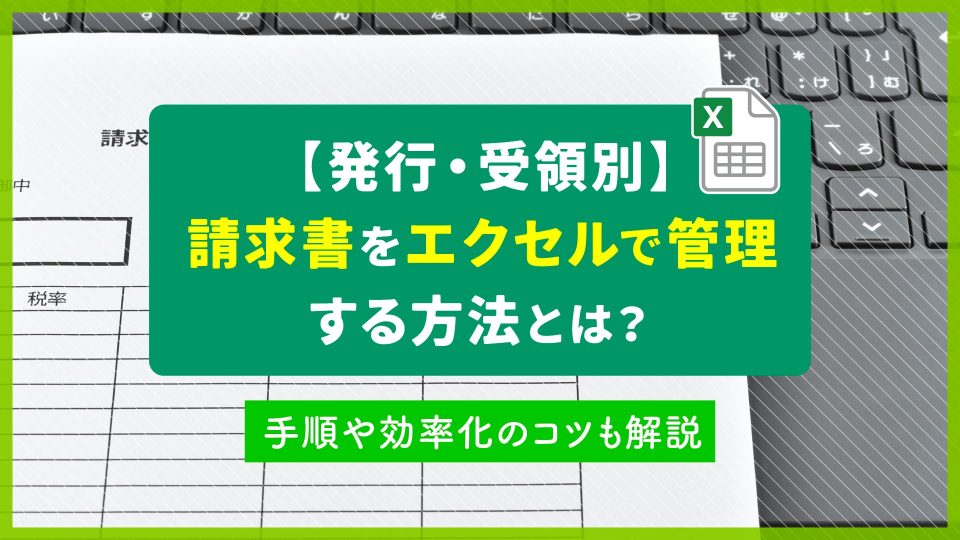工事を完成させても、契約書を交わしていないことで工事代金が支払われないケースがあります。建築業界では工事代金に関するトラブルが発生しやすく、契約書を交わしていても未払いとなるケースも過去には存在しました。
本記事では、契約書がなくても工事を請け負ったことを立証する方法や、未払い工事代金を回収する方法などを解説します。ぜひ参考にしてください。
契約書なしでも未払い工事代金は回収できる

法的には、契約書がなくとも工事請負契約は成立します。口約束であっても未払いの工事代金を回収できる可能性はありますが、契約書がある場合と比べると手間と時間がかかります。
契約は口頭でも成立
そもそも契約とは、当事者間で権利や義務を発生させる法律上の合意です。契約成立の要件については、民法522条2項にて「法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と明記されています。契約の成立では、必ずしも契約書の作成が必須ではなく、たとえ口頭であっても、工事発注者と請負業者には権利や義務が生じることになります。
一方、建設業法19条1項では、契約の締結に際して書面を作成することが求められています。ただし、あくまでも建設業法上の義務に留まり、契約成立の要件には含まれていません。よって、契約書がない状態で工事代金の未払いが発生した場合であっても、当事者同士の合意が立証できれば、工事請負契約は成立します。
工事代金請求権の立証には困難が生じる
契約書を作成していない場合は、工事請負契約の成立や、請負代金額の立証が困難になります。立証責任は工事代金を請求する請負業者にあるため、本来の業務とは別にリソースを確保しなければなりません。
また、立証に失敗すると、未払いの工事代金の回収はできません。建設業法のルールや実務慣行があるため、契約書がないと請負業者は不利な状況に陥ってしまいます。状況を打開できる可能性はありますが、手間と時間がかかります。
契約書なしで工事代金請求権を立証する方法
法律上はメールや口約束などであっても、工事発注者と請負業者の合意が事実であれば工事請負契約は成立します。ここでは、契約書がない場合に工事代金請求権を立証する方法を解説します。
資料や記録を総合的に活用
契約書がなく、未払いが発生した場合は、工事代金請求権を立証することで工事代金を回収できます。立証するためには、資料や記録などの間接的な証拠を積み上げていく方法が有効です。立証に役立つ証拠としては、以下のものが挙げられます。
- 発注者とのメールのやり取り
- 発注者との打ち合わせ資料やメモ
- 発注者との通話やオンライン会議の記録
肝心なのは、発注者が工事や代金について合意していた事実を証拠として立証することです。同じ内容であっても、複数の資料・記録があった方が、情報の信憑性は高まります。
商法に基づく報酬請求権を主張
工事請負契約に基づく工事代金請求権を立証できない場合は、商法上の報酬請求へ切り替えます。商法第512条では、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」と明記されています。
商人には事業者も該当するため、請負業者が発注者のために工事を実施した場合は、契約書や合意の有無にかかわらず、実施内容相当の報酬を請求することが可能となります。
未払い工事代金の回収方法

ここからは、未払い工事代金を回収する具体的な手順を紹介します。まずは話し合いでの解決を目指し、それでも支払いを拒否し続けるのであれば、然るべき措置を講じていきます。
関連記事:請求漏れ・支払い拒否が発生した時の対応は?原因や具体的な防止策、注意点を解説
1. 立替払い制度の利用(協力業者の場合)
立替払い制度を利用することで、従業員の給与などの支払いを工事発注者から受けられる可能性があります。工事発注者が特定建設業者であれば、立替払い制度の要件を満たします。特定建設業者とは、1件の請負工事の合計額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上)の下請契約ができるよう、許可された業者のことです。
立替払い勧告は建設業法41条で定められており、国土交通大臣または都道府県知事の裁量により行われるかが決まります。
2. 発注者に催告
発注者への催告とは、工事を依頼した業者に直接支払いを請求する行為を指します。工事発注者とは今後も取引が継続する可能性があるため、事実や要望を冷静に伝えることを心がけましょう。
相手側にも事情があるケースも少なくないため、まずはメールや書面などで請求し、反応がなければ電話や訪問を含む対応を検討します。文書を作成する際は、遅延損害金と支払期限を明記するのも有効です。
3. 内容証明郵便を送付
相手側に催告をしても応じない場合は、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明する制度で、受領の有無も確認できます。
内容証明郵便は、請負業者が作成することもできますが、弁護士への依頼も可能です。内容証明を受け取って期限までに支払いがなければ次の手段へと進みます。
4. 支払督促の申し立て
支払督促の申し立てを行うことで、裁判所から工事発注者に支払督促を発布してもらえます。簡易裁判所への申し立てになるため、民事訴訟と比べると、短期間・低コストで手続きできます。
ただし、相手から異議申し立てがあったときは通常訴訟に移行します。異議申し立てがなく、仮執行宣言が付されれば、差し押さえによる未払い工事代金の回収が近づきます。
5. 訴訟を提起
訴訟では、請負業者側が原告として訴状を作成し、証拠を提出します。裁判所は、被告側の反論答弁書などをふまえて、未払い工事代金の有無について判決を下します。
訴訟を起こすことで、工事代金未払いの問題は決着しますが、証拠が不十分だと判断されると敗訴となる可能性もあります。ただし、実際は判決の前に和解にいたるケースも少なくありません。和解となった場合は、双方が納得した金額が支払われます。
6. 財産の差し押さえ(強制執行)
強制執行とは、裁判所に申し立てを行い、相手方の財産を強制的に差し押さえ、返済にあてることを決定する手続きです。
財産を差し押さえるためには、公的機関が作成した債務名義が必要となります。債務名義には、確定判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促などがあります。
工事代金請求権の時効に注意
未払いの工事代金を請求するときは、時効に注意しましょう。ここでは、消滅時効期間と時効を阻止する方法を解説します。
工事代金請求権の消滅時効期間について
工事代金請求権は、一定期間行使しないと時効となって消滅します。時効となる期間は、工事請負契約を締結した時期によって異なります。
具体的には、2020年3月31日までに請負契約を締結した場合は、工事完成日の翌日から3年で時効となります。2020年4月1日以降は民法が改正された影響で、工事完成日の翌日から5年に延長となりました。
時効を阻止する方法
時効を阻止する方法は、民法の改正前後で異なります。民法が改正される前の時効は「中断」「停止」、民法が改正された後の時効は「更新」「完成猶予」と表現されます。
2020年3月31日以前の契約は、次の手続きをすることで中断もしくは停止となります。
- 裁判上の請求
- 差押え
- 仮差押え
- 債務の承認 など
2020年4月1日以降の契約は、次の手続きをすることで更新もしくは完成猶予となります。
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 和解・調停
- 判決等による権利の確定
- 強制執行
- 担保権の実行 など
工事契約書は必ず交わすようにしよう

未払い工事代金をスムーズに回収するためには、工事契約書があると良いです。後回しにせず、工事を開始する前には、必ず契約書を作成しましょう。
建設業法第19条で義務付けられている
前述したとおり、建設業法19条1項では、契約の締結に際して書面を作成することが義務付けられています。工事請負契約書を作成せずに工事を行うと、建設業法違反に問われるリスクが発生します。建設業法の要件を満たしていない工事請負契約書は無効となるため、必要事項の抜け漏れがないよう注意しましょう。
契約書がない場合のトラブル例
契約書を交わさず工事をした場合、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 工事代金が支払われない
- 水掛け論になり、取引先との関係が悪化する
- 損害賠償請求される
急ぎの修繕が必要な工事や、小規模な工事などは契約書がないまま着工するケースもあるかもしれません。しかし、契約書がないことでトラブルに発展しやすくなるため、工事のスケジュールや規模に関わらず、必ず作成しましょう。
契約書がない追加変更工事もトラブルに発展しやすい
建築業の現場では、どうしても口約束の追加工事が発生しやすくなります。契約書がない追加変更工事はトラブルの元です。工事発注者から、「この変更は依頼していない」「こんなに高額になるとは思わなかった」といわれることがないよう、事前に契約書を交わして了承を得ることが大切です。
まとめ
民法上は、契約書がなくても工事請負契約は成立します。未払い工事代金の回収も可能ですが、証拠を集めたり、回収の手続きを行ったりと、大きな負担が生じます。これらの問題は、契約書を作成することで解決できるので、できるだけ着工前に契約書を交わすようにしましょう。
工事代金の回収をはじめ、現場の業務を効率的にしたい場合は、建設業に特化したツールの導入がおすすめです。なかでも「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。受発注を丸ごと電子化でき、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しています。
気になる方はぜひ、以下から無料で資料をダウンロードしてみてください。
※本記事は2023年12月22日時点の法律に基づき執筆しております。