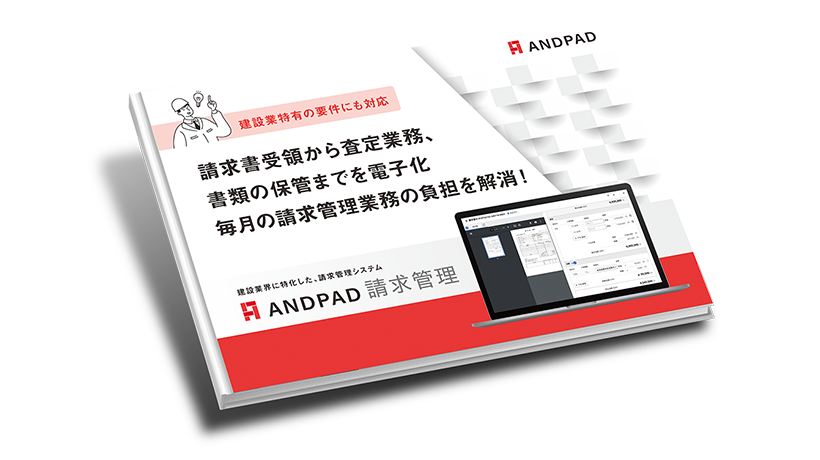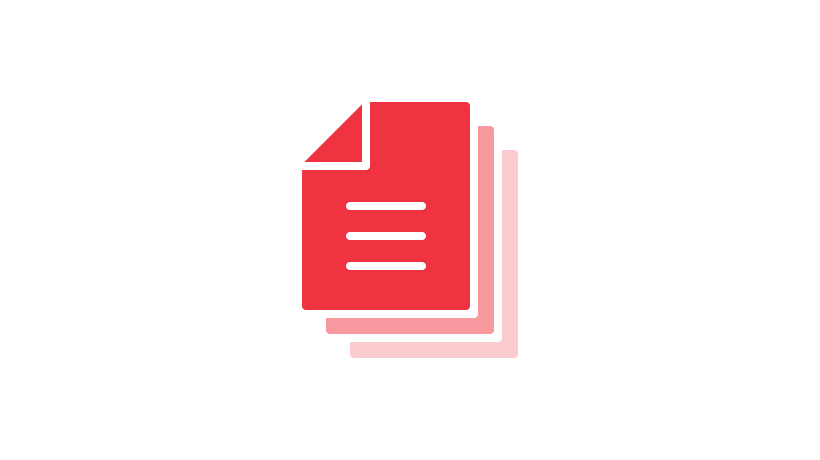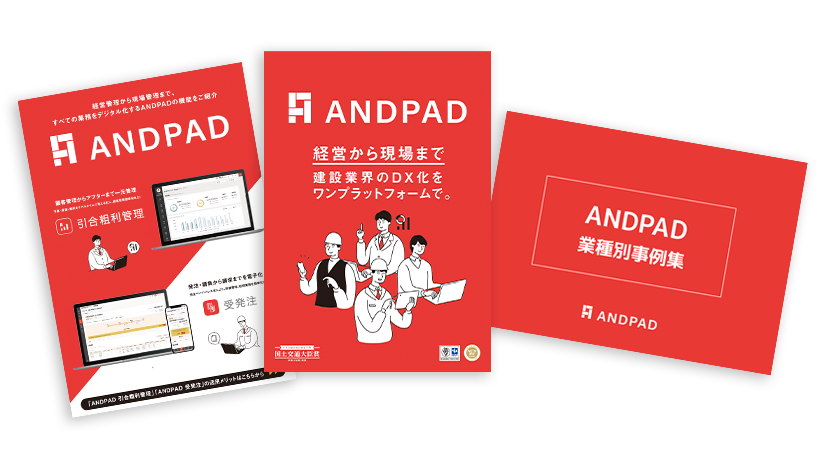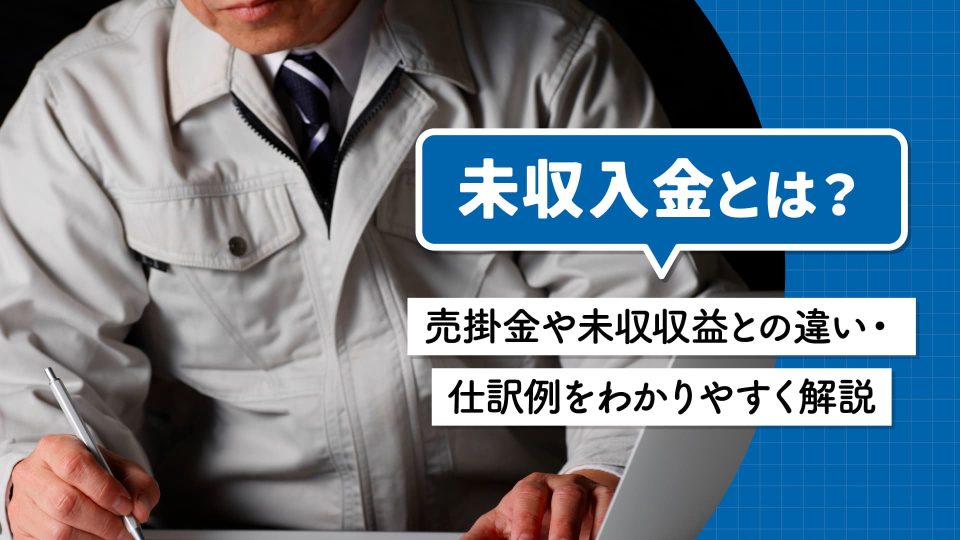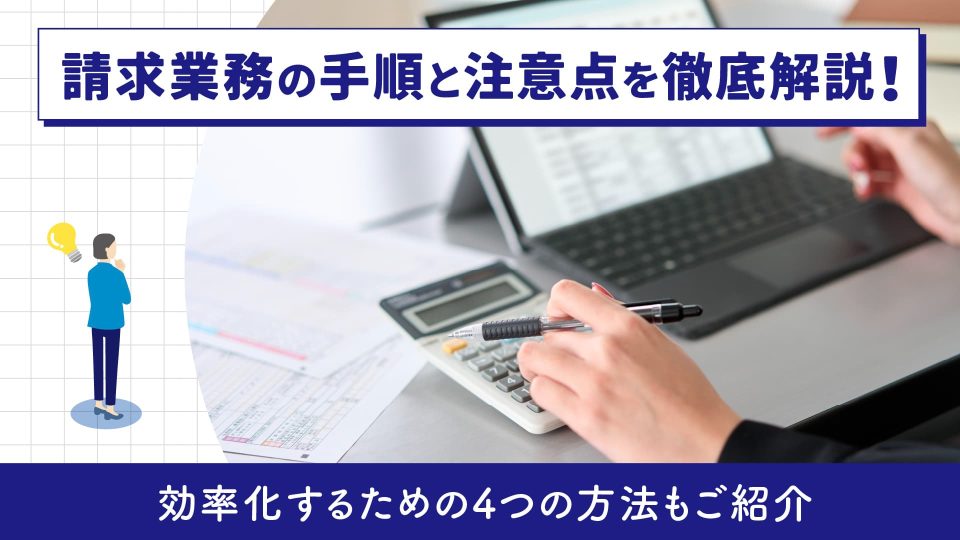未収入金とは、営業活動以外の一時的な取引で生じた、まだ徴収できていない対価を計上する勘定科目です。ただし、混同しやすい言葉があり、区別がついていない人も珍しくありません。この記事では、未収入金の定義や混同しやすい言葉との違いなどを解説します。業務上知識を身につけたい人は、参考にしてください。
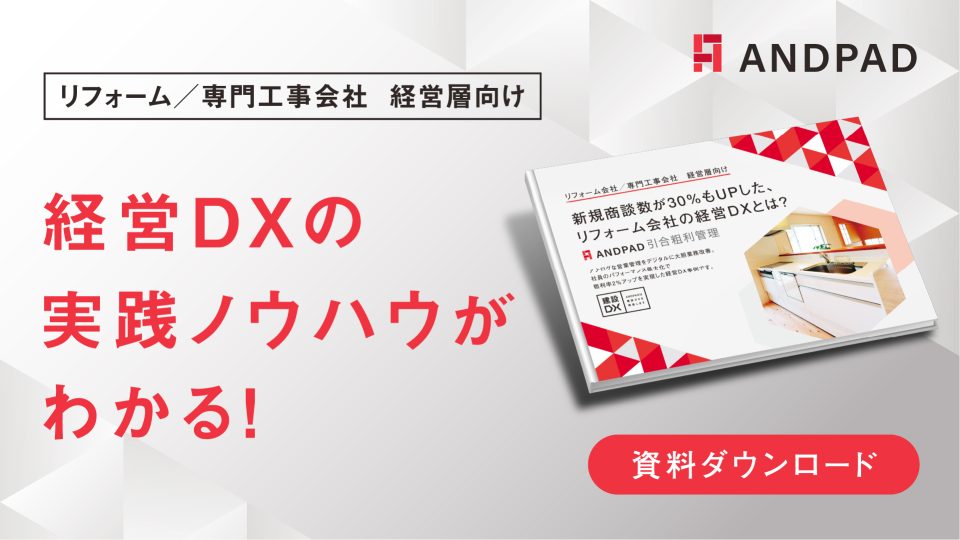
リフォーム会社向けに、リフォーム会社に経営DXが求められる理由や、ANDPADを活用したDXのステップについてご紹介しています。
未収入金とは?定義を解説

営業活動以外の一時的な取引において、商品またはサービスを供与したにもかかわらず、まだ対価を受領していないケースで用いる勘定科目です。対価の受取が即座にできない固定資産や有価証券の売却、本業ではない商品・サービスに対する代金の受領が翌月になる場合などが該当します。
一般的に一時的な債権として扱われ、貸借対照表における流動資産へと反映させます。企業の資金繰りや財務状況を把握するうえで重要な指標になるため、適切に管理しましょう。
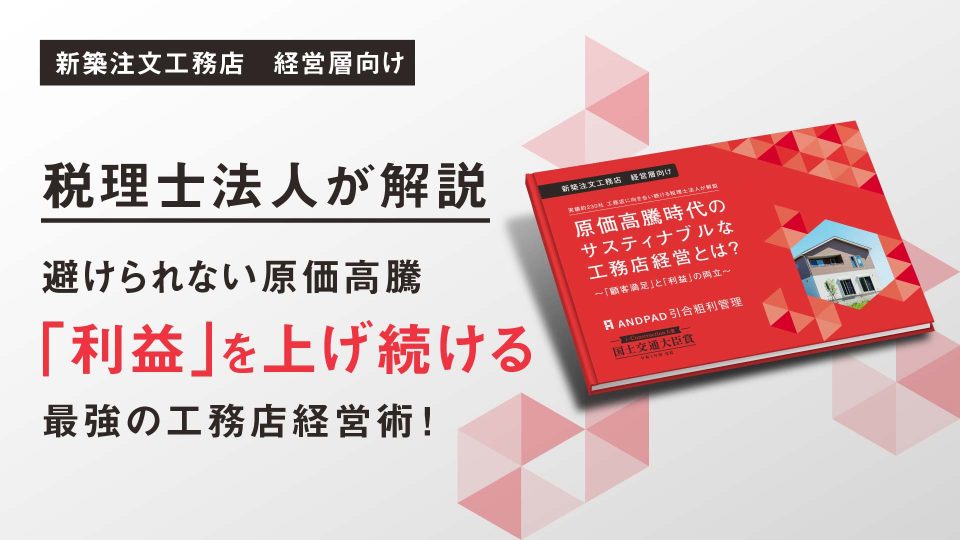
新築注文工務店の経営者方向けに、利益・原価管理をより正確に、スピード感をもって把握するノウハウ、原価管理の精度向上を実現したANDPAD活用事例などをご紹介しています。
未収入金と間違われる科目
未収入金と混同しやすい2つの勘定科目があります。それぞれの特徴、違いを解説します。
売掛金との違い
売掛金との大きな違いは、本業である営業活動で生まれる債権であるかです。売掛金は営業活動により生まれた債権です。サービスの供与や物品の販売など営業活動によって生まれた対価で、まだ受け取っていないものが対象となります。
貸借対照表に記す際は同じく流動資産として記しますが、それぞれ区別できるよう勘定科目を分けて記さなければなりません。
未収収益との違い
未収収益とは、取引内容に違いがあります。未収収益は、時間の経過により持続的に発生する収益のうち、決算日までに提供済みだが翌期以降に徴収見込みのある金銭債権です。未収入金が一時的な取引による債権であるのに対し、未収収益は持続的なサービス提供による取引で生まれる債権です。
未収収益は経過勘定へと仕訳されます。経過勘定とは、収益や費用を当期と次期に正しく配分し、期間損益計算を適正に行うための勘定科目で、通常の取引と異なる会計処理が必要です。
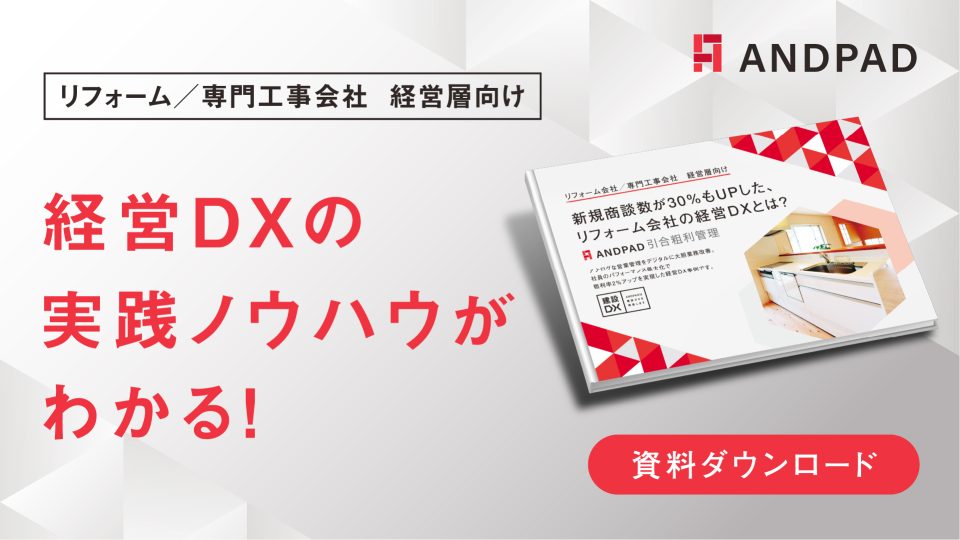
リフォーム会社向けに、リフォーム会社に経営DXが求められる理由や、ANDPADを活用したDXのステップについてご紹介しています。
未収入金の仕訳方法
未収入金が生まれた際に、どのように仕訳を実施するのか具体的な例を挙げて解説します。
未収入金が発生した場合の一般的な仕訳例
営業活動ではないサービスの供与により、例えば80万円の未収入金が生まれた際に、貸借対照表では「資産の部」の「流動資産」へと仕訳します。借方へ「未収入金」80万円、貸方へ「雑収入」80万円と記します。
未収入金が入金された場合の一般的な仕訳例
取引で生まれていた未収入金の80万円が現金の形で入金された際に、仕訳は借方へ「現金」80万円、貸方へ「未収入金」80万円と記します。
固定資産を譲渡した場合の仕訳例
固定資産を譲渡した際に、債権の徴収予定が1年以上先であれば「固定資産」へと仕訳します。また、譲渡した際の「未収入金」における、資産の帳簿価額と譲渡価額の差額に注意しましょう。例えば、帳簿価額80万円の固定資産を90万円で譲渡して利益が生まれた際に、借方へ「未収入金」90万円、貸方へ「固定資産」80万円、「固定資産売却益」10万円と記します。
不動産を貸付した場合の仕訳例
自社で保有する不動産を貸付し、ひと月の賃貸料として40万円が生まれた場合、借方へ「未収入金」40万円、貸方へ「賃貸料収入」40万円と記します。賃貸料を現金で得た場合、借方へ「現金」40万円、貸方へ「未収入金」40万円と記します。消費税込みで記す際は、借方に「未収入金」44万円、貸方に「賃貸料収入」40万円、「仮受消費税」4万円と記します。
機械設備を売却した場合の仕訳例
機械設備を売却した際は、直接法と間接法という2種類の仕訳方法があります。直接法では固定資産から減価償却費を直接差し引きます。例えば45万円で機械を購入し40万円で売却、減価償却10万円だった場合、借方へ「未収入金」40万円、貸方へ「機械設備」35万円、「固定資産売却益」5万円と記します。
間接法では、固定資産を直接減らさず減価償却累計額を計上し、償却額の合計を表します。借方へ「未収入金」40万円、「減価償却累計額」10万円、貸方へ「機械設備」50万円、「固定資産売却益」5万円と記しましょう。
未収入金での会計処理時の注意点
未収入金を会計処理する際は、いくつか注意すべき点があります。おもな3つの注意点を解説します。
発生主義による会計処理を行う
企業における会計の原則は、発生主義に基づいています。発生主義とは現金の動きに関係なく、収益や費用は取引が生まれたタイミングで反映させる考え方です。
現金の受領や支払いが生まれた時点で収益を反映させる「現金主義」では、取引日と実際にお金が動いた日に違いが生まれます。そのため、資産を売買した際に売却損益や債権残高を正しく把握できません。
回収予定経過残高と取引相手の信用状態を確認する
未収入金の管理には、回収予定経過残高、取引相手の信用状態などを把握しましょう。未収入金は将来的に徴収すべきお金を示す勘定科目のため、残高管理に気を付けなければいけません。
取引先の財務状況や支払い履歴などを調査し、徴収予定日を過ぎても徴収できないケースでは迅速に対応しましょう。取引と同じ会計年度内に徴収見込みがないケースでは、取引相手が信用状態に欠けるのであれば貸倒引当金へと反映させましょう。
未収収益を未収入金として扱っている場合の経過勘定の処理
未収収益は会計制度上では「経過勘定」にあたります。経過勘定とは、サービスの供与または時間の経過によって生まれる、費用と収益を調整するための勘定科目です。そのため、決算時に特殊な会計処理が必要です。未収収益は「見越し」もしくは「繰り延べ」として処理します。
見越しとは、次期にずれて支払いや受領が実施されるケースで当期の収益・費用として処理する方法です。繰り延べとは、次期以降の収益・費用として処理する方法です。

ANDPADには顧客管理から粗利・原価管理まで一元管理できる「引合粗利管理機能」があります。ご利用企業様における具体的な活用方法・導入効果をまとめた事例集をご紹介しています。
未収入金と買掛金を相殺するには

企業の債権債務の管理において、未収入金と買掛金の相殺が必要になるケースがあります。適切に実施できると、決済リスクを軽減できます。
相殺する条件
未収入金と買掛金を相殺するには、民法第505条にある相殺の規定により、以下の3つの条件を満たさなければいけません。
- 同一相手先に対する金銭債権と金銭債務であること
- 相殺が法的に有効で、企業が相殺する能力を有すること
- 企業が相殺して決済する意思を有すること
また、会計上すべて総額で表示する原則(企業会計原則、貸借対照表原則、総額主義の原則)がありますが、上記の条件をすべて満たしていれば相殺して表示できます。
相殺の手続きと注意点
未収入金と買掛金を相殺する際は、まず書面で取引先に通知して相殺の意思を示します。意思表示が取引先に伝わった時点で、相殺の効力が生まれます。そして、相殺する金額を両勘定から減額し、相殺の手続きを終えます。相殺の手続きを進める際は、以下の3つの点に注意しましょう。
- 契約を締結した際、相殺を禁止する特約を定めた場合は相殺できない
- 回収の時効期間が違う債権を相殺する場合は、注意が必要
- 第三者の権利を害する相殺は、無効になる可能性がある
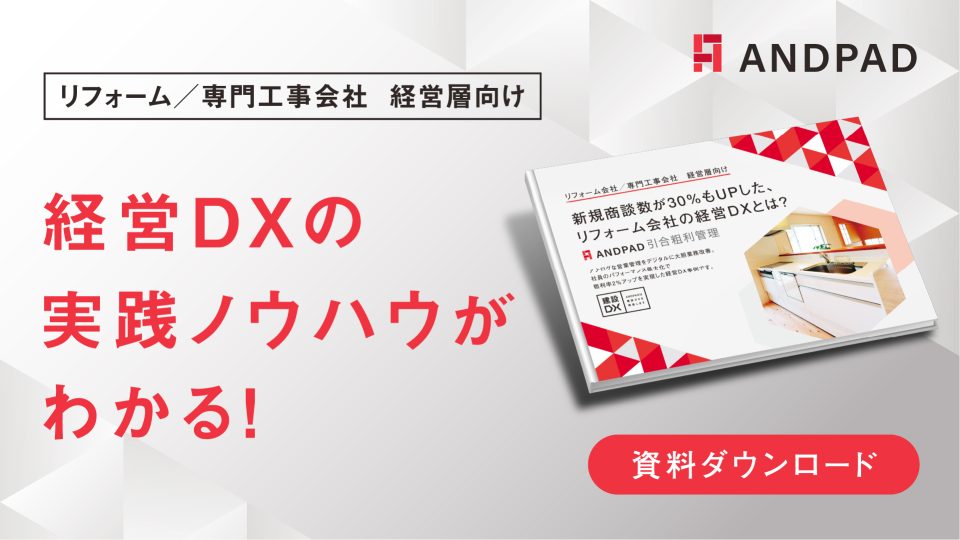
リフォーム会社向けに、リフォーム会社に経営DXが求められる理由や、ANDPADを活用したDXのステップについてご紹介しています。
「未収入金」「売掛金」「未収収益」の違い

最後に未収入金、売掛金、未収収益の3つの違いを改めて整理します。2つの観点から解説します。
計上対象となる取引の違い
3つはそれぞれ、計上対象の取引が違います。売掛金とは、商品の販売のように営業活動で生まれた債権です。未収入金とは、営業活動ではない収益に対する債権です。未収収益とは、決算日までに収益は生まれているものの、入金は次期になるものを指します。
この3つは会計処理も違い、未収入金と売掛金は取引時に反映させる一方で、未収収益は決算時に反映させます。
貸借対照表上の違い
未収入金、売掛金、未収収益の3つは、いずれも貸借対照表上では同じ「資産」として反映させます。資産の部は流動資産、固定資産、繰延資産の3つに区分されます。通常1年以内に現金化できる見込みがあるため、未収入金と売掛金は流動資産として反映させます。一方、未収収益も通常は流動資産に仕訳されますが、一般的には「その他の流動資産」として表示します。
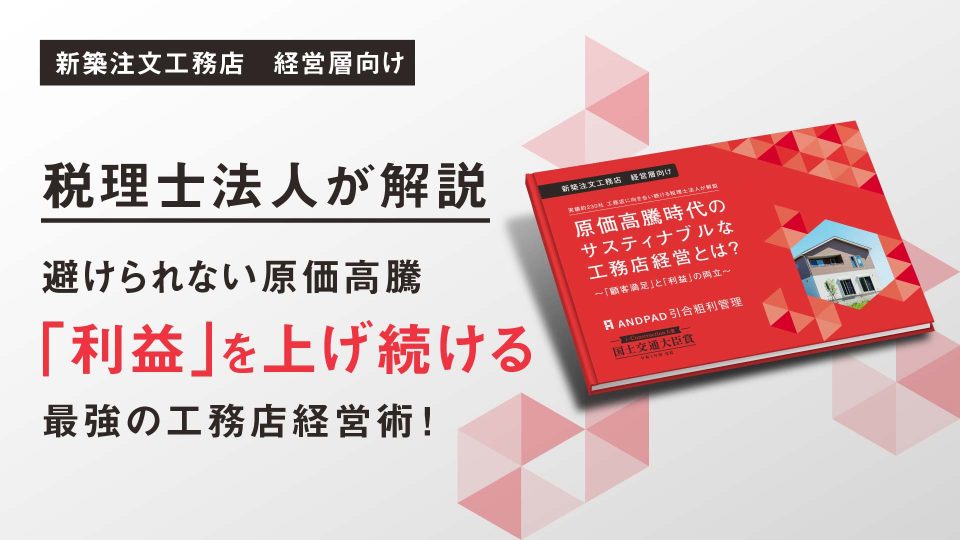
新築注文工務店の経営者方向けに、利益・原価管理をより正確に、スピード感をもって把握するノウハウ、原価管理の精度向上を実現したANDPAD活用事例などをご紹介しています。
建設業の未収入金を可視化するなら「ANDPAD Analytics」がおすすめ
建設業界では、引渡後の入金漏れや未収金の滞留が資金繰りに大きな影響を与えるケースも少なくありません。「ANDPADアナリティクス」では、2025年6月のアップデートで「入金予定未登録」「未収金管理」ダッシュボードが追加され、入金予定の登録漏れや回収未完了の案件を自動で検知できるようになりました。
契約額に対して入金予定や実績が不足している案件を可視化し、回収漏れを未然に防ぐことが可能です。特にリフォーム業をはじめ、引渡後に入金が発生する業態において、資金管理の精度向上に大きく貢献します。
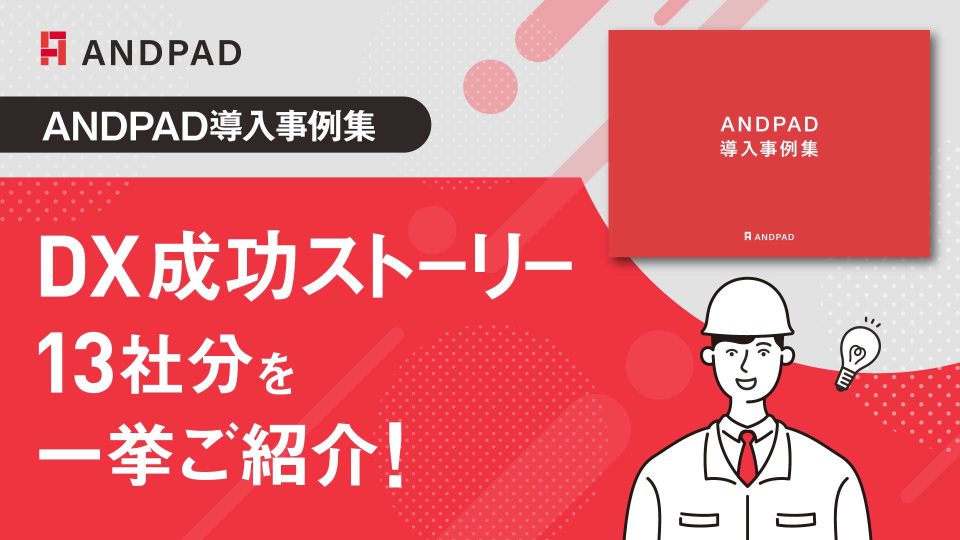
ANDPADをご検討中の方向けに、各社が抱えていた課題、DX成功に至るまでの導入事例をまとめてご紹介しています。ゼネコン、設備工事、太陽光、注文住宅、リフォームなど、幅広い業種の事例をピックアップしています。
まとめ
未収入金とは営業活動以外の取引で生じた、徴収できていない対価を反映させる際の勘定科目です。混同しやすい勘定科目があり、仕訳方法などと合わせて理解しておくことが重要です。違いを正確に認識しましょう。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、使いやすいUI・UXを実現する開発力から、数多くの企業・ユーザーに利用されています。年間数千を超える導入説明会を実施しており、手厚いサポートも特長です。未収入金の管理・処理も容易になります。ぜひANDPADの導入をご検討ください。