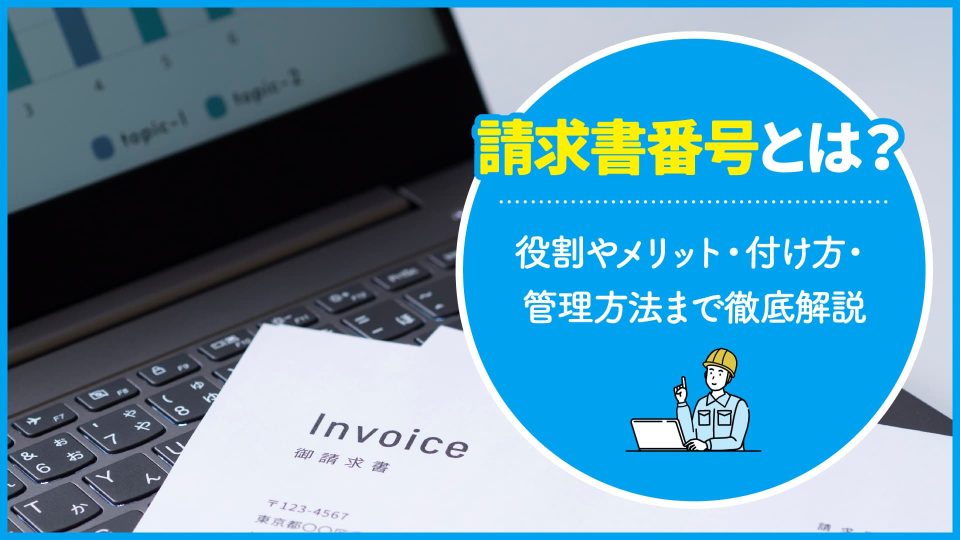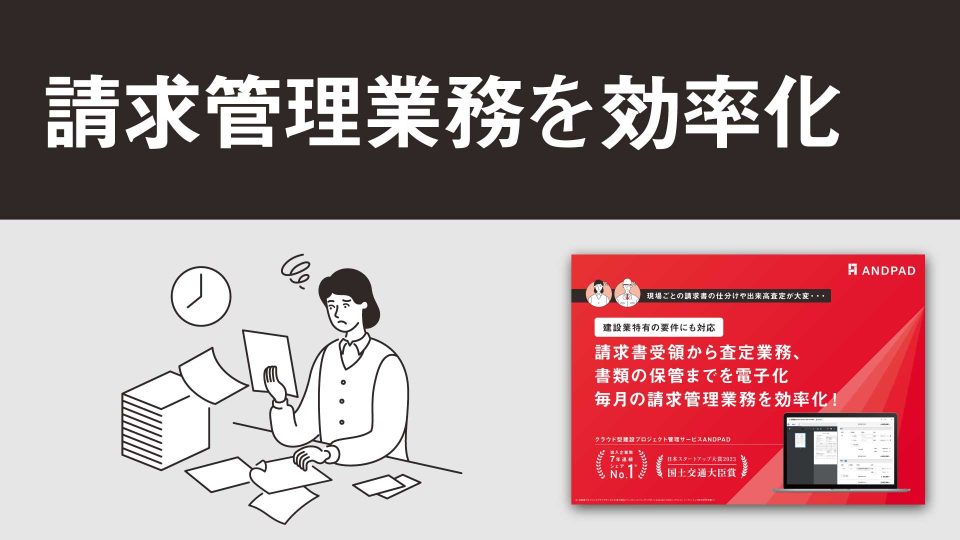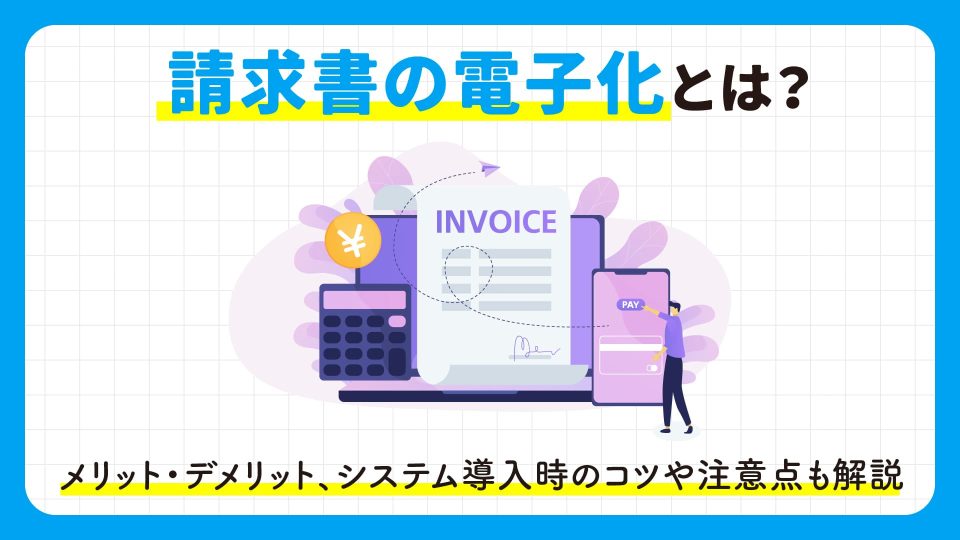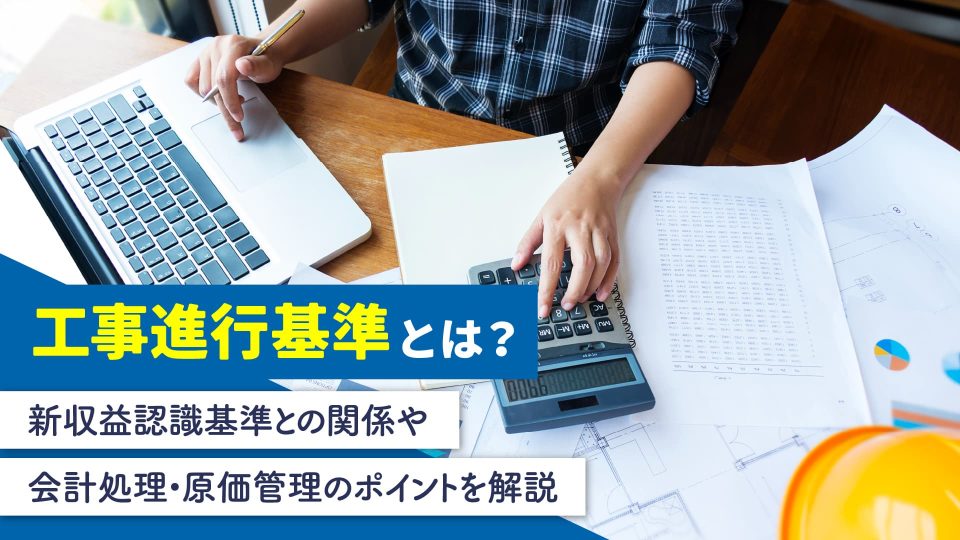請求書番号とは、書類を管理するための個別の番号です。一般的に、書類の右上に記載し、管理業務の効率化やミスの防止などに活用します。この記事では、請求書番号の概要やメリット・付け方・注意点などを解説します。インボイス制度開始による、請求書記載項目の変更点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
請求書番号とは?基本知識を解説

請求書番号とは、通し番号のことです。「000-20250610-0003」といった番号を割り振り、書類に記載します。一般的には、適格請求書(インボイス対応)を含む請求書の右上に番号を記載する項目があります。
法律上、請求書番号の記載は義務ではありませんが、書類の整合性や業務フロー上の重要な役割を果たすため、多くの事業者が記載しています。
請求書番号が必要な理由と基本的な役割
請求書番号の記載は義務ではありませんが、多くの事業者にとって必要なものです。見積もりから請求までの流れを関連付けることで、請求漏れをはじめとしたミスの防止につながります。データ管理だけでなく、業務効率化にも貢献するでしょう。
複数の請求書を発行する場合や、経理業務の効率化などを目的とする場合、記載する必要性が高まります。管理の効率性を重視するために、個別の番号を付けることをおすすめします。
請求書番号を付けるメリットと活用効果
請求書番号は、他の書類や取引先とのやり取りに活用されます。ここでは、メリットと活用効果を解説します。
同じ取引の見積書・納品書などと紐付けられる
請求書番号は、書類の照合に役立ちます。たとえば、同じ取引の見積書・納品書など、固有の番号として紐付けることが可能です。他の書類と一貫した管理ができるため、関連書類を保管する際に便利です。
また、記載漏れやミスを防ぎ、書類の相互確認や関連付けの作業をスムーズにすることで、取引の状況を把握しやすくなります。取引の透明性を高めるためにも、番号の記載は重要です。
取引先とスムーズにやり取りできる
固有の番号が割り振られていると、取引に関するやり取りをスムーズに行えます。問い合わせがある場合でも、迅速に内容を確認できます。アフターフォローにも素早く対応できるため、取引先の安心感が高まり、自社への信用も向上するでしょう。
請求書番号が記載されていると、再発行の手続きにも対応しやすくなります。2回目以降の再発行において異なる番号を割り振ることで、二重請求といったトラブルの防止につながります。
データの保存や検索がしやすくなる
固有の番号が記載されていると、データの保存や検索にも便利です。該当の請求書を即座に検索できるため、書類を探す時間を大幅に短縮できます。紙の書類でも時間を短縮できますが、データ保存の方が業務効率の向上につながるためおすすめです。
2024年1月1日から施行された改正電子帳簿保存法において、請求書の電子保存が義務化されました。
請求書番号の付与方法

請求書番号には、基本的な記載方法があります。ここでは、付与方法を解説します。
法的なルールはない
請求書番号を記載する際に、法的なルールはありません。事業者独自の方法で、個別の番号を割り振る必要があります。混乱を避けるためには、一度決定したルールを守って運用することが重要です。
顧客番号・日付・取引番号を組み合わせたルール設計例
一般的に、請求書番号は、顧客番号・日付・取引番号の3つを組み合わせて決めます。以下、顧客番号「001」、「2025年6月15日13時55分」に「1回目」の取引が行われたケースです。
| 請求書番号の付与方法のルール | 請求書番号 |
| 顧客番号 + 取引日時 + 取引番号 | 001202506151355001 |
| 顧客番号 + [ – ] + 取引日時 + [ – ] + 取引番号 | 001ー202506151355ー001 |
| 顧客番号 + 取引日時(下10桁) + 取引番号 | 0012506151355001 |
他には、順番の採番や取引先コードと請求月の採番、取引先コードと請求月ごとの発行回数での採番など、記載する方法はさまざまです。
請求書番号を付ける際の注意点
請求書番号を付ける際は、複雑な文字列や重複を避けましょう。ここでは、注意点を解説します。
文字列を複雑な設定にしない
請求書番号は、わかりやすい文字列にしましょう。個別の番号を割り振る際、セキュリティ強化のために複雑な文字列を用いる場合もあります。しかし、ルールや運用などの管理が難しくなり、ルールを決めにくくなる点に注意が必要です。また、ミスの原因にもなるため、機密性の高い取引以外は、複雑な文字列の設定を避けましょう。
重複しないようにする
請求書番号は、正確に管理するため重複を避けることが大事です。再発行の場合は、同じ番号を割り振るケースがありますが、それ以外は重複しないように注意が必要です。自社の採番ルールを決め、番号の重複をチェックするフローを構築しましょう。請求書発行システムを使用すると、ルールに従って自動で番号が割り振られるためおすすめです。
インボイス制度開始による請求書記載項目の変更点
インボイス制度によって、請求書に記載する内容が変更になりました。ここでは、記載項目の変更点を解説します。
適格請求書発行事業者の登録番号を記載する
インボイス制度によって、適格請求書発行事業者の登録番号の記載が必要となりました。登録番号とは、適格請求書の要件の1つです。事業者ごとの番号として、マイナンバーや法人番号と重複しないものを指します。課税事業者は「T+法人番号」、個人事業主などは「T+数字13桁」となります。
税率ごとに区分して記載する
適用税率と消費税額を記載する際は、税率ごとに区分しなければなりません。標準税率10%と軽減税率8%に分けて、それぞれの税率を記載しましょう。消費税額に1円未満の端数が生じた場合、税率ごとに1回の端数処理が必要です。表記は税抜・税込のどちらで記載しても問題ありません。ただし、請求書内では、記載のルールを統一しましょう。
適格請求書発行事業者登録番号を確認する方法
適格請求書発行事業者登録番号は、法人と個人で確認する方法が異なります。ここでは、確認する方法を解説します。
法人の場合は「法人番号公表サイト」で確認する
法人番号公表サイトとは、法人番号の指定を受けた法人等の3つの情報を確認できます。
- 商号または名称
- 本店または主たる事務所の所在地
- 法人番号
サイト内で番号を入力すると、上記3つを検索できます。事業者の氏名・名称や登録年月日、所在地なども検索できます。ダウンロード機能やWeb-API機能を活用して、データを取得することも可能です。一般的に、取引先の適格請求書や登録番号を知っている場合、確認用として活用されています。
個人事業主は「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認する
適格請求書発行事業者公表サイトでは、取引先が個人事業主の場合に登録番号を調べられます。検索方法は、以下の2つです。
- 登録番号を入力する
- 「公表情報ダウンロード」から確認する
13桁の登録番号を入力すると、事業者の名称や登録年月日、所在地などを確認できます。登録番号がわからない場合は、データのダウンロード機能を活用しましょう。「法人」「人格のない社団等」「個人」ごとに、最新の情報をダウンロードできます。
参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁
クラウド型サービス・システムで効率化と法令対応が可能

クラウド型サービス・システムを活用すると、請求書業務を効率化できます。オンライン上でどこからでも利用でき、毎月発生する請求書管理の負担を軽減できます。電子帳簿保存法の要件も満たしたサービスやシステムを使用すると、インボイス関連の業務の効率化が可能です。
また、書類の一元管理や番号の自動処理など、書類の発行に役立つ機能も活用でき、ヒューマンエラーの削減にもつながるため、サービスやシステムの導入をおすすめします。
ANDPADなら建設業に特化した請求管理が可能
ANDPAD請求管理とは、建設業特有の要件を満たした請求管理システムです。請求書の回収や工事ごとの振り分け、出来高査定、相殺、承認など、さまざまな要件に対応しています。電子帳簿保存法にも対応しており、請求管理の業務全般を大幅に効率化できます。
また、紙の請求書の保管スペースが不要になり、請求書データの検索も可能です。ANDPADのサポート体制も活用できるので、導入前後どちらも安心して利用できます。
まとめ
請求書番号は、個別の番号を割り振って書類を管理するものです。同じ取引の見積書・納品書との紐付けや取引先とのスムーズなやり取りなど、さまざまなメリットがあります。ただし、インボイス制度にも対応する必要があるため、請求書の管理サービスやシステムの活用がおすすめです。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスです。使いやすいUIUXを実現する開発力があり、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。年間数千を超える導入説明会を実施しており、手厚いサポートも特長です。ぜひ利用をご検討ください。