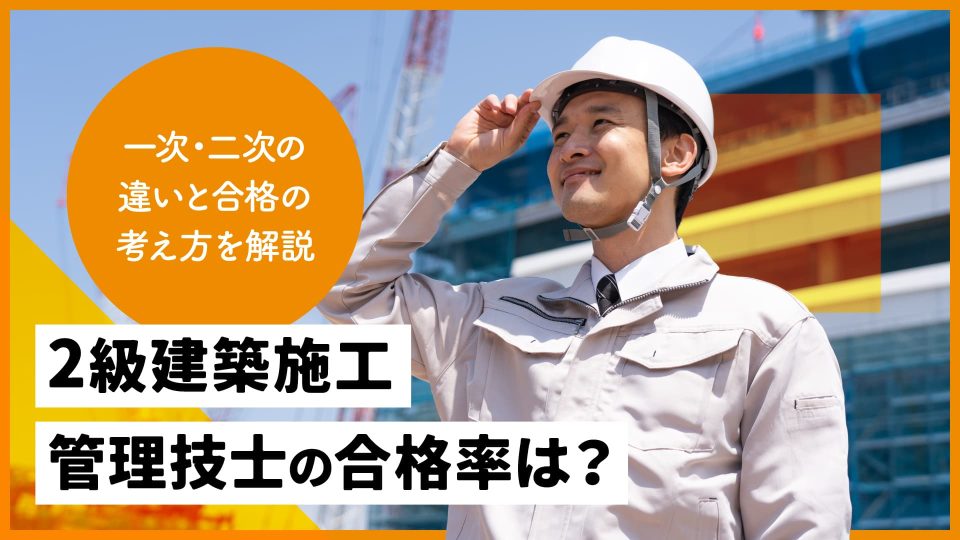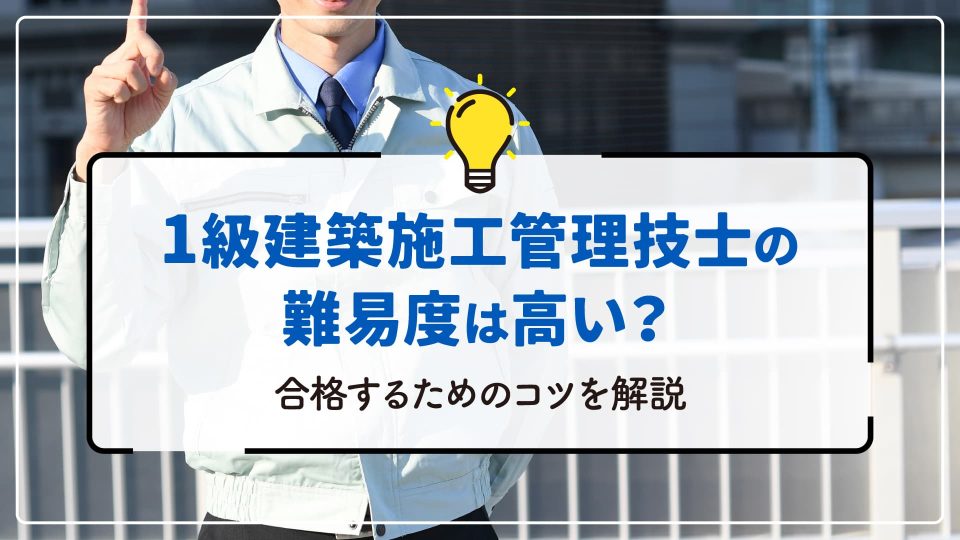レガシーシステムとは、新しい技術や仕組みの普及により、相対的に古くなったシステムを指します。業務効率の低下やコスト増加、セキュリティリスクの増大などの問題が指摘されています。この記事では、レガシーシステムが問題視される背景や2025年の崖との関係、脱却方法について解説します。DX推進に役立つ知識を提供するので、参考にしてください。

ANDPAD(アンドパッド)は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。ANDPADの「サービス概要」「導入メリット・導入事例」「サポート体制」がわかる資料3点セットをご用意しています。
レガシーシステムとは?基本知識を解説

レガシーシステムとは、新しい仕組みが登場したことで相対的に古さが目立つシステムを指します。英語の「Legacy」には「遺産」という意味があり、時代遅れになった既存のシステムを表す言葉として使われています。
レガシーシステムと呼ばれる基準は明確に定まっておらず、利用年数や形式で一律に決まるものではありません。近年ではクラウドやDXの普及により、従来のオンプレミス型システムなどが「レガシー」と位置づけられるケースが多くなっています。
レガシーシステムが問題視される背景
レガシーシステムが問題視される背景は、業務パフォーマンスの低下やコストの増加などさまざまです。以下で、詳しく解説します。
業務パフォーマンスの低下
レガシーシステムは従業員の業務効率を下げ、結果として社内全体の生産性を低下させます。改修要件に応じて部分的に手を加え続けると、コードが複雑化して「スパゲッティ化」と呼ばれる状態になり、システム全体の保守性や拡張性が著しく低下します。さらに、長期間の利用によってバグに対応できなくなったり、データ消失のリスクが高まる可能性がある点にも注意しましょう。
保守・運用コストの増加
レガシーシステムを使い続けると、保守や運用にかかるコストが年々増えていくという課題があります。長期間の改修や機能追加によって構造が複雑化し、メンテナンスが難しくなるためです。新しい機能を組み込む場合やトラブル対応には多大な時間と労力が必要で、その分費用も膨らみます。
管理の属人化
レガシーシステムは特定の技術や知識を持つ人に依存しやすく、属人化につながります。その結果、一部の担当者に負担が集中し、退職や異動で不在になるとシステムがブラックボックス化する危険があります。特に1990年代後半から2000年頃に構築されたシステムを知る人材は、2025年以降に定年を迎えるため、今後は担当者不在への対応を検討することが不可欠です。
セキュリティリスクの増加
企業にとって深刻な問題となり得るのがセキュリティリスクです。システムが古くなるほど脆弱性を突いたウイルスや攻撃が増え、防御力が低下してしまいます。サポートが終了したシステムは新たな脅威に対応できず、さらにブラックボックス化によって限られた人材しか扱えないため、人手不足や工数増加のリスクが高まります。
法改正などの変化への対応が困難
レガシーシステムは、法改正に対応できなかったり、老朽化が進んでいるリスクがあります。近年はビジネス環境の変化に加え、システム要件を更新する法改正も相次いでいます。
たとえば、電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降は電子取引データの保存が義務化されました。こうした変化に柔軟かつ迅速に対応できないことで、企業は競争上不利になる可能性が高まっています。

ANDPAD(アンドパッド)は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。ANDPADの「サービス概要」「導入メリット・導入事例」「サポート体制」がわかる資料3点セットをご用意しています。
2025年の崖とレガシーシステム刷新の必要性

経済産業省は、2018年9月に2025年の崖について警告を発しました。以下で、2025年の崖の基本情報と、レガシーシステムとの関係について解説します。
2025年の崖とは
2025年の崖は、レガシーシステムのブラックボックス化や現場の対応力低下によって既存システムの刷新が進まない状況を意味します。2025年前後には、「固定電話網(PSTN)の終了」「SAP ERPの保守サポート終了」「IT人材不足の深刻化」なども重なるため、DXが遅れると、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が発生する可能性があります。
2025年の崖とレガシーシステムの関係
2025年の崖を避けてDXを進めるには、レガシーシステムの刷新が不可欠です。古い技術を使うレガシーシステムは、最新のデジタル技術や規格と互換性がなく、新しく取得したデータと連携できないためです。
データは「21世紀の石油」とも呼ばれ、ビジネスをはじめあらゆる分野で重要性が高まっています。経営資源としてデータを十分に活用できなければ、DXの取り組みも十分な成果を上げられません。
レガシーシステムからの脱却方法

レガシーシステムを脱却し、最新のデジタル技術を活用できる環境に移行する方法として、「マイグレーション」と「モダナイゼーション」があります。それぞれについて詳しく解説します。
マイグレーション
マイグレーションとは、既存のハードウェアやソフトウェア、データなどのIT資産を新しい環境に移行することを指します。具体的には、アプリケーションやストレージ、データベース、BPM(ビジネスプロセス管理)などを新環境へ移す作業が含まれます。以下で、それぞれについて解説します。
1. アプリケーションの移行
アプリケーションの移行とは、既存のアプリケーションと同じ機能を持つ新しいアプリケーションに切り替えることを指します。主な方法は、以下の3つです。
- ストレートコンバージョン:現行のプログラムを新しい環境でそのまま再コンパイルする方法
- リライト:新しい環境に合わせて言語やソフトウェアを書き換える方法
- スクラッチ開発:一から新しいアプリケーションを開発する方法
2. ストレージの移行
ストレージの移行とは、データが保存されている記憶装置を新しい環境に移すことです。オンプレミス環境では、3〜5年ごとに行っている担当者も多いですが、アプリケーションやソフトウェアの移行と同時に行う場合は大規模な作業となります。スケジュールや容量、接続性などに注意する必要があります。
3. データベースの移行
データベースの移行はアプリケーション移行に伴って行われます。具体的にはデータベースソフト自体の移行や、アプリケーション内のデータの移行です。既存アプリケーションのデータ形式を新環境に合わせて変換するケースもあります。
4. BPM(ビジネスプロセス管理)の移行
BPMはBusiness Process Managementの略で、業務プロセスを評価・分析し、効率化を進めるための具体的な方法を検討・実行することを意味します。買収や合併、新市場への参入、組織変更などで業務プロセスが変わる際に移行が行われます。
BPMの移行では、社内に蓄積されたデータやデータベースも一緒に移行する必要があり、アプリケーションやストレージの移行とあわせて実施されることが一般的です。
モダナイゼーション
モダナイゼーションとは、既存のIT資産を活かしながら、古いソフトウェアやハードウェアを新しい製品や設計に置き換えて現代化する手法です。主なメリットは、現行機能を維持しつつ老朽化したシステムを最適化できることです。代表的な手法として、「リプレイス」「リライト」「リホスト」が挙げられます。それぞれについて詳しく解説します。
1. リプレイス
リプレイスは、既存のシステムやソフトウェアを新しいパッケージに入れ替える方法です。業務プロセスを見直すことで効率化が図れます。一方で、大規模な変更になるためコストや現場の反発が生じやすい点がデメリットです。
2. リライト
リライトは、現行のプログラムを新しい環境に合わせて書き換える手法です。セキュリティや処理速度の改善を目的に、コード変換ツールなどを使って既存システムのプログラム言語を新しいものに置き換えます。なお、機能や仕様は基本的に変更しない点が特徴です。
3. リホスト
リホストは、サーバやOS、ミドルウェアを新しい環境に構築し、既存のアプリケーションやデータをそのまま移行する方法です。業務効率化の効果は限定的ですが、移行作業は比較的スピーディーに行えます。
まとめ
レガシーシステムとは、最新の技術に比べて旧式とされるシステムのことを指します。業務効率の低下やコスト増加、法改正への対応困難など、企業に多くの課題をもたらします。これらを回避し、DXを進めるには、マイグレーションやモダナイゼーションによるシステム刷新が不可欠です。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、建設業界でトップシェアを誇るサービスです。さまざまな業種の企業やユーザーに利用されており、直感的で使いやすいUI・UXが特長です。年間数千件の導入説明会を実施しており、手厚いサポート体制も整っています。ぜひ導入をご検討ください。