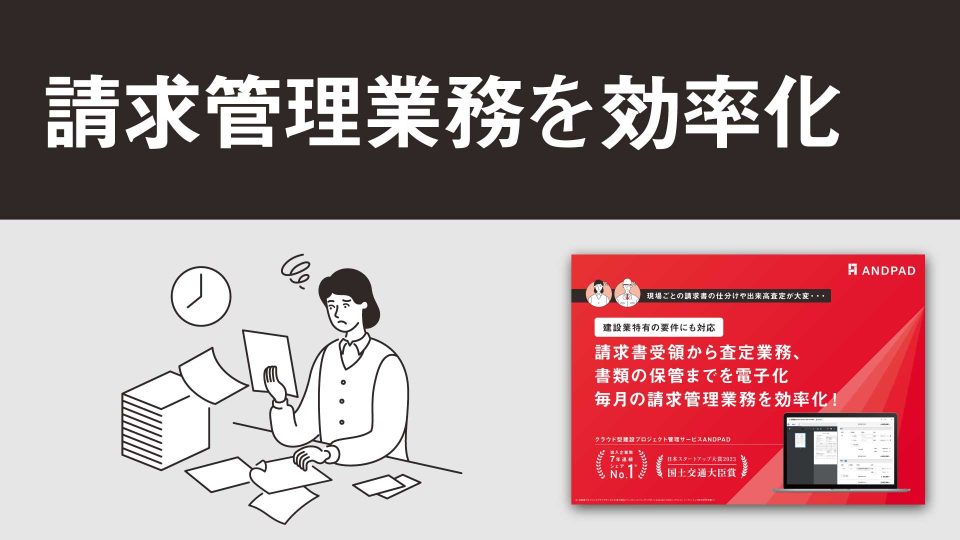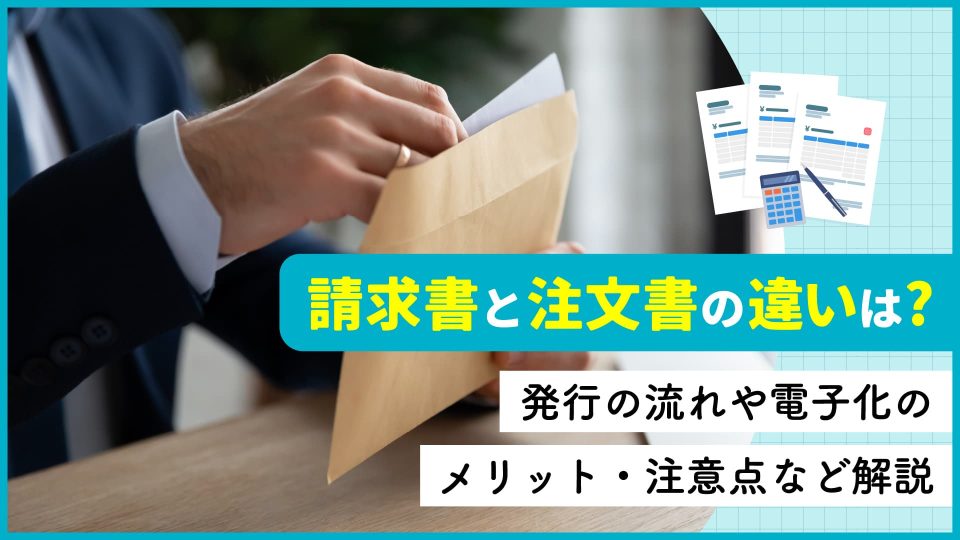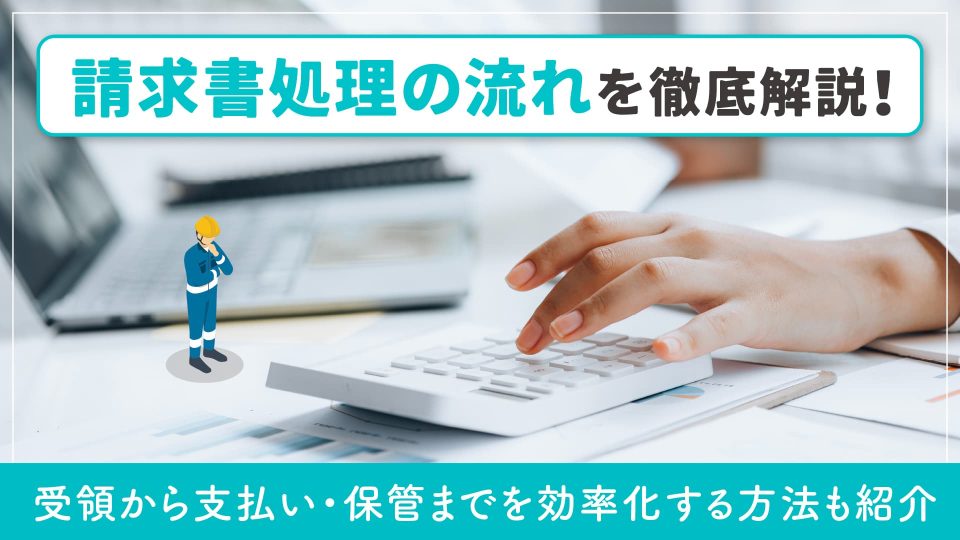電子帳簿保存法では、請求書を保存する際の要件が定められています。この記事では、電子帳簿保存法の解説から請求書の保存方法、保存の要件、電子帳簿保存法のメリット、注意点などを解説します。自社で請求書を保存する際に、どのような点に注意すべきか知りたい人は参考にしてください。
電子帳簿保存法とは
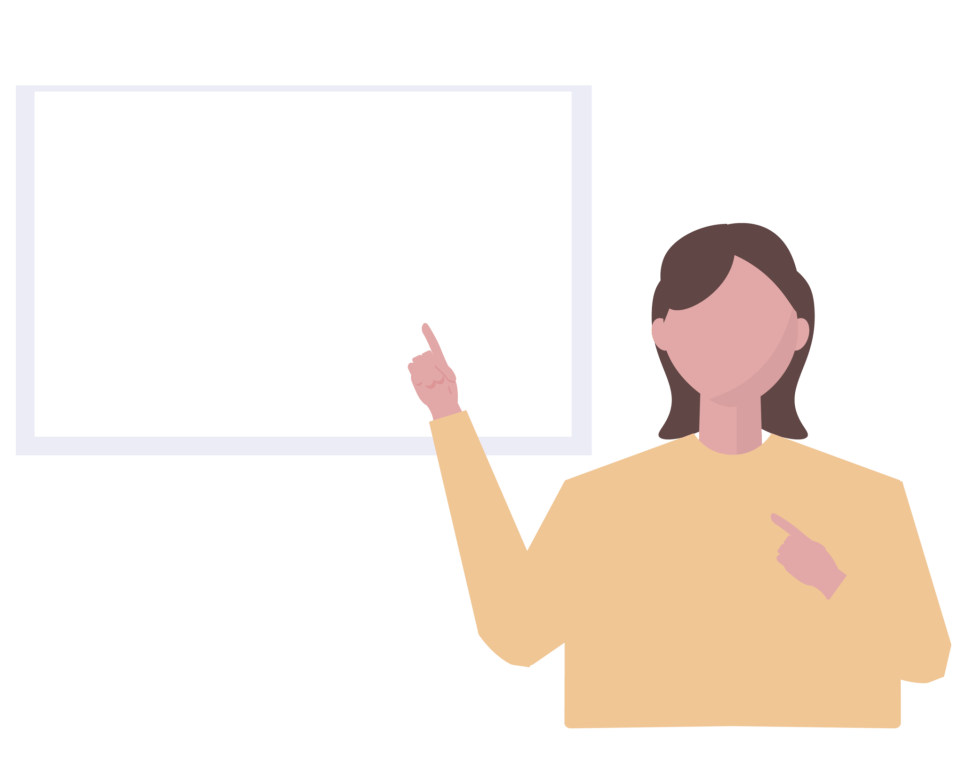
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿書類を一定の要件のもと、電子データとして保存することを認めた法律です。1998年7月に施行されました。従来は紙で扱っていた請求書や領収書などを電子データとして保存できるようになり、文書管理の効率が上がるとともに共有や検索が簡単になっています。
電子帳簿保存法は数回の改正が実施されており、近年では2022年の改正が話題になりました。この改正により、電子取引の書類は紙に印刷するのではなく、電子データのままで保存することが義務付けられています。
自社が発行した請求書の控えの保存方法
商品・サービスの売手側が請求書を発行した場合、控えも保存しなければなりません。適格請求書(インボイス)発行事業者であれば、買手側から求められると適格請求書(インボイス)を発行する義務があり、控えも作成し保存しなければなりません。詳細を以下で解説します。
電子データの請求書の控えの保存方法
電子データで発行した請求書の控えは、電子データのまま保存しなければなりません。電子取引の要件に従わず、電子データをプリントアウトして保存することは認められていません。ただし、電子データとして保存したうえで、自社内での確認用にプリントアウトして保存することは可能です。
また、適格請求書(インボイス)を電子データで発行した際は、インボイス制度の要件に従い保存しなければなりません。
紙の請求書の控えの保存方法
紙の請求書を発行した場合、控えは紙の原本のまま保存すれば問題ありません。また、請求書をコピー機やスマートフォンでスキャンした後に電子データとして保存する方法もあります。どちらの方法で保存するかは任意での選択が可能です。
紙の請求書をスキャンしてデータ保存した場合、紙の請求書は破棄しても構いません。ただし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たさなければいけません。
自社が取引先から受領した請求書の保存方法
自社が取引先から受領した請求書は、定められた方法で保存しなければなりません。請求書を受領した場合も、自社で発行した場合と同様に2つの方法があります。以下で詳細を解説します。
電子データの請求書の方法
従来は電子データで受け取った請求書は、電子データから紙に出力しての保管も可能でした。しかし、2024年1月以降は電子データを紙に出力して保存すること不可となり、要件に従って電子データのまま保存しなければなりません。原則としてすべての事業者が対象となっています。
参考:国税庁
電子データで受け取った請求書を社内確認用にプリントアウトしたい場合は、電子取引のデータ保存の要件に従ってデータも保存しておく必要があります。
紙の請求書の保存方法
取引先から紙で受け取った請求書は、2つの方法で保存が可能です。受け取った紙の状態のまま保存する方法と、コピー機やスマートフォンでスキャンした後に電子データとして保存する方法です。紙で受領した請求書は、会計処理後ファイリングして保存すれば要件を満たします。
スキャンして電子データとして保存し、紙の原本を破棄する場合は、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件を満たさなければなりません。
電子帳簿保存法における請求書データの保存の要件

電子帳簿保存法において保存要件は3つの区分があり、請求書の保存に関する部分は「電子データ保存方式」と「スキャナ保存方式」の2つです。それぞれがどのようなものか解説します。
電子データ保存方式
電子データ保存方式とは、PDF形式をはじめ電子データとして発行される請求書の保管方法です。電子データをメールで送信した場合は「電子取引」となり、発行側も受領側も電子データのまま保存しなければなりません。電子取引のデータ保存は「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たす必要があります。
真実性の確保とは、データの改ざんがないと証明するものです。タイムスタンプや記録が残るシステムを利用して、授受や保存をします。可視性の確保とは、保存したデータをいつでも閲覧できる状態にすることです。ディスプレイやプリンターを備え付けたり検索機能を付けたりします。
スキャナ保存方式
スキャナ保存方式とは、保存要件を満たしたうえで、紙で発行した書類をスキャンし電子データで保存する保管方法です。保存要件は書類の種類ごとに異なります。請求書・領収書をはじめとする重要書類は一般書類よりも要件が厳しく、カラー画像での保存、保存期限を守らねばなりません。なお、電子データ保存方式は義務ですが、スキャナ保存方式は任意です。
電子帳簿保存法対応のメリット
電子帳簿保存法に対応することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、おもな4つを解説します。
経理の業務効率化
多くの企業は帳簿書類を年度ごとに分けて保管しており、その中から目当ての書類を1枚ごと探すには手間と時間がかかります。帳簿書類を電子データで保存すると、検索機能を活用できます。検索機能を活用すれば、目当ての書類を容易に探せます。
書類探しの手間を省けると業務効率が上がり、生産性向上につながるため売上や業績アップも見込めます。また、紙で管理するとオフィス内でなければ帳簿を閲覧できませんが、電子化しクラウド上に保存すると場所や時間に関係なく閲覧できます。
コストの削減
書類を紙ベースで作成すると、紙代に加えて印刷代、郵送代などの費用がかかります。特に、2024年10月に郵便料金が値上げされたため郵送代の負担が大きくなりました。そのため、紙で請求書を発行する場合、発行側の負担が増えてしまいます。電子帳簿保存法に則り請求書を電子データで作成すると、この費用を削減できます。
参考情報:2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。 – 日本郵便
オフィスの省スペース化
法人は取引記録を帳簿につけ、当該事業年度の確定申告書の提出期限翌日から7年間保存する義務があります。国税帳簿書類は多くの場合、ファイルやバインダーに綴じて保管します。7年間保管すると、オフィスの一角を書類が占有することになります。帳簿書類を電子データ化すると紙で保管する必要がなく、オフィスの省スペース化につながります。
参考:国税庁 問17
セキュリティの強化
紙ベースの帳簿書類は、一般的にオフィス内に保管します。オフィスが無人になる際は、盗難防止のためオフィスとキャビネットを両方施錠します。ただし、鍵が壊されて帳簿書類が盗まれたり、引っ越しの際に書類を紛失したりする危険性もあるでしょう。帳簿書類を電子データで保存すると、セキュリティを強化できます。
電子帳簿保存法対応における発行側の注意点
電子帳簿保存法の対応において、発行側はどのような部分に注意すればよいでしょうか。2つの点を解説します。
編集不可の形式で発行する
請求書は改ざん防止のため、編集できない形式で発行しましょう。WordやExcelなど編集可能な形式で送付すると、送付先で編集され、データが改ざんされる可能性があります。電子帳簿保存法ではPDF文書の保管が認められています。電子帳簿保存法の要件である「真実性」を担保するためにもPDFや画像データなど編集しにくい形式に変換して送るようにしましょう。
電子印鑑を使用する
電子データで作成した請求書は押印が不要です。ただし、押印があると偽装防止につながるため、習慣として請求書に押印する企業も多くあります。押印する際は、電子データに押印できる電子印鑑の使用がおすすめです。タイムスタンプでも、押印同様に偽造を防げます。
法令上、タイムスタンプの付与は義務化されていませんが、偽造リスクの軽減や電子帳簿保存法に対応するためにも、タイムスタンプを導入するとよいでしょう。
電子帳簿保存法対応可のシステム導入を検討しよう
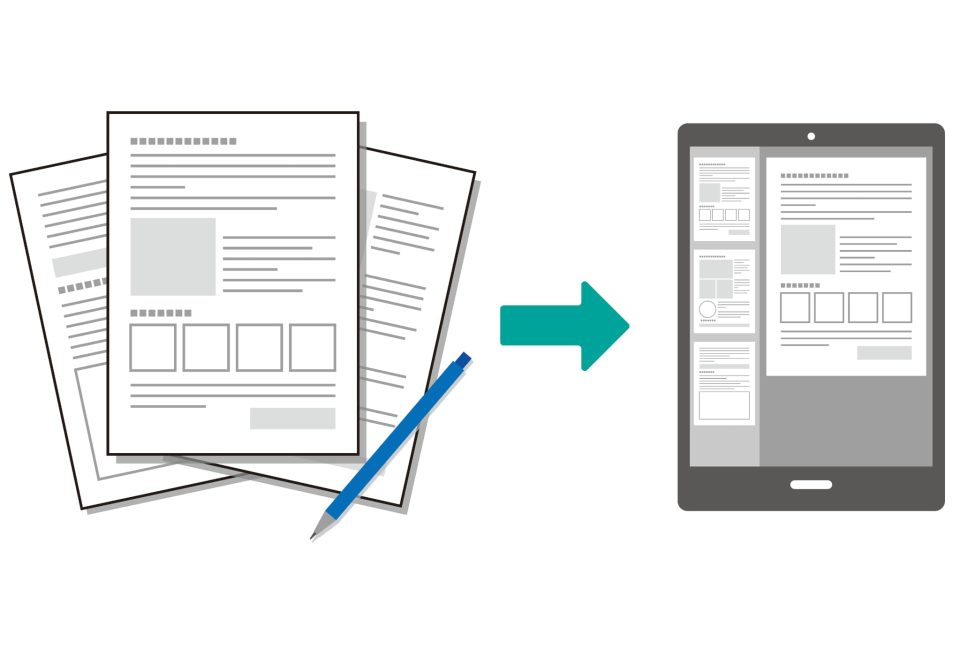
紙で受け取った書類に加え、電子データで受け取った書類も管理できるシステムの導入を検討しましょう。電子帳簿保存法に対応したシステムであれば、担当者間での共有や確認が不要になり、業務の効率化が進められます。
従来は経理処理や電子取引の保存にかかっていた時間を削減し、業務を効率化したい場合は、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討するとよいでしょう。
電子帳簿保存法にも対応した「ANDPAD請求管理」で法対応と業務効率化を両立
ANDPAD請求管理は、電子帳簿保存法に対応しています。電子データ保存方式における「真実性の確保」や「可視性の確保」、スキャナ保存方式の要件を満たしています。請求書の回収や振り分け、請求書データの出力など、業務に役立つ機能が多く搭載されていますので、導入を検討してはいかがでしょうか。
まとめ
電子帳簿保存法において、電子データは電子データのまま、紙のものは紙のままもしくはスキャンして電子データとして保存する方法があります。スキャンする場合は「スキャナ保存」の要件を満たせるよう注意しましょう。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、使いやすいUI・UXを実現する開発力から、数多くの企業・ユーザーに利用されています。年間数千を超える導入説明会を実施しており、手厚いサポートも特長です。請求書の作成が容易になり、他の書類も一元管理できますので、ぜひANDPADの導入をご検討ください。