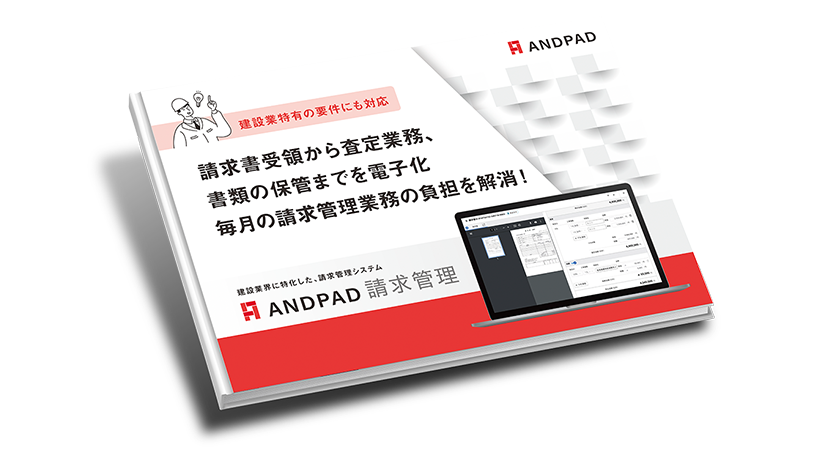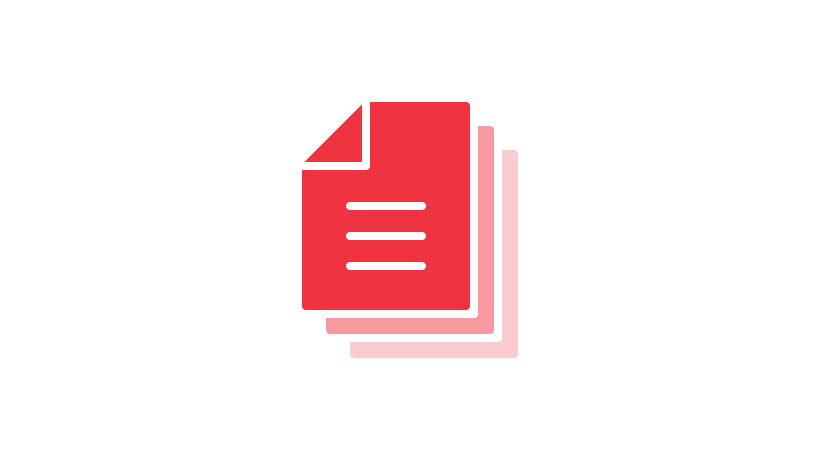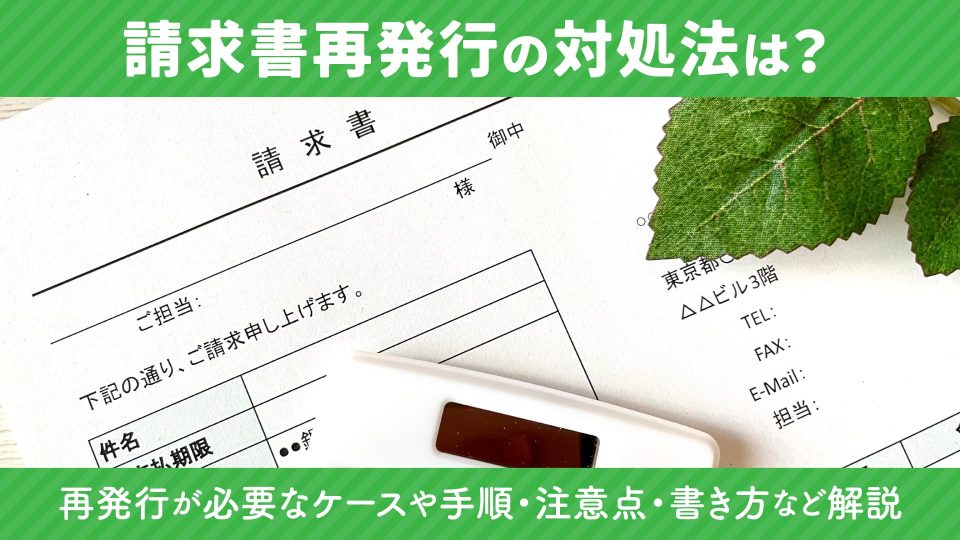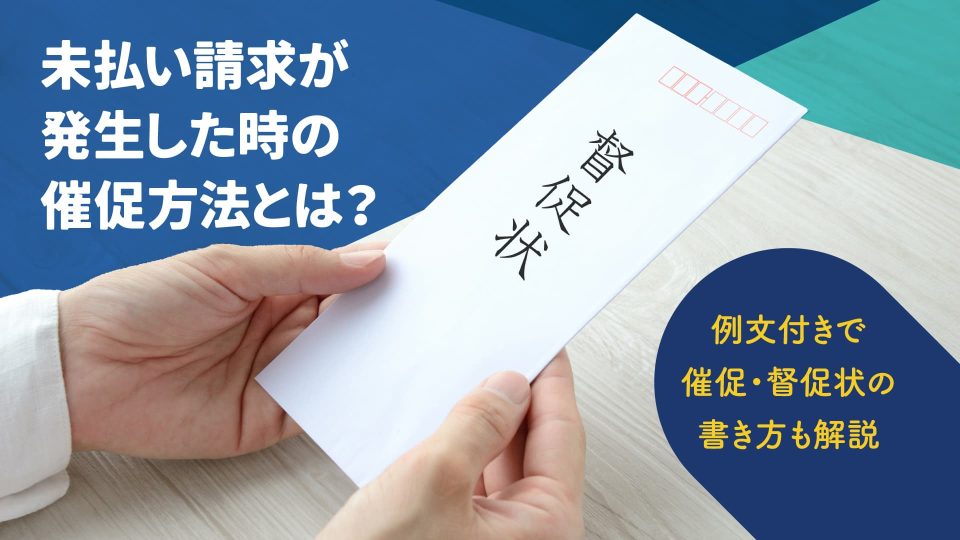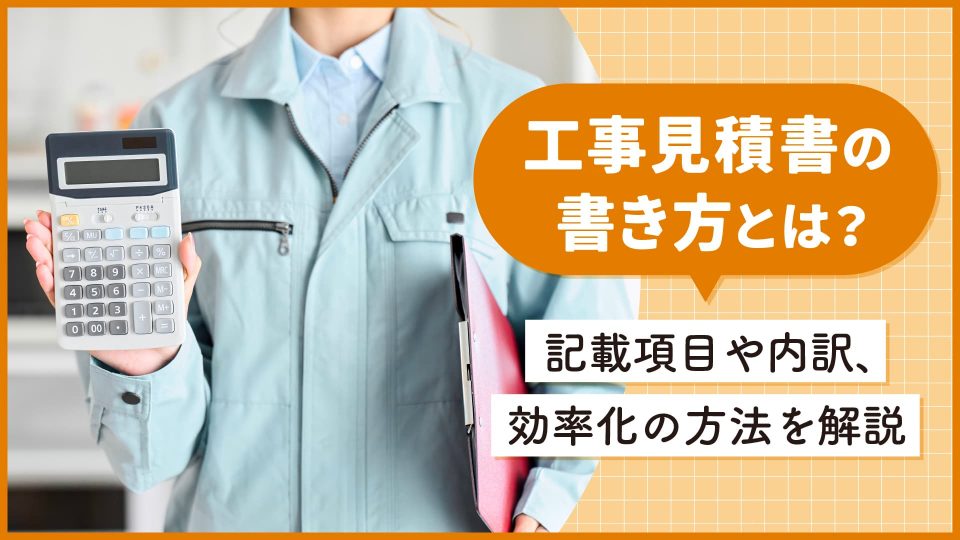請求書を紛失したり、内容にミスがあったりする場合は、再発行で対処します。元の書類との整合性や取引先との連絡など、さまざまな注意点があるため、事前に確認しましょう。この記事では、請求書再発行の対処法、手順や注意点を解説します。効率化の方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
請求書の再発行はできる?

取引先の事情や内容の変更など、必要に応じて請求書の再発行は可能です。請求書は取引の事実を証明するためのもので、取引内容や金額、振込先などを確認できるようにしなければなりません。また、発行元も受領先も一定期間の保存が義務付けられています。
請求書の再発行が必要なケース
請求書は紛失や内容の変更が必要になった場合には、再発行をしなければなりません。ここでは、再発行が必要なケースを解説します。
取引先が請求書を紛失した場合
取引先が請求書を紛失した場合は、再発行が必要です。書類を破損した場合も同様に再発行で対処します。ただし、請求書の内容を変更した場合、二重請求を防ぐことが重要です。請求書番号や取引先の企業名などを確認し、同一の請求書が存在しないように気を付けなければなりません。
支払い方法の変更による対応が必要になった場合
支払い方法を変更する場合は、請求書の内容を修正して再発行します。たとえば、代金を一括払いから分割払いにしたり、支払いの期日を変更したりするケースです。ただし、変更後に未払いや納期の遅れなどが発生すると、契約違反やトラブルに発展する可能性があります。事前に念書や覚書を取ったうえで、内容を変更しましょう。
記載内容の誤りを指摘され、再発行を求められた場合
自社のミスで記載内容の誤りを指摘された場合も、再発行をする必要があります。取引先に記載ミスがあった旨を伝えたうえで、該当部分を変更しましょう。取引先が変更前の情報をもとに入金する可能性があるため、早急に対応しなければなりません。再発行をしたら、記載内容を間違えた原因を確認し、同じミスを起こさないように対策を講じることが重要です。
請求書を再発行する際の手順
請求書を再発行する際は、内容の確認後、訂正と送付をします。ここでは、再発行の手順を解説します。
契約内容を確認する
はじめに契約内容の確認をします。請求書に記載されている日付や企業名、氏名、案件の内容、金額などの項目を確認しましょう。実際の取引の内容と合致しているかを確認し、再発行の必要があるかどうかを精査します。請求書を修正した場合には、指摘があった箇所の変更だけではなく、他の箇所も確認することが重要です。
内容を訂正して再発行・送付する
変更点を確認したら、該当の箇所を訂正して再発行をします。紛失の場合は、請求書の発行日や契約内容など、該当の書類を特定できる情報を伝えることが必要です。記載内容に誤りがあった場合は、請求書の誤りを特定し、双方で内容を確認したうえで再発行します。
請求書を再発行する際の注意点・書き方

請求書を再発行する際は、記載内容の変更や取引先の対応などに注意が必要です。ここでは、再発行の注意点を解説します。
請求書の日付と前回の発行日を合わせる
再発行する請求書の日付は、訂正前と同じでなければなりません。異なる日付にすると、別の請求書として処理される可能性があるため、注意が必要です。再発行した日付を記載する場合は、備考欄に「再発行日」と明記するとよいでしょう。これにより請求書の管理や検索などがしやすくなります。
再発行である旨を明記する
元の請求書と区別できるように、目立つ箇所に「再発行」と明記しましょう。赤文字で記載したり、文字の大きさを変えたりすると、書類の混同を防げるためおすすめです。また、再発行の理由や変更された内容などは、備考欄に記載しておくと、今後の確認をする際に役立ちます。
請求書番号を変更する
請求書を再発行する際は、請求書番号の変更が必要です。たとえば、元の番号が「○○○○○○」の場合、「○○○○○○-1」のように枝番を付けます。元の書類との関連性や再発行であることが一目で確認できて、管理がしやすくなります。経理作業における混乱を防止するために、枝番で管理しましょう。
支払期日が過ぎていた場合は内容を確認する
支払期日が過ぎていた場合、契約内容の確認をしましょう。再発行の請求が遅延損害金を発生させていたり、契約違反に該当したりする場合、法的な問題に発展するケースがあります。双方の企業に損失を与える可能性があるため、契約の条項を確認したうえで再発行をして、適切に対処することが必要です。
ミスを訂正する際はお詫びの連絡をする
請求書のミスを訂正する際は、お詫びの連絡をしましょう。再発行した請求書には「古い請求書の破棄をお願いいたします」という文言を添えて送付します。同じミスが起きないようにする対策について記載することも必要です。
手数料に関する合意を得る
請求書の再発行は契約内容によっては手数料がかかるケースがあり、取引先との関係によって契約が異なります。請求書の再発行に際して、再発行手数料や振込手数料が発生するケースもあるため、あらかじめ取引先と合意しておきましょう。
電子帳簿保存法に則って保存する
再発行された請求書のデータのやり取りをする際は、電子帳簿保存法に則って保存しなければなりません。同法律において「取引が確定したもの」が保存対象となるため、訂正後の請求書を保存する必要があります。電子データとして受領した場合は、紙保存は認められないため、注意が必要です。
適格請求書は再発行できる?
適格請求書は再発行できます。再発行は、売り手である適格請求書発行事業者が対応します。「修正インボイス」として再発行が認められており、その場合の名称は「修正版」や「再発行」などに変更しなければなりません。
インボイス制度における記載項目
インボイス制度における適格請求書の記載項目は、以下のとおりです。
- 請求書の宛名:企業名や氏名の正式名称
- 請求書を発行する側の情報:発行する企業名や氏名、住所、連絡先などの正式名称
- 請求書の発行日:初回発行の請求書に記載した発行日
- 請求書番号:初回の請求書番号に枝番を追加
- 取引内容:商品やサービスの名称、数量など
- 取引金額:取引した商品の単価や小計、消費税、源泉徴収など
- 支払期日:初回発行時と同じ日付で、支払期日を過ぎた場合は別紙で他の日時を指定
- 振込先の情報:振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義
請求書再発行は請求書作成ソフトの導入がおすすめ

請求書の再発行は、専用のソフトを使用すると作業を効率化できます。ここでは、その特徴について解説します。
二重請求をはじめとしたトラブルを防止できる
請求書作成ソフトを使用すると、二重請求をはじめとした、請求に関するトラブル防止につながります。システムを活用することで、手入力・手計算などによるヒューマンエラーを防止できるためです。また、請求書の電子化によって、紛失リスクの軽減も期待できます。再発行のトラブル以外にも、さまざまなリスクを防止できます。
自動化によって手間を削減できる
請求書の再発行業務は、専用のソフトで自動化できます。請求書の作成から発行、再発行までの作業を効率化し、業務負担の軽減が可能です。また、業務フローの見直し・改善にもつながるため、作業全体を効率化できます。担当者の確認作業の負荷を減らすためにも、ソフトの導入はおすすめです。
法改正に対応しやすくなる
クラウド型の請求書作成ソフトを活用すると、自動アップデートにより法改正に対応できます。最新の法規制のもと、請求書作成の業務ができて、インボイス制度の導入や改正電子帳簿保存法などにも対応が可能です。専門的な知識がなくても、法律違反のリスクを防げます。
建設業特化のクラウド型請求管理システムなら「ANDPAD請求管理」
「ANDPAD請求管理」は、建築・建設業界の業務に特化した、クラウド型請求管理システムです。受領から査定業務、書類の保管までを電子化に対応しており、さまざまな業務の負担を軽減できます。
また、請求書の自動振り分けや、請求書への注文番号や工種の紐付け、電子帳簿保存法に対応したデータ管理なども可能です。毎月の請求管理業務の負担を軽減する際に、有効に活用できます。
まとめ
取引の事実を証明する請求書は、再発行ができます。ただし、二重請求などのトラブルにつながる可能性があるため、内容の確認や誤入力などに注意しましょう。請求書作成ソフトを活用すると、ミスを減らして業務を効率化できるのでおすすめです。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスです。業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しており、使いやすいUI・UXを実現する開発力が特長です。年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートも整っています。請求書の再発行をする際に、ぜひご活用ください。