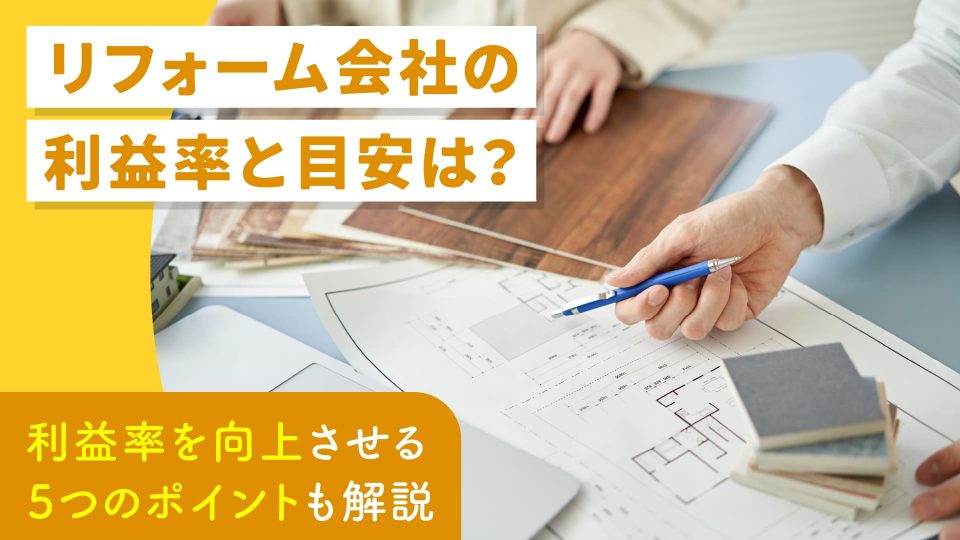BCP対策とは、企業の活動を継続させるための事業計画です。事前に対策を決めておくことで、災害をはじめとした事業停止の被害を最小限に抑えられます。この記事では、BCP対策の概要や必要とされる背景、メリット、デメリットなどを解説します。策定手順も解説しますので、参考にしてください。

ANDPAD(アンドパッド)は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。ANDPADの「サービス概要」「導入メリット・導入事例」「サポート体制」がわかる資料3点セットをご用意しています。
BCP対策とは

BCP(Business Continuity Plan)対策とは、事業継続計画のことです。緊急事態が発生した場合を想定して、事業の方針や体制、手順などを決めます。たとえば、事故や不祥事といった人的災害、自然災害、テロなどを想定し、被害を最小限に抑えるために準備を行います。
BCP対策は、事業の継続と早期復旧を実現するために欠かせない取り組みです。緊急時だけでなく、BCP訓練という事前訓練の対策も含まれます。
BCPと防災計画との違い
BCPと防災計画はどちらも非常時を想定した準備ですが、目的と対象が異なります。BCPは事業を継続するために実施されるもので、サイバー攻撃や感染症など不測の事態から事業や顧客を守ります。対して、防災計画は命や資産を守ることが目的です。地震や水害などの自然災害から、従業員や設備などを守るために実施します。
BCPとBCMの違い
BCPは事業継続計画であり、BCMの基盤となる取り組みの1つです。「BCM(Business Continuity Management)」は、事業継続の管理・維持を指します。BCP対策の策定を含め、計画から実行、管理を含む取り組みまで含まれます。BCMは、緊急時に機能するようBCPを社内に浸透させることが目的です。
BCP対策が必要とされる背景
BCP対策が必要とされる背景には、企業を取り巻くリスクの多様化・複雑化があります。昨今、地震や新型コロナウイルスの蔓延、自然災害の被害拡大など、企業に甚大な被害を与えるリスクが増えています。
事業を継続するには、緊急事態に備えて組織運営を維持できる対策が必要です。ステークホルダーの要望や法規制なども求められており、さまざまなリスクに備えるためにBCP対策が重要視されています。
建設業におけるBCP対策の重要性
建設業においても、BCP対策は重要な役割をもちます。BCP対策を実施することで、緊急事態が起きた場合でも事業の継続や早期復旧ができ、被害を最小限に抑えられます。建設業は社会的な役割が大きい業種であり、災害やパンデミックなどのリスクに最大限備えなければなりません。社会全体の早期復興のためにも、建設業にとってのBCP対策は重要な取り組みといえます。
BCP対策を実施するメリット

BCP対策は、緊急事態の対応や企業の信頼性を守るために必要です。ここでは、BCP対策を実施するメリットを解説します。
緊急事態が起きた場合でも対処できる
BCP対策を実施すると、緊急事態でも速やかに対処できます。指示する人や具体的な行動を策定しておくことで、迅速に初動の対応ができるためです。予測不能な事態に直面すると、人間は冷静さを失いやすくなるため、判断や行動を明確にする必要があります。平常時にBCP対策を策定し、緊急事態に対応できるように従業員の意識を高めることが大事です。
企業の信頼性を高められる
BCP対策により事業の継続性を確保することは、企業の信頼性につながります。日本では自然災害が多いため、緊急事態に備えることが企業としての安心感を伝える手段になります。取引先やステークホルダーだけでなく、地域社会からの信頼を高めることも可能です。緊急時に迅速な対応ができると、企業のイメージアップの効果が期待できるでしょう。
事業基盤を固められる
BCP対策により、事業継続のリスクを把握でき、事業基盤を固められます。たとえば、データのクラウド化やバックアップ体制の強化をすると、被害を抑えながら事業を継続できます。緊急事態が起きると、ライフラインの停止やシステムの破損、データの紛失などのリスクが高まるため、BCP対策が有効です。
BCP対策を実施するデメリット
BCP対策は、コストがかかる点に注意が必要です。ここでは、BCP対策を実施するデメリットを解説します。
策定のコストがかかる
BCP対策の策定には、人件費や時間、手間、コンサルティングなどのコストがかかります。専門知識も必要となるため、企業によっては対応が難しい場合があります。また、BCP対策を継続し、教育の効果の維持も重要です。従業員を教育する必要もあるため、さまざまなコストがかかることを想定する必要があります。
リスク分散にコストがかかる
BCP対策には、緊急事態に備えたリスク分散のコストもかかります。たとえば、企業のデータをバックアップする際に、データセンターで管理・保存する際の費用です。別拠点を設置することで、本社の被害があった場合でも事業を継続できますが、環境を整備するための費用がかかります。
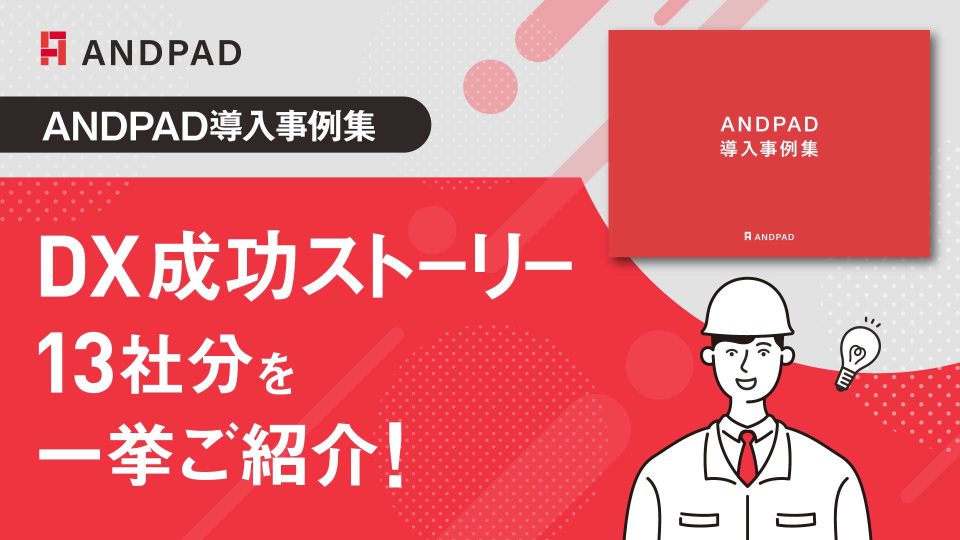
ANDPADをご検討中の方向けに、各社が抱えていた課題、DX成功に至るまでの導入事例をまとめてご紹介しています。ゼネコン、設備工事、太陽光、注文住宅、リフォームなど、幅広い業種の事例をピックアップしています。
BCP対策を策定する流れ
BCP対策には、目的の明確化やリスクの把握などが必要です。ここでは、策定する流れを解説します。
1.目的や方針を明確にする
最初にBCP対策の目的や方針を明確にしましょう。顧客やステークホルダーが自社に対して求めていること、社会的な役割などをもとに決めます。また、企業理念や経営方針の見直しをしたうえで、企業が目指すものを再確認することも大事です。BCP対策は企業全体での取り組みであるため、目的や方針を決める際に、体制の構築も進めましょう。
2.現状の課題・リスクを洗い出す
BCP対策の策定は、現状のリスクを正確に把握することが大事です。自然災害や感染症、サイバー攻撃など、自社が抱えるリスクを洗い出しましょう。現状の問題点を正確に把握することで、より効果的な対策を考えることができます。さらに具体的にリスクを定義することによって、BCP対策の精度を高められます。
3.必要な事業内容を決める
リスクを洗い出すと、事業継続において守るべき「中核事業」を特定できます。中核事業とは、企業の存続に欠かせない事業や、売上の大部分を占める事業、顧客との信頼関係に重要な事業のことです。これらの事業を選別することで、限られた時間やリソースを効率的に配分し、事業継続につなげられます。
4.リスクに優先順位をつける
BCP対策をする際は、リスクの優先順位をつけましょう。リスクが発生する頻度や深刻度合いなどを把握し、損失の被害を判断する必要があります。緊急事態には、平時と比べて人的・物理的リソースが制限されます。すべてのリスクに対応できないため、事前に重要な事業をリストアップすることが大事です。
5.具体策を検討する
BCP対策の具体策を検討する際は、想定されるリスクごとに達成できるかどうかを判断しましょう。事故や災害などを想定して、迅速かつ的確に対応方法を決めておくことが大事です。指示役や連絡係など、具体的に役割を決めるとスムーズに対処ができます。また、個別のリスクに対応できるように、段階ごとに対策を検討することも必要です。
BCP対策を策定する際の課題・注意点
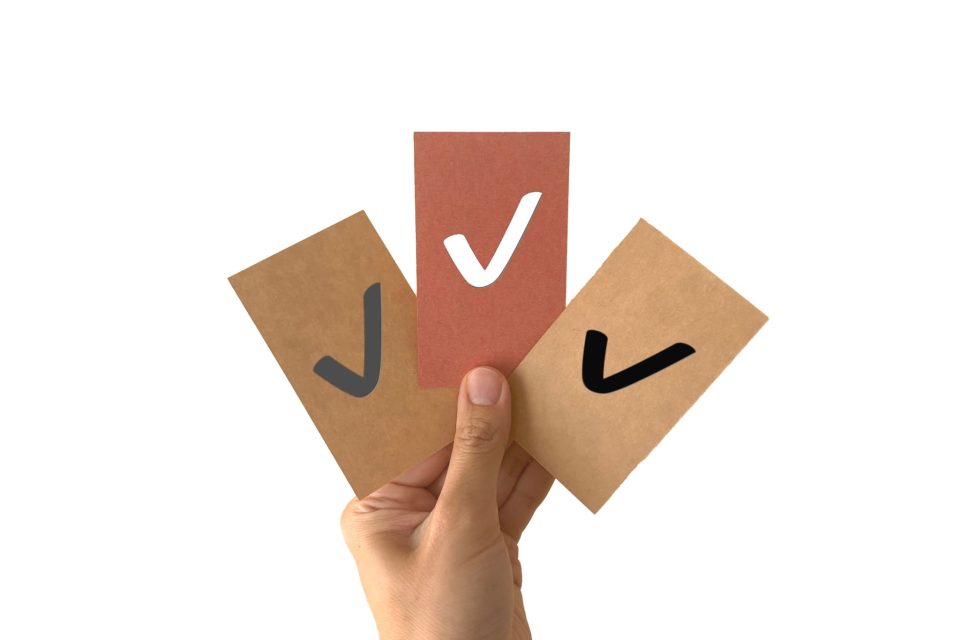
BCP対策は形骸化しないように注意しましょう。たとえば、予算や人材が足りない場合、計画の実効性がなくなる可能性があります。企業によって課題はさまざまですが、リソースや能力などを踏まえたうえで、具体的かつ実行可能な計画を立てることが必要です。
また、BCP対策は、実践的な訓練を行ったうえで課題の改善も求められます。業務内容の変化に伴い、定期的に内容の更新もしなければならないため、継続的に見直しができる体制を構築する必要があります。
BCP対策の効率化にはツールの導入がおすすめ
BCP対策の効率化には、情報共有や安否確認などができるツールが有効です。最新の更新内容を効率よく共有できるため、常に変化する事業環境やリスク要因にも柔軟に対応できます。
また、多くのツールにはデータを自動保存・更新する機能があり、データのバックアップや復旧などがスムーズに行えます。クラウド型のツールを活用すると、設備や機器が破損した場合でもシステムの継続利用ができ、業務中断のリスクを抑えられます。
建設現場のリスク管理を支えるクラウド型建設プロジェクトサービス「ANDPAD」
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」は、BCP対応の運用面を支える情報共有・連絡手段として有効活用できる機能が備わっています。例えば、チャット機能を使うことで、必要な情報をメンバーへ一斉に共有し、情報共有の時間を削減できます。
また、案件ごとにフォルダを作成して情報を集約できるため、必要なデータに容易にアクセスできます。タイムリーな進捗報告ができ、迅速なBCP対策の実行を支援します。業務管理や品質向上にも活用できるため、建設業の現場担当者や経営者におすすめです。

ANDPADには関係者全員とのコミュニケーションを効率化する「チャット機能」があります。ご利用企業様における具体的な活用方法・導入効果をまとめた事例集をご紹介しています。
まとめ
BCP対策とは、事業継続計画のことです。事故・不祥事の人的災害などを想定し、迅速に対処するために具体策を検討します。緊急時の被害を最小限に抑えるには、BCP対策を効率化できるツールの導入がおすすめです。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、シェアNo.1サービスです。BCP運用の効率化に寄与する機能を多く搭載しており、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力があり、年間数千を超える導入説明会を実施するなど、手厚いサポートも特長です。ぜひ利用をご検討ください。