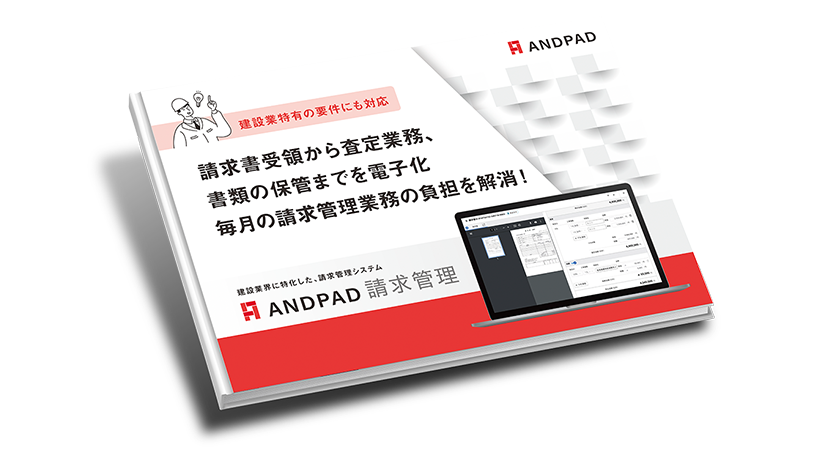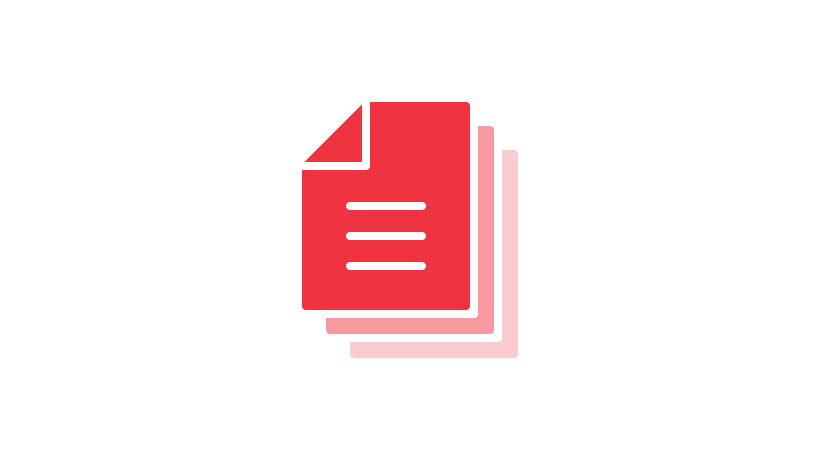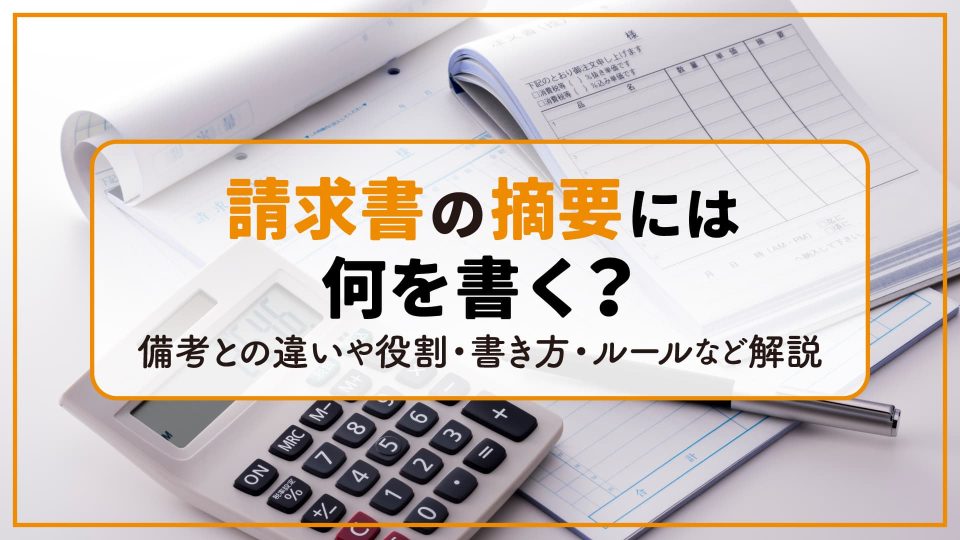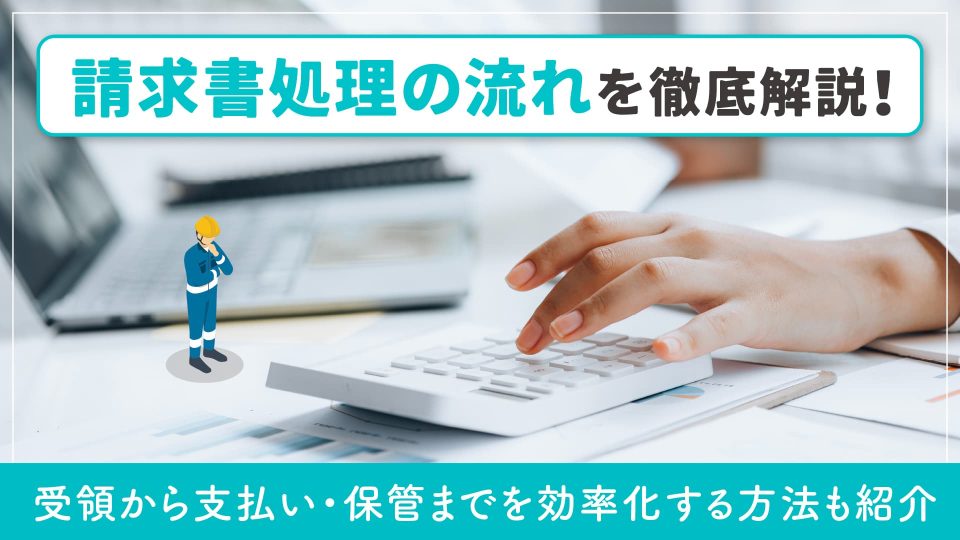請求書の摘要欄は、取引の重要なポイントを簡単にまとめるために使われます。ただし、摘要欄の記載は必須ではないため、どう書くか迷う人も少なくありません。この記事では、請求書の摘要について、請求書における摘要と備考の違い、摘要の記載ルール・注意点、具体的な書き方のポイントをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
請求書の摘要(名目・品目)とは
摘要とは「概要」や「要約」といった意味を持ち、英語では「summary」にあたります。請求書における摘要欄には、取引内容の要点が記載されるのが一般的です。請求書には商品名・数量・単価などが通常記載されますが、請求の詳細が伝わらないことがあります。摘要欄に用途や注意点を書いて、顧客がわかりやすいようにしておきましょう。
請求書における摘要と備考の違い

請求書を作成する際、「摘要」と「備考」は似ているように見えますが、それぞれの目的や使い方は異なります。摘要は請求内容の要点を簡潔に示すもので、摘要欄を見るだけで取引の概要を把握できます。
一方、備考は補足的な情報を記載する欄です。支払い条件の詳細や配送に関する案内などの記載に使われます。備考欄には重要な注意点を加えられますが、請求の中心的な内容の理解につなげる役割は持ちません。
書類別に見る摘要の役割
取引に欠かせない請求書では、金額や品目のほか、取引内容や注意点を伝える摘要欄が重要です。領収書や見積書でも同様に、取引の内容を補足し、誤解やトラブルを防ぐ役割を果たします。以下では、各書類における摘要欄の役割について解説します。
請求書
請求書に記載する基本項目は、顧客名や取引日、金額、品目などです。品目欄に書かれた商品やサービスの名称を見れば、取引の概要をある程度理解できます。そのため、請求書では摘要欄を設ける必要はあまりありません。多くの請求書では備考欄が用意されており、追加の情報がある場合は備考欄に記載するのが一般的です。
領収書
領収書における摘要は「但し書き」を指します。領収書には、相手先名・金額・取引日とあわせて但し書きを記載する必要があります。相手先名や金額だけでは何に対する支払いか判断できないため、但し書きには取引の内容を明記します。書籍代やノート代といった具体的な商品名を記載するのが一般的です。
見積書
見積書における摘要の扱いは、請求書と同じで、基本的に必要ありません。見積書には相手先名や金額、取引日とともに品目欄が設けられており、販売する商品名や提供するサービス名が記載されます。
品目欄の内容だけで取引の概要がわかるため、摘要欄を設ける必要はほとんどありません。必要な補足情報がある場合は、多くの見積書に備えられた備考欄に記入します。
摘要の記載ルール・注意点

売上・経費・消費税に関する摘要の記載ルールと注意点について解説します。わかりやすい請求書を作成するための参考にしましょう。
売上
売上を摘要欄に記載する際は、取引の全体像がわかるように以下の内容を含める必要があります。
- 取引年月日
- 売上先、取引相手
- 品名、提供したサービスの内容
- 数量
- 単価、金額
- 1日の売上合計
納品書控などで取引内容を確認できる場合は、取引先ごとの1日の売上合計をまとめて記載しても問題ありません。なお、摘要に記載する内容は帳簿の種類によって異なります。売掛帳では取引先ごとに記帳するため、摘要に相手先名を書く必要はありません。対して、仕訳帳では摘要に取引先名を記載する必要があります。
経費
経費の摘要欄に記載すべき主な情報は、以下の通りです。
- 取引内容に応じた勘定科目(福利厚生費、消耗品費、地代家賃、水道光熱費など)
- 取引年月日
- 取引の事由
- 支払先
- 金額
少額費用は、科目ごとに1日の合計額をまとめて記載可能です。摘要欄には過度に詳細な情報を書かないようにしましょう。複数人で帳簿を付ける場合は記載ルールを統一すると、一貫性が保たれ確認や分析が容易になります。
消費税
消費税に関する摘要欄には、以下の情報を記載する必要があります。
- 顧客の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
上記の情報は、取引の全体像を把握し、正しい税務処理を行うために重要です。また、摘要欄が明確であれば、顧客が税務調査を受ける際にも対応がスムーズになります。さらに、2019年10月導入の軽減税率制度により、対象品目を含む取引では、摘要欄にその旨を明確に記載する必要があります。
インボイス制度導入後の摘要
顧客が消費税の課税事業者の場合、インボイス(適格請求書)の発行が必要です。ただし、3万円未満の公共交通費など一部の取引では、顧客が特定事項を記載した帳簿を保存すれば仕入税額控除が認められます。帳簿に記載すべき事項は、以下の通りです。
- 自社(請求書発行側)の名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 自社の住所
- 特例対象である旨
上記を正しく記載することで、顧客の税務処理を支援するとともに、自社の取引記録の正確性も保てます。
摘要欄の書き方・ポイント

摘要欄は、取引内容を簡潔かつ正確に伝えるための重要な欄です。以下で、摘要欄の書き方とポイントについて詳しく解説します。
誰にでも伝わるように正確に書く
摘要欄には、取引に直接関わっていない第三者でも内容を理解できるよう、分かりやすく具体的に記載しましょう。摘要を正しく記入することで取引内容がはっきりし、顧客は請求内容を正確に理解できるため、誤解やトラブルを防げます。
また、明確な摘要は顧客の会計処理を円滑にし、税務調査が入った際にも取引の正当性を示す証拠となります。摘要欄の記入には手間がかかりますが、重要性を考慮し、空欄にすることは避けましょう。
情報過多にならないようにする
摘要欄には取引内容を明確に書くことが重要ですが、詳細すぎる必要はありません。文字数に制限がある場合もあるため、必要な情報を簡潔にまとめましょう。
軽減税率の対象となる品目を明確にする
2019年10月に始まった消費税の軽減税率制度により、2025年現在も標準税率10%と軽減税率8%が混在しています。顧客が仕入税額控除を適用するためには、必要事項が記載された証明書が求められるため、請求書の摘要欄にはどの商品やサービスが軽減税率の対象であるかを明確に記載する必要があります。
例えば、「健康食品(軽減税率8%)」のように、対象品目が一目でわかる形で記載しましょう。軽減税率対象品目が判別できないと、顧客が正確に仕入税額控除を受けられない可能性があります。
空白を作らない
摘要欄には、取引に関する情報を必ず記載することが重要です。空欄のままにすると、取引内容を後から確認しにくくなるだけでなく、税務調査時にレシートや請求書との照合に時間がかかる場合があります。取引相手の名前や内容など、必要な情報は漏れなく記入しましょう。
建設業の請求書管理を効率化するなら「ANDPAD請求管理」
建設業の請求書管理を効率化したい場合、「ANDPAD請求管理」の導入がおすすめです。ANDPAD請求管理は、請求書の受領・確認・保管をすべて電子化できる請求管理システムです。
工事別の請求書整理や回収業務、出来高の査定、相殺・承認手続きまで建設業向けの機能を備えています。電子帳簿保存法にも対応しており、毎月の請求業務を大幅に効率化できます。
まとめ
請求書の摘要欄は、取引内容の要点を簡潔に記載する欄です。品目欄の情報で取引内容はある程度把握できるため、必須ではありません。しかし、摘要欄を活用することで、売上や経費、消費税、軽減税率などの重要情報を補足でき、顧客が請求内容を正確に理解しやすくなります。
クラウド型の建設プロジェクト管理ツール「ANDPAD(アンドパッド)」は、業種を問わず多くの企業やユーザーに利用されています。直感的に操作できるUI・UXが特長で、年間数千回以上の導入説明会を開催しており、手厚いサポート体制も整っています。詳細は資料でご確認ください。