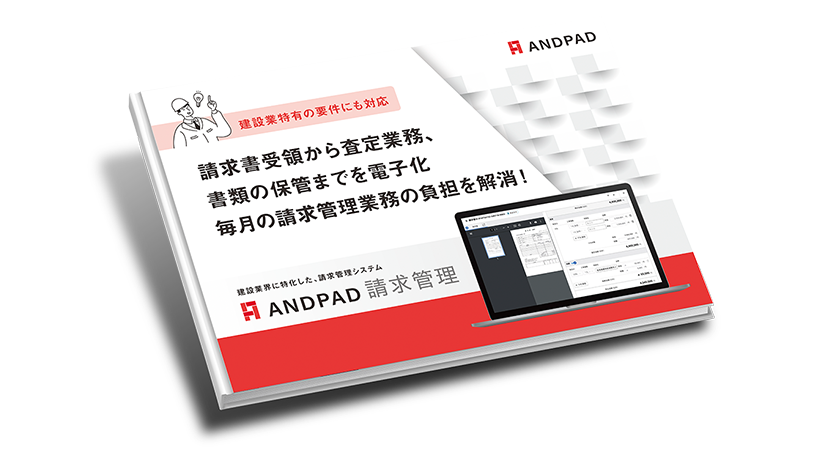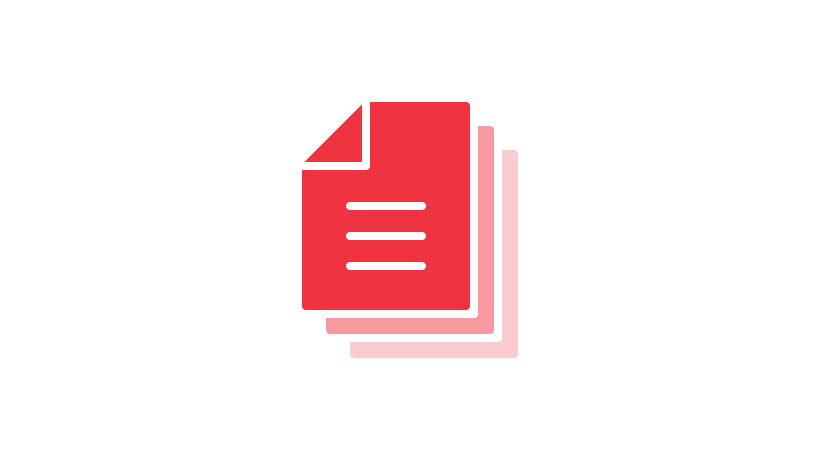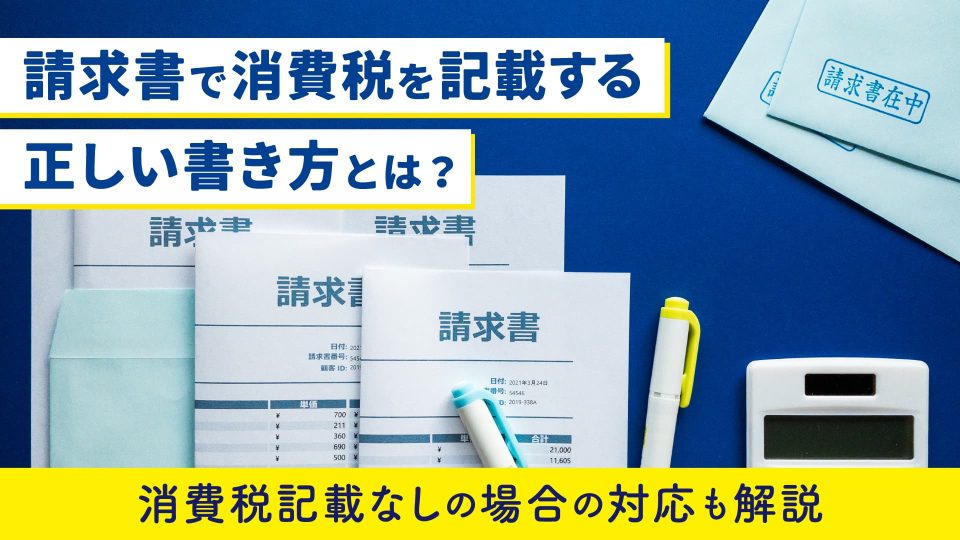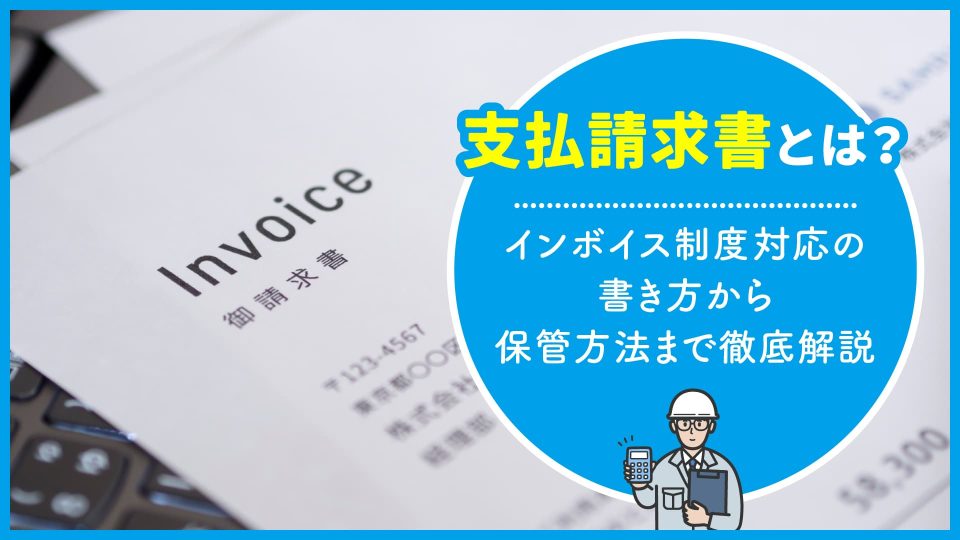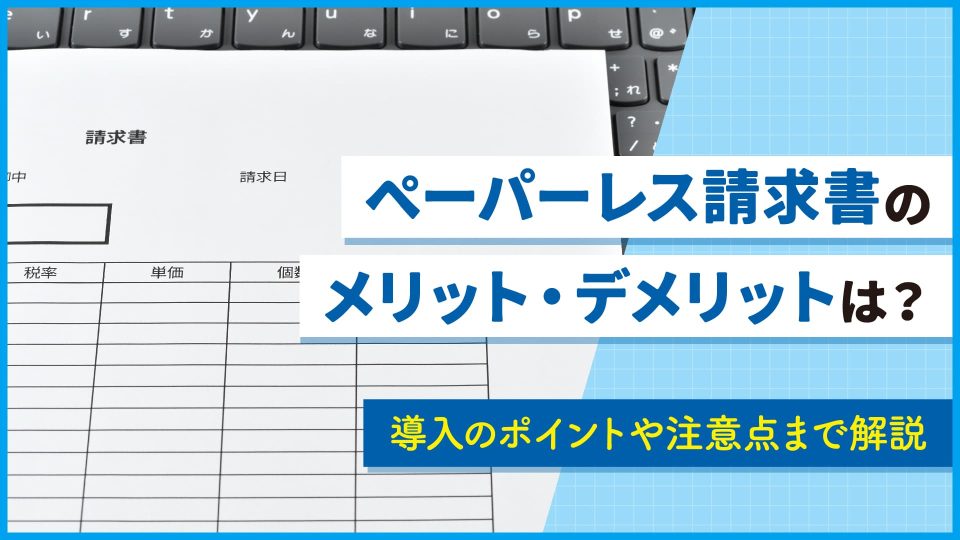請求書に消費税を記載する必要はあるのか、記載するのであればどのように書けばよいのかわからず悩んでいる人も多いでしょう。この記事では、請求書に消費税を記載する正しい方法と請求書に記載すべき項目、請求書のミスを防ぐ対策などについて解説します。適格請求書(インボイス)に記載すべき項目についても解説するので、経理担当者は参考にしてください。
請求書の発行と消費税法の関係

請求書を発行するにあたって、関係してくるのが消費税法という法律です。ここでは、消費税法と請求書との関係について解説します。
請求書の発行は消費税法によるきまり
請求書は、取引ごとの請求額を明らかにするために重要となる書類です。請求書は、消費税法で原則として発行と保存が義務付けられています。これは、事業者が売り上げ取引で預かる消費税額と仕入れ取引で支払う消費税額を正確に把握することが求められるためです。また、その際、一定の事項を記載する義務があり、抜け落ちがあると請求書自体が無効となる可能性があるため注意が必要です。
消費税法とは
消費税法とは、消費税について必要な事項が定められた法律です。国内では、商品の販売やサービスの提供など、ほとんどの取引に対して消費税が課税されます。消費税法では、国内の取引における課税の対象や納税義務者、税額の計算方法、申告方法などについて細かく記載されています。
なお、消費税法を理解するには、消費税そのものの特徴を押さえておく必要があります。消費税は、税金の負担者と納税者が異なる間接税の1つです。
消費税法における請求書の書き方と記載すべき項目
請求書に決まった書式はありませんが、必ず記載しなければならない項目があります。
宛名
請求書は、請求相手を明らかにしなければなりません。そのため、宛名の記載は必須です。一般的には、「株式会社〇〇 御中」「〇〇会社 〇〇部〇〇 様」など、受け取り側の企業名や個人名を記載します。宛名と敬称は1文字空けることが一般的です。
発行日
請求書には、発行日も記載しなければなりません。ただし、請求書の作成日が発行日となるわけではありません。請求書の作成日や印刷日をそのまま記載するのではなく、事前に取引先とすり合わせて発行日を決めておくことが一般的です。
発行者の情報
請求書の発行者の情報も、わかりやすく記載することが求められています。題目の右下あたりに、会社名や屋号、会社の所在地、連絡先などを記載したうえで、印鑑を捺印します。法人であれば、社印、個人事業主であれば個人名や屋号を印した印鑑を押します。
取引内容
どの商品やサービスをどれくらい取引したのか、取引内容も明確にしましょう。内容(品目やサービス名)、単価、数量、金額の4項目に分けて記載するとわかりやすいでしょう。
合計金額は税込で記載する
請求書で消費税を記載する場合、各品目の記載方法は内税、外税どちらでも法的には問題ありません。ただし、最終的な請求金額は税込で記載しなければならないと定められています。
適格請求書(インボイス)に記載すべき項目

適格請求書(インボイス)を発行する場合、上記の請求書に必要な情報とあわせて、適格請求書発行事業者の登録番号と税率ごとの消費税額を記載する必要があります。それぞれについて解説します。
適格請求書発行事業者の登録番号
消費税の仕入税額控除が適用されるために、「適格請求書」の交付・保存が求められます。請求書には、適格請求書発行事業者氏名や名称とあわせて、登録番号が必要です。登録番号は、インボイス発行事業者ごとに割り振られています。法人であれば「T+法人番号」個人事業者や社団は「T+13桁の固有番号」です。
税率ごとの消費税額
適格請求書には、税率ごとに消費税額を記載する必要があります。標準税率(10%)と軽減税率(8%)それぞれの合計金額と適用税率を記載します。インボイス制度では、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行わなければなりません。
請求書に記載する消費税の端数処理の方法
端数処理の方法は「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」がありますが、どの方法を選択してもよく、国税庁はその判断は各事業者に任せるとしています。処理方法で請求書の数字が変わるため、社内で端数処理の方法は統一させましょう。
消費税が記載されていない請求書を受け取った場合の対応
受け取った請求書に消費税が記載されていない場合もあるでしょう。その場合の対処法について解説します。
再交付を依頼する
消費税の記載がない請求書を受け取った場合、仕入れ先に不備について連絡を入れ、再度、消費税額を含む正確な請求書の再発行を依頼する方法もあります。取引先とのスムーズなやり取りのためにも、請求書を受け取ったら内容に不備や漏れがないかを確認し、早急に修正と再発行を依頼することが望ましいでしょう。
請求書で内税・外税を記載する場合の違い
請求書の合計額には、税込の金額を記載する必要がありますが、各項目においては内税、外税どちらでも問題ありません。ここでは、内税、外税のメリット、デメリットを解説します。
内税とは
内税は、税込価格(総額表示)のことです。内税表示では、取引品目ごとの単価金額いずれも税込表示になります。ただし、内税表示であっても、合計金額のうち、いくらが消費税かを適用税率ごとに計算して記載しなければなりません。内税の消費税額の計算方法は、以下のとおりです。
- 消費税額=税込価格÷(1+消費税率)×消費税率
内税のメリット
内税で表記する場合、仕訳が簡便になるメリットがあります。簡易課税制度の対象となる事業者にとっては、消費税の計算をまとめて処理できる税込経理方式が適しているでしょう。また、税抜経理方式と比較すると、特別償却や特別税額控除の金額が大きくなるため、節税対策になります。
内税のデメリット
内税では、期末の消費税総額を元に最終利益を確定させます。そのため、会計期間の途中に損益が判断できません。また、消耗品費や交際費も消費税込の金額で処理されるため、所定額を超えた場合に、経費や損金として処理できません。
外税とは
外税とは税抜価格(本体価格)のことです。取引品目ごとの単価、合計はいずれも税抜で表示します。税抜価格は、以下の計算式で導き出せます。
- 税抜価格=税込価格÷(1+消費税率)
外税のメリット
外税で記載する税抜経理方式では、取引ごとに発生する消費税を仮払消費税・仮受消費税として計上します。そのため、会計期間の途中でも損益を正確に把握できるメリットがあります。
外税のデメリット
税抜経理方式では、各取引で消費税額と本体価格を区別して経理処理を進めなければなりません。そのため、計算処理の手間が増すのがデメリットになります。
請求書作成業務を効率化する方法

請求書作成は状況によって煩雑になったり、細かな処理が必要になったりと負担が大きい業務の1つです。ここでは、請求書作成業務を効率化する方法を2つに分けて解説します。
クラウドサービスやツールを活用する
記載すべき事項が抜けていたり、誤りがあったりしたら、請求書を正しい内容に修正する必要があります。請求書発行システムや請求書作成ツールを活用することで、消費税に関する記載項目を漏らすことなく、正確に記載しやすくなります。毎月発生する請求書業務を効率的に進めるために、クラウドサービスやツールによる電子化がおすすめです。
会計ソフト連携や自動化によりミスを防ぐ
会計ソフトには、請求書作成や経費精算、証憑管理などが一緒になっているものもあります。データを自動連携させることで、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。また、手作業による照合作業の時間が削減でき、入力ミスも減らせるでしょう。
建設業の請求書にまつわる業務は「ANDPAD請求管理」で効率化
建設業における請求書関連業務の効率化には、「ANDPAD請求管理」の利用がおすすめです。「ANDPAD請求管理」は請求書の工事ごとの振り分け、注文・工種との紐付け、出来高査定など建設業特有の要件を満たした請求管理システムです。請求書の受領・査定・保管までを電子化できるため、毎月の請求管理業務の負担軽減につながります。
まとめ
請求書に記載する最終的な請求金額は、税込表記にしなければなりません。その他、請求書に記載すべき項目や保存については、消費税法で定められています。請求書は、記載項目や数値が誤っていると再発行が必要になる場合もあります。手入力でのミスを防ぐために、会計ソフトと連携したり、請求書発行システムや請求書作成ツールを活用したりしましょう。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。使いやすいUI・UXを実現する開発力が特長で、年間数千を超える導入説明会を実施するなどサポート体制も整えています。詳しくは、資料をご覧ください。