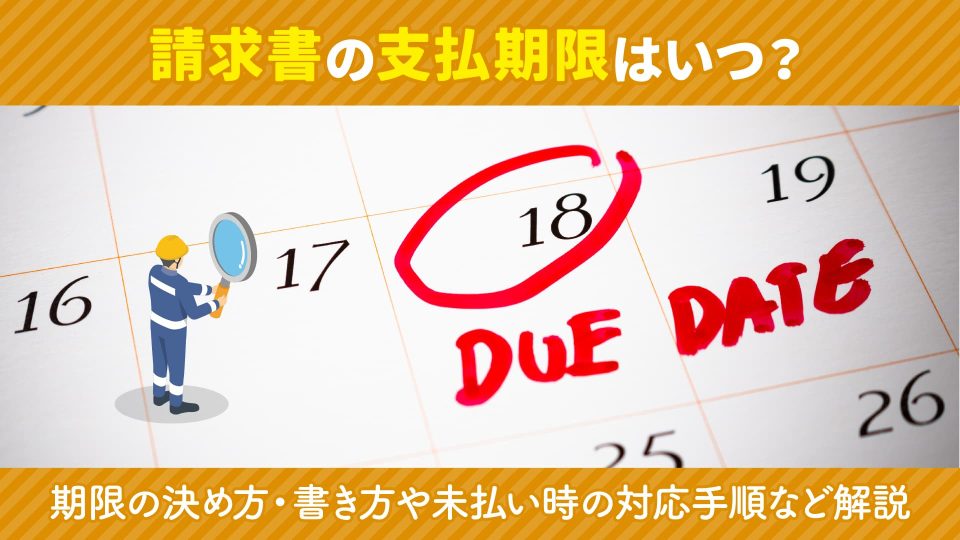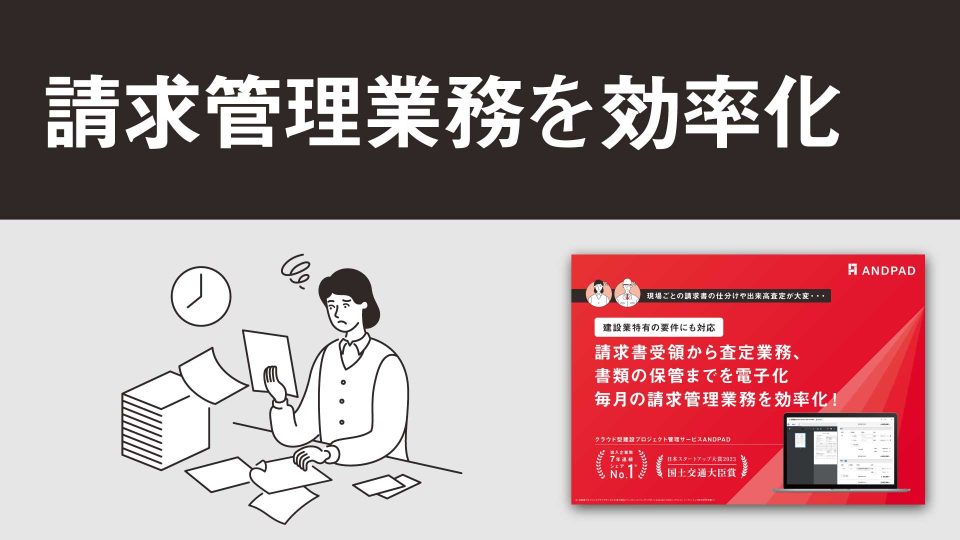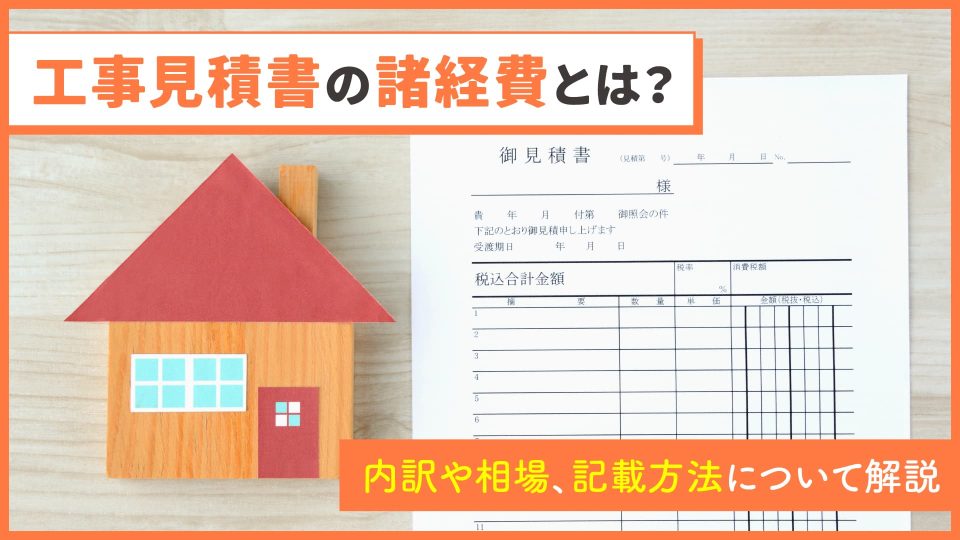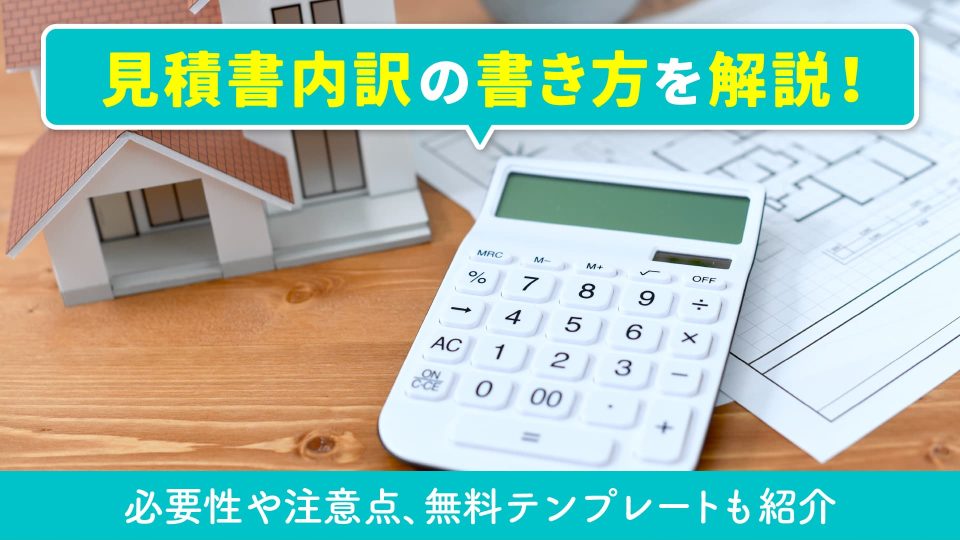請求書の支払期限は、取引先が代金をいつまでに支払うかを明確にする重要な項目です。決め方や記載ルールを理解することで、支払い遅延やトラブルを防げます。この記事では、支払期限の決め方から、支払期限を過ぎた場合の対応手順まで分かりやすく解説します。請求書を作成する際に、参考にしてください。
請求書の支払期限とは
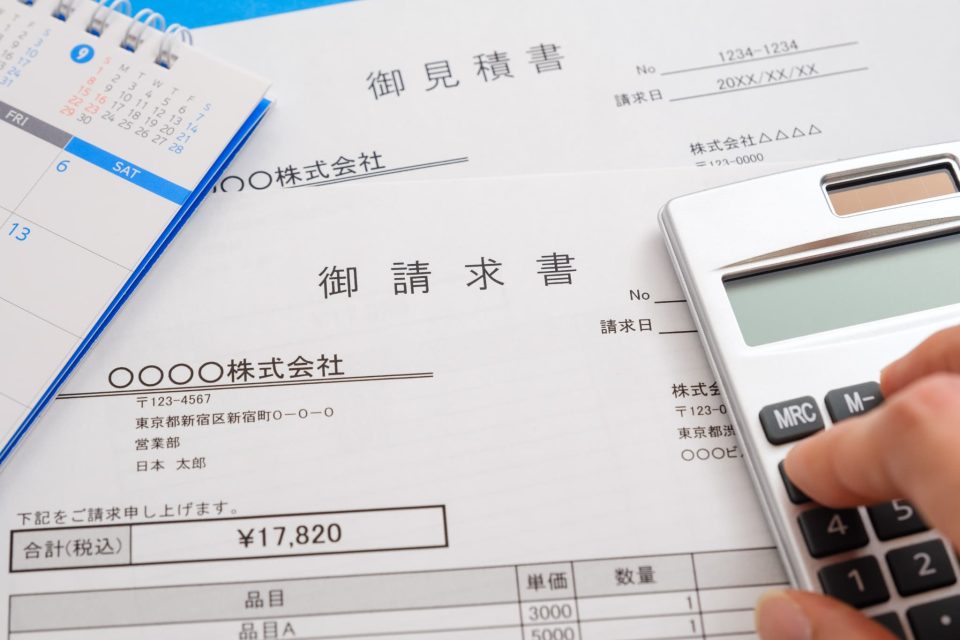
請求書の支払期限とは、取引に対して買い手が代金を支払う期日のことを指します。請求書を発行する際には、支払期限をあらかじめ設定しておくのが一般的です。支払期限は、企業ごとに定められた「支払いサイト(締め日または請求日から支払日までの期間)」にもとづいて決まります。支払いサイトについて詳しく解説します。
支払いサイトとは
支払いサイトとは、請求から実際の支払いまでにかかる期間のことです。簡単に言えば、「請求書の締め日から支払い日までの期間」を指します。以下で、請求書の締め日と支払い日について解説します。
請求書の締め日
請求書の締め日とは、納品や業務の完了に区切りをつけ、期間内の報酬をまとめて請求するために設ける日付です。例えば「月末締め」の場合、その月に納品や作業を行った分の報酬を集計し、請求書にまとめて記載します。
請求書の支払い日
請求書の支払い日とは、あらかじめ決めた締め日の対象期間に行った業務や納品に対して、代金がいつ支払われるかを示す日付のことです。例えば、「月末締め・翌月末払い」のような条件であれば、その月に発生した作業報酬は、翌月の月末に入金されることになります。
請求書に支払期限を記載する理由
請求書に支払期限を記載する理由は、トラブル回避や法的効力の確保のためです。以下で、それぞれの理由について詳しく解説します。
トラブル回避
請求書に支払期限を明記することで、入金のタイミングに関する誤解を防ぎ、支払いに関するトラブルを回避できます。支払期限が記載されていないと、取引先がいつまでに支払えばよいのか分からず、支払いが遅れる原因にもなります。円滑な取引関係を保つためにも、支払期限の設定は欠かせません。
法的効力の確保
請求書は、売り手が代金請求の証拠として法的に発行する重要な書類です。買い手は請求書を法人なら7年間(欠損金繰越のある年度は10年間)、個人事業主は5年間保存する義務があります。適格請求書(インボイス)発行事業者の場合は、売り手・買い手双方に保存義務があります。
また、2024年1月以降は電子帳簿保存法の改正により、電子発行した請求書はデータのまま保存することが義務付けられています。
請求書の支払期限の決め方と正しい記載方法

請求書の支払期限は、買い手がいつまでに代金を支払うかを明確にするために設定します。多くの企業は「月末締め翌月払い」や「翌々月払い」などを採用しています。支払期限に法的な決まりはありませんが、取引慣行から外れた支払期限を設定すると取引先が混乱し、支払い遅延やミスの原因になることがあります。
異なる支払期限を設ける場合は、事前に取引先へ伝え、認識のズレを防ぐことが重要です。また、「下請代金支払遅延等防止法」では物品等を受領した日から60日以内の支払いを義務付けてており、早めの支払いが望まれます。なお、設定した支払期限が年末年始や土日祝日の場合は、注意が必要です。以下で、詳しく解説します。
設定した支払期限が年末年始・土日祝日の場合
請求書の支払期限を毎月同じ日に設定すると、管理がしやすくなります。ただし、設定した日が銀行の休業日と重なることもあるため、注意が必要です。特に年末年始や土日祝日の連休期間は支払期限と重なる可能性が高いため、あらかじめ対応ルールを決めておくべきです。
例えば、「支払期限が年末年始や土日祝日にあたる場合は、前の営業日に支払う」といった取り決めを取引先に伝えておくことで、トラブルを防止できます。
請求書に支払期限の記載がない場合の対応方法
請求書に支払期限の記載がない場合は、取引先に確認しましょう。契約書で「月末締め翌月末払い」などと定めているケースもあります。契約に支払期限の記載がなく、資本金1,000万円超の企業が下請けやフリーランスに業務を依頼する場合は、「下請法」により納品から60日以内の支払いが必要です。
また、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、2024年11月1日以降は資本金や企業規模に関係なく、フリーランスに業務委託するすべての発注者に60日以内の報酬支払いが義務付けられています。
支払期限内に支払いがなかった場合の対処法と対応手順
取引先から支払期限内に入金が確認できない場合は、速やかに適切な対応を行うことが重要です。放置すると資金繰りや取引関係に悪影響が及ぶ可能性があるため、段階を踏んで問題解決を図る必要があります。以下で、対応手順について順を追って解説します。
1. 自社の請求内容に誤りがないか確認する
取引先から入金がない場合、まずは自社の請求内容に誤りがないかどうかを確認しましょう。請求書の送付漏れや誤った金額、支払期限の誤記載、あるいは請求先の取り違えなどが原因で支払いが滞っている可能性があります。請求内容の誤りを把握せずに催促すると、取引先との信頼関係に悪影響を与える可能性があるため、注意しましょう。
2. 取引先へ支払い状況を確認する
自社の請求内容に問題がないことを確認したら、取引先に連絡して支払い状況を確認します。支払いの遅れは担当者の認識違いや処理の遅延が原因の場合が多く、催促のメールを送れば、早期に対応してもらえるケースが大半です。
メールには支払い予定日や請求書の再発行についても明記しましょう。それでも支払いがない場合は、電話で直接担当者と話し合い、必要に応じて支払期限の延長交渉も検討しましょう。
3. 内容証明郵便を用いて正式に請求する
取引先が支払いに応じず、通常の催促で解決しない場合は、内容証明郵便を使って正式に請求する方法があります。内容証明郵便は、郵便局が送付した文書の内容と送付日を公的に証明するもので、万が一裁判になった際に強力な証拠となります。
また、内容証明郵便を送ることで、売掛金の消滅時効を通常の5年から6か月延長でき、裁判や支払督促などの法的手続きを行いやすくなります。請求書には、具体的な支払期限や支払いがなかった場合の法的対応についても明確に記載しておくことが重要です。
4. 裁判所に支払督促を申し立てる
内容証明郵便での請求後も支払いがなければ、裁判所に支払督促を申し立てます。支払督促は、通常の訴訟よりも費用が安く、手続きも簡単に進められるため、早期の解決を目指せます。迅速に債権回収を行いたい場合に有効です。
請求の時効期間は支払期限から5年間

請求書の時効期間は、支払期日の翌日から数えて5年間有効です。時効期間を過ぎると、請求書にもとづく支払い請求ができなくなります。
債権の消滅時効については、民法の改正により規定が変わりました。改正前の2020年3月31日までに発行された請求書は有効期限が2年とされていましたが、2020年4月1日以降に発行された請求書は有効期限が5年に延長されています。
建設業の請求管理なら「ANDPAD請求管理」の導入がおすすめ
建設業で請求管理をする場合、「ANDPAD請求管理」の導入がおすすめです。以下で、サービス内容について詳しく解説します。
「ANDPAD請求管理」のサービス内容
「ANDPAD請求管理」は、請求書の回収から工事ごとの振り分け、出来高査定や相殺・承認まで、建設業の特有の業務に対応した請求管理システムです。現場ごとの仕分けや査定・承認作業をオンラインで行えるため、現場監督や工事部門長も場所を問わずスムーズに対応できます。経理担当者は基幹システムへの手入力が減ることで、業務負担が軽減されます。
さらに、電子帳簿保存法に対応しているため、請求書の紙管理や検索の手間を削減し、月次の請求業務全体を効率化します。
まとめ
請求書の支払期限は、取引において買い手が代金を支払う期限のことで、取引を円滑に進めるために欠かせません。期限設定は取引先との合意をもとに適切に行い、超過時は速やかに確認や催促をしましょう。
建設業の請求書の管理には、クラウド型の建設プロジェクト管理ツール「ANDPAD(アンドパッド)」もおすすめです。年間数千回に及ぶ導入説明会を開催し、充実したサポート体制を整えています。業種を問わず多くの企業や利用者から支持されており、使いやすさを追求した設計が強みです。詳細は資料をご確認ください。