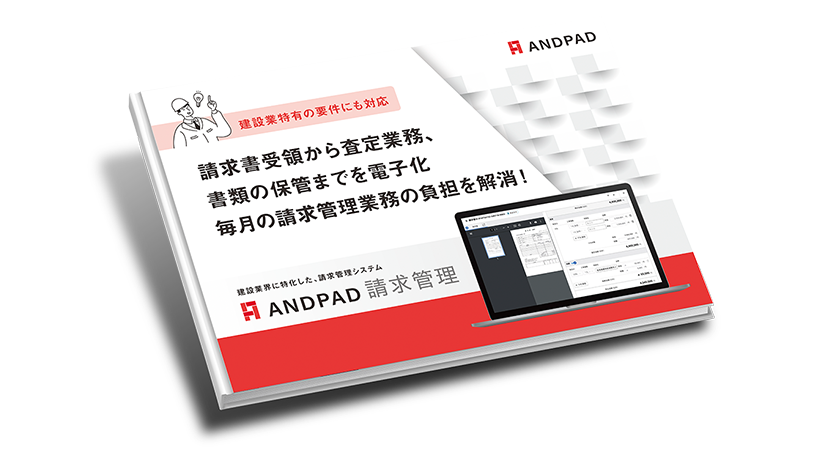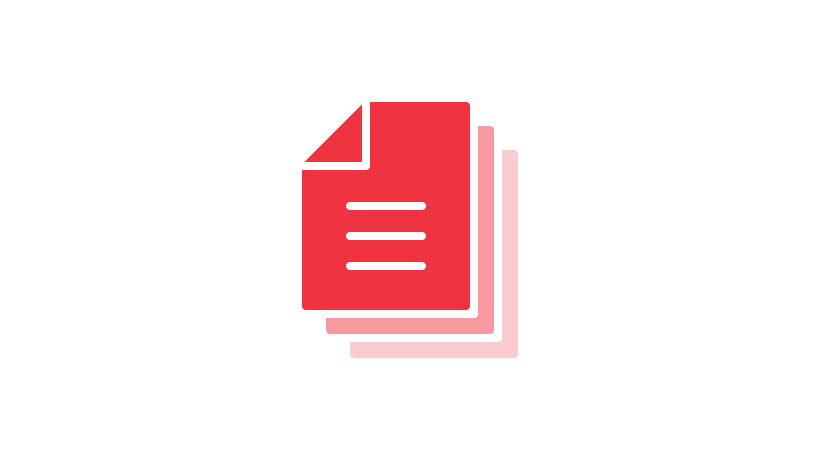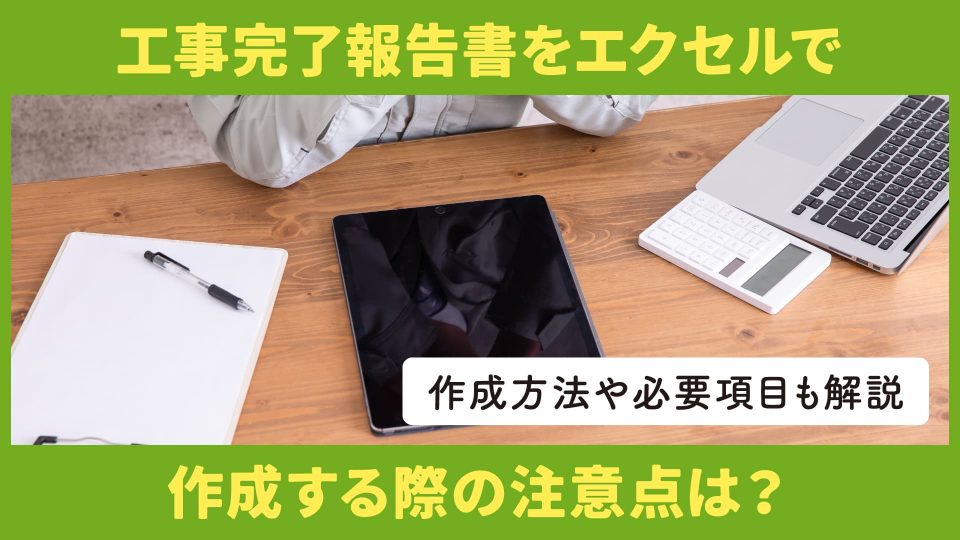工事完了報告書は、専用の書式や市販の様式を使って作成できます。エクセルを使った無料のテンプレートもあり、比較的容易に作成できる書類です。この記事では、工事完了報告書の定義や作成方法、記入が必要な項目などを解説します。エクセルを用いて工事完了報告書を作成する人も、それ以外の方法を活用する人も参考にしてください。
工事完了報告書とは

工事完了報告書とは、どのような書類なのでしょうか。ここでは、工事完了報告書の定義や作成の目的などを解説します。
工事完了報告書の定義と目的
工事完了報告書とは、特定の工事が、無事に契約または規定に基づいて完了したことを証明する書類です。工事完了報告書があることで、完了した工事の全体像を把握できます。
工事完了報告書を作成する目的は、工事の進行状況や最終的な結果を記録することにあります。他にも、使用した材料や費用を明確化することや、担当者同士の認識の食い違いを防ぐといった目的があります。将来的に類似プロジェクトを行う際の、計画の参考資料とする目的もあります。
工事完了報告書の作成は義務?
工事完了報告書の作成には、法的な義務がありません。しかし、「固定資産計上時期の根拠」となるため、実務上は重要な書類です。トラブルに遭った際、裁判での証拠にもなります。工事完了後のトラブル防止において、報告書の作成は重要です。
工事完了報告書の作成方法
工事完了報告書の作成方法は、3種類あります。専用の書式や市販の書式、Web上で入手できる無料のテンプレートがあります。それぞれについて解説します。
専用の書式を使用する
元請会社が専用の書式を用意している場合があります。この場合は、元請会社から工事完了報告書を受け取り、その書式に沿って記載します。元請会社の決めたフローで提出してください。
市販の書式を使用する
工事完了報告書を一から作るのは、手間と時間がかかります。効率的な作成を目指す場合は、すでに必要項目が網羅された市販の書式を使いましょう。自社の報告内容に合った書式のものを選んでください。
無料のテンプレートを使用する
エクセル用の無料テンプレートを活用することも、方法の1つです。関数を使った自動計算ができるため便利です。レイアウトの変更においても自由度が高く、自社に合わせたテンプレートにアレンジできます。計算が自動であるため、手書きやワードよりも正確に記入できます。
工事完了報告書の書き方と必要項目

工事完了報告書の書き方について解説します。報告書に記載すべき内容は、全部で14項目あります。それぞれの項目について、具体的に何を記入すべきか確認してください。
1. タイトル
まずはタイトルに「工事完了報告書」と記載します。どのような書類なのか、ひと目で分かるようにすることがポイントです。
2. 作成日・報告書番号
工事完了報告書は元請会社へ提出する書類ですが、自社でも管理するために、それぞれ通し番号と作成日を記載します。
3. 宛名
宛名には、請負会社の名前を記載します。このとき必要に応じて、電話番号や住所も記載しておくと分かりやすいでしょう。正式な文書のため、社名は省略せず、以下のように記載します。
- (株)→ 株式会社
- (有)→ 有限会社
- (名)→ 合名会社
- (合)→ 合同会社
- (資)→ 合資会社
4. 角印
工事完了報告書には、押印する義務がありません。しかし、角印を押印することにより、正式な文書であるといった証明になります。角印の押印位置については、印影の中心と社名の末尾が適度に重なるよう配置することが一般的です。
5. 工期
工事が行われた期日を記載します。工事が複数日にわたる場合は、工事の開始日と完了日を記載しましょう。
6. 会社情報
自社の正式名称を記載します。必要に応じて、住所や電話番号、メールアドレス、FAX番号なども記載しましょう。
7. 工事名
工事件名(現場名)を記載します。工事の件名を記載することで、後から書類を管理しやすくなります。
8. 工事の概要
工事の概要を簡潔に記載します。どのような工事かを概ね把握できる内容にします。
9. 工事の内容
工事や取引に関する内容を記載します。施工箇所や使用材料、施工方法など、関係者が工事の詳細を理解できるよう、簡潔かつ明確に記載しましょう。
10. 請負金額
契約時に定めた請負金額を記載します。材料費については、請負金額に含まれた費用であっても、その内訳を記載します。費用の記載欄がない場合は、材料を購入した際の納品書のコピーや領収書を資料として添付してください。
11. 担当者名と印鑑
工事の担当者名を記載し、印鑑を押します。
12. 工事写真
元請会社によっては、工事完了写真の添付が必要な場合もあります。工事を行ったことを証明するだけでなく、工事後にトラブルが生じたり、不備が見つかったりした際に活用されます。特に、修繕・改修工事を行う場合には、工事前後の写真が必要です。工事前の写真は、後から撮影できないため、事前に確認しておきましょう。
13. 工事場所
工事現場の住所を記載します。
14. 備考
上記に記載できなかった詳細や特記事項などを記載します。
工事完了報告書の作成ポイント
工事完了報告書を作成する場合は、いくつかのポイントがあります。通し番号や工期の書き方などについて解説します。
報告書に通し番号をつける
工事完了報告書を作成する際は、通し番号をつけましょう。これは「〇〇様邸の工事完了報告書について」といった問い合わせがあった際に、すぐに該当の書類を探せるようにするためです。通し番号があることで、社内での連携も取りやすくなるでしょう。
請負金額の書き方
請負金額は、税込と税抜どちらで記載するといった決まりはありません。しかし、税抜金額と消費税額を分けて記載することで、より正確な金額の把握が可能となります。
請負金額について認識の齟齬が生じるとトラブルの原因となるため、工事費用の内訳を含めて金額を明確に記載します。材料費や交通費が含まれる場合は、その明細も記載しましょう。添付する領収書や明細には、必ず現場名を記入します。現場名の記載がない場合、正式な書類として認められないことがあります。
取引内容・条件を記載する
工事の内容・条件は、可能な限り具体的に記載しましょう。認識の相違を減らすためです。例えば「〇〇様邸バスルームのリフォーム」のように、現場名だけでなく施工した箇所も記載するとよいでしょう。
エクセルで工事完了報告書を作成する際の注意点
エクセルで工事完了報告書を作成する場合は、以下の注意点を確認しましょう。大量のデータ管理や入力ミスの可能性に考慮し、慎重に作成を進めることが重要です。
大量のデータ管理が必要
エクセルの場合、1つのファイルで複数のシートを作成できるため、シートを増やして工事完了報告書を作成するケースがあります。便利ではあるものの、シートが増えるごとに読み込みに時間がかかり、かえって使い勝手が悪くなってしまいます。
ファイル自体の容量が大きくなったり、それぞれを別ファイルで作成する場合であっても、数が増えたりすると、サーバーへの負担はかかってしまいます。増えていくデータをどのように管理するのか、検討する必要があるでしょう。
入力ミスが生じやすい
エクセルで工事完了報告書を作成する場合、データは基本的に手入力となります。そのため、ミスが生じやすいことは理解しておかなければなりません。例えば、データを入力する列が1列ずつズレている、数字が間違っているなどです。作業中、誤って数式を消してしまう可能性もあるでしょう。
膨大なデータを目視で確認しながら入力すると、人的ミスが起こりやすくなります。二重チェックにするなど、チェック体制を整える必要があるでしょう。
新旧ファイルの保存に管理コストが発生する
エクセルは、リアルタイムでの情報共有には適しません。共有にタイムラグが発生し、新旧ファイルの管理が複雑になるためです。例えば、編集中の情報は、作業者しか操作できません。他の人が編集中のファイルを開いても、情報が更新されておらず、古い情報を新しいものと誤認してしまう恐れがあります。
どのファイルが最新のデータか分かりにくいため、バージョン番号を付与して管理することも重要です。
工事完了報告書の提出方法

工事完了報告書は、以下のような流れで提出します。
- 工事を請け負う
- 工事が完了する
- 工事完了報告書を作成する
- 元請会社に工事完了報告書を提出する
ただし、これはあくまでも例ですので、実際には元請会社のフローに沿って提出してください。
工事完了報告書の提出期限と保存期間
工事完了報告書の提出は義務ではないため、提出期限に関する法的規定はありません。提出期限については、元請会社の規定を確認して対応します。
また、工事完了報告書の控えは、一定期間保存しておきましょう。保存期間について法的な規定はありませんが、建設業法施行規則第28条において、帳簿類を建設工事ごとに5年間保存するように定められています。このため、工事完了報告書も同様に、5年間の保存を基本としておくとよいでしょう。
まとめ
工事完了報告書をエクセルで作成する場合は、書類に通し番号をつける、工期や請負金額は明確に記載するといったポイントに注意しましょう。どのような工事完了報告書を作成すべきかお悩みの人には、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」がおすすめです。
シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーに利用されています。使いやすいUI・UXを実現する開発力と丁寧な導入説明会、手厚いサポートが特徴です。詳細については、以下よりお問い合わせください。