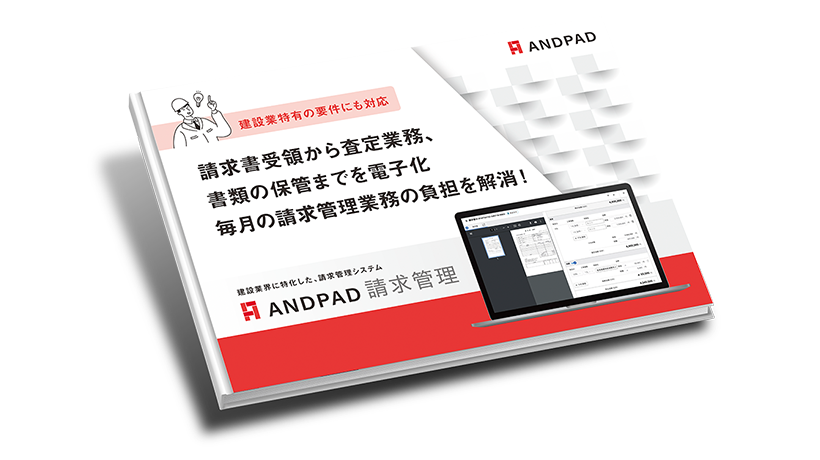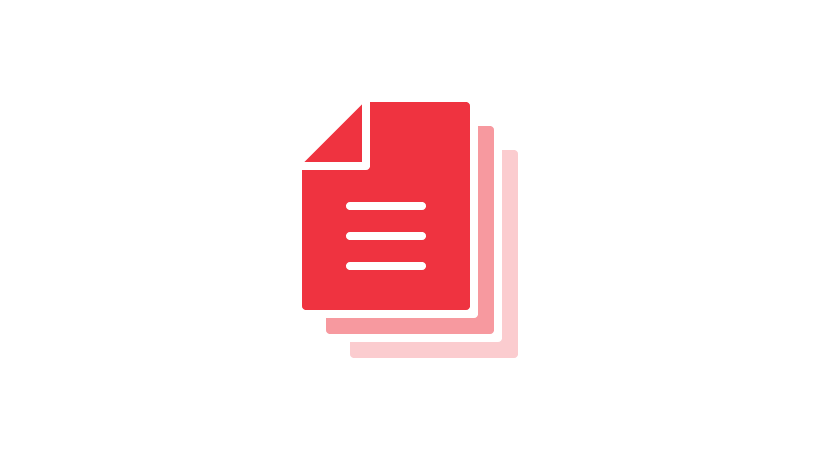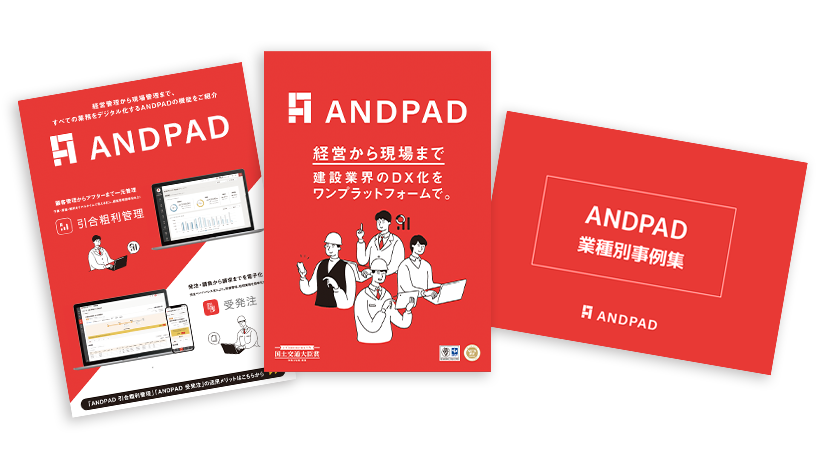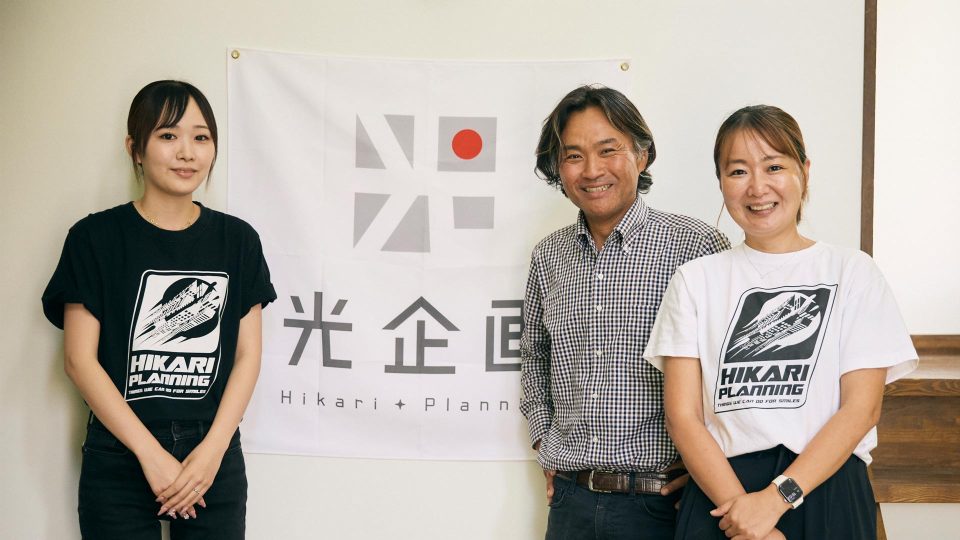内藤電機株式会社のご紹介
岐阜県岐阜市に本社を置き、総合電気工事の設計・施工・メンテナンスを手がけている内藤電機株式会社。創業より75年にわたり、岐阜県内で数多くの施工実績を積み上げながら、名古屋・東京・金沢・大阪の各支店・営業所においても着実に事業を拡大し続けている。
同社が携わる電気工事は、ビルや施設の大規模電気設備から店舗のインテリアライティング、照明器具・コンセントの増設までと実に幅広い。どれも生活や社会に欠かせないインフラを支える工事のため、閉店後に行う夜間工事や工場の稼働が停止する休日の工事、突発的に発生する緊急の修理対応と、不規則な勤務が発生し、就業環境の整備や残業時間の増加に課題を抱えていた。
そこで、同社は「社員が長く安心して働ける環境」を実現するために、ANDPADを活用して業務効率化・生産性向上への取り組みを強化している。今回は、内藤電機株式会社でDX推進を担当する皆さんにインタビューを実施。ANDPAD導入前の課題、導入後の変化についてお話を伺った。
情報管理を一元化、ANDPADに蓄積されたデータが財産に
同社は、工事部・電設部・施設部と、担当する物件によって部門を分けて幅広い電気工事に対応している。なかでもANDPADの活用が浸透しているのが、電設部と施設部だ。
電設部では、工場・倉庫・事務所などの新築工事・改修工事にともなう電気設備工事を手がけている。まず、電設部の部長を務める野々垣様にANDPAD導入前の課題を伺った。
「以前は、担当者一人ひとりが自分の裁量で案件の管理を行っていて、協力会社との連絡手段も、スマートフォンのコミュニケーションアプリやメールとバラバラでした。資料も紙で出力して協力会社に配布していたため、打ち合わせを兼ねて来社してもらう機会も多く、管理する紙の量も多かったです。」(野々垣様)
また、電設部の場合、同じ顧客からの依頼が多いため、工場内の環境や動線を理解している協力会社に継続して発注するのが通常だった。ただ、いつも依頼をしている協力会社の予定が押さえられないと、発注先を決めるのに時間がかかってしまっていたという。「現場の情報が可視化・共有ができていないことが課題だった」と、野々垣様は当時を振り返る。
そこで野々垣様は、部署全体でANDPADにデータを蓄積するべく、案件の管理をANDPADに一元化した。また、情報管理の一環として写真台帳の活用も進めているという。
「今は、ANDPADの案件に現場の情報をまとめて格納しているため、新規の協力会社さんに依頼する際も、情報を抜け漏れなく伝えられるようになりました。また、お客様への報告書作成にあたって、ANDPADの写真台帳を活用する社員も増えています。報告義務の有無はお客様によって異なりますが、ANDPADに保管されている情報に助けられることが多いので、今後は全現場統一で写真台帳を残していく予定です。『ANDPADのデータは電設部の財産になる』といった意識を持って、情報を記録・保管するようにしています。」(野々垣様)

業務の流れが可視化され、段取り・トラブル対応がスピーディーに
次に、施設部の平岩様にお話を伺った。同社の施設部では、百貨店や大型ショッピングモールなどの店舗内装工事、インテリアライティングを主に手がけている。
商業施設の電気工事では、突発的な修理対応も含めて、大小さまざまな案件が非常に多く寄せられる。そのため施設部では「工事情報の蓄積」といった目的よりも、「スピーディーに段取りを組む」ためにANDPADを活用しているという。
「ANDPADの導入によって工程が可視化され、誰でも同じ手順で段取りが組めるようになったのが大きな変化です。ANDPADを見れば、経験の浅い若手社員がどのように工事手配を進めているのかを見られるので指導もしやすくなりました。工事の進捗状況や協力会社さんの稼働状況など、管理者として把握しておきたい情報もリアルタイムで確認ができて助かっています。」(平岩様)
また、施設部では、現在ANDPADを介して協力会社から写真付きの報告も上げてもらっているという。
「夜間工事の場合、担当者が現場に立ち会えないときでも、ANDPADの報告によって状況を把握しやすくなり、問題発生時の対応もスピーディーになりました。協力会社さんの報告によって夜間工事にかかる負担は軽減してきています。」(平岩様)
そのほか、ANDPAD図面の利用もスタートし、活用が進んでいる。
「先日商業施設全体の電気設備の調査においてANDPAD図面を利用しました。事前準備として、ANDPADに資料を取り込み、写真撮影をする箇所に記録ピンを立てました。3組に分かれて調査を行ったのですが、図面上の記録ピンの色の変化によって、お互いがどこまで進んだのか完了状況がわかり、動線が重ならずスムーズに調査が進められました。写真も漏れなく撮影できて、写真整理も簡単でした。」(平岩様)

閑散期にANDPADにしっかり向き合う時間を取った
現在、同社ではANDPADの利用が定着しはじめており、協力会社の利用率も上がりつつある。では、同社はどのように利用の浸透を進めたのだろうか。
「社員や協力会社さんがANDPADの利用に慣れる時間が必要だと考えて、業務の閑散期から利用を開始し、ANDPADに向き合う時間をつくりました。協力会社さんのなかには、ANDPADの導入目的を『内藤電機の担当者が楽をしたいからだ』と誤解されている方もいたので、お互いが効率良く業務に取り組むために必要だと、じっくりお話をして理解してもらいました。協力会社さんも実際にANDPADを使っていくなかで、ANDPADの利便性に気づき、徐々に利用が浸透していきました。」(平岩様)
仕事が分散化できるようになり負担が軽減、社員に改善意識も芽生えた
では、ANDPAD導入後にどんな変化が生まれたのか。電設部、施設部それぞれの変化について伺った。
「電設部では、これまで1人の担当者が顧客担当としてお客様についていましたが、今はメインとサブの社員でANDPADで情報共有をしながら複数人でお客様をフォローしています。若手側には『先輩に見てもらえている』という安心感が生まれ、先輩側には『分業できた』という負担の軽減が生まれて非常に好評です。仕事の分散化によって、業務を代わりに頼むことができるようになり、休みも取りやすくなっています。ANDPADを通じて現場の情報や先輩たちのノウハウを吸収できる環境が整ったこともメリットです。」(野々垣様)
「ANDPAD導入後は残業時間が25%減で推移しています。ANDPADを介して協力会社さんから報告を受けられるようになったので、「この案件は職人さんに任せて遠隔で確認しよう」「この案件は現地に足を運んでお客様との関係を深めよう」といった判断ができるようになりました。ANDPADにデータが蓄積されればされるほど、どの案件を優先するか、判断もしやすくなっている感覚です。」(平岩様)
また、「社員の意識にも変化が生まれている」と平岩様は話す。
「一番の大きな変化は、社員がこれからの働き方について真剣に考えるようになったことだと思います。ANDPAD導入に向けて、案件の整理や業務の平準化を全員で進めたことで、「忙しいから対応できない」という後ろ向きな考え方から、「ANDPADを使って改善に取り組もう」という考え方に変化してきました。」(平岩様)
「人」を大事に、DXと働きやすい環境づくりを進めていく
同社は、「休日の取りやすさ」や「会社の将来性」といったテーマで月1回チームでディスカッションする「未来をつくる会」を発足したり、2024年11月からクラブ活動を開始したりと、会社自体に愛着を持ってもらえるような取り組みにも注力している。「ANDPADの運用によって、上司と若手がお互いをフォローし合う協力体制が根づき、社内イベントやクラブ活動に参加できる時間の余裕も生まれてきている」と野々垣様は話す。
最後に、今後の展望を伺った。
「ANDPADを駆使して、現場訪問回数や作業時間を削減していきたいです。そして、その余剰の時間を若手が技術や知識を高める時間に充てていければと思います。『私たちの世代で変えていく』という強い想いで取り組み、社員の働き方を変え、人材育成にさらに力を入れていきたいです。」(平岩様)
「真面目な人間が多いのが、当社の一番の強みだと思っています。誠実な対応によってお客様に「人」として信頼していただいているからこそ、担当者に依頼が寄せられ、県内トップクラスの実績につながっていると考えています。今後も当社ならではの「人」の良さを根幹にしながら、お客様や協力会社さんに信頼していただけるように経営に取り組んでいきたいです。そのためにも、社員がいきいきと働き、生活できる会社になるための仕組みづくりは必須です。この仕組みづくりに、ANDPADを活用していきたいですね。」(内藤様)