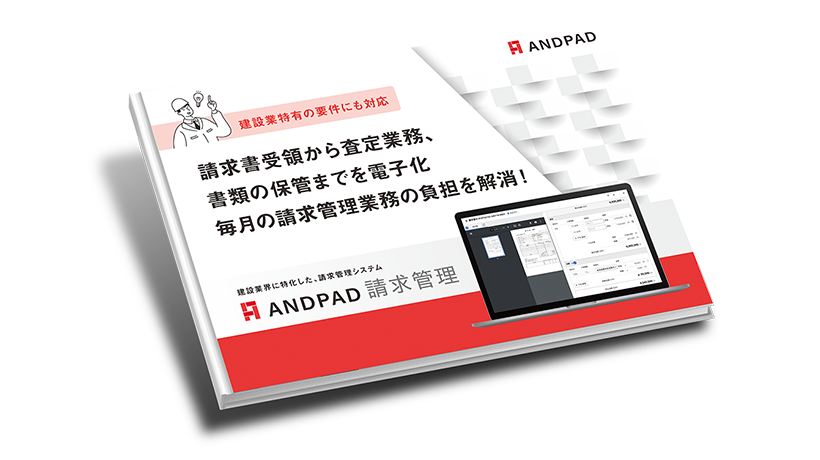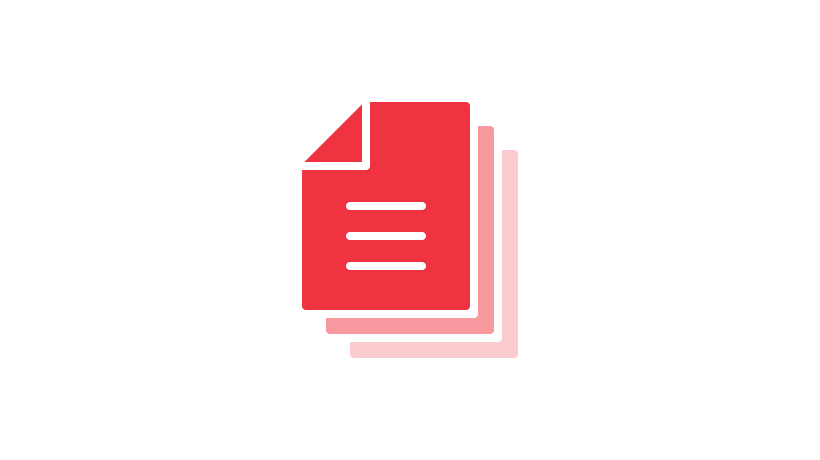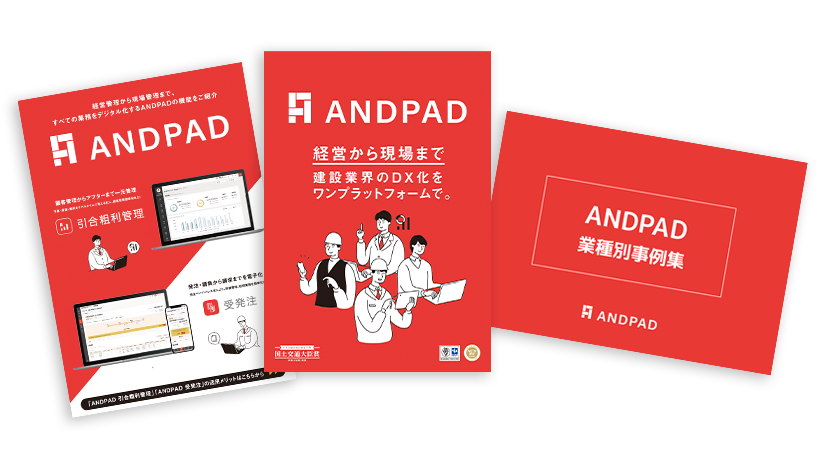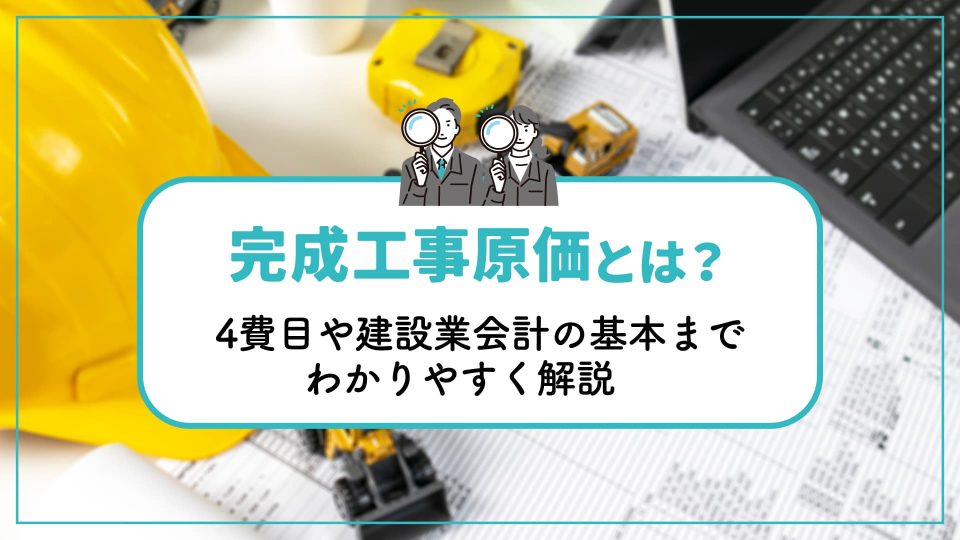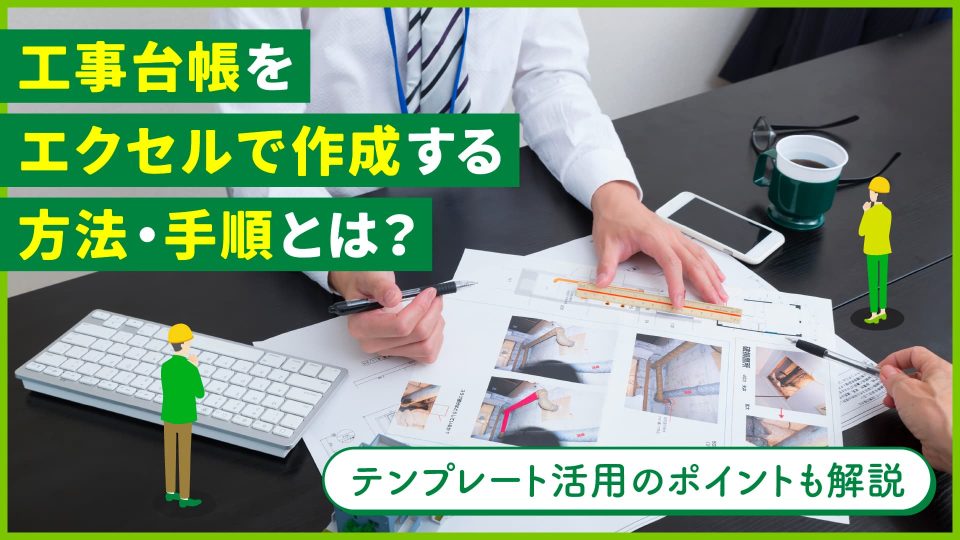建設業会計においては、工事原価または完成工事原価といった用語がありますが、建設業以外では使われないため、どのようなものであるかを知らない人も少なくありません。この記事では、工事原価の基本情報や種類、完成工事原価の4費目などについて解説します。完成工事原価について知りたい人は参考にしてください。
工事原価とは?基本知識を徹底解説
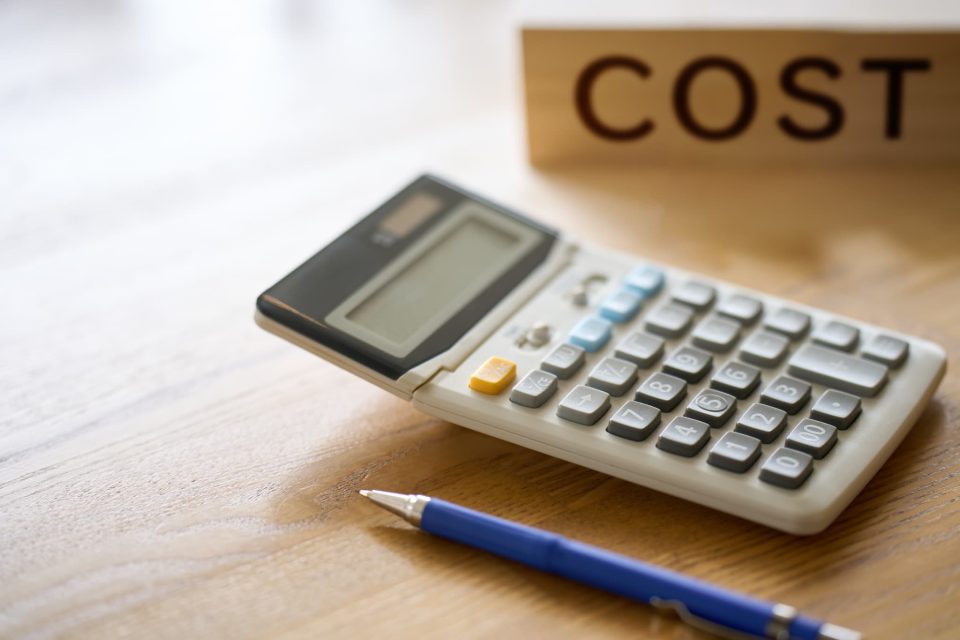
工事原価とは、建設物の工事にかかった原価で、建設業会計のみで用いられる科目です。工事原価には、工事の収入を得るために要した、直接的な費用が含まれます。
建設業では、工事が1年以内に終わらず数年にわたって続くケースもあります。そのため、一般的な会計処理とは異なる、「完成工事原価」と「未成工事支出金」といった勘定科目を用いて、工事にかかった費用を適切に処理する必要があります。
工事原価の2つの種類
前述のとおり、工事原価には「完成工事原価」と「未成工事支出金」という、建設業会計でのみ用いられる科目があります。ここでは、それぞれの科目について解説します。
完成工事原価
完成工事原価は、建設業で会計年度内に完成した工事に要する費用総額で、一般会計における売上原価。基本的に材料費、労務費、外注費、経費の4つですが、工事で収入を得るために要した直接的な費用が、工事原価に該当します。
たとえば、商品販売の場合、仕入れに要した金額のうち、当期の売上に関する部分が売上原価として計上されます。しかし、建設業は仕入れたものを販売する業種ではないため、商品販売において仕入れに該当する部分には、一般会計とは異なる科目が用いられます。
未成工事支出金
未成工事支出金とは、まだ完了していない工事に要した費用です。製造業会計では、仕掛品や半製品に該当します。仕掛品とは製造途中で販売できないものを指し、途中段階での製造にかかった費用を表す勘定項目です。未成工事支出金は仕掛品と同様に、未完了の工事にかかった費用を指します。
未成工事は、費用に見合った収入が得られていないのが一般的であるため、確定申告ですべての工事原価を計上すると、一時的に赤字となる可能性があるため、適切に未成工事支出金として処理することが重要です。収支のバランスを取り、翌年以降へと繰り越す必要があります。
完成工事原価を構成する4要素
完成工事原価は、建設業の原価管理における重要な概念です。おもに「材料費」「労務費」「経費」「外注費」の4つの要素を指します。それぞれの要素について、特徴を解説します。
材料費
建設工事において直接的に用いられる、材木やセメント、鉄筋、ガラス、砂利といった材料にかかる費用です。また、特定の工事に必要な機械や道具も材料費に該当します。ただし、複数の現場で使用するために購入した機械や材料は間接材料費とみなされるため、全額が工事原価にはなりません。
間接材料費は、使用した工事で分け、当該工事で消費したと見込まれる分を、工事原価として計上します。材料費は、基本的に原価報告書に記されている価格を転記します。完成工事原価と未成工事支出金で分ける必要があるケースでは、誤らないよう注意しましょう。
労務費
工事に関わる人材の賃金や給料、福利厚生費、手当などを指します。工事に関わった作業員に要した費用は、すべてを労務費として工事原価に計上します。正社員やアルバイト、短期雇用者などの区別はないため、それぞれの現場に何人の作業員が関わっていたのかを、正確に把握しておきましょう。
一方、工事現場に直接関わりのない、事務員・管理職の給与、手当などは、工事原価に含まれません。現場で働く作業員以外の人件費は、労務費ではなく一般会計の販売費や一般管理費に計上する必要があります。
経費
材料費、労務費、外注費以外で、工事に要したさまざまな費用を指します。おもに、設計費や動力用の水道光熱費、通信交通費、建設に必要な機器や重機類の原価償却費、メンテナンス費用などが該当します。
建設工事の大部分は受注して進めるため、材料費や労務費、外注費が間接費に分類されるケースは多くありません。しかし、経費においては、直接的な費用として分類できない項目があり、その場合には間接経費として計上する必要があります。なお、間接経費へと計上したものを適切に分けるための原価計算は慎重におこないましょう。
外注費
外注費とは、建設工事の一部や部材の加工を外部に委託した際に発生する費用です。外注費は工事原価の一部で、外注先は専門工事会社や資材加工会社などです。工事原価における外注費の割合は大きく、外注費を把握しなければ工事原価の正確な申告はできません。外注費と労務費は区別が難しい場合があり、特に消費税の取り扱いなど、税務上の処理に影響ができる可能性があるため注意が必要です。
たとえば、工事に関する作業を別の協力会社に委託した場合は外注費となります。ただし、材料費を自社で支払い、工事のみを委託した場合は、労務費内の労務外注費として処理します。他の企業から作業員を派遣してもらって工事を進める場合も労務外注費として処理します。
建設業会計の特徴

建設業会計には「工事完成基準」と「工事進行基準」の2つの考え方があることが、大きな特徴です。工事完成基準とは、工事が完成し引き渡された時点で、収益と費用を一括で計上する方法です。工事が数年にわたる場合でも、完了するまで売上や利益が計上されないため、会計期間ごとの業績が把握しにくく、資金繰りに影響が出る可能性がある点がデメリットです。
一方、工事進行基準とは、工事の進捗度合いに応じて収益と費用を各会計期間に計上する方法です。これにより、各期間の収益と費用をより正確に把握でき、安定した経営状況の把握につながります。
一般会計との違い
建設業会計と一般会計との大きな違いは勘定科目です。すべての勘定科目ではないものの、名称や内容が一般会計とは異なります。例えば、一般会計における売上高は「完成工事高」、売上原価は「完成工事原価」、売上総利益は「完成工事総利益」という科目になります。勘定科目以外にも、工事の特性に応じた独自の原価計算を行う点も、建設業会計の大きな特徴です。
工事完成基準の特徴
工事完成基準は工事完了後や引き渡し完了後に、一括で売上や経費を計上する方法です。この方法では、工事が完了するまで収益・費用が認識されず、工事や引き渡しが完了したタイミングで利益が確定します。何度も計上する必要がないため、手間を減らせて会計処理が容易になる点がメリットです。
ただし、数年間にわたる工事の場合、工事が完了するまでは売上や経費を計上できません。
工事進行基準の特徴
工事進行基準は、工事の進捗度合いに応じて収益と費用を定期的に計上する方法です。この方法は、工事の進捗に合わせて計上するため、各期間の収支を正確に把握でき、安定した経営判断につながる点がメリットです。
現在は、多くの建設会社が工事進行基準を採用しています。ただし、進捗評価や収支報告の操作による不正な会計処理のリスクがあります。
完成工事原価を適切に管理して建設業の経営を強化
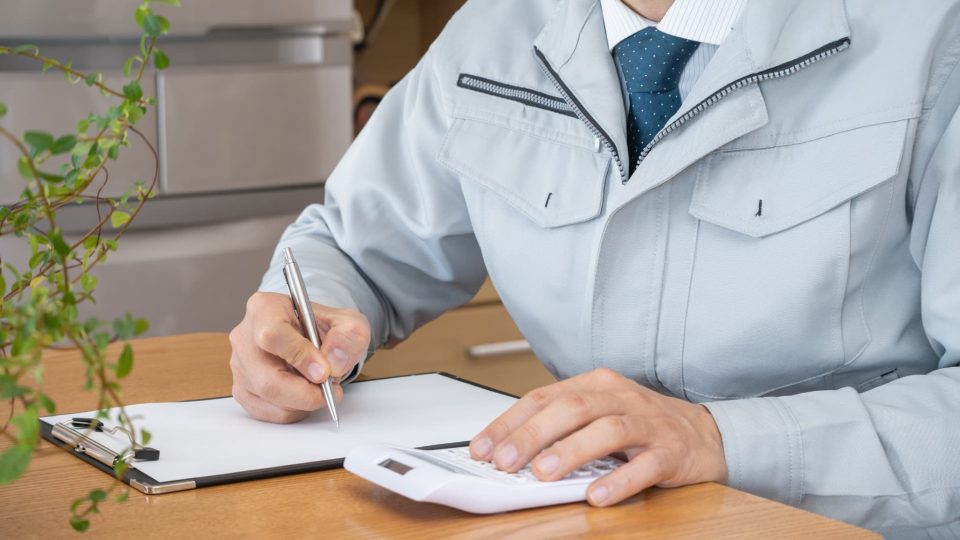
建設業の経営強化には、完成工事原価を適切に管理することが重要です。完成工事原価の適切な管理は、見積精度の向上や企業の競争力強化にも役立ちます。建設業界は近年、労務費の高騰や材料費の変動、熟練技術者不足など課題が増えています。原価管理は即座に成果が出るものではないため、継続することを意識して経営基盤の強化へとつなげましょう。
リアルタイムで原価・粗利を可視化するANDPAD引合粗利管理
「ANDPAD引合粗利管理」では経営に重要な、顧客管理から営業進捗、粗利・原価管理などのデータを集約し、リアルタイムかつ正確に把握可能です。過去の実績はもちろん、当月の着地や来月の見込みを可視化できます。建設業に特化したシステムであり、導入によって業務効率から経営改善までを実現できるでしょう。
まとめ
工事原価は、建設工事にかかった費用の総称で、工事による収入を得るために直接的に要したすべての費用が含まれます。建設業会計には「工事完成基準」と「工事進行基準」の2つの考え方があり、現在は工事進行基準を採用するケースが増えています。
クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD(アンドパッド)」は、建設業界におけるさまざまな情報を一元管理できるツールです。シェアNo.1サービスとして、業種を問わず、数多くの企業・ユーザーが利用しています。年間数千回に及ぶ導入説明会を開催し、充実したサポート体制を整えています。まずはお気軽にお問い合わせください。