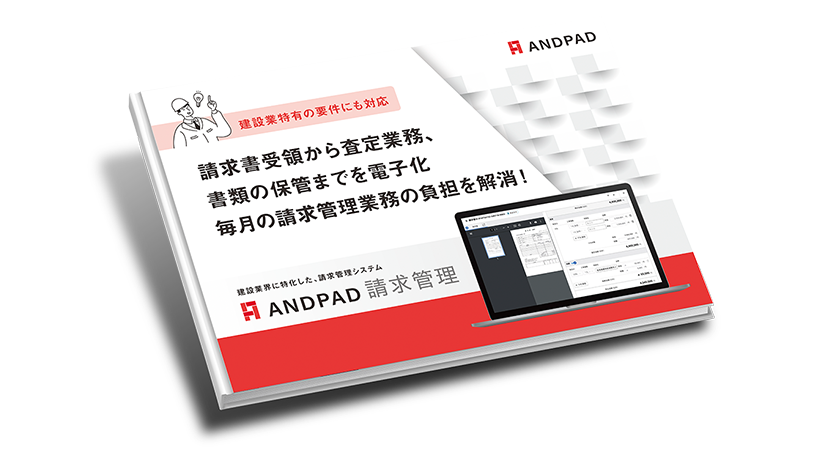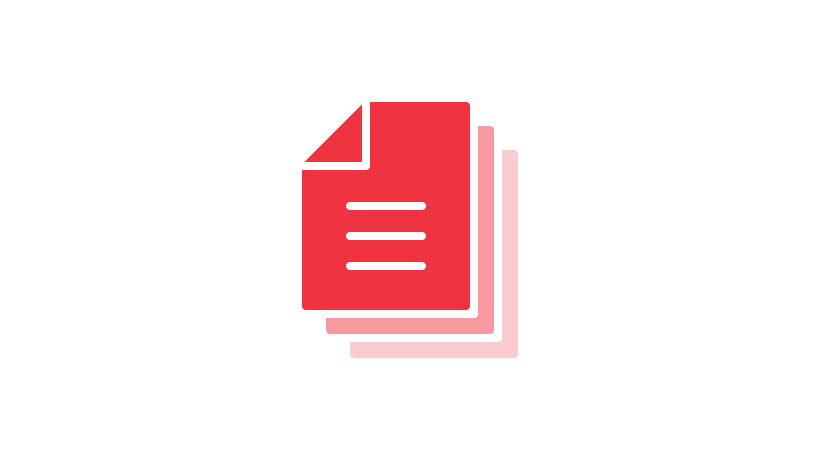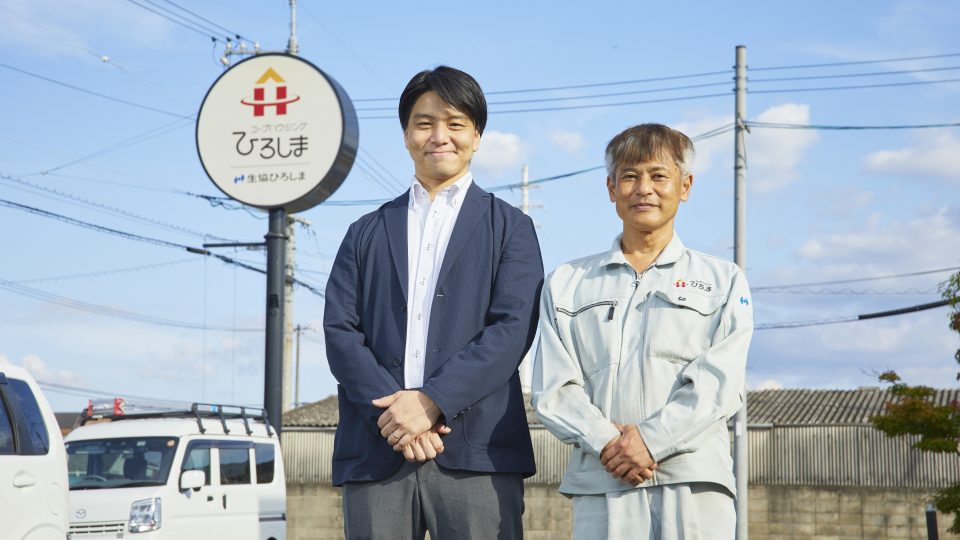一世紀を超える歴史を持つ大林組は、建設業のデジタル化に力を注いでおり、各分野の設計情報を1つのBIM(ビルディング インフォメーション モデリング)モデルに統合する「ワンモデル」という方針を掲げている。現場におけるBIMの活用をサポートする、BIMマネジメント課の宮村様に、BIMの運用における現状と課題を詳しく聞いた。
商業施設から伝統建築まで
ものづくり精神による建設事業
大林組は1892年(明治25年)の創業以来、ものづくり精神に根ざした事業を幅広く展開している。国内や海外の建築・土木事業をはじめ、エンジニアリング事業やグリーンエネルギー事業など、建設の枠を超えた事業を拡大している。
大林組九州支店は、JR長崎駅ビルなどの複合商業施設から、福岡市地下鉄七隈線の延伸工事、資生堂福岡久留米工場といった生産施設まで、さまざまな施工実績を持つ。2016年の熊本地震で被災した熊本城天守閣の復旧工事では、一世紀超にわたる大林組の伝統技術と最新技術を組み合わせて、熊本城をよみがえらせるだけでなく、耐震補強も行った。
BIMの活用方針「ワンモデル」
設計情報を一貫して活用
大林グループは中期経営計画に「事業基盤の強化と変革の実践」を掲げ、生産性や付加価値の向上を目指す。そのために生産のDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組み、デザイン、構造、設備などの各分野の設計情報を1つのBIM(ビルディング インフォメーション モデリング)モデルに統合する「ワンモデル」というBIMの活用方針を打ち出している。
そもそも、BIMとは、コンピューター上に作成した建築物などの3Dモデルをベースに、さまざまな情報を付加して活用するツール。従来の2次元のモデルと違い、実際の建築物に近いイメージを作成できることから、業務の効率化だけでなく、関係者とのコミュニケーションの精度を高めることにもつながる。こうしたメリットから、BIMを有効活用することで、日本の建設業界が抱える人材不足や労働時間の短縮といった課題の解決に役立つと期待されている。
大林組は2010年代初頭からBIMの導入を始めた。宮村様は、現場での経験を経て、2013年からBIMの導入に携わっている。「私が所属するBIMマネジメント課では、多種多様な現場に向けて、BIMを導入し、業務の効率化をサポートしています。本社のDX本部や建築本部BIMソリューション部と連携しながら、BIMやICTを活用した建設現場のデジタル化に取り組んでいます」と宮村様は説明する。
BIMマネジメント課では、BIMのメリットや可能性について現場に知ってもらうため、勉強会の実施や社内留学制度などを活用し、BIMの活用を促してきた。「こうした取り組みの結果、社内や関係者間でのBIMの認知度が高まってきたと感じます」と宮村様は手応えを感じている。

BIM活用の理想と現実の
ギャップを埋める「ANDPAD BIMサービス」
BIMのメリットが広く認識されるようになったとはいえ、実際の現場での活用にはハードルが残されていた。建設業ではこれまで、設計図や仕様書などを2次元の文書で作成することがほとんど。そのため、3次元のBIMを新たに導入することは、従来の業務に大きな変化をもたらす。常に膨大なタスクを抱えて走っている現場で、業務の方法を変えることは、言葉でいうよりはるかに大きなエネルギーを要する。
「現場のメンバーがBIMを導入したいと考えても、実際には日々の実務に追われて対応する余裕がないのが現状です。BIMマネジメント課ではそうした部分をサポートしていますが、将来的には、現場主導でBIMを活用できるようになってほしいという思いもあります。このギャップに課題を感じていました」と、宮村様はBIM導入の現実を明かす。
そうした中、宮村様はあるとき、本社のDX本部からANDPAD BIMサービスの紹介を受けた。「BIMマネジメント課で行っていた仮設BIMのモデリングなどの施工活用支援業務を外部委託したいと考えて、ANDPAD BIMサービスを活用することにしました」と宮村様。
ANDPAD BIMサービスは、BIMの設計から施工フェーズにおける課題を整理し、お客様の状況に応じた最適なBIM活用を支援するコンサルティングサービス。単にBIMモデルの作成を代行するだけではなく、建築業での業務経験があるスタッフが現場の社員とコミュニケーションを図りながら、どのようなシーンでBIMを活用すべきかなど、より効率的な運用方法などについてアドバイスを行う。BIMを使い始めた現場や、これからBIMを導入する現場においても、経験豊富なスタッフがBIM運用を手厚くサポートする。
「ANDPADのスタッフは、BIMに関する知識だけでなく施工に関する知識も豊富で、モデリングはもちろん、施工検討に関する質疑や提案をもらいました。当初はモデリング業務だけを外部委託できればよいと考えていましたが、自主的に問題点の洗い出しや提案などを行ってくれて、想定以上のサポートが得られたと満足しています。実際の運用の場面では、私は事前に現場と外部委託する部分のすり合わせを行う程度で、あとは現場とANDPADのスタッフが直接やりとりしてくれました。これによって、1現場におけるBIM運用に関する私のサポート業務は、体感で8割は減ったと思います。その時間をよりコアな業務に注ぐこともできるようになりました」と宮村様は笑顔を見せる。
また、現場社員からも「掘削ステップの作成や数量算出などを行っていただき、協力会社との調整が円滑にできた」「足場のBIMモデルを作成してもらうことで、業務の時間を大幅に短縮することができた」といった声が上がっているという。

現場でのBIM活用も広がる
BIMから足場申請図の作成も
さらに、多忙な現場でも少しずつBIMの活用が定着しつつあると宮村様は話す。「九州の某現場では、足場の計画と同時に地下の工事が並行していて、現場監督者は地下の工事を管理しながら、足場の設置届の対応も求められていました。工事の計画内容などを期限内に労働基準監督署に提出する、いわゆる、労働安全衛生法の88条申請です。躯体の形状が複雑で詳細な検討が必要だが日々の現場管理業務で検討に時間を多くさけない状況であったため、ANDPADのサポートがなければ、期限内の提出は出来なかったかもしれないと現場から聞いております。このようなANDPAD BIMサービスを使った好事例は、他の現場でも紹介していこうと思っています」。
10年以上にわたってBIMを推進する業務に携わってきた宮村様は、「近年は、協力会社の間でもBIMを活用するケースが増えてきたと感じています。この先、BIMの活用が広がっていけば、従来、紙の図面や仕様書など、さまざまな媒体に分散化していた情報が集約され、スムーズに情報が伝達できるようになるでしょう。これが当社の『ワンモデル』が目指すところであり、建設業界全体で取り組むべき効率化の1つの姿だと考えています。その実現に向けて、パートナーであるANDPADと二人三脚で進んでいきたいと思います」と力を込める。
大林組は、BIMを運用する自社ルールの「Smart BIM Standard」を一般公開するなど、建設業の業務革新に向けて積極的に取り組んでいます。大林組がリードする建設業の改革に、今後も目が離せない。