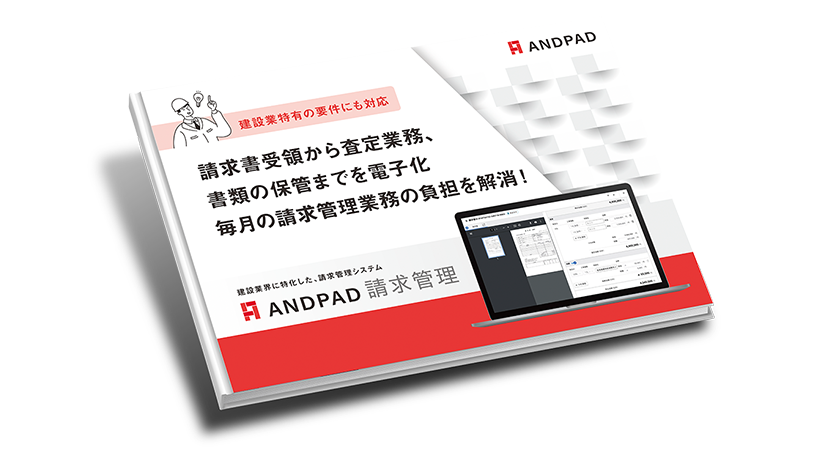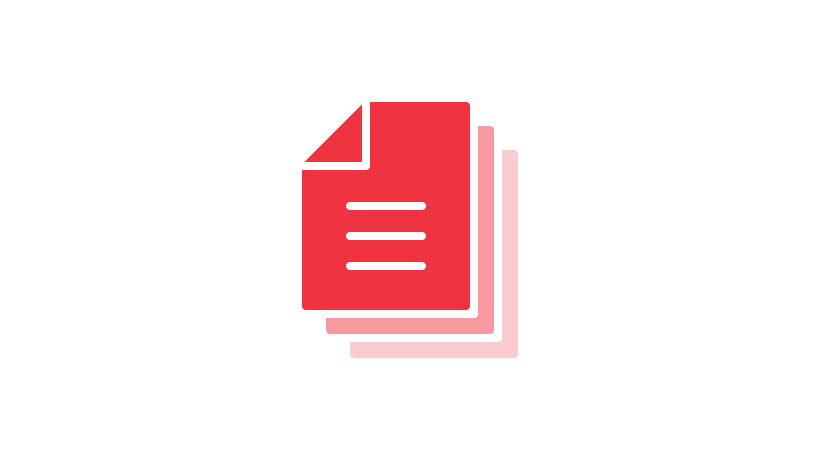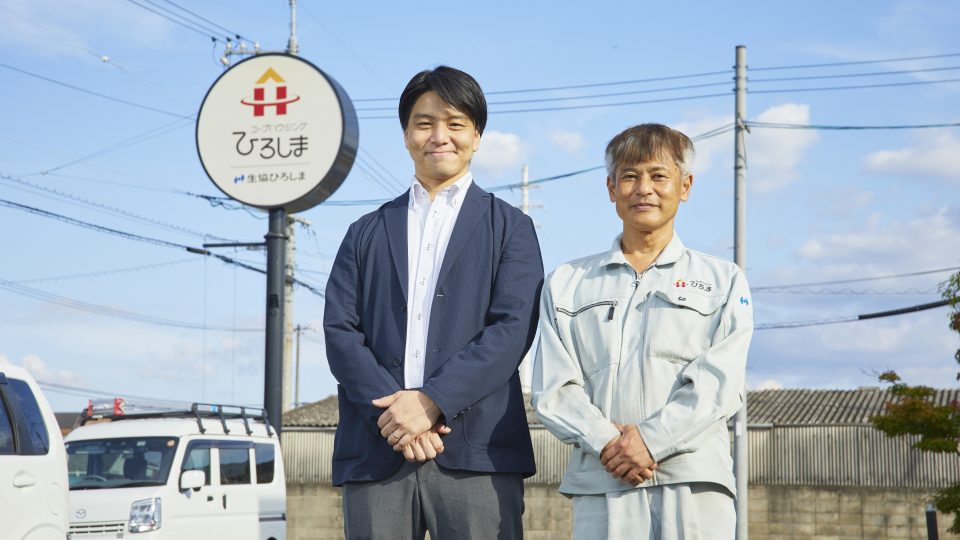「人が使う、人のためのDX」を掲げ、「生産プロセス」「経営基盤」「サービス・ソリューション」の3つの領域でDXを推進している大成建設株式会社。なかでも「生産プロセス」の領域においては、BIM/CIMやAI、IoT、ロボットといった多様なデジタル技術を活用する取り組みに注力し、DXを加速している。
この「生産プロセス」のDXの一環として、大成建設とアンドパッドは、2024年より現場BIM推進のための検証プロジェクトを開始。2025年からは、BIMとデータ連携したANDPAD図面の「配筋検査」機能の現場検証を実施している。
今回は、本プロジェクトを推進している大成建設株式会社 建築本部 デジタルプロダクトセンター DX生産システム推進室 平田 祐之介様にインタビューを実施。大成建設のBIM活用に向けた取り組みやアンドパッドとの連携、今後の展望などを伺った。また、実際に「配筋検査」機能を現場で利用し、検証を行っている加芝 亮様・浅野 真治様には、検証中に実感した効果について伺った。
デジタル人材が集う専門部署が軸となり、DXを推進
全社を挙げてDX推進に取り組んでいる同社では、全国の作業所支援やDX推進を担うデジタルプロダクトセンターを建築本部に設置している。平田様は、デジタルプロダクトセンター内の「DX生産システム推進室」に所属し、「進化型DXパッケージ施工」の開発・試行・展開に尽力されている。
平田: デジタルプロダクトセンターは、設計から施工におけるプロセスの生産性向上を目指す組織です。現在は、私が所属する「DX生産システム推進室」のほかに、「設計支援室」「フロントローディング室」「建築生産室」などの8つの部署があります、設計・施工・設備など、各分野で経験を積んだ社員が集まり、作業所の支援に取り組んでいます。
「進化型DXパッケージ施工」は、BIMを起点にデジタル技術を活用し、建設現場のDXを図っていく取り組みです。「データ連携」「リモート化」「AI・システム」「ロボット」の4領域でさまざまなプロジェクトが動いています。固定概念にとらわれることなく、建築現場を変革するために積極的に試行を繰り返しています。
DX推進体制を強固にするために、同社は人材育成にも注力。近年は、現場で施工管理業務を担う技術者に加え、デジタルに特化した「建築デジタルエンジニア」の採用をスタートしている。
平田: 「建築デジタルエンジニア」は、施工管理に携わる社員とは違った新しい視点で、建設現場を変える「光」を見つけていく人材として期待されています。入社まもない若手社員は、現場で経験を積みながら、デジタル技術導入に向けた検証を行っていますが、ゆくゆくはDX推進に携わっていく予定です。
BIMデータを活用し、人と人をつないでいく

同社が開発を進める「進化型DXパッケージ施工」の軸となるのが、BIMデータの活用だ。これまでも同社は新築現場においてBIMデータを作成してきたが、今後は現場全体でさらなるBIM活用を目指すという。その一環として、同社とアンドパッドは、BIMデータとANDPADを連携した機能開発に取り組んでいる。
平田: BIMは、建築現場に関わるさまざまな部署・役職・立場をつなぐツールのひとつだととらえています。正しいデータを正しくつなげられれば、「人」と「人」がつながり、業務の進め方に変革を与えられる―そんなイメージを持ってBIMデータを活用した新たな機能開発や検証に取り組んでいます。
アンドパッドとは、施工段階ごとに現場実証を行い、BIMデータが有効活用できるユースケースと機能について検証しています。作業所への利用浸透を図るためには、「現場ですぐに使えて、省力化を実感できる」ようなアプリであることが重要です。その点、アンドパッドのみなさんはゼネコンでの勤務経験・現場経験がある方が多く、私たちが機能の要望をお伝えすれば、形にしてくださるので助かっています。実際の現場にこまめに足を運び、現場の声を聞きながら真摯に開発に取り組んでくれる姿勢も頼もしいです。
配筋検査の「準備業務」「検査業務」の効率化を目指して
同社とアンドパッドは、施工段階に合わせ、現場で実効性のあるBIM活用に取り組んできた。そして今回、配筋検査の業務効率化に向け、ANDPADとBIMデータを連携した「配筋検査」機能の現場検証を新たに開始している。まずは、平田様に開発の背景について伺った。
平田: 従来の配筋検査では、検査の準備段階で、構造リスト(豆図)や配筋要領図、構造伏図などから情報を拾い出して黒板を作成しなければならず、多くの時間と手間がかかっていました。当社も以前は紙で情報を整理し、手書きの黒板で撮影をしていました。
現在、配筋検査の際には、まずクラウドで構造図や配筋要領を開いて確認し、その後、工事写真撮影ソフトを立ち上げて黒板を検索し、内容を照らし合わせてから撮影する……と複数のツールを行き来して情報を確認する必要があり、検査業務が煩雑化していました。
また、写真撮影の進捗管理については、表計算ソフトでリストにして管理している作業所もあれば、紙ベースで管理している作業所もあり、管理方法が統一できていないのも課題です。情報管理が属人化しているため、リアルタイムで進捗把握・情報共有が難しいのも現実です。
そこで、配筋検査業務の効率化により現場の負担軽減を図ること、同時に配筋検査の準備業務も効率化すべく、BIMデータを活用した「配筋検査」機能の開発に着手しました。
ANDPADとBIMデータを連携し、検査に関わる情報を一元管理
では、BIMデータとANDPADを連携した「配筋検査」機能とは、どんな機能なのだろうか。詳細を紹介していただいた。
平田: 今回検証を行っている「配筋検査」機能は、ANDPADとBIMデータを連携し、配筋検査の準備業務・検査業務・進捗管理を効率化する機能です。
まず準備業務については、BIMデータから検査に必要なデータを自動で取得し、図面、黒板情報、チェックリストなどの情報をANDPADに登録するだけで完了するようになります。そのため、検査準備にかかる時間を大幅に短縮できるようになっています。
また、BIMデータとANDPAD図面を紐づけ、検査箇所にピンが設定されるようにもしています。ピンを選択すれば、該当検査箇所の黒板などの情報を呼び出して、検査や写真撮影ができる仕様になっており、ANDPAD図面上で検査の進捗状況も確認できます。
平田様は、「将来的には、BIMデータさえあれば検査準備の時間がゼロになる世界を目指す」と意気込む。今後の開発内容も業務効率化への期待が膨らむものばかりだ。
平田: 現在、打設工区単位で、自主検査や施工者検査、監理者検査といった複数の検査形式に対応できる機能や、検査ごとに進捗確認ができるステータス管理機能の検証も進めています。ゆくゆくは、AIを組み合わせて、撮影位置や撮影内容の整合性をチェックしたり、撮影漏れ防止のアラートを出したりするような仕組みも導入できれば、生産性向上だけではなく品質向上にも役立てられると考えています。
まだ検証段階ですが、協力現場からは前向きなフィードバックが返ってきて非常に参考になっています。特に検査業務に従事する若手社員は、DXに興味を持ち、自分事としてとらえてチャレンジしてくれている感覚があります。業務効率化が進めば、若手社員が施工技術を学ぶ時間も確保できるようになり、人材育成の観点でもDXのメリットは大きいと考えています。
検査時間が半減、写真整理も効率化

加芝様・浅野様は、同社の「建築デジタルエンジニア」として採用された方々だ。現在は、施工管理担当者として現場経験を積みながら、現場でさまざまなデジタルツールを活用し、そのフィードバックを行っている。では、実際に「配筋検査」機能を利用してみて、おふたりはどのような効果を感じているのだろうか。
加芝: 従来の検査方式とANDPADの「配筋検査」機能の両方を経験しましたが、「配筋検査」機能を利用した場合、現場での情報確認が格段に早くなったと感じています。以前は、クラウドや工事写真管理ソフトなど、複数のツールを開いて情報を参照する必要がありましたが、ANDPADは必要な情報が一画面に集約されており、確認作業が大幅に効率化されています。私の所感では、1件あたりの情報確認にかかる時間は半減したと感じています。
浅野: 写真の整理も効率化されたと思います。従来の工事写真管理ソフトは、撮影した写真がバラバラに保存されてしまうため、検査後に写真の判別や整理に多くの時間を取られていました。その点、ANDPADは黒板ごとに撮影写真がフォルダ分けされていくので整理の手間がなくなり、負担が軽減されています。
加芝: 検査や写真撮影の進捗をアプリ上で一元管理でき、工事係全体で共有できるのも便利です。これまでは、写真撮影の進捗管理表を作成してクラウドに置き、私と浅野で更新していたのですが、その表を作成したり、更新したりする手間がなくなりました。上司に説明する際にも、これまでは進捗管理表をもとに改めて資料を作成して提出していましたが、ANDPADであれば黒板に沿って写真撮影をするだけで情報がリアルタイムで更新されていくので、資料作成の手間も省けています。
「現場第一」で今後の開発も進めていきたい

「建築デジタルエンジニア」として検証にも関わりながら、実際の現場で経験を積む加芝様と浅野様。業務効率化・生産性向上に意欲を持って取り組むおふたりに、これからの抱負を伺った。
浅野: 現場で苦労していることや、デジタルツールの利用に慣れるまでにかかったプロセスなど、今感じている「生」の感覚が今後DXに関わる上で非常に貴重だと考えています。まだまだ現場の業務に慣れている段階ではありますが、改善できる点をなるべく多く見つけて上司にフィードバックし、できるところから試行していきたいと思います。
加芝: 現場業務の効率化や負担軽減、情報共有の円滑化を実現するためにも、まずは従来のやり方を学ばなくてはと思い、日々の業務に向き合っています。現在の配属現場はDX推進の取り組みに積極的で、私もANDPADをはじめ、いくつかのツールを試行していますが、やはり現場に出て使ってみないとツールの良し悪しが見えてこないと実感しています。今の施工管理業務をしっかり理解した上で、デジタルでどうより良く変えていくか、何ができるかを探っていきたいと思います。
最後に、平田様に今後の展望を伺った。
平田様: どれだけ見た目が良いソフトであっても、現場が使いやすく、利便性が実感できるものでないと利用は浸透しないものです。今後もBIMデータを「誰でも作業しやすく使いやすい」形に落とし込み、現場の施工管理担当たちの「かゆい所に手が届く」ようなツールをアンドパッドとともに細かく作り込んでいきたいです。